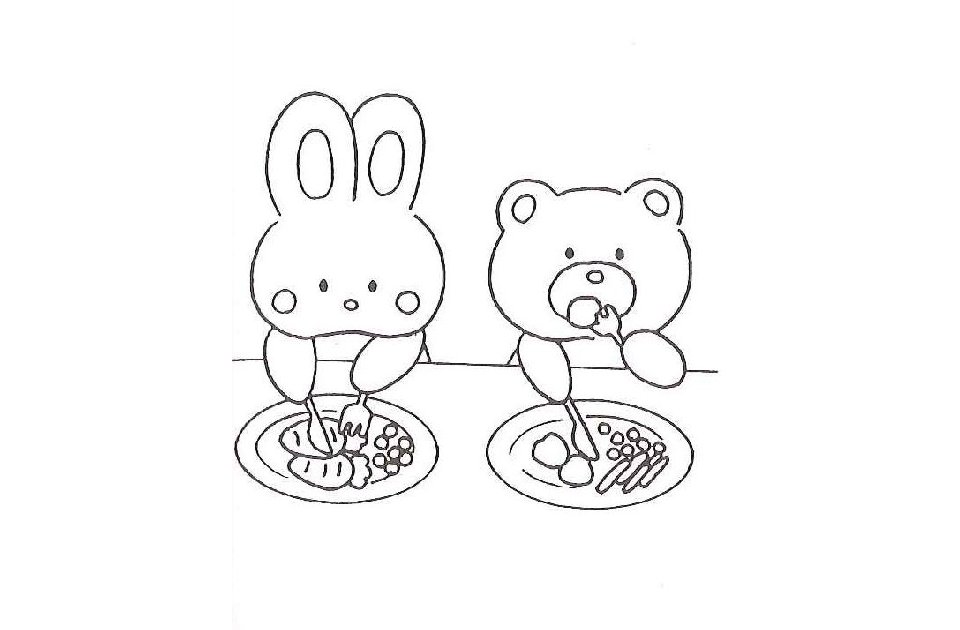|
大学生の「私」は
「 「いや、なにも話はしていない」 私はズボンを 「お父さん、何か変なんですよ。ぼくが八時ごろお 「 私は 私は、部屋の中を見まわして立ち上がると、窓を閉め部屋の灯を消した。そして、頭をすくめながらベッドに身を横たえた。 家の中は 「 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
|
私は、 「そうか、それは 私は、 「どこで生まれるのかな。 私は、 「水ってこわいですね」 「そうかね」 私は、しかたなく答えた。 「 弱ったな、と私は思った。 しばらくして、私は上のベッドで 「暑いんですけど、窓を開けていいですか」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | ||
|
低い声が、もれた。 私は、 ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | ||
□□□□□□□□□□□□□□