
これからの教育に求められる方向は四つあると思います。
第一は、受験と競争に勝つことを中心とした教育ではなく、本当の実力をつけるための教育を目指すということです。
第二は、外部に委託する他人任せの教育ではなく、家庭や地域を中心とした自分で学ぶ教育を目指すということです。
第三は、成績や得点だけを考えた没価値の教育ではなく、日本の社会に生きるための価値観を持った文化の教育を目指すということです。
第四は、現代の社会に適応するためのエスカレーターに乗る教育ではなく、自主独立の人間として生きる教育を目指すということです。
その中で、最も重要なものが実力をつけるための教育です。
受験という競争に勝つための教育ではなく、生きる実力をつけるための教育を行うには、それに合わせた毎日の自習が必要です。
言葉の森で行っている自習は、現在やや複雑になっているので、今後学年別に自習の内容を整理して、もっとわかりやすく取り組みやすいものにしていきたいと思っています。
現在自習として取り組もうと思っているものは四つあります。
第一は、課題の長文の音読です。これには、読解マラソン集の音読も含みます。
第二は、毎日の10ページ以上の読書です。
第三は、毎日10分程度の暗唱練習です。
第四は、問題集読書をもとにした。四行詩の作成です。
まず、長文音読についてです。
音読は、同じ文章を繰り返し読むというところに意義がありますが、同じ文章を繰り返し読むことを家庭で徹底させるのは、実は難しい面があります。
そこで、音読のできる家庭はそのまま音読を続けていけばいいのですが、毎日の音読を徹底できない場合は、ウェブで同じ文章を繰り返し聴くという仕組みをゲーム的に作っていきたいと思っています。
現在、速聴のページがありますが、これを速聴だけではなく普通のスピードの朗読としても聴けるようににして、その朗読を毎日子供が聴きます。
朗読を聴いている途中で、何かのメロディーが流れるようにするので、その朗読が終わったあとに、そのメロディーが何のメロディだったかを選択してボタンを押すという仕組みです。
このようにすれば、保護者が一緒について音読をチェックするようなことは必要なく、子供が自分で文章を毎日読んでいくことができます。
また、毎日ができない場合でも、1週間のスケジュールを決めておけば、時間のあるときにこの自習をまとめてやっていくこともできます。(つづく)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。音読(22)

夕方の家族のお喋りは、大いに盛り上がります。お父さんは、いま取り組んでいる仕事の話をいろいろしてくれます。お母さんも、よく勉強していて、お父さんの専門分野についていろいろな質問をします。
お母さんも、自分の趣味の仕事を持っているので、その話をすると、今度はお父さんがいろいろな質問をします。もちろん、ここにK君も加わります。夕方のお喋りは、にぎやかな討論会のようでした。
僕は、こんなに面白い話を毎日していれば、テレビやゲームなんていらないなと思いました。
夕飯の食卓は、野菜が盛りだくさんです。ほとんどは、自宅で育てているもののようです。
庭がなくてもベランダや窓ガラスで栽培できる野菜が増えているので、どこの家庭でも、野菜は自宅で作っているようです。
肉類はあまり食べないらしいので、僕が、
「どうして」
と聞くと、
「食べられる動物の身になったら、かわいそうだからだよ」
と、K君は笑いました。未来の社会の人は、他人ばかりにではなく、動物に対しても共感する気持ちを持っているようです。
ちょうど社会全体が、他の人も他の動物も含めて、一つの家族のように相手のことを考えているから、わざわざルールを作ったり取り締まる人を作ったりする必要がないのだと思いました。
僕は、日本の歴史を学んだとき、徳川綱吉が出した「生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい)」を悪法のように教わっていましたが、未来の日本の学校では、綱吉の精神は逆に評価されているということでした。
食事を始めると、窓からリスや小鳥が入ってきました。これらの小動物の中には、ベランダの巣箱で暮らしているものもいるようです。
人間の間にまじって、リスや小鳥がテーブルの上には上がらずにちゃんと横で待っています。
ペットとして飼われているわけではないので、つかまえたり手でさわったりすることはできませんが、手の届くぐらいの近さでみんなにぎやかにえさを食べていました。
近所の家の中には、トンビやフクロウと一緒に住んでいる家もあるようです。
寝る時間になっったので、ベッドに行こうとすると犬がついてきました。ゴンタという名前で、3歳のゴールデンレトリバーです。
K君は、いつも犬と一緒に寝ているようです。
「今日は、君がゴンタと一緒に寝たらいいよ」
と、K君が言いました。面白そうなので、僕は、
「うん、ゴンタおいで」
と言いました。
今日一日いろいろ新しい経験でくたびれたので、僕は、ベッドに入るとすぐに寝てしまったようです。
朝、スースーという音で目が覚めると、僕の目の前に、寝ているゴンタの顔がありました。僕は、ちょっとふざけて犬の真似をして、ゴンタの鼻をペロリとなめました。ゴンタは、ぱちりと目をさましました。(おわり)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
完結ですか~。
終わってしまって、ちょっと寂しいです。
とても好きでした。
ポプラ社あたりから出版してほしいです(笑)。
エズミカレンさん、ありがとうございます。
ふと思いつきで書いているうちに、長くなってしまいました。
でも、なんだか将来ありそうな話でしょう(笑)。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

未来の社会では、子供が学校で勉強するのと同じように、大人もみんな熱心に勉強や習い事をしています。会社が終わると、ほぼ毎日必ず何かの習い事をしてから家に帰ってきます。
未来の社会では、人間が学校を卒業して就職するようになると、すぐにそのような習い事をいくつも始め、そこからだんだん自分の好きな習い事に絞っていき、これと決めたものはそれから10年も20年も続けます。
すると、40歳ぐらいになると、自分がその習い事を教える仕事もできるようになってきます。そこで、みんなそれぞれに工夫して、自分がこれまで身につけたものを組み合わせて教えるので、そこで、新しい習い事の創始者になる人も多いようです。
そうして、勤めていた会社を定年でやめるころになると、もう自分ですっかり新しい仕事を教える準備ができているそうです。
K君のお父さんは、そう教えてくれました。
僕は、昔、中学の社会科の授業で、「日本の経済発展にはこれから内需が必要だ」ということを習いましたが、日本人どうしがお互いに習い事を教えるというのが、未来の新しい内需になっているようでした。
しかも、こういう習い事は、何十年も続けてきているものなので、中には普通の人の及びもつかないような高度な技能を持つ人もいます。そういう人は、人間国宝のような称号が与えられて、4年に1回開かれる文化オリンピックで表彰されるそうです。
僕がいた過去の日本の社会でも、碁や将棋の名人、包丁一本の料理職人、作詞家や作曲家など、自分の持っている技術で生きている人がいましたが、未来の社会では、それがいろいろな分野に広がっています。
中には剣玉名人のような、一見簡単にできそうなものもありますが、それを何十年もきわめている人がいるので、今では高度な芸術的スポーツのようになっているということでした。
昔の日本の社会では、みんなが「欲しい」と思うものは主に「物」でしたから、「物」を買って豊かな生活を送っても、収入は別のところで働いて稼いでこなければなりませんでした。すると、働けなくなると収入がなくなってしまいます。
「物」の社会では、買えば買うほどお金が減ってくるので、みんなはなるべくお金を使わないようにしていました。
しかし、未来の日本の社会では、みんなが「欲しい」と思うものは、「物」よりも自分の「修行」になっています。自分の「修行」は買っているうちに、自分の能力になってきます。すると、今度は、その能力を売ることができるようになります。
このようにして、「修行」の社会では、お金を使えば使うほど自分の能力が増えてくるので、みんながなるべくお金を使うようになっています。貯めておいても自分の能力は増えないからです。
こうして、「物」の消費社会から、「修行」の自己投資社会に世界で最も早く移行した日本の社会は、今では世界一豊かな国になっているということでした。
日本が、世界で初めてこういう修行の社会になったのは、日本人が勉強好きだということが大きな理由のようでした。(つづく)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)
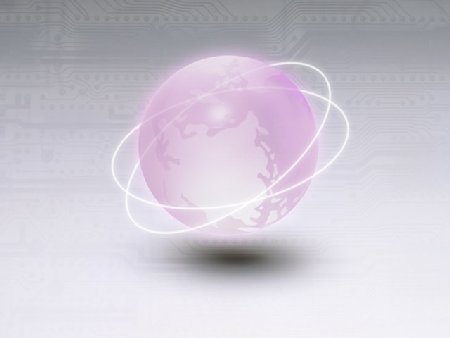
未来の社会では、レジに人がいない店もよくあるので、自分で商品のバーコードを読み込んで、表示された金額を払ってくることも多いようです。
「少なめに払っていくなんて人はいないの」
と、僕が聞くと、
「だって、もし自分がお店をやっていて、少なめに払われたら嫌でしょう」
と、K君は当然のように答えました。「もし、自分が相手だったら」という考え方をみんなが自然にしているようです。
警察というのも、とっくの昔になくなっているということでした。悪いことをする人がほとんどいないし、いても、みんなで事情を聞いて対処するので、警察の仕事というのがなくなったそうです。
法律も、常識でわかるくらいのものに簡素化されて、しかも年々減っているようです。
「法律や警察がないなんて、不思議な社会だね」
と、僕が言うと、
「だって、家族の中だってもともとそんなのないじゃない。家族が広がったのが社会だと思えば、不思議なことなんてないさ」
と、K君は言いました。
「こういうのは、世界中で実現しているの」
と、僕が聞くと、これも不思議なことに、こんなふうになっているのは日本だけのようです。
世界のほとんどの国は、まだ警察もあるし法律も複雑で、しかも争いがなかなか絶えません。だから、治安のいい日本の社会を見学しに、毎年世界中の国から視察団がいくつも来るようです。
しかし、なぜ日本だけが、このように正直な人が多く、しかも、他人に対する思いやりのある人が多いのかまだよくわからないようでした。(しかし、その後の研究によると、左脳で感情や自然の音を処理する日本語脳にその秘密があるようだということでした)
家の中に入って、K君としばらくおしゃべりをしているうちに、K君のお父さんやお母さんが帰ってきました。
みんなが集まると、夕方はテレビなどを見ずに、もっぱらみんなでおしゃべりです。
子供が小中学生のころは、父親も母親も残業や転勤がなく、いつも早く帰ることができるそうです。社会のルールでそう決まっているということでした。
子供も、夕方、塾や習い事に通ういうことはありません。そういうのは昼間のうちに行けるからです。
学校は、勉強を教えてもらいに行くところではなく自分で勉強をしに行くところなので、自分で自由に行く日を決めることができます。
特別なことを勉強したり習いたいからという理由で塾や習い事に行く人は、学校の中にそういう場所があるので、そこに行きます。
しかし、子供が自由に何をしてもいいとなると、全体の勉強のバランスがくずれてしまうこともあるので、ときどき勉強全体のコーチのような人が、子供や両親と相談して、数ヶ月のおおまかな勉強のメニューを提案します。子供は、そのメニューを参考にしながら、自分の好きなことを中心に自由に勉強や習い事の予定を組んでいます。
だから、学校は行きたいときに行けばいいのですが、ほとんどの子供は、毎日決まった時間に学校に通います。友達といる方が楽しいし、毎日同じペースで生活した方が楽だからです。
ところで、未来の社会の不思議なところは、子供が学校で勉強しているのと同じように、お父さんやお母さんなどの大人も、みんな熱心に勉強や習い事をしていることです。
実は、これが未来の日本の社会の豊かさを生み出しているひとつの大きな理由なのでした。(つづく)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)