
子供が小学校高学年から中学生になったときに、言うこと聞かせられる親にも共通点があるようです。
子供が小さいときは、細かいことはあまり言いません。子供にのびのびと、やりたいようにやらせて、多少脱線しても平気です。テストの点数が悪くても気にしません。
しかし、肝心なときだけ強く短く叱ります。このときの叱り方は、いったん口に出したら妥協はありません。
だから、子供はのびのびしていますが、いざここが肝心の場面だとわかると素直に親に従います。
こういう叱り方は、一般に父親の方が得意で母親は苦手なようです。だから、本当は母親は、叱り役をあまりしない方がいいと思います。母親が叱ると、年中小言と言うような叱り方になることが多いようです。
父親は、普段はにこにこしているだけで、子供たちの脱線も大目に見ていますが、ある基準を越えるときだけ、「おい」と一言(笑)。子供は、すぐにその基準の中に戻り、またのびのびと遊び出すというような叱り方です。
では、既に親子の間で、親の言うことを子供が聞かないという関係ができている場合はどうしたらいいのでしょうか。
まず、父と母が協力することが大事です。父親が叱っているときに母が子供の味方をしたり、母親が叱ってるときに父が子供の味方をしたりしたのではよくありません。しかし、それは、父と母が一緒になって子供を叱るということではありません。
それから、両親が子供に向かって、お互いの悪口を言うのももちろんよくありません。「葉隠」に、「愚かな母は、子供を味方につけたいという思いから、父の悪口を言うことがある」と書いてあります。これは、父親にとっても同様です。両親が、子供に対しては、お互いに相手のことをそっと褒め合うというのが理想です。
私は、学校教育で、こういうことこそ教えるべきだと思います。知識として知っているだけでも、家庭の雰囲気は大きく変わると思います。
子供の教育にとって大事なのは、親の言っていることが正しいかどうかということよりも、両親が一致しているということです。
しかし、父親と母親の間で非協力の関係が既にできている家庭も多いと思います。^^; そういうときは、気迫で臨むしかありません。
大事なことは焦点を絞ることです。あれもこれも言うこと聞かせるのではなく、ほとんどのことは本人の自主性に任せ、ある基準のいくつかのことだけは断固として守らせるようにします。
そして、いったん叱り始めたら、途中で妥協はせずに最後まで貫徹することです。こういうときのやりとりは、体力も理屈も関係なくただ勢いだけが必要です。子供が成長すると、体力も理屈も次第に親を上回るようになってきますが、親は気迫だけは負けなければいいのです。
しかし、更に言えば、親が子供をうまく叱れなくて、言うことを聞かせられなくても、長い目で見れば、子供は成長とともに必ず親の言おうとしていたことを理解します。
どんな子供でも、自分が親の年になれば、親の言いたかったことがわかってきます。そのためには、親がたとえその場で言うことを聞かせられなくても、少なくとも言葉の上では正しいことを子供に伝えておくことだと思います。(おわり)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
早速、主人にも読んでもらいます!
> なるほどさん
強くて優しくて面白いお父さんになるようにがんばってください。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117)
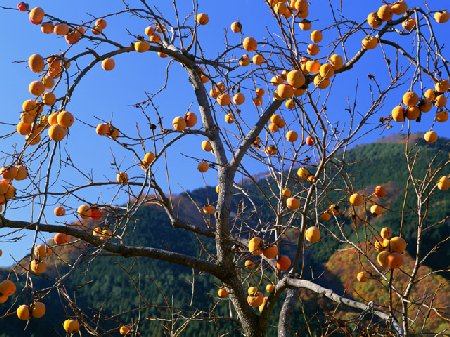
時どき、「親が言っても言うことを聞かないので、先生の方から言ってください」というようなことを頼まれることがあります。
いちばん多いのは、「本を読むように言ってください」ということです。しかし、親が言うこと聞かせられないのに、他人が簡単に言うことを聞かせることはできません。
親はその子と一緒に十数年も暮らしているのに対して、先生は毎週電話で十分話をするだけです。しかも、まだ先生と子供が接触して何週間もたっていないということも多いのです。
親は、いざとなれば子供をぶっとばすこともできます。もちろんそういうことはほとんど必要ないと思いますが(笑)。しかし、もしそういうことがあっても、一晩たてば仲よくなるのが親子です。
他人は、そうではありません。例えば、教室で子供をひどく叱ったときは、そのあといくらフォローしても、1週間後にまたその子の顔を見るまでは落ち着きません。あのとき叱らないで、もっとうまくやる方法があったのではないかと、折に触れて思い出すからです。
叱るというのは、そういうストレスのたまることなのです。
子供を叱れない親は、そういう苦労を避けているだけではないかと思います。子供が言うこと聞かないのは、単に親が本気になっていないからです。
では、なぜそういう親子関係になってしまったのかと考えると、言うことを聞かせられない親に一つの共通する傾向があるように思います。
それは、子供が小さいときに、細かいことを注意したり管理したりしすぎたのではないかということです。
子供が小学校2年生のころまでは、誰でも親の言うことをよく聞くので、親もつい細かく注意しすぎることがあります。
しかし、細かい注意ですから、中には子供が守れないことも出てきます。
子供が小学校5年生ころになって自覚ができてくると、親が言ったことでも、「できない」と自己主張することがあります。
そのときに、その注意がもともと細かい些細なことであった場合は、親はそれ以上無理させることができなくなります。そうすると、あとはなしくずし的に、親の言うことを聞かなくなっていくのです。
つまり小学校低学年のころに言うことを聞かせすぎると、小学校高学年になって言うことをきかなくなるというパターンです。小さいときに気楽に叱りすぎたので、叱ることに重みがなくなってしまったのです。
例えば、成績が悪かったので叱るなどというのは、最もよくない叱り方です。
成績が悪かったときは、子供は既に心の中では暗い気持ちでいます。そういうときこそ、親が、「大丈夫、大丈夫。こんなの気にしない。テストの成績なんて、あなたの中身に全然関係ないんだから」と明るく励ましてあげることが大切です。
こういう対応をしているお母さんの言うことなら、子供はしっかり言うことを聞くようになるのです。(つづく)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
良い事書きましたね。僕はインドネシアで日本語を勉強しているので、作文を読むと勉強になることです。
e-mail:fiyad.30@gmail.com
> fitriyadiさん
コメントありがとうございます。
インドネシアは、今、火山の噴火などで大変そうですが、自然の豊かないいところと聞いています。
いつか遊びに行きたいと思っています。
日本語の勉強、ぜひがんばってください。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117)

受験で作文・小論文の課題に取り組む人のために、試験前の準備を「言葉の森新便」から転載します。
作文の試験で、いちばん頼りになるのが、自分がこれまでに書いた作文の蓄積です。
作文をたくさん書いていると、その中に必ず、自分でも驚くほどいい表現や実例や意見が入った文章を書くことがあります。そういう文章を蓄積しておくことが作文の試験対策です。
これまで作文を書いていなかったが、これから試験があるという人は、とりあえず10種類のテーマを決めて作文を書いていきましょう。テーマを変えて10本の作文を書いていると、試験の本番でもその中のいくつかの実例や表現で生かせるのが出てきます。
====言葉の森新聞の記事より====
(1)これまでの作文をファイルしておきましょう。
(2)上手に書けていると思ったところに赤ペンで線を引いておきましょう。
(3)線を引いたところを何度も繰り返し読んで、覚えましょう。
(4)これまでに書いた作文の中で、自分らしい体験実例が書かれているところを二つ選び、その実例をいつでも書けるようにしておきましょう。
(5)試験の始まる直前まで、作文のファイルを読みましょう。
(6)課題が出されたら、頭の中にあるこれまでのいい実例、いい表現であてはまりそうなものを思い出して、問題用紙の横などにメモしましょう。
(7)全体の構成は、第一段落「説明と意見」、第二段落「理由・方法・実例」、第三段落「理由2・方法2・実例2」、第四段落「第一段落と同じ意見」という形を基本にしましょう。それぞれの段落の長さは150字ぐらいが目安です。
(8)構成メモを考えたら、字数配分で8割ぐらいまでのところは、できるだけ速く書き、最後の2割はじっくり書くようにしましょう。
(9)結びの第四段落には、できるだけ「確かに……」という言葉で反対意見に対する理解を入れましょう。
(10)書き出しと結びの意見は必ず対応させましょう。
(11)課題文の中にあるキーワードは、できるだけ結びの5行の中に入れましょう。
(12)習った漢字は全部使いましょう。書こうとする漢字に自信がないときは、別の表現の仕方を考えましょう。
(13)できるだけ指定の字数ぎりぎりまで書きましょう。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89)