現在、「学習の手引」を改訂中です。
「学習の手引」の記事を簡素化するために、「暗唱フォンの作り方」はホームページの方に掲載します。
====
教室で一斉に暗唱するときや、狭い家で兄弟一緒に暗唱するとき、大きい声は出せないが、自分の声はしっかり聴きたいということがよくあります。
暗唱の仕方の中には、聴いて覚える方法もあります。高速聴読がその方法ですが、人によっては聴くだけでは覚えにくいようです。耳栓をして周囲の雑音が入らないようにしながら、内耳で聴く方法もあります。しかし、これも人によっては覚えにくいようです。
一方、先人の例を見てみると、シュリーマン、本多静六、貝原益軒、湯川秀樹など、みんな声を出して暗唱する方法でした。人間は、いったん自分の声として出した言葉を、聴くときにも言葉として認識します。声を出すことによって二重にその言葉が自分のものになるのです。
●暗唱フォンシングル型A4の紙を1枚用意します。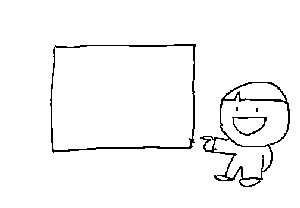 | 1枚を二つに折ります。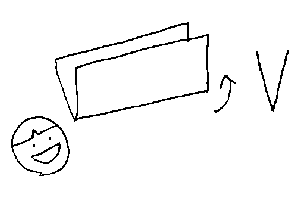 |
二つに折った線を基準に三つに折ります。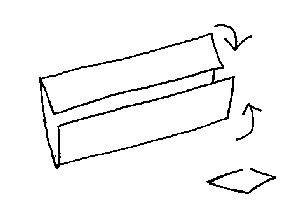 | 裏返してまた三つに折ります。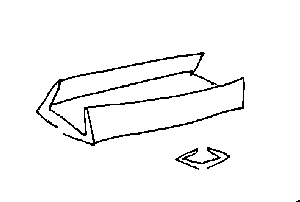 |
片側の端を箱を作るように折り立ててホッチキスで止めます。 | 両側の端を同じように止めて長い箱を作ります。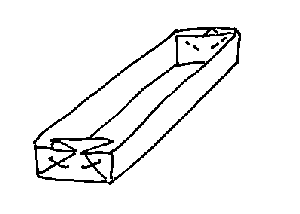 |
箱の真ん中あたりを折って120度ぐらいの角度にしてホッチキスで止めてできあがり。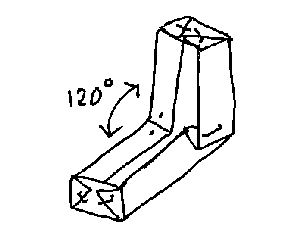 | |
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121) 生徒父母向け記事(61)

アルキメデスは言った。
てこがあれば地球でも動かしてみせると。
努力や根性の差はせいぜい二、三倍だが、
道具や方法の差は、十倍にも百倍にもなる。
子供たちの勉強もそうです。
勉強の道具と方法を知っているかどうかで、成果が大きく変わります。
例えば、受験勉強の場合、志望校の過去問を勉強の戦略の中に組み入れていたかどうかが勉強の能率に大きく影響します。
ところが、ほとんどの高校3年生は、過去問を最後の力試しのようなものとして位置づけています。
こういう勉強の方法は、だれかに教えてもらわなければ気がつきません。
同じことが、仕事にも、人生にもあてはまります。
いい仕事をするには、何よりもいい道具と方法が必要なのです。
弘法が筆を選ばなかったのは、筆にこだわらなかったということであって、悪い筆が好きだったということではありません。(あたりまえですが)
勉強というのは、知識を身につけることよりも、知識を身につける方法を身につけるものなのです。
ということで、今日のテーマは、道具と方法。
1、道具や方法についてひとこと、
又は、
2、「ど、う、ぐ」又は「ほ、う、ほ」うで五七五(変な区切り方)、
又は、
3、何でも自由にどうぞ。
子供たちの勉強の仕方を見ていると、方法を知らないために遠回りの努力をしているということがよくあります。
たぶん、同じことが、大人の人生や仕事や子育ての仕方にも言えるのでしょう。
方法を共有するという点で、インターネットは新しい道具となっているのかもしれません。
それでは、今日も、いい方法を見つけて、うほうほと楽しい一日をお過ごしください。(ゴリラか)
言葉の森のfacebookページ
http://www.facebook.com/kotobanomori
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=299546470091524&l=212e910681
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119) facebookの記事(165)

いい子だけ褒めて、子供がみんなよくなるかというと、
よくなるのは、その褒められたいい子だけ。
みんなをひとりひとり別の理由で褒めるのが
褒め方の工夫のしどころになる。
大人はつい手を抜いて、いい子だけ褒めて済ませようとします。
そして、それではみんながなかなかいい子にならないので、無理やり競争させようとしてしまうのです。
例えば、兄弟で、上の子が本をよく読むのに、下の子があまり読まない場合、
「お姉ちゃんは本をよく読んだのにねえ」
と言っても、下の子は読むようにはなりません。
例えば、作文の文集で、上手な作品だけ掲載してみんなの前で褒めても、ほかの子はその子のように上手な作文を書こうとは思いません。
隣の子を、「○○ちゃんはとてもいい子なんだよ」と褒めても、自分のうちの子は、その子のようになろうとは思いません。
いずれも、いい子を褒めれば褒めるほど、ほかの子は意地でも反対の方向に行きたくなるのです(笑)。
褒め方は、ひとりひとり別の理由で、その子だけを褒めるのが、親や先生の工夫のしどころです。
ということで、今日のテーマは、その子ひとりだけ。
1、その子ひとりだけについてひとこと、
又は、
2、「そ、の、こ」又は「ひ、と、り」で五七五、
又は、
3、何でも自由にどうぞ。
ひとりひとり別の理由で褒めるというのは、努力によってもできることですが、そういう天性もあるようです。
サッチャー元首相は、一時、学校の先生になりたいと思ったそうですが、よく考えて、自分には先生になる才能がないとあきらめたそうです。
確かに、サッチャーさんに勉強を教えてもらいたい子供は、あまりいないでしょう。
「今度の担任、サッチャー先生だって」
「わあ、やだー」
となりそう(笑)。
サッチャーさんには、別の天性があったのです。
それでは、今日もひとりひとりのいいところを見ながら、楽しい日曜日をお過ごしください。
言葉の森のfacebookページ
http://www.facebook.com/kotobanomori
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=298934753486029&l=e709700a69この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) facebookの記事(165)

スポーツの勝ち負けは、
力比べで決まるが、
本当の勝ち負けは、
志で決まる。
子供の教育を考えてみると、今の社会では、成績の良し悪しで学歴が決まり、学歴の良し悪しで将来が決まるような感覚を多くの人が持っています。
しかし、本当はそうではありません。
昔、一太郎が日本のワープロソフトの定番でした。
しかし、ワープロの市場が広がると、マイクロソフトのワードが、エクセルやアクセスとの連携を売りにシェアを伸ばしてきました。
どんなにいい製品でも、総合力の力比べになれば負けることもあります。
しかし、一太郎はその後も勝負を投げずに、こつこつといい仕事を続けてきました。
そして、今、内容的にはもう一太郎は、いつワープロソフトの定番に復活してもいいほどになっています。
ワープロソフトの内容自体は、これから大きく変化していくでしょう。
パソコンソフトの時代からネットサービスの時代になれば、全く違う形のものになるかもしれません。
しかし、志のあるものは、どんな変化にも対応していくと思います。
教育も同じです。
子供の未来を決めるのは、その子の志です。
志さえあれば、人間は、自ら変化を作り出していくこともできるのです。
ということで、今日のテーマは志。
1、志についてひとこと、
又は、
2、「こ、こ、ろ」ざしで五七五、
又は、
3、何でも自由にどうぞ。
売れる市場で、売りの競争をしているときは、どれが本物かわかりません。
しかし、売れなくなったとき、力の差ではなく志の差が出てくるのです。
それでは、今日も、志を内に秘めて、いい一日をお過ごしください。
一方的にならないように。(^^ゞ
ワードにも、もちろん志はあるでしょう。
しかし、一太郎の志とはちょっと分野が違うのです。
(この比較をすると、アメリカと日本の比較文化論になりそうです)
言葉の森のfacebookページ
http://www.facebook.com/kotobanomori
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=298339996878838&l=b850bf8ee7
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) facebookの記事(165)