
●小学校1、2年生から3年生に移るときに大きな変化
言葉の森でこれから勉強してきたみなさんが、新年度から新しい学年でどういう勉強をするかということを説明します。
まず、大きく変わるのが小学校3年生からです。小学校1、2年生の生徒は、これまで自由な題名で作文を書いていました。「きょうのこと」や「このまえのこと」という内容の作文が多かったと思います。
小学校1、2年生のときにテーマを決めた作文を書こうとすると、材料が見つからないことがあります。また、材料が見つかってもそれを長く書く力がまだありません。作文を書く練習の中には、文章を書くことと、何を書くか考えることの両方がありますが、小学校低学年では、その書くことを考えることを両方行うのは負担が大きいのです。だから、今日あったことなどのように、書くための材料がそのまま事実としてあることを、その事実の起こった順序で書いていくというのが1、2年生の練習です。
しかし、小学校3年生からは、自由な題名の作文ではなく、題名の課題が与えられた作文を書く練習をしていきます。これは、例えば、「がんばったこと」「いたかったこと」「ないしょの話」などという題名です。また、月に1回は、長文を読んで感想文を書く練習をしていきます。
小学校1、2年生の教材に、毎週の課題の長文がありますが、1、2年生のころはこの長文は特に使いませんでした。しかし、小学校3年生から、毎月第3週目に、この長文をもとに感想文を書く練習をしていきます。感想文を書くためには、長文を何度も読んで内容を消化している必要がありますが、3週だけ長文を読んでくるという形だと忘れてしまうことが多いので、感想文のある週も、題名課題だけの週も、毎日長文を音読する自習をしておくといいのです。
自由な題名から課題の題名に移ると、初めは急に書きにくくなったように感じます。「この題名では、書くことがない」という場合が出てくるのです。そして、毎年、何人もの生徒から、「1、2年生のころのような自由な題名で書きたい」という声が出てきます。
この場合の対策は、次のとおりです。
まず、作文の授業がある日までに、課題集を見て、次の週がどういう課題なのかを確かめておきます。次に、その題名に合わせて作文に書く材料を見つけます。課題の中には、「ひとりでお使いに行ったこと」などという題名もありますから、まだひとりでお使いに行ったことがないような人は、1週間の間にお使いに行く経験をしておくというのが材料の準備になります。そして、自分の経験だけでは、材料に限界があるので、お父さんやお母さんに似た話を取材するようにします。
似た話を取材するというのは、小学校1、2年生のころにしていた人もいると思いますが、自由な題名のときは、お父さんやお母さんも似た話のしようがないことが多かったと思います。ところが、小学校3年生の題名課題になると、お父さんやお母さんも、更におじいちゃんやおばあちゃんも、似た話の焦点が絞られるので話をしやすくなります。こうして、子供の作文の課題をもとに、家庭で楽しくお喋りをすることができるというのが作文の勉強の特長です。
小学校3、4年生のころに、家族で作文の課題をもとに毎週対話をする習慣を作っておくと、その習慣を小学校高学年の難しい作文課題になったときも延長して続けていくことができます。小学校3、4年生の課題では、子供が自分の経験だけで書くこともできますが、小学校5、6年生の難しい課題になると、子供の経験だけでは実例が見つからないということも増えてきます。
例えば、小学校5、6年生では、受験作文の課題に出てくるような抽象的なテーマが多くなります。「思いやり」「努力」「自立心」などというテーマになると、子供自身の経験だけでなく、親の経験談が作文の内容を深める役割を果たします。
しかし、家族で特に対話をする習慣のなかったような子供の場合は、小学校5、6年生になってから急にそういう話を切り出すことがなかなかできません。親子の対話が本当に必要になる高学年のころに、その対話の習慣を作るのでは間に合わないことも多いのです。そこで、小学校3、4年生のころから対話の習慣をつけておくことが大事になってきます。
自由な題名から、題名課題、感想文課題に上手に移行するためには、作文を書いたあとの対応も工夫していく必要があります。特に感想文課題のときは、これまで自由な題名で上手に長く書いていた生徒が、急に短くしか書けなくなってきます。その場合、子供本人がうまく書けなかったと自覚しているので、周囲のお父さんやお母さん、そして先生が、「感想文課題は難しいから、字数は短くてもいい」ということと、「こういう難しい勉強に取り組むことに意義がある」ということを子供にしっかり伝えていく必要があります。
そして、感想文課題のときも、お父さんやお母さんに似た話を取材できるように、毎週の長文を音読し、子供が自分なりにその長文の内容を把握しておくことが必要になります。授業の前に長文を1回だけ読んで、自分の経験の範囲だけで書くのでは、感想文課題はなかなか書けません。作文の勉強というのは、作文を書いている1時間の勉強だけではなく、そのために長文を読んで家族で対話を交わすという準備の時間も勉強に入ります。その準備のときに、作文を書く力がついてきます。そして、それは、やりがいのある楽しい準備なのです。
(つづく)
facebookの関連記事。
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=484303588282477この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森の特徴(83) 小学校低学年(79) 生徒父母向け記事(61) 対話(45)

今日の記事は漫画です。
小学校1、2年生から作文なんて、まだ早いと思っている人が多いと思いますが、中学生や高校生になるまで長く続けられる子は、小学校1,2年生のころから始めた子が多いのです。
それは、なぜかというと、学年が上がり課題が難しくなっても、それまでに書き慣れているので、その難しい課題も自然にこなしてしまうからです。
逆に、中高学年になってから始めると、難しい課題になると詰まってしまうことが多くなります。
というのは、言葉の森では、小学校3年生から感想文の勉強が入り、小学校5年生から受験にも対応できる難しい感想文が入ってくるからです。
そして、中学生では意見文、高校生では論説文と、課題はどんどん高度になります。
作文の勉強というのは、問題を解く勉強と違って、自分の中から書くものが出てこないと進みません。
だから、作文のような主体的な勉強こそ、低学年からスタートする必要があるのです。
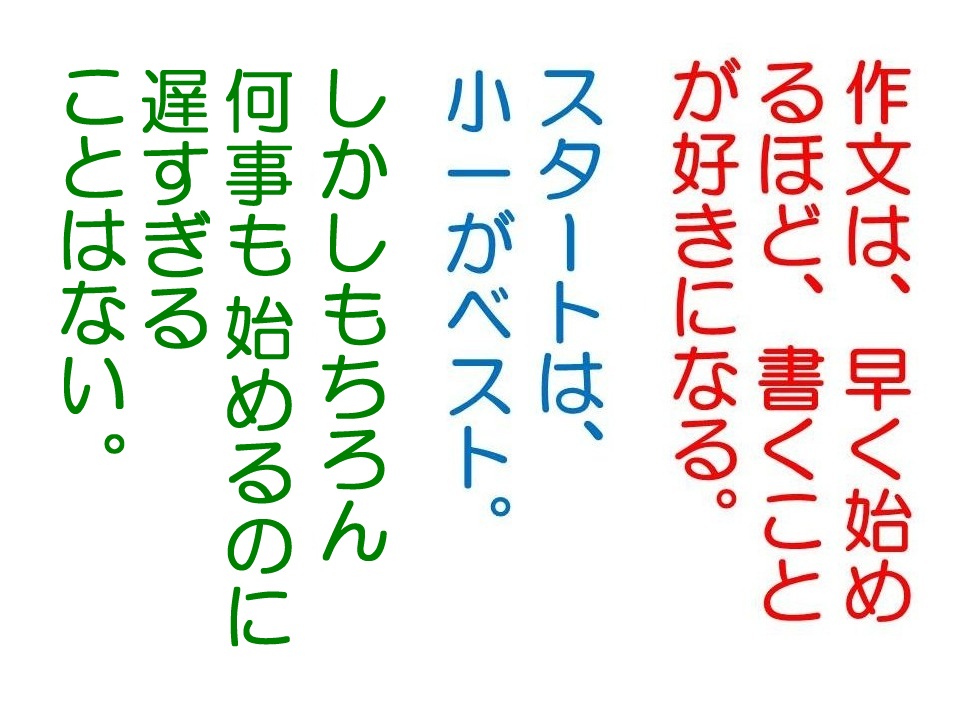

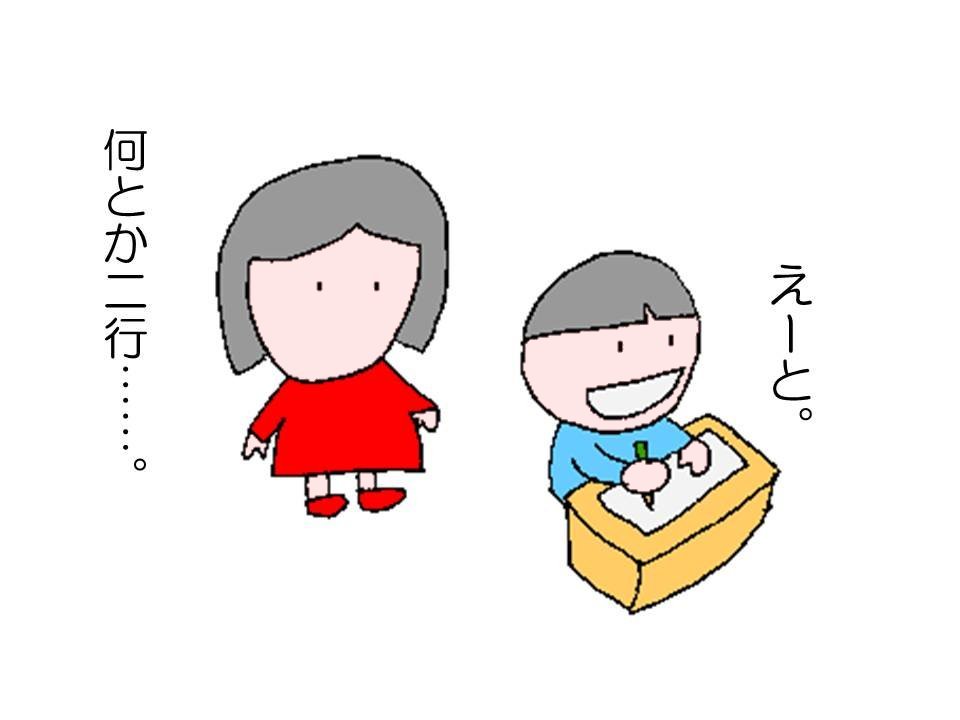







以下は、今日のfacebook記事からの引用です。
====
勉強を長く続けられる子の共通点は、小学校低学年の早めの時期から始めていることです。
しかし、学年が上がり勉強に飽きる子の共通点は、小さいころに勉強をさせられすぎていることです。
ここから出てくる結論は……。
早めに始めて、楽しく続ける、ということです。
言葉で言うのは簡単ですが、これがなかなか難しい。
早めに始められるようなお母さんは、どうしても熱心になりすぎで、楽しく続けられるお母さんは、スタートが遅くなりがちです。
だから、大事なことは、勉強の内容を絞って、その絞ったことだけを確実に毎日続けることです。
その絞った勉強の中でいちばん大事なのが読書と対話です。
読書や対話というのは、勉強のように見えないかもしれませんが、子供たちの思考力を育てる最も重要な要なのです。
今日は、ちょっと雨模様。
しかし、暖かい雨なので、草木の春の準備のようなお湿りです。(先日の大雪とは大違い。)
もうすぐ新年度です。
草木も、人も、新しいスタートに向けて動き始めているようです。
それでは、今日もいい一日をお過ごしください。
====
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。小学校低学年(79) 作文教育(134)

国語力をつけるいちばんのポイントは、難しい文章をしっかり読むことです。
国語の成績を上げるテクニックのようなものはありますが、それらはすべて枝葉の技術であって、受験前の短期間でも身につくものです。しかし、技術が身につくといっても、それはその生徒のもともとの実力の範囲までであって、そのもともとの実力が難しい文章を読んでいるという蓄積なのです。
国語力と運動力は似ているところがあります。
あるところまで力がつくと、その力が持続できるというところもありますが、同時にメンテナンスをしていないと、やはり力は落ちるのです。
小学校低中学年のころに国語の成績がよかったが、高学年や中学生になって成績が下がり始めたとすると、それは学年が上がるにつれてその学年にふさわしい読書をしていなかったということになります。
しかし、ここで問題になるのは、低中学年のころの読書は誰でも楽しく読めますが、高学年や中学生にふさわしい読書は、なかなか読めないということです。それは、そういう本を読む機会自体があまりないからです。
そこで、役に立つのが問題集読書です。これは、入試問題集の問題文を読書の補助として読んでいく練習です。実は、入試問題集の文章というのは、読む力がある生徒にとっては興味を持って読める文章なのです。
ところが、入試問題集の文章は、受験生を対象にしているので、最低限のルビしか振ってありません。そのため、5年生の生徒が中学入試問題集を読もうとすると、読めない漢字が結構出てきます。
そこで、言葉の森が考えたのが、漢字の読みだけを学年を先取りしておくという勉強法です。漢字の書き取りも、もちろんできるに超したことはありませんが、大事なのは読みの力の方です。
読みだけを先行させる教材として開発したのが、教育漢字集と常用漢字集です。これは同じような性質の漢字を並べて、イメージを描きながら暗唱できるようにした漢字集です。
https://www.mori7.com/kg/koku/kk.pdf
https://www.mori7.com/kg/koku/jk.pdf
中には、面白いつながりのものがあります。
例えば、小3の漢字で、「九州 県央 空港 世界」。九州から世界へ飛び立つ感じで暗唱できます。
また、小4の漢字で、「氏名、順番、着席、配置」。これも、教室で勉強の始まるような感じがわかると思います。
小5の漢字で、「女性、婦人、美容、素敵」。これは。そのままです。
常用漢字では、「昆布、漬物、釜飯、飽食」。食べ過ぎに注意というイメージです。
こういうつながり方の約50文字を暗唱して、それを読めるようにするとともに、暗写で書けるようにするというのがこの漢字集の使い方です。
言葉の森で作ったオリジナルの漢字集ですが、ホームページにアップロードしているので誰でも使えるようになっています。
PDFなので、ちょっと重いため、表示されるまでに少し時間がかかるかもしれません。
本当はphp版(html版)の方が縦書きで軽く表示できるのですが、まだ縦書き表示のブラウザが限られているために、php版とpdf版を両方併用しています。
言葉の森では、この春からこの漢字集の取り組みを強化して、子供たちがなるべく早く入試問題集のような難しい文章を楽に読めるようにしたいと思っています。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。漢字(17) 問題集読書(33)

●目標の明示化、数値化、集計化の共有
子供が小学校低学年のころは、親子だけで勉強を進めていくことができます。しかし、小学校の中学年や高学年になると、子供ひとりでは、勉強に張り合いが持てなくなってきます。
そこで活用できるのが、友達と一緒に取り組む勉強です。子供時代は、他人も同じことをしているというだけで、そのことに対して意欲を持ち続けられる時期です。単に誰かが一緒にいるだけで、やる気になるのです。学校や塾での勉強が進みやすいのも、そういう事情があるからです。
そこで、家庭学習でも、近所の子供たちと一緒に勉強するという方法が考えられます。親が先生のように何かを教えるという形の勉強ではなく、子供たちの自学自習を見守るという勉強ですから、勉強中には私語を慎むなどというルールさえ決めておけば、誰でもこの勉強法に取り組めます。この場合、学年が違っても問題はないので、兄弟のいる家庭では、兄弟が一緒に勉強するというだけでも、家庭学習を進めやすくなります。もちろん、学年の近い子が一緒にいれば、それだけ意欲は持ちやすくなります。
●グラフ化による実感
集計した数値は、簡単に棒グラフや折れ線グラフで表せるようにします。数値化の利点は、このようにビジュアルなものに変換できることです。
一般に、勉強にビジュアルな要素を持たせようとすると、教材の段階からの工夫が必要になります。現在の通信教材などの中にはそのように工夫をしているものが数多くありますが、教材に最初から盛り込まれたビジュアルな要素に頼っていると、そういう教材がないと勉強できないということになります。
勉強の基本は、自分で選んだ教材と方法で自分なりに勉強することですから、シンプルな教材でも自分なりに楽しく取り組めるように工夫する必要があります。その楽しさが、数値化に基づいたグラフ作成なのです。
●自習表を活用したグラフ作成
言葉の森の港南台通学教室では、生徒が自分なりの自習をできるように、作文ノートの末尾に簡単な自習表を作ってもらうようにしています。
自習の中心になるのは、音読、暗唱、読書ですが、このほかに、算数・数学や英語の自習をしている生徒もいます。この自習の内容は、本人が決めるものですから、無理のない範囲で自由に決めることができます。最低限共通して取り組むものは、読書を毎日10ページ以上することですから、誰でもそれなりに自分の自習表を作ることができます。
この自習表で、その日の自習のできたところに本人が○又は◎をつけ、保護者のサインをもらってきます。それを1週間分、先生が見て先生もチェックをします。
◎や○や×がついた自習表だけでは、集計をしていないので、推移や比較などがわかりません。そこで、◎や○の数をもとに棒グラフや折れ線グラフを作ります。こうすると、自分の勉強の跡がビジュアルに確認できるので、毎日の学習が意欲的に続けやすくなります。
また、勉強の最中は、タイマーなどを利用して、自分の決めた時間内にできることを目標にします。これも、意欲的に取り組む動機になります。
勉強の進み具合が自分の目で見られるようになると、外部からの強制や競争、「早くしさない」などの催促がなくても、自然にてきぱきと勉強に取り組めるようになります。これが、理想的な自学自習の方法です。
そして、週に1回の教室での授業の際に、それらの成果を生徒どうしで共有して楽しめる機会を作れば、意欲化は更に進みます。通信の生徒の場合は、ネット利用をうまくコントロールすれば、ネットを利用して成果を共有することができます。
■言葉の森の今後
言葉の森では、創立以来、作文の指導だけを行ってきました。幼稚園生から社会人までの作文専科の教室です。
なぜ作文専科かというと、ほかの教科の勉強、つまり国語、算数・数学、英語などは、勉強するための教材も方法も世の中に豊富にあるので、教える必要はない思っていたからです。答えのある勉強は、自分で答え合わせをして進めることができるので、他人が教える必要はないと考えていました。
しかし、今は、教材が豊富にありすぎて、かえって勉強の仕方が混乱している時代のようです。低学年のころから、学習塾に通ったり通信教材をやったりしている子の中に、いろいろなことをやって忙しいわりに本当の実力がついていない子が増えてきたのです。
子供たちの中には、低中学年なのに勉強が忙しくて読書の時間が取れないという子も出てきました。低中学年のころは、勉強など何もしなくても読書さえしっかりしていれば心配はありません。逆に、本を読んでいない子は、低中学年のころにいくら成績がよくても、それがあとまで続きません。
このようなことから、簡単にできて実力のつく正しい勉強の仕方を、作文指導のオプションとして行うことしたのです。
これからの時代は、個性の時代です。単にみんなと同じような勉強が、みんなよりもよくできるだけでは不十分です。勉強しか取り柄がないということでは、社会で自分らしく活躍することはできません。しかし、勉強ができずに個性だけがあるということでも困ります。それでは、社会に役立つ個性にはなりにくいからです。
勉強もできて、遊ぶ時間もたっぷりあり、自分の個性を伸ばしていける、そういう教育の環境が求められています。
そんな新しい勉強のスタイルを、家庭学習を進める形で作っていきたいと考えています。
(おわり)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92) 勉強の仕方(119)