
最近、小学5、6年生から、言葉の森受講の問合せが多くなっています。公立中高一貫校で作文試験があるためだと思います。
大手の学習塾や通信講座でも、最近作文指導に取り組むようになっていますが、それらの指導の多くは、言葉の森が昔からホームページに掲載している指導法を真似たようなものです。
これは、国語の読解の勉強法も同じで、学習塾や通信講座でやっている、要約の仕方、読解問題の解き方、記述問題の書き方などは、言葉の森が昔からホームページに掲載しているようなものです。
しかし、それはそれでいいのです。言葉の森は、できるだけ多くの人が利用できるように、オリジナルに作成した教材の多くをオープンにしているからです。
ところで、教材というハードな部分は誰でも真似ができますが、実際の指導というソフトな部分では、伝えにくいノウハウがあります。
特に、作文の勉強は、他の教科の勉強と違い、「書き方がわからない」「なかなか書き出せない」「途中でどう書いていいかわからなくなった」「時間がかって終わらない」「一応書けているが物足りない気がする」「書き方を注意したら書かなくなった」など、勉強の中身ではなく勉強の周辺で解決しにくい微妙な問題が次々と出てきます。
そのときに役立つのが電話指導です。また、言葉の森では、担当の先生からの電話だけでなく、事務局でも随時電話相談を受け付けています。
事務局に相談するのは、お母さんが、どう対処していいかわからなくなってということが多いのですが、そういう難問のほとんどは、簡単なアドバイスで解決してしまうことが多いのです。
本当は簡単に解決できることを時間をかけてこじらせて、親子でくたびれているケースが意外と多いのです。
そこで、4月から、体験学習中の生徒の保護者と、入会したばかりの生徒の保護者に、事務局から、授業のあとの電話のフォローを入れることにしました。その電話フォローで改めてわかったことは、どの家庭も作文の勉強のさせ方で、共通して勘違いしたやり方をしてしまうことが多いということです。
どんなことがあるかというと、まず、子供の書いた作文のおかしいところを、すぐに注意したり直したりしてしまうことです。
直して上手になるぐらいなら、誰でも簡単に作文指導ができ、日本中の子供たちはみんな作文が得意になっているはずです。ところがその反対に、作文指導に熱心な先生が教えるほど、作文の苦手な子が増えてしまうのです。
直せば上手になるというのは、作文の勉強の勘違いのいちばん大きいものだと思います。
では、直さないで、どうやって上手にしていくのでしょうか。(つづく)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。公立中高一貫校(63)

この連休明けに、言葉の森のホームページをスマートフォン対応にしました。
パソコンの画面で見ると、横幅が900ピクセルぐらいになっているだけで変化はあまりありませんが、スマートフォンで見ると横幅が半分ぐらいのサイズになり、文字も少し大きくなります。また、縦に3列の画面が1列だけになるので、そのままずっと下まで見ていけば全部の画面が見られるようになります。スマートフォンよりも少し画面が大きいタブレット端末の場合は、スマートフォンよりももう少し幅が広くなります。
これからのインターネット利用は、パソコンよりもタブレットやスマートフォンが主流になると思います。
今後、ほかのページもスマートフォン対応で見やすいものにしていく予定です。
しかし、スマートフォン対応の先にあるものは、グーグルグラスのようなウェアラブルコンピュータになると思います。
目の前に広がる景色のような感じのモニター画面になるので、マウスやキーボードなども変わります。たぶん手袋をつけて、バーチャルな画面を手で操作するような形になるのでしょう。
画面のサイズは、理論的には360度ですから、インターネットの世界はますますバーチャルリアリティの世界になっていきます。
こういう世界で大事なことは、知識やお金や物や消費ではなく、自分の手で何かを作り出すことになります。
世の中は、大きく変わるように見えますが、実は科学技術の進歩のあとに、だんだんと人間本来の姿に戻っていっているのだと思います。
(写真はCNETより)
http://japan.cnet.com/news/service/35031656/19/
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。インターネット(25) 言葉の森サイト(41)

タブレットPCを使った作文教育の利点について考えてみました。
第一は、図や絵を同時にかけるということです。文章を書く前に、自分がやこれから書こうと思うことを図示できるように考えておくことが大切です。簡単なメモのようなものであっても、事前に全体の構成を考えて書き出すのと、何も考えずに書き出すのでは文章のまとまりに大きな違いが出てくるからです。そのときに、手書きが役に立ちます。
第二に、手書き入力をして、その手書きの文字を文字認識する形で書いていくと、自然に読みやすく丁寧な字を描くようになります。字の丁寧さは、人間が「丁寧に書きなさい」と何度も言ってもなかなか直らないのが普通です。しかし、機械が丁寧に書かれた文字しか正しく認識しないということになれば、子供は自然に丁寧に書くようになります。
第三に、漢字を覚えるようになることです。手書きで書いた文字を変換すると、漢字の候補が出てきます。これまでは書けない漢字があると、人に聞くか辞書で調べるかしかありませんでした。手書き入力した文字を変換するのであれば、手間をかけずに自分の書こうとする漢字を調べることができます。
第四に小学校低学年の生徒でも普通の漢字かな交じり文をテキスト形式で書けるので、森リンのような自動採点ソフトが使えます。文書の評価は人間が行うと、甘くなりすぎたり辛くなりすぎたりしますが、ソフトによる評価は客観的なので、文章力を向上させる励みになります。
第五に、これからの文章はただ文字を書いて埋めるだけではなく、その文章に写真や画像や音声などの様々な表現手段を組み合わせるものになってきます。文章を書く目的のひとつは、他人に感動や情報の中身を伝えることですから、文字以外の様々な表現媒体も併用していく必要があります。
言葉の森では、今後タブレットパソコンと手書き入力を活用した作文の指導法考えていきたいと思っています
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。インターネット(25)
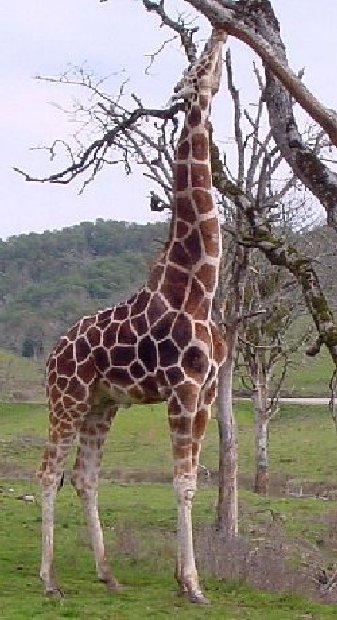
小学校6年生の子生徒のお母さんから、森リンの点数についての質問がありました。表現語彙はとても高いが、思考語彙が少ないために点数がなかなか上がらないということです。
これは小中学生であれば、多くの人が感じていることだと思います。森リンは大学入試の小論文の評価に合うように作られているので、作文に書くテーマ自体が難しいものであることを前提にしています。すると自然に、作文の中に、実例だけでなく、その実例の裏付けになる説明や考えを書くようになってきます。
ですから、今、小中学生で思考語彙の点数が低い人でも、課題がこれからだんだん難しくなり、その難しさに合わせた文章書いてると自然に思考語彙の点数が上がってきます。
言葉の森の「森リンの丘」というサイトに、小学校1年生から高校3年生・社会人までの代表作品が学年別に載っています。(ただし、小学校4年生までの作品は、上手な作品を掲載すると、そのことによるマイナスの方が大きいため今は載せていません。お母さんやお父さんが、子供に、「こういうふうに書いてみなさい」と言うことが多く、ほとんどの子供がそれによって劣等感を持ってしまうからです。)
ここで、高学年や中学生、高校生の作文を見ると、森リンの点数がどういうふうに上がっているかが分かると思います。
思考語彙の点数を上げるコツは、実例だけでなく説明や意見を書くことです。ですから、接続語や助動詞の使い方が大事になってきます。
接続語いうのは、「例えば」「しかし」「だから「すなわち」「したがって」「言い換えれば」「つまり」「わかりやすく言えば」など、自分の書いた文章を、別の言葉で言い換えるような内容を書いていくことです。
助動詞というのは、「だろう」「に違いない」「かもしれない」「のはずだ」などの言葉です。思考語彙というと、「思う」とか「思った」という言葉を考えがちですが、森リンの点数は、同じ語彙は1種類として数えるので、「思う」がたくさん使われていても思考語彙が増えたことにはなりません。いろいろな言い方で自分のい考えた内容を表していくのが大事です。
ところで、森リンの点数を上げる上でいちばん大事なことは、やはり難しい文章を読むことで、自然に難しい語彙を使えるようになることです。
個々の作品んついては、点数が高かったり低かったりしますが、年間を通してみると、真面目に勉強している生徒は、必ず右肩上がりに点数が上がっていきます。
以前、ひとりずつの生徒に、その棒グラフをフラッシュで表示していたのですが、フラッシュの使用をやめたので、いまはその棒グラフが表示されていません。今後、html5のグラフ機能で、各人の作文の進歩が一目でわかるようにしていきたいと思っています。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森リン(103)

(クリックすると大きくなります)
ウェブの生誕何十周年だとかいうことを聞いたので、昔の言葉の森のページを見てみました。
1996年9月に開設したのですが、そのころの画面はなく、1年後の1997年の画面がありました。
今とあまり変わらない……(笑)。
中央やや左にかいてあるモグラのような得体の知れない動物は、当時小2の子がかいた「コモリン」という名前の想像上の生き物です。
http://web.archive.org/web/19970502140902/http://www.mmjp.or.jp/shine/
これを見ると、当時からかなり進んだページを作っていたのだとわかります。
その後、開発をしていなかったので、今はかなり遅れていますが。(^^ゞ
しかし、これからまたがんばっていきたいと思っています。
これから作るのは、スマートフォンに対応したページです。
しかし、その後の流れを予測すると、たぶんスマートフォン対応のページというのは将来なくなると思います。
昔、携帯対応のページというのがありました。文字だけの軽いページでしたが、その後スマートフォンがリッチなページを表示できるようになると必要なくなってしまいました。
今、スマートフォン対応のページが必要なのは、スマートフォンで見ることのできる画面が小さいからです。
ところが、今、googleが開発しているグラスは、たぶんウェブをスマートフォンの画面で見るのではなく、眼鏡の中で見るのだと思います。(あくまでも推測)
すると、サイズの制約というものはなくなります。
そして、サイズの制約がなくなるどころか、360度すべてがウェブの画面として表示されるようになります。ほとんどマトリックスの世界です(笑)。
インターネットの進歩は速いので、追いつくことを考えるよりも、新しい展開を予測して先取りしていた方が楽しいと思います。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。インターネット(25) 言葉の森サイト(41)

小学校低学年の勉強で大事な事は、長時間はやらないこと、毎日やることとです。
そして、一度始めたことはできるだけ長く続けるようにすると、そのほかの勉強も、勉強以外の生活もいろいろなことが継続しやすくなります。「継続は力なり」という言葉はよく言われることですが、これは勉強でも人生でもいちばん大切なことだと思います。この継続が習慣を形成し、習慣が第二の天性を形成するのです。
言葉の森で小学校低学年から勉強を始めた子は、誰でも途中で一度や二度はスランプに陥ることがあります。ある学年のときに、その前の学年よりも字数も森リンの点数も下がるということがあります。しかし、そういうときでも細く長く続けていた子は、その後必ずまた再び実力を伸ばしていくようになるのです。
そのようにして、高校生まで勉強続けた生徒は、文章を書くことに対する自信がついてきます。文章力は大学入試の小論文試験などで使うこともありますが、それ以上に社会に出てから大きく役に立つものです。
なぜこういうことを自信を持って言えるかというと、小学校低学年から高校生以上まで続けた生徒をたくさん見てきたからです。その反対に、途中でやめてしまった子は、その理由がどうであれ、やはりもったいないと思います。受験などで多忙のためにいったん退会せざるをえなかった生徒は、また時間を見てできるだけ早い時期に再開するといいと思います。
この高校生まで継続する力が、小学校低学年のころの勉強の仕方にあります。
低学年の勉強で大事なことは、成果を上げることではありません。成果を上げようとすると、どうしても長時間勉強をさせたり、難しい問題をできるようにさせたりしたくなります。大事なことが成果をあげることではなく子供が自分の力で毎日勉強する習慣を作ることです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。小学校低学年(79) 勉強の仕方(119)

鳥インフルエンザが問題になりそうな時期に、あまりいい話題ではないかもしれませんが、教室の近くに来ている野鳥たちの話です。
言葉の森の通学教室では、昔オカメインコや文鳥を買っていました。ヒナから育てた手乗りのオカメインコや文鳥なので、よく教室の中を自由に飛び回っていました。
しかし、オカメインコや文鳥は、もともと南の国にいる鳥なので、日本の冬の寒さには屋外では耐えられません。そこで今はペットの小鳥ではなく、言葉の森の近くに来る野鳥たちを手なづけることにしました。野鳥といっても、スズメやハトやカラスやツバメです。
でも、この中でカラスだけは、性格のいいカラスと悪いカラスがいるようで、性格のいい方の(たぶんハシボソガラス)は温和なのですが、性格の悪い方のカラス(たぶんハシブトガラス)は、ほかの鳥たちをいじめるようなのです。やがてその性格のいい方のカラスも来なくなってしまいました。そこで、カラスはペットからは除外。
毎朝餌をやっているうちに、スズメたちはだんだん慣れてきて、お腹がすくと窓の外で鳴き出すようになりました。やがて、そのスズメが言葉の森の建物の東側にある電気メーターに巣を作ってしまいました。電気メーターなので、たぶん冬でも温かいのでしょう。先日、その巣からヒナのスズメが飛び出してきました。
今は住宅事情でペットを飼えない家庭も多いと思いますが、子供たちはみんな動物好きです。マンションなどでもベランダに小鳥たちの巣を置いておけば、家でペットを飼わなくても、自然にいる生き物たちと接する機会が増えるのではないかと思いました。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
スズメなら私の住んでいる東京でも見かけます。
夏のある日の朝散歩でマンションに住んでいるのでマンションのそこら辺をうろちょろしていると見かけない声がしたので探してみるとすぐに見つかりました。招待は野鳥のそこら辺を飛び回っているスズメでした。私は興味本位で追いかけまわしました。もちろんスズメはびっくりしてそこら辺を逃げ回り捕まえるのに結構な時間と筋肉を使いました。(笑)帰ってきてすぐ学校に行ったので机の上でぐだーっと白目見せながら寝ていました。学校の友達のMちゃんからは本当に大丈夫と言われました。これからもスズメをあちこち頑張って探し回ろうと思います。
スズメが都会で最近少なくなったのは、巣を作れるような空間が、今の家にはなくなっているからのよう。
公園に巣箱などを設置してあげたらいいのにね。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教室の話題(26) 息抜き(19)

5月1日のfacebook記事に、手書きの話を書きました。
どうやって書いたかというと、手書きで書いたのです(笑)。
やり方は、まず、スマートフォンでNoteAnytimeβを起動。mazec2βという文字認識ソフトとつなげているので、指で書いた文字がすぐに認識されます。
(いずれのアプリも、android、iOSに対応しているようです。このアプリを作ったMetaMojiは、一太郎の浮川さんの作った会社です。さすが。)
同音異義語の変換と選択という作業がないので、キーボード入力より、考えの流れが中断されません。これは、日本語入力にとって画期的なことです。
英語などは、同音異義語が少ないので音声入力も簡単なのですが、日本語の音声入力は、同音異義語に加えて漢字で書くか仮名で書くかという選択もあるので、かなり大変です。
その点、手書き入力はそういう煩わしい、文章を書くのに本質的なことではない操作で頭を悩ますことがありません。
手書きで書いてテキスト変換した文章をコピーして、そのあとtumblrというブログサービスに投稿してみました。これでインターネットに接続すれば、いつでもどこからでも利用できます。
手書き入力の利点は、文字以外に、絵や図も簡単に書けることです。そして、小学校1年生でも、テキスト入力ができることです。
漢字変換機能もあるので、自分の書いたひらがなの文字を漢字に変換すれば、漢字も覚えられます。(たぶん、そういう勉強的な使い方をする子はあまりいないと思いますが)
これで何がいちばん変わるかというと、小学校1年生から森リンという小論文自動採点ソフトを使えるようになることです。森リンは、文章を解析して、表現の多様性や思考性や語彙の難易度を数値で表します。だから、自分の書いた文章が客観的にどういうレベルにあるかということを判断できます。
これまでの作文指導は、人間が評価する形しかありませんでした。人間が評価するときのいちばんの欠点は、評価力のない人が文章を評価すると、欠点を指摘するだけで終わってしまうことが多いというです。これで、多くの子が作文嫌いになってきたのです。
これから、家庭でもタブレット端末を使うことが多くなると思います。
たぶん、今年あたりから、小学校1年生の子が、自分で手書きで書いた作文を、言葉の森の「作文の丘」からテキストで送り、「今日の作文の森リン点は、80点だった」などと喜ぶような日が来るのではないかと思います。
【参考ページ】(宣伝するわけではありませんが)
「あらゆる端末で使える手書きノートアプリNote Anytime」
http://product.metamoji.com/ja/anytime/

====facebook記事、ここから。
これからは手書きの時代になりそうです。
特に日本語は音素数が少ないので、同音異議語が多いからです。
それがダジヤレを作りやすいという利点にもなっていますが。
むかーし、十五年程前ですが、やはリタブレットで、小学校低学年の子に手書きでパソコン入力をしてもらったことがあります。
当時の子供たちが今年ちょうど大学四年生ぐらいです。
そのころはまだ機能が低くて手書きはストレスがたまりました。
でも、今の手書きは全く快適です。
たぶんこれからの作文は、タブレット作文になると思います。
もう、字がきたないとか、漢字を使わないとかいった小言はなくなります(笑)。
キーボードの歴史は、せいぜい数十年。手書きの歴史は、その百倍はあります。
新しいツールによって古い文化がよみがえってきたのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。小学校低学年(79) 森リン(103) インターネット(25)