
小6の部
小6の「ふふふ」さんの作文の森リン点は80点でした。(思考語彙43点 知識語彙75点 表現語彙78点)
この作文のよいところは、お母さんに取材した実例が生きていることと、「物には……」というように感想を一般化して大きく書いていることです。たとえや結びの表現もよく工夫しています。
私だけの宝物
ふふふ
私は、九歳の誕生日から三年以上ずっと同じ筆箱を使っている。クラスの皆は毎年、新しい筆箱に替える。それは、筆箱というよりもポーチ形やペン立てにもなるケースだ。可愛いキャラクターが描かれており、さらにたくさんのキーホルダーをジャラジャラとつけている女の子もいる。中はカラーペンやシャーペンでパンパンになっている。だが、私のは赤の牛革でできていて、普通の長方形の筆箱だ。中には鉛筆五本、赤青ボールペンに消しゴム、定規しか入っていない。そんな筆箱を見ると、友達は、
「なんか一年生の筆箱みたいだね。なんで変えないの?」
などと、言ってくる。だが、私はシンプルで使いやすいこの筆箱をとても気に入っていて、大切に使っている。
この筆箱は、九歳の誕生日プレゼントとして、母からもらったものだ。
「大切に長いこと使ってね。できたら、中学三年生まで使ってくれたらうれしいな。」
と、言われた。ちょうど一年生から使っていたピンク色のクラリーノの筆箱のふたがベロンとむけて、壊れかけていたからだ。私は、母にどうしてこの筆箱を選んだのかを聞いてみた。
「ママが小学校に入学する時、おばあちゃんがえんじ色の革の筆箱を買って来てくれたの。でも、ママは『そんなのより、もっと可愛いのがいい~』と言って泣いたの。それでキキララの筆箱を買ってもらって、それを使ったんだ。しょうがないから、その筆箱はおばあちゃんが今でもずっと使っているんだよ。」
と、母は教えてくれた。
「えっ!そんな前から使っているの?その筆箱、見たことあるよ。」
と私は驚いて言った。
「ママはその時、全然わからなかったけれど、大人になって、良いものを大事に長く使った方がいいと分かったから、それを知ってほしくてプレゼントしたんだよ。」
「物には魂が宿る」とよく聞く。確かに一つの物を長く大切に使っていると、それがあるだけで気持ちが落ち着いたりすることがあると思う。長く大切にされた古いものは味わいや気品みたいなものが感じられると、アンティークが好きな母は話してくれた。古くて大切にされたものは、人間にとって、その人にしかわからない大切な物になる。私の筆箱は、他の人には可愛くない古ぼけた筆箱に見えるだろう。でも、私にとってはあると落ち着くし、ずっと一緒に勉強してきた仲間みたいなものだ。だから、ずっと大切にしていきたい私だけの宝物だ。
私はまた今日も、赤い筆箱を開く。
「今日も一日、勉強、頑張るか!」
中2の部
中2の「しろめウサギ」さんの作文の森リン点は85点でした。(思考語彙56点 知識語彙65点 表現語彙83点)
複数の意見を総合化した形でよくまとめています。
桃太郎の昔話の実例が、構成に広がりを与えています。このように話題を広くとりながら、しかもひとつの意見にまとめていくのが構成力のあるところです。
面白さと魅力
しろめウサギ
今の私たちの 「流行」といえば、スポーツ関連のモノだろう。例えば、ラグビー。今まではニュースなどでラグビーを見たことがなかったが、ワールドカップのあの活躍ぶりに日本人を心を躍らせた。これまでも同じようなことはことはいくつもあった。サッカー・野球・水泳・・・。どれも本当に素晴らしいのだが、その「流行」は長くは続かなかった。流行はスポーツの場合、いい成績を残したとき・チームの中に特徴的な人がいたとき、○○フィーバーなどと呼び、日本人は跳ね上がった。しかし、ほかの競技で新しい成績が残ると、日本人の木はすぐにコロッと変わってしまうのだ。こうして流行は長くはつづかなくなってしまう。これからも「流行」は長続きはしないのだろうか。
流行のモノは多くの人の気持ちを引き付ける力がある。日本には流行語大賞というものがある。その一念でよく使われた言葉・印象的だった言葉を決めるものである。その流行語が決まった後のテレビは特にすごい。その言葉を残した、お笑い芸人のネタや、スポーツ選手。その人たちばかりがテレビでよく見かけるようになるのだ。流行語の言葉の引用のされ方はそれぞれであるが、人から人へ、メディアを通して日本中に知れ渡るのだ。スポーツやお笑いに興味はなかったとしても、流行語となった言葉だけはなぜか知っていて、よく使うという人は少なくはないだろう。「流行」がひきつける言葉の引力はとても強いものだと思った。
一方、古典のモノが長い間愛されてきたのは、それだけの魅力があるからだ。音楽で言うと、バッハやベートーヴェン・ショパンやほかのさまざまな作曲者の曲が約200~500年もたった今でも聞かれ続けている。歴史的には、その長い年月の間にたくさんの事件が起こっているのに、形も変わらず音楽は私たちの心を今でも癒し続けてくれる。長い間人々に愛され続けるものというものは、時代を超えて感じさせられる何かがしっかりとその中に含まれているからなのだろう。昔話の桃太郎は、桃から生まれた男の子。皆さんはここに驚いたのではないだろうか。ありえないことが書いてあったからこそ、日本中の人が桃太郎の話を面白いと思ったのだろう。桃太郎の場合は、その意外さが魅力につながったのかもしれない。
確かに、古典にも流行にもいいところがある。しかし、最も大切なことは、古典や流行などとこだわらずに、自分なりにその魅力を見つけ出していくことだ。「真に良いことは、新聞に大きな騒ぎを起こすことなく、小さく始まる。」という名言があるように、そのものの良さを知るためには、自分なりに解釈してみて、自分なりに魅力を考えてみた方が、より面白さを感じるのだろう。理解して魅力を考えてみれば、想像力も豊かになるし、発想力・脳の回転も速くなる。それを続けてみれば、自分の成長にプラスになるに違いない。
高校生の部
高1の「れたす」さんの作文の森リン点は88点でした。(思考語彙59点 知識語彙87点 表現語彙80点)
個性を大切にするための複数の方法がバランスよく書けています。体験実例も個性的です。
「規則とは、表現の自由を奪うものではなく、人々が快適に過ごすために作られるものである」という光る表現も結びに上手に入れています。
規則規則規則の中で光る個性
れたす
私は、中学校に入学し、初めて生徒手帳を手にした時の衝撃を未だに覚えている。そこには、校則が何ページにも渡って書き綴られていたのだ。
「こんなに決まりごとがあるの?」
と新たな生活に馳せた希望がしゅんとしぼんでしまったような気がした。私たちは、規則に縛られずに個性を大切にすべきだと思う。そのためにはどうしたら良いだろうか。それには二つの方法がある。
第一の方法は、自分自身を表現することだ。私は、小学生の頃からピアノを習っている。そして、いつも教わっている先生に勧められ、中学一年生と二年生の時に作曲し、それを発表会で披露したことがある。普段は誰かが作った曲を弾いていて、強弱記号など楽譜に書かれていることを分析し実際に表現していくことはとても難しい。しかし作曲は、その何百倍も難しかった。まずどの音から始めれば良いかがわからない。また確固たるテーマがないと、部分的に出来上がっていくだけで、それぞれを合わせた時、違和感が生まれてしまう。そこで、私は一日の様子を音で表現しようと考えた。初めは明るく、穏やかな感じをイメージし、途中からハプニングがあったように不安で、暗い感じをイメージして作っていった。作曲している間、私には今まで感じたことのないような充実感や緊張感があり、自分のイメージに音を近づけていくことがこんなにも難しく、そして楽しいことを初めて知った。これが自分を表現して、他人に伝えるということなのだろう。
第二の方法は、途中経過を大切にする考え方に変えていくことだ。私は、学年が上がるにつれテストの解答欄が大きくなっている気がする。小学校の頃は、ただ答えが合っていればマルがもらえたが、高校生にもなるとどこかの式が抜けていると答えが合っていてもバツにされてしまう。それは、結果だけでなく途中経過も大切にする考え方がポピュラーになってきている証拠である。ここで、学年が上がるにつれて増加するものは解答欄の面積だけではない。例えば、公式の数もそうである。高校生になると、数学だけでなくほぼすべての教科にあらゆる「公式」が存在する。しかもそのうちのほとんどは、覚えているか覚えていないかのグレーゾーンに浮遊しているのだ。それは、どうしてか。おそらく、多くの生徒が形から覚えようとするからだろう。要するにどうしてそのようになるのかと言う疑問を誰も抱かないのである。このように何も考えずに暗記作業を始めるため、短期記憶で終わってしまう。それを長期記憶にするためには、やはりテストの途中式と同じく、公式の途中式を自分で書いたりして、理解しなければならない。私も実際、高校受験の時はそのようにして公式を覚えるようにしていた。だから、公式が思い出せないということもあまりなかったし、あるいは公式がありすぎてどれがこの問題に当てはまるのかがわからないという事態もあまり起こらなかった。このように途中経過を大切にする考え方は、現在の教育にフィットした考え方なのである。
確かに、規則がなければ社会は成立しないだろう。しかし規則とは、表現の自由を奪うものではなく、人々が快適に過ごすために作られるものである。このように、規則の中で生活することに窮屈な思いをするのはおかしいのである。だから私たちは、規則に縛られずに個性を大切にするべきだと思う。私は、また機会があれば作曲に挑戦し、しっかり自己表現ができる人間になりたい。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子供たちの作文(59) 森リン(103)

言葉の森では、2月から、寺子屋オンエアシステム(googleハングアウトとskypeを利用した対話型の学習システム)で、オンエア特別講座を行います。
これは、言葉の森の生徒であればどなたでも参加できます。ただし、事前に、googleハングアウトとskypeの利用できるパソコンが必要になります。(現在市販されているパソコンであれば、簡単な登録だけで利用できるものがほとんどです。)
今回は、初回の講座として試験的に行いますので、受講者はモニターとして募集します。したがって、全2回の参加費用は無料です。また、モニター謝礼として、お子様に1000円の図書カードをお送りします。
講座終了後、保護者の方に、ハングアウトの会合で感想を述べていただくか、又は簡単なレポートを提出していただくことをお願いします。
実施する講座は下記のとおりです。
参加を希望される方は、言葉の森事務局までご連絡ください。(電話 045-830-1177 ファクス 045-832-1466)
googleハングアウトやskypeをまだ利用したことがない方でも、当日までに設定していただければ参加できます。設定の仕方についての資料は別途お送りします。ご希望の方には事前に接続テストを行います。
| 番号 | 講座名 | 対象学年 | 保護者参加 | 1回目 | 2回目 | 内容 |
| 1 | 親子作文講座 | 新幼長~新小2 | 保護者同伴 | 2/22(月)17:00~17:30 | 3/7(月)17:00~17:30 | 作文がまだあまり書けない低学年の生徒を対象に、親子の対話を生かして構成図を書き作文を書く練習をします。この講座で楽しく作文を書くコツを身につけてください。 |
| 2 | 紙折り暗唱講座 | 新小3・新小4を中心に全学年 | 小学生は保護者同伴 | 2/23(火)18:00~18:30 | 3/1(火)18:00~18:30 | 暗唱がまだあまり得意でない生徒を主な対象に、どんな難しい長文でも繰り返し読めば暗唱できるという紙折り暗唱のコツを説明します。暗唱教材は、「春はあけぼの」(枕草子)です。 |
| 3 | 公立中高一貫校講座 | 新小5・新小6 | 保護者同伴 | 2/24(水)18:00~18:30 | 3/2(水)18:00~18:30 | 実際の公立中高一貫校入試の適性問題をもとに、問題の解き方とともに家庭での勉強の仕方を説明します。 |
| 4 | 定期テスト対策講座 | 新中1~新中3 | 保護者の参加は自由 | 2/25(木)20:00~20:30 | 3/3(木)20:00~20:30 | それぞれの生徒の前回の定期テストの分析の仕方と、次回の定期テストの対策の立て方を説明します。テストは匿名にして資料として使います。 |
| 5 | センター国語満点講座 | 新高1~新高3 | 保護者の参加は自由(保護者だけの参加も可) | 2/26(金)20:00~20:30 | 3/4(金)20:00~20:30 | センター試験のような選択式の国語問題の解き方を説明します。実際に問題を解いていただき、そのあと各自の疑問点について解説をします。保護者だけの参加もできます。 |
・時間はいずれも30分となっていますが、そのときの話の様子で15分ほど時間が延長する場合があります。
・参加者には、別途それぞれの講座資料をお送りします。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
子供が本がが大好きで 学校で1番冊数を読んでいます 暗記も好きで家で覚えますが ただひたすら読むので コツがわかればもっと楽しくなると思い応募しました
yamatokoさん、こんにちは。
読書も暗唱も好きなのですね。その得意分野をどんどん伸ばしていくといいと思います。
今度、読書についても、学年別の読書紹介コーナーなどを作りたいと思っています。そこで、ほかの人の紹介で読みたい本があったら、個人間で貸し借りをするような形です。
暗唱は、お母さんも一緒に練習していくといいので(笑)今度の講座でコツをつかんで親子で一緒に楽しんでください。
先日はオンエア2回目の講座を受講しましてありがとうございました。構成図の利点が理解できました。子どもの自己肯定感も作文指導で高められるんだと思いました。学校では内容のふくらませられない課題例えば、動物愛護について書くこと のようにペンが進まない場合はどう進めたらよいのかなと思いました。
iwaさん、ご参加ありがとうございました。
作文の課題は、その年令に応じたものがあります。
事実の経過を書いていくのが小学校低学年で、それを立体的に(似た例を入れたり、説明を入れたりして)書くのが中学年、一般化して(人間や社会の視点で)書けるのが高学年です。
動物愛護というテーマは、高学年向けの説明文、意見文のテーマですから、低中学年ではうまく書けなくていいのです。
お母さんが一緒に構成図で書くときは、親子で具体的な実例を思い出すた形でふくらませていくといいです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101) オンエア講座(41)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
ダウンロードしました。まだよくわかりませんが、勉強などに役立てていきたいと思います。
はーい。ありがとうございます。
スマホアプリの中に、「アプリ連絡」というページがあるので、そちらからも送っておいてください。
よろしくお願いします。
ダウンロードしました。
アプリ連絡の場所が分かりませんので、こちらから送信します。
otowaさん、ありがとうございます。
アプリの方で自動的に集計しているので、すみませんが、アプリの右側にある2ページ目の「アプリ連絡」というところからコードとパスワードを入れおいてください。
ダウンロードしました。教室の生徒にも
すすめました。アプリ連絡のほうは、生徒さん用みたいなのでこちらから連絡させていただきます。
いさきさん、ありがとうございます。
今はまだ一部分しかできていませんが、これから「山のたより」などもスマホで簡単に見られるようにする予定です。
目の体操、やってみました。面白いです。
ホームに戻るボタンがあるとよりよいな、と思います。
言葉の森新聞など楽しみな記事が出先の空き時間などに読めて便利です。
いつもお世話になっております。
高学年からの入会で、数ヵ月が経ちました。
本日ダウンロードしました。
興味深い内容が沢山あり、
これから少しずつチェックしていきたいと思います。
スマホでチェック出来るので便利です。
これからもよろしくお願いいたします。
ゆよた様
ありがとうございました。
これから、更に内容のあるページを増やしていきたいと思っています。
土屋けいすけyoromu0056 20160507
▽
土屋けいすけもダウンローどできました。が、アンドロイド版は、いくらインストールしようとしても、アプリが見つかりません、となってしまっています。アンドロイドでグーグルハングアウトするのに便利そうですが、なくなってしまったのでしょうか?
すみません。
今、googleplayの基準が変わったため、ダウンロードができないようになっているようです。
近日中に、ダウンロードできるようになりますので、そのときにまたお知らせします。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森サイト(41)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
こんにちわ! 長文暗唱のページを初めて拝見いたしました。 娘はまだ年少ですが幼稚園の朝の課程でこの「雨ニモマケズ」と暗唱しております。 2歳の頃から取り組んでいたので年少1学期の時点で完全の暗唱できるようなっております。 意味はわからずともリズムにのってサラサラと暗唱しており、毎日聞く私も暗記してしまいました 笑 今は諺にも取り組んでいるようです。
Shinoさん、ありがとうございます。
幼児から小2までの間は、何でも苦もなく吸収する時機なので、この時期に日本語のいい文章を繰り返し音読暗唱する機会を作っておくとよいと思います。
意味を理解する必要はないので、目標はすらすら読めるようになることだけに置いておくといいです。
なぜ、意味を理解する必要がないかというと、大きくなって必ず意味を知る機会が出てくるからです。
すると、それまで意味がわからずに読んでいた過去の経験が、全部意味を伴って自分の中に残るからです。
それから、暗唱がすらすらできると、つい勉強的な暗唱をさせたくなりますが(笑)、そういう方向には進まずに、いい文章をより長いまま暗唱できる方向に向けていくといいと思います。
ご返信ありがとうございます! いつもためになる記事を拝見し、日々の子育ての指針にさせていただいております。 子供に対する教育というより、自分自身の教育が必要だと感じております。
Shinoさん、こんにちは。
子供と同じように、親も親の役割は初めてなので、いろいろ試行錯誤をしながら柔軟にやっていけばいいのだと思います。
何かあれば、いつでもご相談ください。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)
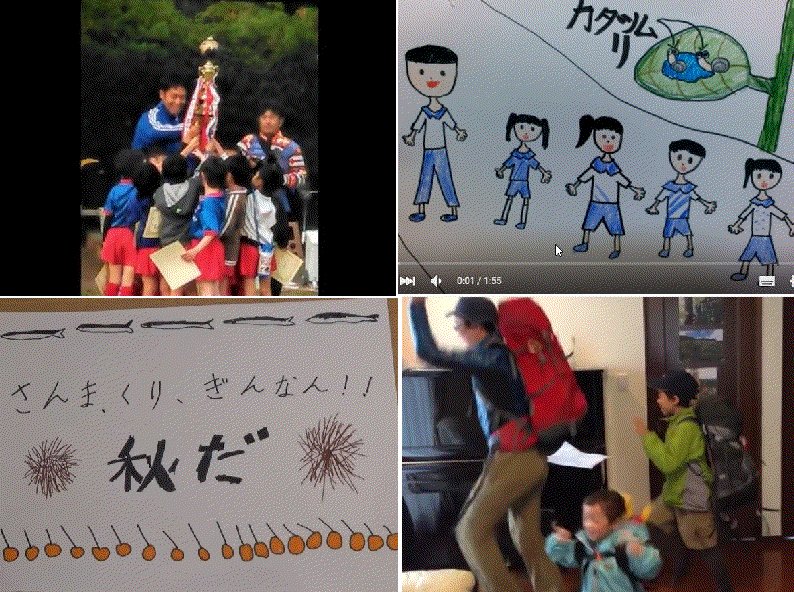
12月に第2回目のプレゼン作文発表会を行いました。
この発表会に参加した言葉の森の生徒で、動画を公開してもいいという承諾のあった人の動画を、「これまでの記録」のページに掲載しました。
▽「プレゼン作文発表会これまでの記録」
https://www.mori7.com/hpk/koremade.php
また、同時に参加した言葉の森の生徒を対象にアンケートを実施し、これも、「アンケート」のページに掲載しました。
▽「プレゼン作文発表会アンケート」
https://www.mori7.com/hpk/anke.php
作文の中心は、もちろん文章ですが、それは表現の手段として文章を使っているということであって、文章を書くことそのものが目的なのではありません。
目的は、相手に伝わるように表現することであって、それを文章でできるようにしているということです。
プレゼン作文発表会は、作文で表現されている内容を、絵や写真や動画や音楽を使って、更に表現を豊かにして発表するという企画です。
言葉の森の生徒のほとんどは通信で勉強していますから、日常的に交流する場はほとんどありません。例外的に夏の寺子屋合宿で会う人もいます、そういう交流に参加できる人はほんのわずかです。
生徒の分布は、日本の場合は、北は北海道から南は沖縄まで、更に海外の生徒もいますから、言葉の森の生徒が一堂に会するような機会はまずありません。
ところが、インターネットを利用したウェブ会議のような形であれば、どこからでも参加できるということが、テクノロジーの発達によって現実的なものになってきました。
言葉の森では、既に、寺子屋オンエアでウェブ会議を利用した家庭学習の指導を行っているので、操作のできる先生はたくさんいました。
そこで、昨年の6月と12月に、プレゼン作文発表会をウェブ会議形式で行ってみたのです。
初めて参加する子供たちもたくさんいましたが、みんな積極的に作文発表と交流を楽しんでくれたようです。
今後、このインターネットテクノロジーを利用した新しい企画を、いろいろな形で提案していきたいと思います。
ところで、言葉の森が、こういう新しい技術を次々に利用できるのは、もとになる作文指導がしっかり定着しているからです。
例えば、言葉の森の生徒が自主的に投稿するコンクールなどでは、毎月何人もの生徒が受賞しています。
▽「入選の滝」
https://www.mori7.com/taki/
また、受験作文コースでは、中学入試から大学入試まで、毎年多くの生徒が合格しています。
▽「合格情報」
https://www.mori7.com/saisou17.php
これからも、長年の蓄積に支えられた充実した指導と、新しい技術を活用した楽しい学習を両立させていきたいと思います。
さて、以下は、言い訳です。
今回は、記事の更新がだいぶ遅れてしまいましたが、それは、激動する社会情勢に対応するために、今後の言葉の森の方針を煮詰めていたためです。
その新しい方針は、ひとことで言うと、ホームページのトップに書いた「明日の日本を支える子供たちを育てる、勇気と知性と共感と創造性の教育」です。
作文指導を土台にして、明日の日本を支える子供たちを育てる教育を進めていきたいと思います。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表交流会(20)

受験作文のい直前の対策と言っても、この時期に新しいことをやるのではありません。ときどき、言葉の森で勉強したものを学校やほかの塾の先生に見てもらう人がいますが、よほどその先生が作文指導に慣れている先生でなければそれはやらない方がいいです。(そういう先生はほとんどいません。)
というのは、作文指導に慣れていない先生ほど、この時期に直す指導をしてしまうからです。もちろん、その直す指導が具体的で本人にすぐできるものであればいいのですが、ほとんどの場合その生徒がすぐにはできないことを言います。
すると、子供は混乱して、これまでできていたことまでできなくなってしまうことがあるのです。
もし万一そういうことをもうしてしまった人がいたら、お母さんかお父さんがしっかりした方針として、「これまでのやり方でやっていけばいい」と言ってあげてください。
これは作文の試験以外のすべての試験にあてはまります。
何事も、最初に決めてやってきたやり方が、いちばんいいやり方なのです。
では、どういう直前対策をするかというと、それはこれまで書いてきた作文をファイルにとじておくことです。
その上で、その作文を読んで、自分なりに上手に書けたと思うところに赤か青のペンで線を引いておきます。(赤ペンは既に担当の先生が引いていることが多いので。)
また読み返してみると、表現を直した方がいいと思うところも出てきます。その場合は、小さい字になってもいいので、その部分をよりよい表現に直しておきます。ひらがな書きになっているところや、誤字のところも同じです。
そのようにしてファイルした作文を、ときどき読み返します。全部読む時間がないときは、上手に書けたと思った傍線の引いてある箇所だけでもかまいません。試験の直前まで何度も読んでいると、試験の本番で同じ表現や実例を使える場面が出てくるからです。
作文の勉強の仕上げは、自分がこれまでに書いた作文を読むことなのです。
また、もっと時間があるという人の場合は、同じテーマで元の作文を見ずに、時間制限の中で同じように書けるかどうかを確かめてみてください。(全く同じに書くというのではありません。大体の方向が同じであればいいということです。)
受験で差がつくのは、時間が限られているためです。同じテーマで何度も書いていると、自分が最高のスピードで書けばどのぐらいの時間で何文字書けるかがわかってきます。この自分の最速の字数を知っていると、試験の本番で残り時間が少なくなったときでも、「あと何分あるから、何文字は書ける」という見通しがつくので、焦らずに書いていくことができます。
作文試験や面接試験の当日には、読みかけの小さい本も持っていくようにしてください。作文の場合は、これまでに書いた作文を見直すのが試験前の準備ですが、それでも時間があるとき、又は面接試験で待っている時間があるときは、持ってきた本を読んでおきましょう。
試験前に本を読んでいると、なぜか不思議なことに、作文や面接の試験のときに、その本の内容を生かせる場面が出てくることがあるのです。
作文試験の本番で、書きやすい、易しい課題が出てきたら、それは普段の心がけがよかったからです。
その反対に、難しい、書きにくい課題が出てきたら、それは逆にチャンスです。自分が難しいと思うときは、ほかの人もみんな難しいと思っています。言葉の森での作文の勉強は構成を重視して練習しているので、難しくて書きにくい課題のときほど上手にまとめて書くことができるからです。
さて、生徒の方はこういう準備でやっていけばいいのですが、お父さんやお母さんも心の準備をしておく必要があります。
合格を目指して勉強することは、とても価値あることです。こういう受験勉強の中で、親も子も鍛えられます。
しかし、人生という長い目で見ると、合格した子も、合格しなかった子も、途中の経過は違っても、なぜかその子の本来の目指していたところに行き着くようになっているのです。
合格が有利で不合格が不利に見えるのは、そのときだけです。その後の人生の中では、有利に見えたことが不利になったり、不利に見えたことが有利になったりして、いろいろな紆余曲折を経て、その子の本来の道を進んでいたことに気がつくのです。
だから、お父さんお母さんは、なごやかな表情で子供の受験勉強の最後の仕上げを見守ってあげてください。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89)

これからの入試では、選択式の問題は次第に少なくなり、記述式の問題が増えていきます。更に、記述式以上に文章力の評価を重視した作文、小論文の試験も増えてきます。
記述力というものは、誰でもそれなりにありますが、入試で大事になるのは記述をするスピードです。
これは読解の問題でも同じで、国語の問題は誰でも時間をかければそれなりにできるようになりますが、スピードを上げて読み取るというところが難しくなるのです。
家でゆっくりやればできるのに、実際の試験ではできないというのは、このスピードが不足しているからです。
読解と記述のスピードを上げるためには、難しい語彙を読み取る語彙力と、難しい語彙も的確に使える語彙力とが必要です。読む語彙力と書く語彙力がそれぞれに必要なのです。
語彙力の有無は、森リン点の数値として出てきます。
人間が読み取って、「何か密度が薄い気がする」と思うものは森リン点が低く、その反対に、「密度の濃い文章という気がする」と思うものは、森リン点が高いという関係があります。
つまり、森リン点は、その文章に使われている語彙の質と量をチェックしているのです。
では、どうしたら語彙力が増えるかというと、ひとつは長文音読で、もうひとつは長文暗唱です。
長文の暗唱に慣れていると、英語の勉強も、算数数学の勉強も、わかりにくいといころはとりあえず暗唱で対応という形がとれます。
これは、決して丸暗記というのではありません。丸暗記というものは、テスト前のそのときだけ覚えていてあとは忘れてしまうような暗記です。
そうではなく、わからないながらも暗唱で丸ごと自分のものにしておくと、あとからそのわからないところが時間の経過とともにわかるようになるというのが暗唱なのです。
この暗唱によって、難しい語彙を読み取る力と、その語彙を使う力がついてきます。
小学校高学年から中学生にかけては、理解の語彙力に比べて表現の語彙力が低くなる時期です。そのため、この時期の子供は作文を書くことに負担を感じやすくなります。
つまり、読む力はあるので、それに比べてあまりに低い自分の書く力を見て、作文が苦手だと思うようになるのです。
この苦手な時期をのりこえる勉強が、音読と暗唱です。
音読は、張り合いがない勉強という気がするので、家庭では続けにくい面があります。また、家庭で音読をしていると、よく親から読み方を注意されることがあります。それでますます音読は続けられなくなりがちです。
暗唱の場合は、暗唱をし終えたあとの達成感があるので、音読よりも続けやすい面がありますが、達成感を感じるようになるまでの最初の練習を乗り切るまでが難しいところです。
言葉の森の寺子屋オンエアでは、音読については、skypeのビデオメッセージで先生に音読を送るという形を取っています。これで、音読を続けやすく感じる生徒が増えてきました。
暗唱については、暗唱に慣れるまでの間、やはり寺子屋オンエアで暗唱クラブのようなものを立ち上げ、それを今年からスタートする暗唱検定でチェックするという形を考えています。
作文力や記述力は、文章を書けば上達するわけではありません。書いて上達するのは、作文力記述力の一部です。文章を書く力は、文章を書くよりも、読む力をつけて上達する面があるのです。
その読む勉強を、毎日の自習という自然な形で取り組めるようにしていくのが大事です。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
「作文力や記述力は、文章を書けば上達するわけではありません。書いて上達するのは、作文力記述力の一部です。文章を書く力は、文章を書くよりも、読む力をつけて上達する面があるのです。 」
私も高1の娘といっしょに読解力アップに励みたいと思います。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 記述力(0)