読書作文キャンプにお申し込みいただいた方へのご連絡です。
別途、メールと葉書でも同じ内容をご連絡します。
今年のキャンプは、保護者の方に多くご参加いただいておりますので、参加者どうしで協力して、より充実したキャンプにしていきたいと思います。
つきましては、下記の日程で、第1回目の打ち合わせ会を行いたいと思います。
日程が急で誠に申し訳ありませんが、お時間のとれる方はぜご参加くださるようお願いいたします。
なお、会合に参加できない方には、あとで動画の記録をごらんいただけるようにします。
▽日時
7月1日(日)20:15~(45分間程度の予定です)
▽会場
https://zoom.us/j/104606743
・パソコンで上記のURLにアクセスすれば自動的にZoom会場に入ります。
・発表学習コースのZoom会場と同じです。
なお、今後の参加者の交流の場として、facebookグループ「言葉の森と家庭学習」のページを使えるようにしました。
https://www.facebook.com/groups/kateigs/
facebookに登録されている方は、ご自由にご利用ください。
■サマーキャンプ説明会&打ち合わせ会 2018年7月1日(日)20:15~
【7/1更新】
1.現在の参加状況
https://www.mori7.com/stg/index_web.php#list
2.子供だけ参加の場合の新幹線利用
(1)特別引率は難しいようなので、出発時は、各家庭で新幹線に乗るまでの対応を。
https://www.mori7.com/stg/index_web.php#1145
(2)那須塩原駅では、集合場所と改札口の両方で待つ。(改札口は1か所)
(3)旅行に関する保険適用の範囲は那須塩原駅に着いてから、那須塩原駅に戻るまで。
3.サマーキャンプの性格
(1)家族キャンプを合同で行うようなイメージで運営したい。
したがって、キャンプの内容は参加者の希望を生かして作り上げる形に。(遊びや勉強のアイデアや希望など)。
(2)スケジュールは、基本的な骨格として提示。
(朝は読書、昼は遊び、夕方は作文・発表、夜は工作・自由)
(3)保護者は自由行動もできる形に。(昼は近くの観光地めぐりなどをして、夜の合宿所の企画に参加など)
4.部屋割り
https://www.mori7.com/stg/index_web.php#1108
(1)子供は、2階の4部屋に各部屋2~4人で宿泊。ほかに8人まで入れる1部屋あり。
(2)大人は、以下の部屋に割り当て
1階
和洋室(10.5帖)二段ベッド2台・和室には布団可……1~4人
和洋室(10.5帖)二段ベッド2台・和室には布団可……1~4人
和室(8帖)布団……1~2人
和室(8帖)布団……1~2人
和室(6帖)布団……1~2人
2階
洋室(8帖)ダブルベッド2台……1~2人
(3)具体的な部屋割りは、後日決めさせていただきます。
5.夜の懇談会
子供が就寝したあと、食堂で(自由参加)。
保護者・講師の交流を深める(飲み物あり)。
昨年は毎晩2~3時間話していた。
6.遊び
屋外では、川のあるところで自由遊び(キャンプ場内の浅い川なので心配はないが大人で手分けして監視)
屋内では、工作を中心とした自由遊び(保護者も遊びを楽しむ形で参加)
工作は、木々レゴ、石塗り、フリスビー作りなど。
屋内遊びは、廊下での風船バレーボール、けん玉、ピンポンなど。
7.食事
(1)基本は、セブンミールに2日前発注で対応(品質面はかなりよいと思われる)
(2)ただし、一律では量が多すぎる場合があるので、おかずはバイキング風に配り直す。
(3)ご飯は、独自に炊いたものを中心に。
(4)おかずや野菜の追加もバイキング風に。(唐揚げ、ミニトマト、ジュースなど)
(5)調理は原則としてしない。(手間がかかることと衛生面から)
(6)ただし、カレー、豚汁、バーベキューなどは独自対応で(このときのご協力をお願いします)。
8.移動
9人乗りトヨタハイエースバン3台で分乗。
合宿所―キャンプ場30分程度。
乗車割りは、後日決めさせていただきます。
9.雨天時
多少の雨天は決行。
大雨の場合は、合宿所の中で自由遊び。
雨が続く場合は、別の観光を検討。
10.個人で用意するもの
https://www.mori7.com/stg/index_web.php#1111
おすすめの本3冊。
表でいつでも着られるような長袖長ズボン(ブヨ対策。あまりいないが刺された子が数人いたので)
1日目の昼食は済ませて参加(ただしキャンプ場でおやつを出す)
川遊び用マリンシューズ
11.家で待つ家族向け動画放映
Zoom又はgoogleハングアウトで。
URLを指定して連絡。
12.保護者のお手伝いお願い
(1)食事の際の配膳、調理の場合の手伝い。
(2)子供のふとんシーツのセット、片付け
(3)部屋の掃除
13.入浴
各部屋に風呂はあるがやや狭い。
合宿所の共同風呂はやや広いが同時に入れるのは3、4人か。
近所に車で15分程度で行けるところに感じのいい温泉あり。夕方大人半数ずつ行ける形に。
14.その他
祖父母の参加も歓迎。
合宿所はペット可だが、キャンプ場はペット不可。
生き物はつかまえても持ち帰らない。
水鉄砲は川では砂がつまるので使えない。
15.今後の連絡と打ち合わせ
遊びや食事などの企画を相談する場としてfacebookグループ「言葉の森と家庭学習」を使います。
https://www.facebook.com/groups/kateigs/
全体への連絡事項は、葉書+ホームページ+メールでお知らせします。
質問や相談は、随時言葉の森までお電話で。
■7/1説明会&打ち合わせ会の動画の記録【7/2更新】
7月1日に行った説明会&打ち合わせ会の記録です。
https://youtu.be/GbGyvGcHSwk
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14)
感想文が楽に書けるのは小5から
感想文が楽に書けるようになるのは、年齢的には小学5年生からです。小学1~4年生は、全体の構成を考えて書くという能力がまだ育っていませんから、大人が全体の方向づけをしなければ自分で本の流れに合わせて感想文の流れを考えていくという書き方はできません。
また、小学1~4年生の場合、似た話がうまく見つかる場合と見つからない場合とでは、作品の出来に大きな差が出てきます。大人(親や先生)が近くにいて、「この次はこんなことを書いたらいいよ」とときどきアドバイスをしてあげなければまとまった作品を書くことはできません。
なぜ学校のふだんの授業で感想文を指導せずに、夏休みの宿題というかたちで感想文を書かせるかというと、感想文は(特に低中学年の場合は)、一人ひとり別のアドバイスをしなければならないからで、30人から40人を相手にした一斉指導ではそういうアドバイスはできないからです。
感想文の宿題を書かせる時間があれば、その時間を読書に充てた方がずっと子供のためになります。
子供まかせでは書けない
「なんでもいいから自分で好きな本を選んで、自分で好きなように書いてごらん」ということでは、感想文は書けません。小学生の場合は、大人がなんのアドバイスもせずに感想文を書かせるぐらいなら、感想文を書くことそのものをしない方がいいのです。単に字数を埋めるだけの感想文は、何の勉強にもなりません。
じょうずな感想文を書くコツはある
書くからには、じょうずな感想文を書いて、コンクールなどに入選したいとはだれもが思うことです。作品の出来具合の半分は、似た話などの題材の部分に支えられています。また、もう半分は、感想の部分の一般化の深まりに支えられています。ですから、感動のある似た話が連想できるような本を選び、感想の部分で大人の人が一般化の手助けをしてあげれば、じょうずな感想文が書けます。
しかし、こういうかたちで親や先生がアドバイスをすることは、子供にとってはあまりうれしいことではありません。また、親や先生に支えられてじょうずな作文を書いても、教育的な意義はありません。ですから、感想文の目標はじょうずな作品を書くことにではなく、ひとまとまりの本を読み、ひとまとまりの文章を書く練習をするということに置くべきです。
書き方の手順「まず本選び」
まず本選びですが、子供が「この本、おもしろいから書きたい」と言うような本が必ずしも書きやすい本であるとは限りません。子供が自分なりに似た話を見つけることができたり、想像をふくらませたりできるような本が書きやすい本です。この本選びは、大人がアドバイスをした方がいいようです。少なくとも、子供には「似た話や想像した話が書けるような本が、感想文の本としては書きやすいよ」と言ってあげるといいと思います。
書きたいテーマが決まっているときは、インターネットの書店を利用して関連する図書を数冊用意すると話題が広がって書きやすくなります。
書き方の手順「次に字数配分」
感想文の宿題は、原稿用紙3枚程度(400字詰めで1200字)の分量で指定されることが多いようです。これだけの分量を1日で書くというのは大変です。無理のない字数配分は、1日1枚(400字)です。感想文の宿題をするために、4日間の予定を立てて、1日目に400字以上、2日目も400字以上、3日目も400字以上と書いていって、4日目に全体を通して要らないところを削り、清書するという予定を立てれば無理なく書くことができます。
書き方の手順「1日目の400字」
本のはじめの方から一ヶ所、似た話や想像した話の書けそうな場所を選び、そこを引用し、自分の似た話を書き、最後に「たぶん」「きっと」「もしかしたら」などという言葉を利用しながら、自分の感想を書きます。
本の引用(1)→似た話(1)(もし…だったらと想像してもよい)(たとえも入れる)→感想(1)(たぶん、きっと、もしかしたらなどと考えてみる)
書き方の手順「2日目の400字」
2日目も同じです。本の中ほどから一ヶ所、似た話の書けそうな場所を選び、そこを引用し、似た話を書き、感想を書いていきます。
本の引用(2)→似た話(2)→感想(2)
書き方の手順「3日目の400字」
3日目も同じように、本の終わりのほうから一ヶ所選んで書いていきますが、最後の感想のところがちょっと違います。1日目、2日目は、引用した小さな箇所の感想でしたが、3日目は本全体についての感想を書いていきます。
小学5・6年生の生徒の場合、この感想は、「○○は(人間にとって)……である」というような一般化した大きな感想を書いてまとめます。この感想の部分は、お母さんやお父さんと話し合いをして、子供自身の考えを深めていくといいと思います。そして、「私はこれから」などという言葉を使い、この本から得たことを自分のこれからの生き方にどうつなげていくかを考えてまとめます。中学生の場合は、結びの5行に「光る表現」を入れていくとよいでしょう。
本の引用(3)→似た話(3)→大きな感想(○○は人間にとって……。私はこれから)
書き方の手順「4日目の清書」
4日目は清書です。お母さんやお父さんが全体を通して読んであげると、要らないところが見つかると思います(書いた人自身には、要らない部分というものはなかなかわかりません。これは大人でも同じです)。この要らない部分を削ります。次に、書き出しの部分に本の引用として情景描写の部分を入れられれば、書き出しの工夫ができます。これは無理のない範囲でやっていくといいでしょう。
書き方の手順「できたらほめる」
書いている途中でも、書き終えたあとでも、親や先生が「これは、おもしろいね」「それは、いいね」と、子供の書いた内容のいいところやおもしろいところをどんどん認めてあげることが大切です。多少おかしいところや変なところがあっても、子供が書いた内容をできるだけ尊重してあげてください。これと反対に「これは、こうした方がいいんじゃない?」「そこは、ちょっとおかしいんじゃない?」などという否定的なアドバイスをすると、勉強でいちばん大事な子供の意欲をそぐことになります。大事なことは、いい作品を仕上げることではなく、手順にそってできるだけ自力で書く力をつけることです。
教室では宿題の感想文の個別指導はしません
感想文の指導には、生徒ひとりずつ異なるアドバイスが要求されます。更に作品として完成させるためには、書いている途中にも頻繁にアドバイスをする必要が出てきます。このような対応は、普段の勉強の中ではできませんので、夏休みの宿題のための感想文指導は、教室では行ないません。
宿題として感想文を提出しなければならないという事情のある方は、教室で練習した長文の感想文で似た話のよく書けたものをベースにして、ご家庭で書き直していかれるといいと思います。
また、どうしても書いた作品を見てアドバイスをしてほしいという場合は、担当の先生ではなく、言葉の森の本部に直接ファクスでお送りください。折り返しファクスとお電話で説明します。(これは有料です。)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
言葉の森が読書感想文指導を行うまでは、感想文の指導というものはどこでも行われていませんでした。
ただ書かせて、上手に書けているものを表彰するというやり方がどこでも普通に行われていました。
そうすると、小学校低中学年の子供はどういう書き方をするかというと、最初から最後までのあらすじを長々と書き、最後に、「楽しかったです。」などというような感想を書いておしまいにするのです。
こういう何の勉強にもならない、ただ読書嫌いや感想文嫌いにするだけの教育がずっと行われていたのです。
もうだいぶ昔の話になりますが、読書感想文の書き方を教えてほしいという要望があったので、言葉の森で読書感想文講座を開いたことがあります。参加したのは、小3から小6ぐらいの生徒でした。
3日間の講座で、全員がひととおり感想文を仕上げました。
そこまではよかったのですが、秋になると、その子たちから次々と、「学校代表に選ばれました」とか、「コンクールに入賞しました」などの声が届きました(笑)。
それで、あまり上手に書かせるのも問題だと思い、読書感想文講座は、その年だけでやめたのです。
ただし、入賞を目的にしなければ、感想文の勉強自体は、意味のあるやり方で進めることができます。
今年の夏休みは、その意味のある読書感想文講座を開く予定です。
作文や感想文というと、表現力の問題だと考える人が多いと思います。
しかし、本当は内容の問題なのです。
内容とは、その文章を書く目的と、その文章の中身となる実例です。
表現の仕方の問題は、そのずっとあとに出てくることなのです。
例えば、野口英世のお母さんが、英世あてに書いた手紙は、表現など全く無視しています。
しかし、それは英世にとって最も価値ある手紙だったのです。
====
おまイの しせにわ みなたまけました わたくしもよろこんでをりまする なかたのかんのんさまに さまにねん よこもりを いたしました べん京なぼでも きりかない いぼし ほわこまりをりますか おまいか きたならば もしわけかてきま
しよ はるになるト みなほかいドに いてしまいます わたしも こころぼそくありまする ドかはやくきてくだされ かねを もろた こトたれにもきかせません それをきかせるト みなのまれて しまいます はやくきてくたされ はやくきてくたされ はやくきくたされ はやくきてくたされ いしよのたのみて ありまする にしさむいてわ おかみひかしさむいてわおかみ しております きたさむいてわおかみおります みなみたむいてわおかんておりまする ついたちにわしをたちをしております ゐ少さまに ついたちにわおかんてもろておりまする なにおわすれても これわすれません さしんおみるト いただいておりまする はやくきてくたされ いつくるトおせてくたされ これのへんちちまちてをりまする ねてもねむられません (野口シカの手紙)
====
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書感想文(19)

「きみも、おいでよ。」
言葉の森では、この夏休みの8月中に、3週連続の朝の作文体験学習を行います。
募集するコースは、幼長から小2の生徒を対象にした親子で作文を書く親子作文コース、小3と小4の生徒を対象にした理科系の読書感想文コース、小5と小6の生徒を対象にした考える受験作文コースです。
オンラインで行うため、保護者の協力がある程度必要になりますが、ほかではまず経験できない企画ですので、言葉の森の作文の勉強に関心をお持ちの方は、この機会にぜひ体験学習にご参加ください。
■コースと対象学年
(1)科学と実験の親子作文コース
対象学年は、幼長、小1、小2。
「しぜんとかがくのはっけん」という本をもとに、家庭で自然の発見や実験をしていただき、その体験をもとに親子で作文を書きます。
お子様がまだ作文を書けない年齢でも大丈夫です。作文を書く楽しさを味わっていただくための企画です。
(2)理科系の読書感想文コース
対象学年は、小3、小4。
「理科好きな子に育つ ふしぎのお話」という本をもとに、家庭で対話や実際の経験をしていただき、その対話と経験をもとに読書感想文を書きます。
読書感想文の書き方と、書く楽しさを味わっていただくための企画です。
(3)中学入試の受験作文コース
対象学年は、小5、小6。
「公立中高一貫校適性検査問題集」をもとに、問題文を読み取り、家庭で対話や調査研究をしていただき、その対話と調査研究をもとに受験に合格する作文を書きます。
受験作文の書き方と、考える楽しさを味わっていただくための企画です。
※現在、寺オン作文コース、発表学習コースでオンラインの授業を受けている方は、この夏休みの体験学習はできません。
■日程
8月中に同じ曜日で3週連続。
・水曜クラス:8月1日(水) 8日(水)22日(水)いずれも9:00~9:45
・木曜クラス:8月2日(木) 9日(木)23日(木) 〃
・金曜クラス:8月3日(金)10日(金)24日(金) 〃
・月曜クラス:8月6日(月)20日(月)27日(月) 〃
・火曜クラス:8月7日(火)21日(火)28日(火) 〃
※
原則として同じ曜日に3回受講していただきますが、他の曜日のクラスに空きがある場合は、他の曜日に振り替えて受講することができます。
※体験学習は、当初同じ曜日で3日間としていましたが、ご都合のつかない方も多いようなので、3日間どの日を選んでもよいようにしました。変更される場合は、新しい日程を選び、古い日程は×で消去しておいてください。
(7/6追加)
※1クラスの定員は6名までです。45分間の授業は学年混在ですが、指導内容はそれぞれの学年に対応したものになります。
■会場
会場は、Zoom会議室です。
https://zoom.us/j/104606743
・パソコンで上記のリンク先にアクセスすると、Zoomの会議室に入れます。
(初めてアクセスするときは、Zoomアプリのインストールが数分行われます。)
・会場の下見でいつでも自由に入室していただいて結構です。
(ただし平日17:00~21:00、土曜9:00~12:00は授業が行われていますので、その時間以外でお願いします。)
■受講料
どのコースも3週連続で9,180円(消費税含む)
教材として、下記の図書をお送りします。
図書費も受講料に含まれますので、既に同じ図書をお持ちの方はご連絡ください。その場合、受講料は、図書費を差し引いた6,480円となります。
■お振込み(7/6追加)
.受講料は下記の金額で7月17日(火)までにお振込くださるようお願いいたします。
▽お振込先
三井住友銀行 港南台支店
普通 6599615 株式会社言葉の森
▽金額(手数料はお客様負担でお願いします)
図書を言葉の森に注文される方 9,180円
図書をご自宅でご用意される方 6,480円
(海外の方は、図書をご自宅でご用意ください。)
※期日までにお振込みがない場合はキャンセルとさせていただきます。
■教材とする図書(受講料に含まれます)
(1)科学と実験の親子作文コース
「しぜんとかがくのはっけん! 366」(主婦の友社)2,484円
(2)理科系の読書感想文コース
「理科好きな子に育つ ふしぎのお話365」(誠文堂新光社)2,484円
(3)中学入試の受験作文コース
「2019年度受検用 公立中高一貫校適性検査問題集 全国版」(みくに出版)2,700円
※海外にお住まいの方には図書はお送りできませんので、それぞれのご家庭でおそろえくださるようお願いいたします。
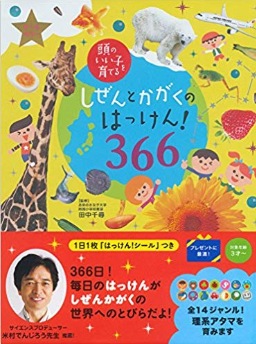
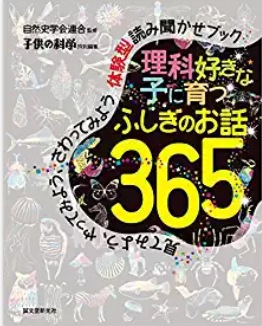
 ■オンライン授業の概要
■オンライン授業の概要
(1)必要な機材は、ウェブカメラのついたパソコン(又はタブレット)です。
(2)Zoomというウェブ会議システムを使います。操作は簡単で、設定の必要はありませんが、45分間の授業には、大人の方も一緒にご参加ください(大人の方は画面に入る必要はありません)
(3)事前に授業の動画を見て、似た例を考えたり実行したりしておきます。
(4)授業の中で、自分の考えたことやしたことを発表します。(低学年の子で自分でまだ発表できない場合は保護者の方がかわりに発表してあげてください)
(5)その発表のあと、作文や感想文を書きます。
(6)書き上げた作文・感想文はカメラで撮影しjpg画像にして、言葉の森のページの指定の場所にアップロードしていただきます。
(7)45分の授業のあと、希望される保護者は懇談会にご参加いただけます。
■資料等(7/6追加)
体験学習の資料等は、後日ウェブに掲載しご連絡いたします。
■掲示板(7/6追加)
体験学習の質問・相談・連絡用の掲示板を作りました。ご自由にご利用ください。
https://www.mori7.com/ope/index.php?k=103
■お申込みはウェブフォームから、又はお電話で
ウェブフォームは、
https://www.mori7.com/kform_pre.php?f=tkg201808
お電話は、
0120-22-3987(045-830-1177)(受付は平日9:00~20:00)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
朝9時から始めるオンラインの作文体験学習です。
テキストを読むだけでなく、実際にその場で教えてもらわないとわかりにくい、親子作文、読書感想文、受験作文の3つのコースについて体験学習を行います。
対象年齢は、幼長から小6まで。オンラインで行う勉強の面白さを味わっていただければと思います。
作文は、マニュアルどおり教えたつもりでも、うまく書ける子と書けない子の差が出てきます。
だから、家庭で教えるのは難しいのです。
よくあるのが、すべて子供の手で自主的にやらせようとすることです。
書くことがなかなか出てこない子から、無理やり書くことを引き出そうとして、結局書けなくしてしまうのです。
もうひとつはその反対に、親が細かくアドバイスをして書かせことです。
最初のうちは、うまく行きますが、やがて親も子もくたびれてきます。
そして、アドバイスをしてうまく書かせたことは、結局子供の実力にはならないのです。
作文をうまく書かせるコツは、手を抜きながら温かく見守り、書き出してからよりも、書く前の準備に力を入れておくことです。
いつもお世話になっております。
仕事の関係で平日朝では参加できないので、冬休みなどには土日等のコースも設定頂けると大変ありがたいです。
次回以降、ご検討よろしくお願いいたします。
確かにそうですね。今後検討したいと思います。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。体験学習(0)
先日の、「子供の読書についてのオンライン懇談会」で、漢字集へのリンクが表に出ていないことに気が付きました。
漢字集のリンクはこちらです。(google chromeの表示に最適化されています。)
▽教育漢字集
https://www.mori7.com/kg/koku/kk.php
▽常用漢字集
https://www.mori7.com/kg/koku/jk.php
▽教育漢字集のふりがなのないもの
https://www.mori7.com/kg/koku/kkk.php
▽常用漢字集のふりがなのないもの
https://www.mori7.com/kg/koku/jkk.php
使い方は、次のとおりです。
(1)ふりがなのついているものを何度も音読し、漢字の読み方を覚えます。
(2)読めるようになったら、ふりがなのついていないもので読めるかどうか試してみます。
(3)全部読めるようになったら完成です。
漢字や計算や暗唱のような基本となる勉強は、同じ教材で続けることが大切です。
1種類の教材で続ければすぐに定着しますが、種類が増えるほど能率が悪くなります。
それは、人間の記憶というものが、単にデジタル的に情報を処理しているのではなく、空間や時間や手触りという感覚と結びついて情報を処理しているからです。
現在の日本では、ものが豊かになっているせいか、子供たちは同じ教材を繰り返すということをしたがりません。
同じ教材を繰り返して勉強するという習慣が身につくのは、小学校低学年のうちです。
今年のサマーキャンプでは、この漢字集で、学年を超えた漢字の読みを勉強していく予定です。
ひとりでは退屈する勉強も、集団で行うとゲームのような感覚でできるからです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
漢字の読みは、読書の量と質に比例しています。だから、学年を超えた漢字をよく読める子は、読む力のある子で、それは学力と結びついています。
漢字の書きは、漢字の勉強をしたかどうかに比例しています。だから、漢字の書き取りができないというのは、ただ勉強していないからだけです。
漢字の書き取りの必要性は、これからどんどん低下していきます。
しかし、漢字の読みの必要性は、今もこれからも変わりません。
漢字の勉強は、読みを先行させて、学年よりも先に進んでいくといいのです。
今のような学校制度のない時代の昔の人たちが、どうして漢字の読みを覚えられたかというと、千字文(せんじもん)という精選された短いテキストがあったからです。
千字の暗唱であれば、毎日10分の練習で1か月で覚えられます。
そして、音さえわかれば、表意文字は文脈から大体の見当がつくのです。
ということで、言葉の森の漢字集は、現代の千字文を目指しています。
声を出して読むとわかると思いますが、意味のある言葉が連想できるようになっているのです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。漢字(17)
小学1、2年生の作文の練習は、楽しく書く習慣をつけることと、正しい書き方を身につけることが第一の目的になります。
「楽しく、正しく書く」ということは、誰にでも共通する基本的な内容なので、習得することは比較的簡単です。
ただし、読む力の向上が伴うことで語彙力や表現力も向上するので、毎日の読書や長文音読や暗唱練習のような家庭での学習は必要になります。
さて、この「楽しく正しく書く」というレベルの作文は、学年が小学3、4年生に上がってくると、ほとんどの生徒ができるようになります。
また、もともと読む力書く力がある子は、小学1、2年生の段階から、かなり自由に「楽しく、正しく」作文を書くことができています。
しかし、ここで、「もう作文は大丈夫」と、小学生の作文力が完成したように考えてしまうことはできません。
受験の作文に対応する本格的な作文力は、小学5年生からの「考える作文」の段階で出てくるからです。
小学5年生から必要になる学力の変化は、作文以外の国語や算数や理科や社会の教科でも共通しています。
小学4年生までの身近な事実に基づいた勉強から、小学5年生以降は、より抽象的な思考力を要求される勉強に切り替わっていくのです。
この学力の変化は年齢的なものなので、いくら作文力の優れている子でも、小学校中学年のうちに、小学校高学年で要求されるレベルの作文を書くことはできません。
例えば、「私の家族」という題名で書く作文は、小学4年生でも、小学5年生でも書くことができます。
しかし、その作文の主題を、「人間にとって家族とは何か」という形で考えることは、小学5年生以降でないとまずできません。
同じく、「ぼくの友達」という題名の場合でも、「友情とは何か」という形で主題を考えることは、抽象的な思考力が育つ小学5年生以降でないとできないのです。
だから、小学5年生からが、主題中心の本当の作文の勉強になるのです。
小学4年生までの作文は、小学5年生以降の作文の準備段階です。
小学1、2年生の勉強の中心が「正しく書く」という意味の「表記」で、小学3、4年生の勉強の中心が「価値ある内容」を「表現豊かに書く」という意味の「題材」と「表現」で、小学5年生以降の作文の勉強の中心が「構成」と「主題」で、中学生以降は、この「構成」と「主題」のさまざまな展開を学ぶという流れになっているのです。
こういう小中高の一貫した体系のもとで作文指導をしていところは、言葉の森だけだと思います。
さて、言葉の森の前身は、大学生対象の作文小論文指導をする教室でした(40年以上前の話ですが)。
大学生の作文指導をしていた教室が、高校生の入試小論文指導を行うようになり、次第に学年を下げて、現在の小学生からの作文指導を行うようになったという経過があります。(それが30年以上前の話です。)
だから、小学校高学年以降の中学生、高校生の作文指導こそが、言葉の森の特徴のある作文指導だとも言えるのです。
今の世の中で、作文指導をしている教室は、通信教育や学習塾も含めていろいろあります。
しかし、小学校高学年から、中学生、高校生にかけての作文指導は、言葉の森が最も長い指導の実績があります。
だから、この小学5年生以降の抽象的な思考力を要求される作文については、言葉の森で勉強することが最も密度の濃い勉強の仕方になります。
小学5年生からは作文の課題が急に難しくなりますが、言葉の森では、毎週の電話指導に加えて、現在はオンラインの少人数クラスによる作文指導も行っています。
オンラインのクラスでは、動画による解説も見ることができるので、難しい課題のときも書き方がよくわかるはずです。
小学3、4年生で既に作文が楽に書けるようになった生徒は、小学校高学年からは「考える作文」になるということを理解し、現在の、題材と表現を充実させる勉強に更に力を入れるとともに、今後はより難しい説明文の読書に取り組んでいってください。
また、小学5年生以上の生徒は、言葉の森で勉強することが最も高度な勉強になっていると考え、これまでよりも更に長文音読と事前の準備に力を入れて取り組んでいってください。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
小学4年生ぐらいで作文のよく書ける子のお母さんが、「もう作文の力は十分についたと思うので、ほかの勉強に力を入れたい」というケースが、昔からよくありました。
以前は、「はい、そうですか」とそのままにしていましたが、本当はそれはすごくもったいないことだったのです。
それは、小4と小5の作文は、質が違うからです。
どんなに作文の苦手な子でも、小4までの課題は誰でも何とか書けます。
しかし、小5からはそうではないのです。
小5の課題になると、書く以前に、課題の文章が読み取れない子が出てきます。
だから、本当は、小5からが本当の「考える作文」の勉強で、小4まではその準備段階です。
小1と小2で、楽しく正しく書く力をつけ、小3、小4で表現と題材を中心した書く力をつけ、その力の上に、小5からの構成と主題を中心にした作文の力をつけていくという関係になっているのです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。受験作文小論文(89)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)
作文や国語の勉強で、最も役に立つのが長文の音読です。
言葉の森が30数年前に、音読指導を始めたころ、世の中に音読の練習をしているようなところはほとんどありませんでした。
そのため、多くの保護者から、どうして音読をするのかとか、音読にどんな意味があるのかとかいうことをよく聞かれました。
しかしその後、音読に効果があるらしいということが広がったせいか、学校や塾でも音読をするようになりました。
ところが、音読は、毎日続けるのがかなり難しいのです。
家庭で、保護者が子供に毎日の音読の習慣をつけられればいいのですが、保護者自身が子供のころ音読をした経験がないことが多く、そのため子供に音読を続けさせることがなかなかできないのです。
これが、かけ算の九九と違うところです。
九九の場合は、親も自分の子供時代やった経験があるので、自信を持って子供に九九の暗唱をっせることができます。
しかし、音読はしたことがないので、自信を持って続けさせることができないのです。
そこで、言葉の森では、音読の練習とゲームの面白さを結びつけるために、読解マラソンというページを作りました。
しかし、このゲームの面白さというのは結局補助的なものであって、基本は保護者または先生の人間によるチェックがないと音読は続けられないということがわかってきました。
ウェブに毎日の記録をするということもできなくはありませんが、そういう機械的な方法では、さぼったり、やらなかったのにやったことにするというようなことがどうしても起きてしまうのです。
そこで、これを根本的に解決する方法として暗唱に力を入れることにしました。
音読は、やっているかいないかが、先生のチェックだけではわかりません。
先生が、「音読している?」と聞き、生徒が「はい」と言えば、それ以上のことは確かめられません。
音読は、毎日続けることが大事なのですが、週に1回や2回でも、子供は「音読をした」と言えるからです。
この音読に対して、暗唱の方は結果がはっきりしています。
毎日やっていれば誰でも少しもつっかえずに言うことができますが、何日かやらない日があると必ずどこかでつっかえたり思い出せなかったりするのです。
音読のチェックのときは、あまりやっていなかった子が、暗唱チェックをするようになってから、かなりの確率で毎日やるようになりました。
そこで、この暗唱の練習をさらに励みになるものにするために、言葉の森では暗唱検定も行うようにしました。
ところが、暗唱している生徒の割合は、本当は百パーセントを目指したいのですが、まだそこまでは到底行きません。
それは、暗唱を続けることも、やはり保護者が自分自身子供時代に暗唱した経験がないことが多いために、家庭で自信を持って子供に続けさせることが難しいからです。
そこで、新しく取り組んだのは、寺子屋オンラインの少人数クラスで暗唱のチェックをすることでした。
人間は、機械やソフトが相手では意欲を持ち続けることはできませんが、他の人間、例えば友達との関係では、意欲を持ち続けることができるからです。
言い換えれば、ゲームは飽きるが友達は飽きないのです。
ただし、その代わり、ゲームや機械と喧嘩する人はいませんが、友達とは喧嘩をしてしまう場合もあります。
つまり、人間にとって他の人間の存在というものは、意欲や感情を伴う分だけ、よい方向にも悪い方向にも強い力を持つのです。
言葉の森では、この人間どうしの関係による意欲をよりよい方向で持たせるために、現在、寺子屋オンラインというオンラインの少人数クラスを開いています。
この人間どうしの交流による学習というものが、これから教育の最も重要な方法になってくると思います。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
ものごとを合理的に考え能率よく進めるというのは仕事や生活の基本です。
そのためには、規格化、標準化、機械化、自動化が必要です。
ところが、子供の成長に必要なものは、往々にしてこれらとは正反対のものです。
だから、人間の教育には、どんなに優れた機械よりも、多少ずっこけていてもいいから人間の存在が必要になってくるのです。
一時、ゲーミフィケーションという教育方法が注目された時期がありました。
今でも、漢字や計算や英単語の練習でゲーム化されているものがよくあります。
しかし、どんなに面白いゲームでも、人間は飽きるのです。
そして、飽きるからそのゲームの裏技を探すような、機械の裏をかくことに喜びを見出すようになるのです。
これは、賞や罰も同じです。
人間は、動物と違って、賞や罰にも飽きるのです。
人間が唯一飽きないものは、他の人間です。
それは、人間というものは、どのような人間も予測できない創造性を持っているからです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101) ゲーム的教育(4)
以前も、記事を書きましたが、海外帰国子女の公立中高一貫校の入試はかなり有利です。
都立中高一貫校の海外帰国子女枠の入試と、オンライン作文の学習
そして、言葉の森には、帰国子女の中学入試の長年にわたる実績があります。
ある程度しっかりした考えを持てる子なら、合格水準までの作文が書けるようにすることはほぼ確実にできます。
しかも、それを現在、寺子屋オンラインというウェブ会議を利用したやり方でリアルにやりとりができるようにしています。
普通の通信教育では、さぼるとか、提出できないとかいうことがあり得ますが、毎週顔を見て勉強するのですから、そういうことはほぼありません。
また、この寺子屋オンラインのクラスの中では、読んでいる本の紹介をしたり、ほかの人の発表に対する感想を述べたりするなど、口頭によるコミュニケーションを生かすようにしています。
このコミュニケーションの蓄積が、面接に役立つのです。
入試のときの面接は、意外と答えにくい抽象的な話が聞かれることがあります。
「尊敬する人」や「志望理由」などの事前に準備できる想定内の質問ではなく、その場で考えて答えるようなことが聞かれることがあるのです。
そのときに、どんなことを聞かれても、一応考えて答えることができるというのは、ひとつの能力です。
最近の子供たちの中には、少しややこしいことを聞かれると、すぐに、「ありません」とか「わかりません」とかいう返事をあっさり言う子がいます。
成績はある程度いいのですが、考えて答えようとするという習慣がないのです。
以前、発表学習コースでも、感想を聞かれると考えもせずに「ありません」と言う子が何人かいたので、「『ありません』という答え方はなし」としたら、全員がしっかり話すようになりました。
こういう面接の練習や作文の練習が、高学年の生徒はもちろん、低学年のうちからできるというのが、オンライン教育のひとつの優れた点になっています。
ただし、難点は、オンラインを敷居が高いと感じる方が多いということです。
オンライン教育の話をすると、即座に、「あ、パソコンはダメなんです」と答える人がかなりいます。
しかし、将来はだんだんとこのオンラインの少人数クラスのよさが見直されてくると思います。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
言葉の森の受験作文小論文指導は、どこの塾や予備校よりも優れていると思います。
ただ、それをあまり宣伝していないだけです(笑)。
特に、中3生や高3生の駆け込み受験対策は、気持ちはわかるのですが、対応仕切れないことが多いのです。
また、国語読解力の成績向上も、以前、センター試験満点講座を行って著しい成果を上げたことがあるように、やはりどこよりも優れていると思いますが、普段の授業の中では特にそういう受験勉強的な対策は行っていないのです。
言葉の森の目標は、もっと広範に、日本の子供たちに作文文化を広げることで、それによって創造力、思考力、表現力、感受性のある子供たちを育てていくことだからです。
そのために、今、力を入れているのが、寺子屋オンラインの少人数クラスです。
この少人数の勉強の中で、作文力、学力をつけるとともに、一緒に勉強する仲間と、小中高とずっと続く友人関係ができるといいと思っています。
そして、いつか大学生や社会人になった卒業生たちが集まって、那須合宿所で同窓会を行うのです(笑)。
海外帰国子女で、中学入試に作文の試験を受けるという人は多いと思います。
たぶん、その分野は、学習塾が力を入れているので、そちらで勉強している人が多いのですが、本当は、言葉の森で勉強するのがいちばんいいのです。
なぜ、そう思うかというと、これまで多くの子が、「ほかの塾(予備校)で勉強していたが、言葉の森でやるようになってからすごくよく書けるようになった」と言うからです。
それは、そうです。指導の年季が違うからです(笑)。
しかし、言葉の森は、そういうレッドオーシャンに力を入れるのではなく、これからの新しいブルーオーシャンを目指しているので、受験ということはあまり前面に出していないのです。
ただし、海外帰国子女枠の作文面接入試は、かなり有利な入試で合格可能性が高いので、お知り合いの方がいたら言葉の森の寺オン作文コースのことを教えてあげてくださるといいと思います。
ちなみに、寺子屋オンラインに関する資料はこちらから申し込めます。
▽寺子屋オンライン送信フォーム
https://www.mori7.net/teraon/teraform.php
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。帰国子女(12) 公立中高一貫校(63)