この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
低学年の生徒が春の新しい勉強を始めるのに、最もいい講座は暗唱です。
小学2年生までの生徒なら、すぐに暗唱ができるようになります。
それは、先入観がないからです。
暗唱の力がつくと、ほかの勉強もどんどんできるようになります。
暗唱の勉強は、実は楽しい勉強です。
やっていると、だんだん気持ちが明るくなってきます。
リズム感のある日本語を繰り返し音読するというのは、気分を明るくするのです。
はじめまして。暗唱についての情報を求めてネットサーフィンをしていたところこの記事を発見しました。私は暗唱についてはものすごく効果が高い方法だと思っています。私は現在大学生なのですが、あるきっかけで暗唱をしようと思い、一ヶ月間毎日5時間以上は英語の暗唱に徹した結果、爆発的な英語の力の伸びと、明らかな記憶力の上昇を感じました。
具体的に暗唱したものを言うとZ会出版の速読英熟語に掲載されている200word程度の分50本と速読英単語上級編に載っている英文48本です。どれも、英文の番号とタイトルをセットで暗唱しており、一時間有ればそれぞれの本を通しで全てそらんじることができます。
暗唱についての書籍や情報は少ないのですが、脳の力を高める最強の勉強法だと思います。最初は暗唱に心理的な負荷を感じてもそこを、耐えて踏ん張るとある時とたんに負荷に感じなくなる時が来ます。暗唱最高です。
高広さん、貴重なコメントをありがとうございます。
中高生の人に、紹介させていただきます。
世の中には、「暗唱なんてただ覚えるだけでしょ。それで何か意味があるの」と言う人がたまにいます。
暗唱は、実際にやったことがない人には、その効果がわかりにくいのだと思います。
私も、ある本の一部を暗唱して、30分間読み続けることができるようになりました。
最初は、こんなのできるかなあと思っていても、やってみると途中から急にできるようになるのですね。
その意味で、暗唱の勉強には、やり遂げたという達成感もあると思います。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121)

動画
https://youtu.be/SddazrsXFOo
3月30日の朝日小学生新聞に、オンライン学習の記事が載っていました。
オンライン学習について、録画形式と双方向型があるという分類をしています。
録画形式は、スタディサプリに見られるような学習で、長所は好きな時間に見られる、繰り返し見られるということです。
短所は、集中が途切れやすいことです。
双方向型の例は、N予備校で、長所は質問がしやすいこと、短所は授業を受けたままになりやすいことと書かれていました。
言葉の森のオンライン学習は、このいずれとも違います。
最も大きな違いは、録画形式や双方向型の授業は無駄が多いということです。
つまり、分かっていることについても、見たり聞いたり時間がかかるということです。
これは、リアル形式の授業も同じです。
言葉の森の指導は、紙ベースの問題集を自主学習形式で行うやり方ですから、無駄なところは飛ばすことができます。
大事なところは、傍線を引くことができます。
分からないところは、繰り返し学習することができます。
これが最も大きな違いです。
好きな時間にできるかどうかということについては、言葉の森は振替授業で対応しています。
質問しやすいかということについては、個別指導の時間が確保されています。
集中して勉強できるかということについては、言葉の森は少人数クラスの対面授業ですから、自然に集中できます。小学1年生2年生でも、十分に取り組みます。
授業を受けたままになるということはありません。それは自主学習と自主学習のチェックが、学習の基本になっているからです。
オンライン学習は、オンラインという目新しさにとらわれているところがありますが、それではリアルな通学形式の学習の劣化コピーでしかありません。
オンライン学習の独自のよさは、例えばZOOMのブレークアウトルームの活用に見られるように、リアルではできないことをやるところにあります。
そして更にもっと根本的な問題は、今のオンライン学習のほとんどが、知識の詰め込みという既存の教育の枠組みの中で行われていることです。
与えられた知識をいかに効率よく詰め込むかということは、今でこそ価値があるように見えますが、いずれほとんど意味がなくなるものです。
例えば、もし今後オンライン形式で受験が行われるようになると、ネットの利用を取り締まることはできませんから、漢字を覚えるとか、歴史の年号を覚えるとかいうことは、ほぼ意味がなくなります。
そのかわり重要になるのは、それらの知識を活用する思考力や創造性になります。
その思考力と創造性、更には共感力を伸ばすことが、これからのオンライン学習の目標にならなければならないのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
オンラインのよさが、いつでもどこでも誰でも利用できることにあるというのは、もう2、30年前から言われている話です。
ところが、今のオンライン学習のほとんどは、まだそのあたりにとどまっているのです。
今のオンライン学習のほとんどは時代遅れです。
未来のオンライン学習の方法は、5人以内の対話と発表、そして内容は創造なのです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。未来の教育(31) 他の教室との違い(22) 言葉の森の特徴(83)
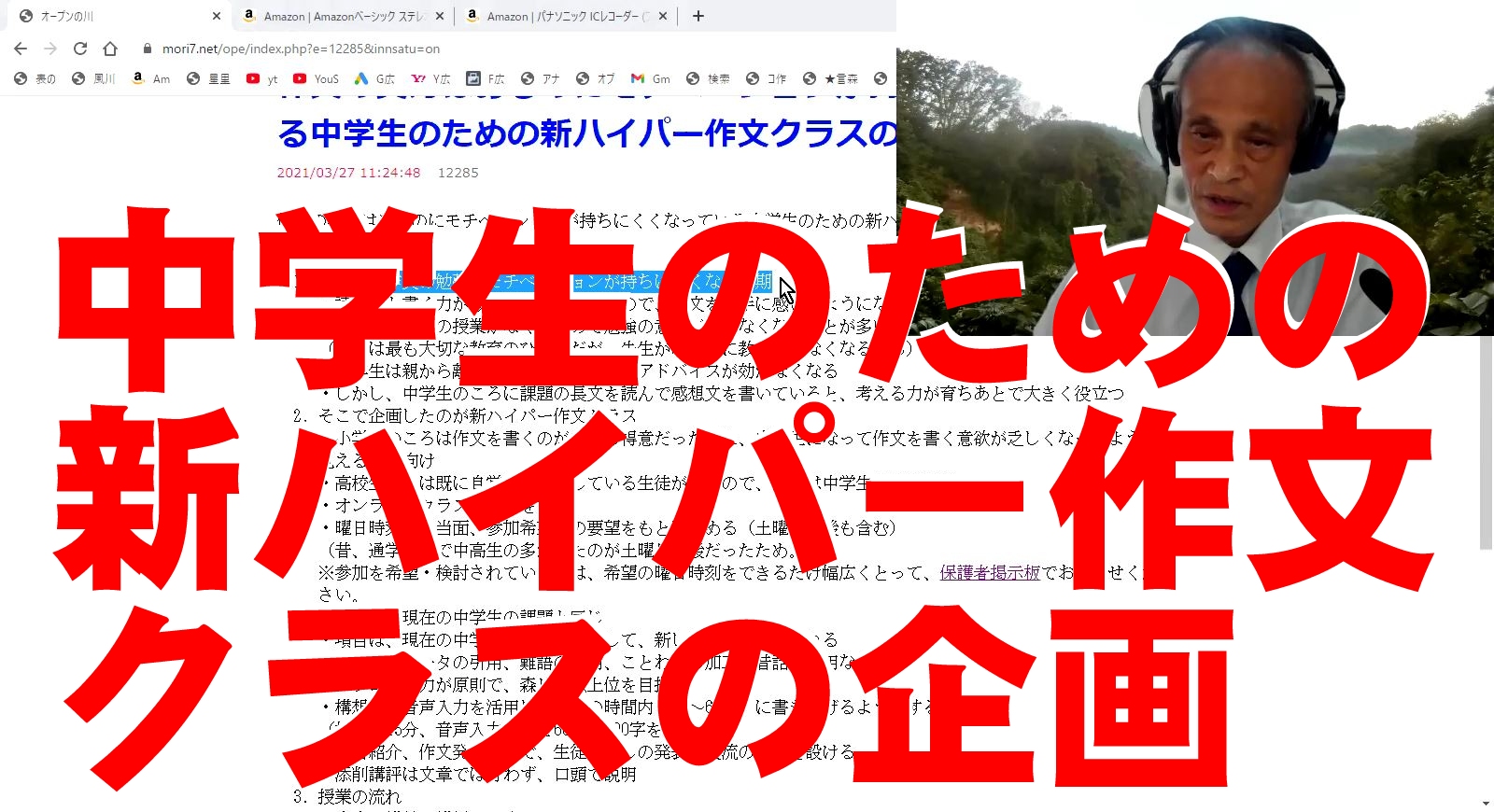
動画
https://youtu.be/EjKb6ElRQB4
- 中学生は作文の勉強のモチベーションが持ちにくくなる時期
・読む力と書く力が最も乖離する時期なので、作文を苦手に感じるようになる
・中学校で作文の授業がなくなるので勉強の意欲がわかなくなることが多い
(作文は最も大切な教育のひとつだが、先生が時間的に教え切れなくなるから)
・中学生は親から離れる時期なので、親のアドバイスが効かなくなる
・しかし、中学生のころに課題の長文を読んで感想文を書いていると、考える力が育ちあとで大きく役立つ
- そこで企画したのが新ハイパー作文クラス
・小学生のころは作文を書くのがむしろ得意だったのに、中学生になって作文を書く意欲が乏しくなったように見える生徒向け
・高校生以上は既に自覚して勉強している生徒が多いので、当面は中学生のみが対象
・オンラインクラスで学習をする
・曜日時刻は、当面、参加希望者の要望をもとに決める(土曜日午後も含む)
(昔、通学教室で中高生の多かったのが土曜日午後だったため。)
※参加を希望・検討されている方は、希望の曜日時刻をできるだけ幅広くとって、保護者掲示板でお知らせください。
・課題は、現在の中学生の課題と同じ
・項目は、現在の中学生の項目に追加して、新しい項目も取り入れる
(例えば、データの引用、難語の引用、ことわざの加工、昔話の引用など)
・パソコン入力が原則で、森リン点上位を目指す
・構想図と音声入力を活用して授業の時間内(45~60分)に書き上げるようにする
(構想図15分、音声入力15分で600~1200字を書く)
・読書紹介、作文発表などで、生徒どうしの発表と交流の時間を設ける
・添削講評は文章では行わず、口頭で説明
- 授業の流れ
・先生の講義と講評 15分
・構想図作成 15分
・音声入力 15分
(音声入力したものはそのままアップロード。後で手直ししてもよい)
・予備 15分
(授業後もブレークアウトルームは自由に使ってよい)
- 用意するもの
・パソコン(子供専用のものを用意しておくとよい)
・音声入力用のICレコーダー、パソコン接続ケーブル
(ICレコーダーはパナソニック ICレコーダーRR-XP009 約9000円がおすすめだが何でもよい。接続ケーブルは、auxケーブル 約800円。何でもよい)
・教材としての書籍2~3冊(後日、指定。データ集、キーワード集など)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
中学生で、毎週課題の長文を読んで、自分で考えて、600字から1200字の作文を書くというのは、実はとても大事な勉強なのです。
しかし、中学では、作文の勉強がなくなることが多いので、子供たちは作文の勉強を続ける意欲を持ちにくくなります。
そこで、より高度な作文の勉強をするために、新ハイパー作文クラスを企画しました。
曜日時刻はまだ決まっていませんが、土曜日の午前又は午後になる可能性が大です。
新ハイパー作文クラスの講師は中根です。
参加希望者が4人以上で開催します。
定員は5人です。
中根が休講するときは、代講はないので、振替の授業を受けていただきます。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。中学生の勉强(21) 作文教育(134)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)