
●教室の移転
8月から教室を移転しましたが、40年間の蓄積のあるガラクタを処理するために、だいぶ時間がかかりました。
特に、本が大量にあり、ほとんどに傍線が引いてあるのでブックオフに出すこともできず、まとめて廃棄業者に持っていきました。
新しい教室は、かなりコンパクトになりました。
生徒は、すべてオンラインで、今は、通学生はいないので、これまでのように駅近くの便利なところに教室を置くという必要はなくなりました。
今度の教室は、近くのJRの駅からは徒歩30分のところです(笑)。
そのかわり、自然に恵まれていて、近くの山と水田のある広い公園があります。
教室の庭のサンショウの木には、毎日のように、アゲハチョウが卵を産みに来ています。
移転の作業が一段落しつつあるので、これから、ホームページの更新と指導運営の充実に力を入れていきます。
●低中学年の子育て
小学3年生までは、子供は親の言うことをよく聞きます。
しかし、この時期に、子供をコントロールしすぎないことが大事です。
子供は、小4のころから次第に自立を始めます。
大事なことは、子供が自立するようになっても、親子の対話が続けられることです。
そのためには、小3のころまでに、子供の自主性を尊重していくことです。
親のペースでやらせた方が能率がいいと思っても、親が指示するのではなく、子供の意向を汲みながらやっていくことが大事です。
勉強は、小3までは、難しいことは何もありません。
勉強の内容よりも、毎日同じ時間に同じ家庭学習をするという習慣をつけることです。
勉強よりも大事なのは読書です。
勉強は、学校でやっていれば十分と考え、家庭では読書中心の生活をしていってください。
読書をしている子は、学年が上がるにつれて学力が伸びていきます。
●高学年、中高生の子育て
高学年や中学生になると、親が子供の勉強を見ることは難しくなるように思いがちです。
塾などで勉強をしていると、親が見ても、すぐにはわからないことをやっているように見えます。
しかし、その場合でも、保護者は時々、子供の勉強の中身を見てください。
そして、子供ができなかった問題を、答えを見ながら一緒に解いてみるということもしてください。
テストの結果の点数を見るだけではなく、テストの中身を見ることが大事です。
小学5年生から、勉強に抽象的な要素が入ってきます。
国語も算数も理科も社会も、知識の勉強だけでなく考える勉強になります。
作文の課題も、小学5年生から急に難しくなります。
しかし、作文は、保護者が最も関わりやすい勉強です。
毎週の作文の課題をもとに、保護者が自分の体験をもとに似た話をしてあげてください。
作文の予習を通して親子の対話を続けると、子供の語彙力と思考力が向上します。
語彙力と思考力は、作文の勉強だけでなく、すべての勉強の分野に生きてきます。
高学年や中学生になると、勉強の量が増えるので、読書は後回しになりがちです。
小学生時代は、学校でも読書指導が行われますが、中学生以上になると、学校では読書指導はなくなります。
しかし、中学生、高校生の読書は、子供の思考力と感受性を伸ばす最も大事な学習です。
特に、中学生以上の生徒は、物語文だけでなく、説明文意見文の読書を進める必要があります。
読書については、子供が使える毎月の予算を決めて、ブックオフやアマゾンで自由に本を買えるようにしておくといいです。
今は、近所に書店がないところも多く、図書館を利用するのも不便なことが多いです。
学校の図書室を利用するのが、最も便利ですが、子供の興味関心が個性化してくると、図書室だけでは物足りなくなります。
子供時代の学習の基本は、学校での勉強とともに、家庭での読書と、さまざまな体験です。
社会人になったとき、学校の勉強はほとんど残りませんが、読書と体験は子供の人間形成として残ります。
子供に読書と体験を勧めるように、保護者も、日々新しい読書と新しい体験に挑戦するようにしてください。
●受験生の取り組み
受験勉強で大事なのは、志望校の過去問に取り組み、過去問の傾向を知り、今後の勉強の対策を立てることです。
しかし、子供のほとんどは、自分では過去問に取り組みません。
過去問は、家庭で、保護者がある程度強制して子供にやらせる必要があります。
過去問は、傾向を知ることが目的ですから、答えを見ながら解いてかまいません。
また、保護者も、過去問を、答えを見ながら一緒に解いてみてください。
そうすると、今後の勉強の方向がおのずからわかってきます。
そして、全教科の平均点が65%から70%を超えるようになるためには、どの教科に力を入れていくかを考えるのです。
受験勉強は、総合点が基準になるので、得意教科を伸ばす勉強ではなく、苦手教科を克服する勉強です。
人生は、得意分野を伸ばすことが大事ですが、受験は苦手分野をなくすことが大事です。
保護者が協力して、受験勉強の大きい方針を決めていくようにしてください。
そして、模試は毎月1回は受けるようにして、おおまかな合否可能性を把握するようにしてください。
重要度の順位は、第一に過去問、第二に模試です。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。懇談会・個人面談(0)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読解力・読解検定(0)
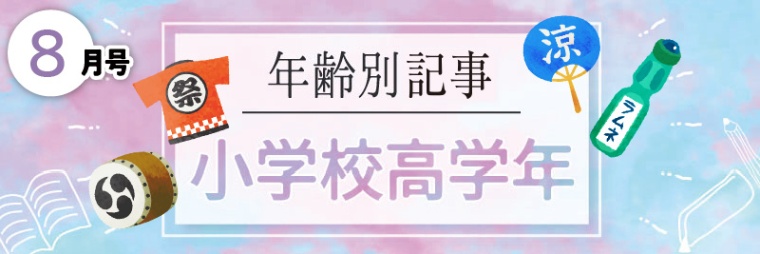
日経DUALに、言葉の森の中根へのインタビュー記事が載りました。
これは、主に小学4・5・6年生の保護者の方に、参考になる話です。
記事の全文は有料会員限定ですが、日経DUALは、いい記事が多いので、ぜひごらんください。
私は、小学4・5・6年生で、いちばん役に立つ勉強は、オンライン5人クラスで行う作文だと思います。
オンライン5人クラスでの授業は、毎週全員の読書紹介があるので、子供たちの読書が進みます。
また、言葉の森では、中学生以上の生徒には、物語文の読書だけでなく、できるだけ説明文の読書をするように言っているので、説明文の読書によって読解力だけでなく思考力も育ちます。
小学生のときの作文課題では、作文に書く実例を保護者にもインタビューするようにしています。
すると、お父さんやお母さんが、とてもいい話をしてくれることが多いのです。
この親子の対話によって、子供の語彙力が伸びます。
特に、小学5・6年生の課題は、人生や社会に関する話題が中心になりますから、親子で深い知的な話まで進むことが多いです。
今の中学受験の作文では、結びの感想の部分でどれだけ深いことが書けるかが大きな差になります。
そのときに、感想を書くための語彙力があることが重要になります。
こういう親子の対話は、子供が中学生になると反抗期になることもあって、なかなかできなくなります。
だから、小学校高学年の時期の作文は、親子の対話という点で、ほかでは得られない貴重な機会になるのです。
「将来の学力にも影響 小学校最後の3年間で学ぶべきことは」
https://woman.nikkei.com/atcl/column/23/101900012/083100020/
====引用ここから====
心身の成長が気がかりな未就学の時期、学習面のサポートが必要となる小学校低学年を過ぎ、わが子が「あっという間に小学校高学年になってしまった」と感じているママ・パパも多いのではないでしょうか。高学年になった子と向き合う上で親が心掛けたいこと、中学受験をするにしても、しないにしても小学校最後の3年間に家庭で取り組みたい学びなどについて、オンラインスクール「言葉の森」代表の中根克明さんに聞きました。
■新たな親子関係の構築を
まだ幼さの残る小学3年生までとは違い、小4以降は親に対する反発心から口答えをするようになったり、親の言うことを聞かず、素直に机に向かわなくなったりするかもしれません。小学校最後の3年間、親はどのようにわが子に向き合えばいいのでしょうか。また、この時期の過ごし方は将来にどう影響するのでしょうか。
オンラインスクール「言葉の森」代表の中根克明さんは「この時期は親子の対等な関係を築くチャンス」と言います。
「よく『10歳からは親の言うことを聞かなくなる』といわれますが、小学4年生以降になると親への反発心が生まれたり、嘘や隠し事、いじめが出てきたりします。わが子の急な変化に驚くかもしれませんが、それで親子関係が破綻するわけではなく、この時期に子どもとしっかり向き合い、信頼関係を築くことができれば、中学生以降に反抗期が来ても乗り越えることができます。
反対に言うことを聞かせようと親が抑えつけたり、勉強や行動を厳しく管理したりすると、将来必要となる自立心が育たないので要注意です」
中学受験をする家庭では、子どもが塾で過ごす時間がだんだんと長くなってきます。
「塾通いをしていたとしても小学校最後の3年間は中学入学前で、まだ時間的に余裕のある時期です。ぜひ、この時期にわが子の好きを伸ばし、親子で人生について話す時間をつくってください。その経験が将来の学力、経験にも生きてきます」
具体的には何をすればいいのでしょうか。詳しく聞いていきましょう。
■詳しくチェック!
・わが子が急に反発するようになったら?
・親は「損得勘定」で話さない
・小学校最後の3年間に必須の学びは〇〇と〇〇
・これからの子どもに学力よりも必要なことは
■次ページから読める内容
幼さが抜ける小4からの過ごし方は
高学年に必須の学びは
「経験」は親がさせるものではない
自分は何が好きで、何が得意かを分かっている子は強い
続きは、日経xwoman有料会員の方がご覧いただけます。
====引用ここまで====
※言葉の森の電話番号が変わりました。
これまでのフリーダイヤルは使えません。
お電話は、
045-353-9061(平日9:00~19:30)にお願いします。
(電話会社の対応が遅れているために、フリーダイヤルに電話をすると9月10日まで間違った転送情報が流れます。)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。メディア(8)

言葉の森の山椒(さんしょう)の木とキアゲハ
日本の教育の問題点は、3つあります。
第一は、相変わらずの詰め込み受験教育が、学校でも、塾でも、保護者の意識の中でも続いていることです。
第二は、集団一斉指導というスタイルから抜けられない学校教育の仕組みが根強く残っていることです。
第三は、家庭教育の不在と、読書教育の不足が広がっていることです。
現在の教育の問題点から生まれている現象としては、不登校の増加、受験後の燃え尽き症候群の増加、指示待ち世代の増加などがあります。
新しく生まれているよい面は、次のようなものです。
第一は、総合選抜型入試の広がりです。
第二は、先進的な大学で行われつつある起業志向の教育です。
第三は、ネット端末の普及です。
今後必要な取り組みは、次のとおりです。
第一は、オンラインの少人数の対話型教育を進めることです。
この場合の少人数とは、5人程度の全員が交流し、全員が個別指導を受けられる人数のことです。
第二は、国語・数学・英語などの知識や技能を吸収する教育だけでなく、創造発表型の教育を行うことです。
具体的には、対話型の作文教育と読書教育、探究学習とも呼ばれている創造発表教育、そして、多様な個性を生かすプログラミング教育です。
第三は、このような教育に対応できる講師の研修です。
具体的には、評価のための講師でも、指導のための講師でもなく、多様な生徒の個性と意欲を促進するファシリテーター型の講師を養成する研修です。
このような教育の結果として、日本に多様な創造教育文化が生まれることが、これからの日本の復活につながります。
今後の経済の中心は、工業製品の需要から教育や文化の需要に移っていきます。
その場合の文化とは、音楽を聴いたり映画を見たりするような消費型の文化ではなく、一人ひとりが自分の個性を活かす創造型の文化です。
かつて、江戸時代の長い安定期を通して、茶道や俳句をはじめとする新しい文化が数多く生まれました。
それと同じようなことがこれから起こります。
そのひとつの象徴的な例は、「さかなクン」が行っている趣味とも仕事とも社会貢献のボランティアともつかない新しい「仕事」です。
言葉の森、このような展望のもとに、これからの教育を進めていきます。
具体的には、5人以内の対話型の作文オンラインクラスを広げることです。
生徒が増えれば、同学年、同レベルの生徒どうしの密度の濃い交流のもとに作文学習を進めることができます。
また、創造型の教育として、創造発表クラスとプログラミングクラスを広げていきます。
創造発表クラスは、集団型の探究学習ではなく、一人ひとりの個性を生かす新しい探究学習を行います。
プログラミングクラスは、今後ウェブ作成も取り入れ、女子も楽しめるプログラミング学習、自分の生活に活かせるプログラミング学習を行っていきます。
教科型の教育としては、国語読解クラス、算数数学クラス、英語クラスを広げます。
教科学習は、家庭での毎日の自主学習と、教室での毎週の個別指導と毎月の確認テストをセットにして学習を進めていきます。
教科型の学習によって、すべての生徒が、その実力に応じて、十分な全教科の学力をつけることを目指します。
また、今後、主に小1から小3を対象にした、国語・算数・暗唱・発表の総合学力クラス(基礎学力クラス)を発展させ、小4から小6を対象にした、国語・算数・英語・発表の新しい総合学力クラスを開始します。
更に、中1から中3を対象にした、国語・数学・英語・理科社会の全科学力クラスも開設する予定です。
これらの総合学力型のクラスは、週1回の授業と毎日の自主学習を組み合わせ、1クラスの受講で全教科がカバーできるようにします。
私は、ちょうど10年ほど前に、今後の教育の方向は、受験から実力へ、学校から家庭へ、点数から発表(文化)へ、競争から創造へとなると考えました。
この方向を発展させて、今後、オンライン少人数クラスの創造発表対話型の教育を進めていきたいと思います。
世界の変革に合わせて教育も大きく変わる 1 2013年9月11日
世界の変革に合わせて教育も大きく変わる 2 2013年9月11日
世界の変革に合わせて教育も大きく変わる 3 2013年9月12日この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森のビジョン(51)