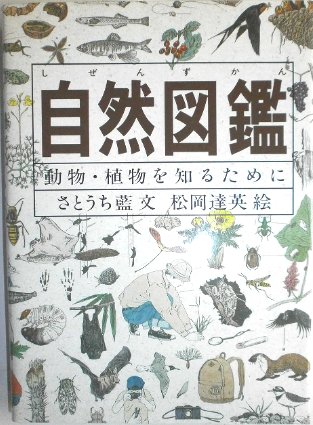
本日の小学生新聞に、食べ物の味の話が載っていました。
これは、小中学生が身近に実験できるものですから、お父さんやお母さんと協力してやってみてください。
・プリンにしょうゆをかけると、ウニの味。
・キュウリにはちみつをかけると、メロンの味。
・たくあんと牛乳をまぜると、ポタージュみたい。
・マグロの赤身にマヨネーズをかけたら、大トロになった。
・薄皮をとったミカンにのりを巻いてしょうゆをつけたら、イクラに似てる。
私も子供のころ、何かにお酢をまぜたら、リンゴジュースになったという記憶があります。
何だったから忘れましたが。
もうひとつ面白い実験は、ニワトリを逆さにして背中を床に押し付けると、そのまま寝てしまうという実験です。
ニワトリのいる家はあまりないと思うので、たぶん実験はできない人が多いと思いますが。
もう一つ、これはちょっとかわいそうなので、やらない方がいいと思いますが、カエルのお腹を何度もさすっていると、カエルもそのまま寝てしまうのです。
水のあるところに放り投げても、そのままあおむけになって寝ていました。
やがて気がついて、起きて泳いでいきましたが。
自然図鑑のような本を用意して、いろいろな実験をしてみるといいと思います。
====
自然図鑑―動物・植物を知るために (Do!図鑑シリーズ)
https://www.amazon.co.jp/dp/4834006883/
(コメントより)
わくわくして本を眺める
小学生の時の愛読書であった事を思い出した。子供にも読ませたくて購入。
家の中、近所でも自然の観察ができる事を教えてくれる。未就学でもイラストを見て楽しめ、恐らく生き物、冒険好きな小学生なら昔の小生のように食い入るように見るに違いない。
……
====
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
創造発表の勉強は、知識的にやるのではなく、実験的にやることが大事です。
実際に、いろいろな事物に接してみると、意外なことがわかります。
その意外なことを学問的に深めていくのです。
もちろん、その学問は、初歩的なことでいいのです。
不思議に思ったことを調べてみるという過程が大事なのだからです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。創造発表クラス(0)

犬も年を取ると目や耳が不自由になります。私も例外ではなく、目はかろうじて見えるものの、耳はほとんど聞こえません。ただ、いつも静寂の世界にいるかというとそういうわけでもないのです。
なぜかわからないのですが、自分に都合のいい音は聞こえてくるのです。そのことは、ママも気づいていて、いつも不思議がっています。
ほかの言葉には反応しないのに「おやつ」という言葉だけは耳に飛び込んできます。
また、ただのドッグフードの音には反応しないのに、ママが私のために野菜を切っている音がするとすぐに気がついて台所に行きます。
「ごはんですよ。」という声も、ただのドッグフードのときは聞こえてきません。でも、手作りごはんのときは、声がすると同時に飛び起きます。
もしかすると、耳が聞こえなくなったのではなく、心がウキウキするものとそうでないものを振り分ける能力が開発されたのかもしれません。
犬も人間も、余計なことに惑わされず、自分にとってプラスになることだけを見たり聞いたりするのが本当の幸せなのではないかと思います。そういう意味では、今の私はとても幸せです。
さて、ごはんまではまだ時間がありそうなので、静寂の世界を楽しむことにします。静寂の世界にいるときは聖者になった気分です。ごはんの準備の音が聞こえてくると、ただの食いしん坊犬に戻るんだけどね。(笑)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。息抜き(19)

結論を先に書きますが、私は、いずれもないと思います(笑)。
もちろん、その本に書かれているやり方で数週間続けた子はいるかもしれません。
しかし、継続して勉強するような子はまずいません。
作文にせよ、読解にせよ、音読暗唱にせよ、先生の励ましや友達との交流があるから続きます。
本に書いてあることを、親に言われたからやるということで継続できる子はまずいません。
だから、勉強は、オンラインクラスでやることが大事なのです。
それなのに、斉藤さんがなぜこのような本を出したかというと、たぶん出版社の企画で出しただけです。
斎藤さんには、言っては悪いですが、作文についても、読解についても、音読暗唱についても、理念や方法というものは何もありません。
それは、斉藤さんの本を読むとすぐにわかります。
ただ、世の中で言われていることをあちこちからコピーしただけの内容です。
そのコピー元には、もちろん言葉の森も入っています(笑)。
オリジナルな考えがなく、実際の裏付けもないままに書かれた本を、タイトルだけ見て購入した人もいると思います。
しかし、これは、本のタイトルがもっともらしいだけで、実際に活用できるものではありません。
作文も、読解も、音読暗唱も、実際に教えてくれる人がいるから初めてできるようになります。
オンラインクラスで、実際の先生と対話を通して勉強することに意味があるのです。
齋藤孝さんが監修している「ブンブンどりむ」は、作文などを教えているのだと思いますが、その方法の中心は「ほめて伸ばす添削」です。
作文が上達するのは、書く前の事前指導があるからです。
書いたあとの添削がいくら詳しく書かれていても、子供の作文力は伸びません。
添削で子供の作文が上達するのであれば、日本中の子供はとっくにみんな作文が上手になっています。
そういう本質的なことを知らずに、斎藤さんが「こども文章力」や「こども読解力」のような本を書いているのは、実際に小学生や中学生に作文や読解を教えたことがないからです。
実際にやったことのない人は、いくらでも観念的にもっともらしいことを書けるのです。
私は、人を批判することは好きではありません。
大事なことは、創造することであって、レベルの低いものを批判することではないからです。
しかし、朝日小学生新聞の毎週の広告を見て、勘違いした勉強を始めてしまう人もいるのではないかと思い、あえて批判的なことを書かせていただきました。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
私は、ブンブンどりむのようなレベルの低いものは誰もやらないだろうと思っていましたが、毎週大きな広告を出しているので、勘違いして始めてしまう人もいるかもしれないと思い、こういう誰かを批判することは好きでないのですが、あえて書くことにしました。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。ブンブンどりむ(0)
 キヅタ
キヅタ
いまだに、読書では国語力はつかないと言っている人がいます。
そういう人は、難しい本を読んだことがない人です(笑)。
難しい本というのは、岩波文庫の
青帯や
白帯の本ですが、今はもっといい本もたくさんあります。
読書には、いろいろな幅があります。
ライトノベルのような本をたくさん読んでいれば、ライトノベルのような作文は書けます。
ライトノベルのような読解問題は、解けるようになります。
読むことは、書くことと問題を解くことの土台になっています。
入試問題は、ライトノベルのレベルよりも上の文章が出てきます。
問題文は、大きく名作の物語文と、説明文に分かれますが、大事なのは、説明文をしっかり読む力をつけておくことです。
しかし、小学校低中学年で、入門的な説明文の本を読むことには多少問題があります。
説明文の本は、熱中して読むということがないからです。
薬を飲むように、義務感で読むような読み方をする子も多いのです。
同様に、「○年生で読む名作」のような本も、子供の読む力はつけません。
短編を断片に読むのではなく、1冊の本を熱中して読むことが大事です。
読書好きな人は、子供のころ、読むのが止まらなくなって、寝る時間も惜しんで読んだという経験があると思います。
読書は、熱中して読むことが大事なのです。
アマゾンで、「
子供 科学 話」などと検索すると、小学生が読める説明文の本がいろいろ出てきます。
こういう本で大事なことは、知識が羅列されているような文章ではなく、原因や方法という理屈が書かれている本を選ぶことです。
ただ、それは読んでみるまでは、わからないですから、子供がその本を読んでいる様子を見ることです。
熱中できる本、繰り返して読む本が、その子供にとってよい本です。
小学校低学年の子にとって、「
かいけつゾロリ」のような本はよい本です。
品の悪い話も多いですが(笑)、文章が説明的なので読む力がつきます。
小学校中学年の子にとって、「
宇宙人のいる教室」もいい本です。
ほとんどの子が一日で読み終えます。
小学校高学年の読書好きな子にとって、「
モモ」や「
はてしない物語」は、いい本です。
自分のことのように没頭して読む子もいると思います。
私は、高校生のころは、三一新書という今はもうない新書判の本を読んでいました。
今の高校生は、
ちくまプリマー新書や
岩波ジュニア新書のようないい本があるので、それらを読んでいくといいと思います。
大学生にとっては、個人的には
ヘーゲルがいい本ですが、これは難しいです。
私は、「
ヘーゲル精神現象学の生成と構造」を読むまで、よく理解できませんでした。
もし子供がそれらの本を熱中して読まないとしたら、その子の読書力がまだそこまで達していないということです。
大事なことは、子供に話しかけても聞こえないぐらい熱中できる本を、子供時代にたくさん読ませることです。
この読書力が、国語力や作文力だけでなく、学力全体の土台になります。
学力というのは、母語である日本語を自分の手足のように自由に使える力だからです。
====
最新脳科学でついに出た結論 「本の読み方」で学力は決まる
https://www.amazon.co.jp/dp/4413045513/
小中学生4万人の脳解析データが実証した衝撃の「科学的事実」とは!
◎読書習慣がないと、毎日勉強しても成績は平均以下
====
小学生は特に、勉強している暇があったら、本を読んでいる方がいいのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
齋藤孝さんは、「齋藤孝先生が選ぶ 高校生からの読書大全」などという本を出していますが、こういう本を読んでも、雑学的な知識が身につくだけです。
高校生は、図書館で「ちくま少年図書館」を読むか、ブックオフなどで「ちくまプリマ―新書」を探すのがいいです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)