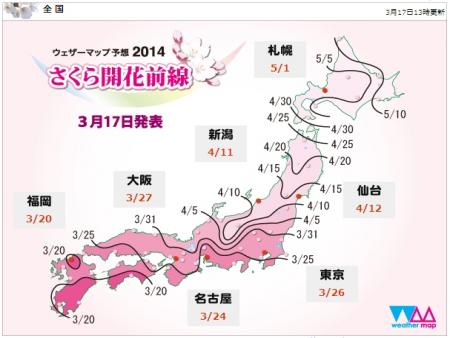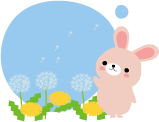 遊びと行事の 実行課題集
4ページ表示
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1~3月
4~6月
7~9月
10~12月
遊びと行事の 実行課題集
4ページ表示
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1~3月
4~6月
7~9月
10~12月
 4月の実行課題集 1
4月の実行課題集 1
楽しい嘘の日


「嘘」がつくことわざ
「嘘」に関することわざを調べてみましょう。いろいろなことわざが見つかりそうです。
たとえば、「嘘から出たまこと」。これは、嘘として言っていたことが、結果として本当になってしまうことです。嘘のつもりで言ったことが本当になってしまうとしたら、気軽に嘘をつくことはできませんね。
「嘘も方便」ということわざは、嘘をつくことは悪いことではあるけれど、時と場合によっては嘘が必要なときもあるというという意味です。友達が新しい洋服を着てきたとき、内心ではセンスが悪いなあと思ってもそのまま口に出して言わずに、嘘でも「かわいい服ね。」と言ってあげた方がよいでしょう。また、病気で入院している人に「顔色が悪いね。」などと本当のことを言ったら、治る病気も治らなくなってしまうかもしれません。そんなときは嘘をつく方が思いやりがあると言えるでしょう。
(下の写真は、ウソ。これはホント。どっちや)
エイプリルフール
エイプリルフールとは、毎年4月1日には嘘をついてもよい、という風習のことです。エイプリルフールの起源は不明で、いつ、どこでエイプリルフールの習慣が始まったかはわかっていません。
4月1日には、世界中で新聞が嘘の内容の記事を掲載したり、TVニュースでジョークニュースを報道したりといったことが広く行われています。
みなさんも、おもしろい嘘を考えてみてはいかがでしょうか。ただし、人を傷つけるような嘘はいけません。飼っている犬が言葉を喋ったとか、宇宙人が訪ねてきたとか楽しい嘘を考えてみてください。
嘘を見抜くトランプ
「ババ抜き」、「ダウト」などのトランプ遊びでは、相手に嘘を見破られないようにすることが勝利の秘訣です。ババ抜きでは、たとえババを持っていても、ババなんて持っていないというようなポーカーフェイスでいることが大事です。ダウトでも、いかにうまく嘘をつくかが重要なポイントです。と同時に、相手の嘘を見抜く力も必要です。そのためには、相手の表情をうまく読み取らなければなりません。にやにやと笑いをかみ殺しているようなときは要注意です。ただし、その表情が裏の裏をかく演技である場合もあるので、さらに注意が必要です。でも、トランプ遊びは、あくまでも楽しくやるのが目的ということを忘れないでくださいね。
 4月の実行課題集 2
4月の実行課題集 2
山菜採りに出かけよう


山菜とは
山菜とは、山や野に自生している食用の植物のことで、苦味があり、アクが強いのが特徴です。アケビ、ウド、セリ、ゼンマイ、タケノコ、タラの芽、ツクシ、フキノトウ、ワラビなど、いろいろな種類があります。
山菜が食べられ始めたのは、縄文時代ではないかと言われています。平安時代には、体に良い食べ物として広まりましたが、山菜が広く知られるようになったのは江戸時代です。江戸時代の三大飢饉のときの食糧難により、山菜のいろいろな食べ方が考案されました。米沢藩の莅戸善政が執筆した「かてもの」には、約80種類の山菜の特徴と調理法が解説されています。
山菜には、血圧を下げる効果があるもの、抗酸化作用のあるもの、糖尿病を予防するもの、鎮痛作用のあるもの、解毒作用のあるものなど、種類によってさまざまな健康効果があります。
山菜採りの注意点
山菜採りに行くときは、長袖、長ズボンで、帽子と軍手も必需品です。
山の中は迷いやすいので、経験者と一緒に行きましょう。クマよけ対策も必要です。
家族で食べられる必要な分だけを採りましょう。また、次期の繁殖のために、根こそぎ採ってしまわないように気をつけましょう。ウドやタケノコは、土ギリギリのところをナイフで切ります。ワラビ、ゼンマイ、たらの芽などは、手で自然に折れるところから採ります。食べごろを過ぎてしまったものは採らないようにしましょう。
ウルシ、スイセン、ドクゼリなど、山菜とよく似た、毒性植物もあるので注意してください。
山菜を使った料理
・タラの芽の天ぷら
タラの芽のはかまの部分を取り、天ぷら粉をつけて揚げます。
天つゆか塩をつけて食べます。
・ウドの炒めもの
塩ゆでをしたウドを炒めます。最後にしょう油、みりん、砂糖で味つけをします。
豚肉やシーチキンと一緒に炒めてもおいしいです。
フキ味噌、ゼンマイのお浸し、セリの白和え、ツクシの卵とじ、タケノコご飯など、山菜を使った料理はほかにもたくさんあります。とりあえず、タラの芽の天ぷらを作ってみタラ? ツクシづくしもいいかもしれませんね。
 4月の実行課題集 3
4月の実行課題集 3
お花見と桜餅、公園のご飯

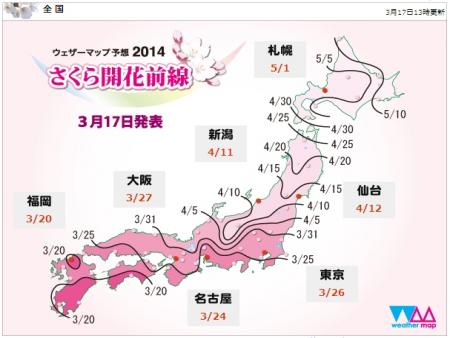
神様のおもてなし
四月になると日ごとに暖かくなり、桜の花や野の花が咲き始めます。桜の花に誘われてお花見に行く人も多いことでしょう。
今では桜を見ながらご馳走を食べたりお酒を飲んでみんなで楽しむお花見ですが、元々は農作業を始める前の卯月(四月)八日に、山から桜の木に降りてきた神様を料理と酒でもてなし、人々も一緒にいただくということがお花見とされていました。桜の花の開花具合によって、その年の作物の出来具合を占ったり、桜の木にはお神酒やお供え物をして、一年の豊作を祈ったのです。この日は神様のために農作業は休まなければなりませんでした。単に人々の楽しみではなく、農耕に結びついた重要な行事だったのです。
娯楽としてのお花見が人々の間に広まったのは、豊臣秀吉の時代から江戸時代にかけてとされています。宴会好きの江戸っ子に受け入れられ、江戸庶民に広まっていきました。
桜餅を作ろう
お花見のお供に「桜餅」はいかがでしょうか。桜餅には江戸風の「長命寺桜餅」と関西風の「道明寺桜餅」がありますが、今回は道明寺粉で作る関西風です。電子レンジを使えば短時間で簡単にできます。耐熱ボウルひとつですむのもお母さんには嬉しいところ。道明寺粉のもちもち感と桜の葉の香りがたまりません。おうちで親子で作って、お花見へ出かけるのもいいですね。
◎材料
・道明寺粉
・砂糖
・水
・食紅
・あん
・桜の葉
朝ご飯は公園で
朝早く、シートを持って、ご飯とおかずを用意して、近くの公園に出かけましょう。
まだ誰も来ていないさわやかな公園で朝ご飯を食べると、縄文時代に戻った気がします。
ご飯とおかずと味噌汁と食器とシートを持って行くだけですから、特にお弁当などを作る必要がなく簡単にできるのがいいところです。不精な人向け。^0^
ただ公園に行ってご飯を食べるという単純なことですが、これが意外と新鮮なのです。
 4月の実行課題集 4
4月の実行課題集 4
タンポポの笛、イチゴゼリー


タンポポの笛
春といえばタンポポ。おさんぽの最中にタンポポを見つけたら、ぜひ笛を作ってみてください。
作り方は簡単。タンポポの茎をちぎる。茎の片側を指でつぶす。つぶした方をくわえて吹く。
茎の長さや、太さによって音が違います。経験から言うと、太い茎がなりやすいです。(綿毛がついているタンポポなど)細い茎だと、吹くのにかなり力がいります。
吹くのにはコツがいりますが、そのうちコツをつかんで吹けるようになると思います。みんなでやれば、ちょっとした音楽会ができそうですね。
カラスノエンドウやスズメノテッポウも笛になります。
スズメノテッポウの場合は、穂の部分を抜き取り、抜き取ったところを口でくわえて吹きます。葉は下向きに。
穂を抜き取るとき、そうっと抜くのがポイントです。
小学校が遠く、通学路が田んぼ道だったのでいろいろな草笛を吹きながらみんなで帰ったものです。^^
イチゴゼリーを作ろう
○イチゴ1パック(つぶすので、特売の小粒のもので十分です。)
○ゼラチン(粉なら5グラム、板なら4.5グラム
○砂糖大匙1杯
○水100cc
1、イチゴを洗い、へたを取る。(このへた取りをお子さんにやらせてください。おうちの方はへたを取った後のでっぱりを包丁で切り落としてください。)
2、耐熱容器にゼラチンと砂糖大匙1と水100ccを加える。
3、イチゴをビニール袋に入れて、つぶす。(お子さんと一緒に手でつぶします。袋に穴があかないようご注意ください。)
4、耐熱容器を電子レンジに入れ、500ワットで1分20秒~40秒加熱する。
5、4につぶしたイチゴを入れて混ぜる。
イチゴは果物?
イチゴは果物だと思われていますが、畑で採れるため、野菜の仲間です。
また、イチゴの果実と思われている部分は、実は果実ではありません。本当の果実はイチゴのツブツブの部分です。私たちが果実だと思っていたところは、めしべの土台が発達したものなのです。
イチゴはへたとは反対側が一番甘いので、大きいイチゴを手で持って食べるときは、へたのそばから食べると最後まで甘く、おいしく食べられます。