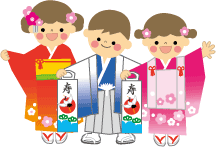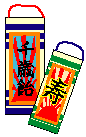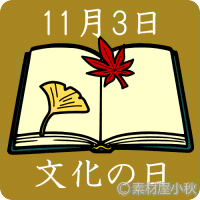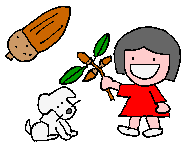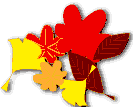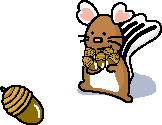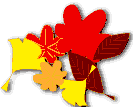11月の実行課題集 1
11月の実行課題集 1
七五三・千歳飴・計量記念日

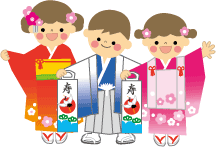
七五三おめでとう!
「七五三」とは、三歳の男女、五歳の男の子、七歳の女の子が11月15日に神社や寺にお参りをし、無事に成長できたことへの感謝と将来の幸せをお祈りする行事です。昔は医療などが未発達で小さな子供が命を落とすことが多かったことから、「七つ前は神のうち(七歳未満の子はまだ神様のもの)」と言われ、神様が子どもの運命を決めると考えられていたそうです。
「七五三」の由来には次のようなことがあります。
・三歳の「髪置き」のお祝い~江戸時代は三歳までは髪を剃る習慣があったため、髪を伸ばし始める儀式がありました。これを「髪置き」と呼んでいます。
・五歳の「袴着」のお祝い~初めて袴をつける儀式です。男女ともに行われていましたが、江戸時代から男の子だけの行事になりました。
・七歳の「帯解き」のお祝い~七歳になった女の子はそれまでの紐で結んでいた着物から、初めて帯を結ぶ着物を着るようになります。この儀式を「帯解き」といいました。帯をしめることで魂が外に飛び出さないようにする意味もあるそうです。「魂が外に出ていってしまったら、いたましいねえ!」
千歳飴を作ってみよう
千歳飴は、おうちで簡単に手作りすることができます。
【材料】(作りやすい分量)
★粉糖 大さじ4
★クリーミーパウダー 大さじ4
★コンデンスミルク 大さじ2
【作り方】
1.ボールに、粉糖、クリ-ミーパウダーを入れ、よく混ぜる。
2.コンデンスミルクを入れ、手でこねる。
3.まな板の上にラップをしき、ひも状に成形する。
白い千歳飴ができます。2の状態の時に抹茶を加えれば緑色、ココアを加えればチョコレート色の千歳飴もできます。それぞれの色をねじったり、マーブル模様にするのも楽しそうですね。(その場合は、小さじ4くらいの分量がよいでしょう。)
11月1日は何の日
11月1日は、「計量記念日」「寿司の日」「灯台記念日」「紅茶の日」「犬の日」など、いろいろな記念日になっています。
まずは、お酢、砂糖、塩などの分量を計って、太巻き寿司を作ってみましょう。中身は、かんぴょう、玉子焼き、きゅうり、カニカマ、でんぶなど、お好みで。その太巻き寿司を持って、灯台見学に行くというのはいかがでしょうか。見学が終わったら、紅茶を飲みながらおやつタイム。おいしそうなにおいに誘われて、犬も「ワンワンワン(111)」と吠えながら寄ってくるかもしれません。
 11月の実行課題集 2
11月の実行課題集 2
文化の日・紅葉狩り


文化の日
11月3日は「文化の日」です。1946(昭和21)年、日本国憲法が公布された日です。平和と文化を重視したこの日本国憲法が公布されたことを記念して、1948(昭和23)年に「自由と平和を愛し、文化を薦める」国民の祝日として定められました。なお、11月3日は、それまでは天長節や明治節と呼ばれ、明治天皇の誕生日による休日となっていました。
この日は、「文化を薦める」ということで、文化祭などが行われ日頃の文化・芸術活動の発表があったり、様々なイベントが催されたりします。自分でも何かを発表したり、作品を出すという人もいるのではないでしょうか。また、それを見に行くという人もいるでしょう。
小学生だと「こどもまつり」のような、参加したり体験したりして楽しめるイベントもありますね。作文のいい題材になりそうです。
台風も過ぎてお天気も安定してきました。ぜひ、いろんなイベントへ足を運び、作文の種を集めてみてください。
紅葉狩り
「秋を見つけたこと」という題名で作文を書く週がありました。友達は、落ち葉、栗、どんぐり、カキ……。いろいろな秋を見つけたようですが、我が家は銀杏を持っていきました。銀杏を拾うところから始め、洗って、皮をむきました。素手でするとかぶれてしまうので、手袋をはめて銀杏をむきました。むいた実を観察すると、実にもオスとメスがあって、形が違うということがわかりました。平安時代では貴族の間で紅葉狩りが流行したそうです。庶民にもこの楽しみが広まったのは江戸時代。紅葉は食べられないので、つまらないという人は、紅葉に限定せず、いろいろな秋を見つけに行くといいですね。
割り箸鉄砲作り
割りばし鉄砲を
作り、
自分の
鉄砲を
使って
射的をします。
割りばしと
輪ゴム、それから、
射的用の
お菓子やおもちゃなどを
用意すれば、
手軽に
遊べます。

http://toy7.net より
 11月の実行課題集 3
11月の実行課題集 3
勤労感謝の日・酉の市


勤労感謝の日
11月23日は、は「勤労感謝の日」です。「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝し合う」ことを趣旨として、1948(昭和23)年に制定されました。これは「新嘗祭」に由来し、農作物の収穫を感謝する儀式であったとされています。「働く人に感謝する日」と思いがちですが、それだけではなかったのですね。
言葉の森では「お米」についての課題が最近続いていますが、いつも美味しいお米を食べられることが当たり前なのではなく、目には見えない多くの人々の働きや自然の力によることに感謝していただきたいですね。家族みんなで食事をしたことなど、作文に書けそうです。
そして、家では家族のために働いてくれるお父さんや、お母さん、おじいちゃんやおばあちゃんに感謝して過ごしたいものです。感謝の気持ちをお手伝いやお手紙、「いつもありがとう」の言葉であわらしてみましょう。
酉の市・熊手作り
酉の市とは、例年11月の酉の日に行われる「祭礼」です。「縁起熊手」を売る風習は全国各地にあります。
酉の市に行って、威勢のいい掛け声を聞きながら屋台をのぞくのも楽しいものですが、オリジナル熊手を作ってみるのも面白いと思います。
100円ショップで売られている熊手に、小判、お札、松竹梅、鶴、亀、鯛、扇、花など、縁起のいいものを飾りつけしてください。できあがった熊手は、おうちの人に飾ってもらいましょう。きっと福が舞い込んでくるでしょう。
スライム作り
不思議な触感のスライムを作ってみましょう。
【用意するもの】
ほう砂(薬局で売っています)・洗濯のり(PVAという表示のもの。100円ショップで購入可能。)・好きな色の絵の具・洗面器やボウル・コップ3つ・スプーン
【作り方】
1.コップに洗濯のりを注ぐ。
2.同じ分量の水を用意して、好きな色の絵の具を加え、よくかき混ぜる。
3.コップ四分の一くらいの水を注ぎ、ほう砂をスプーン一杯分加え、よくかき混ぜる。
4.洗濯のり、色水をよく混ぜる。そこへ、ほう砂を入れた水を加えさらにかき混ぜる。
ほう砂を加えるとすぐ、固まり始めます。水気がなくなってきたら手にとってまとめましょう。
 11月の実行課題集 4
11月の実行課題集 4
芸術の秋


木の実でアート
石や落ち葉でもさまざまな作品が作れますが、もう一つ、木の実でも手軽に工作を楽しむことができます。公園や林、山などでは、マテバシイ、シラカシ、コナラ、ツブラジイ、トチ、メタセコイヤ、ジュズダマなど、いろいろな木の実を見つけることができます。それぞれのその形をいかして木の実工作が楽しめます。
<用意するもの>
木の実(煮沸消毒した方が雑菌もなくなりますし、どんぐりの割れるのを防ぐことができます。)・接着剤・ピンセット・ハサミ・ポスターカラー(極細)・フエルト生地等・かまぼこなどの木の板
作り方は特に決まっていません。板の上などに、木の実を好きなように置いて接着剤でつけていきます。ポスターカラーで模様や顔を書いてもおもしろいですよ。
身近にある自然のもので芸術の秋を楽しみましょう。「芸術の秋なんて飽き飽きだあ。」なんて言っている人は誰ですか?!
石でアート
秋には山や川へハイキングやキャンプに行くことがあるでしょう。そんな時、少し足下を注意してみると、面白い形の石が落ちていることがあります。そんな石ころを持ち帰り、絵の具でペイントしてみましょう。
よくよく見ているうちに、 「この石は細長くて電車みたいだ」「いや、こちらの石は大好きなあのキャラクターにかっこうが似ている」「いやいや、あっちの石はお父さんの顔の形にそっくり」など、むくむくと想像がわいてくることがあるはずです。思いきって筆を手にとり、そのイメージを石ころに描いてみてください。
描き始める前に石の表面をたわしで洗う、やすりで削るなどしてきれいにしたり、着色が終わったあとにニスを上塗りしたりと、「加工」に一手間かけると、完成度がより高まりますよ。
落ち葉でアート
落ち葉もアートの素材になります。立体的な石ころアートと違うのは、「色合いがそれぞれに異なる」「紙に並べて組み合わせることができる」というところです。
紅葉した落ち葉を使って、赤・白・黄色のチューリップを作ってみたり、茶色の落ち葉をぐるりと一周させて、ライオンのたてがみを作ったり……。たくさん集めて、巨大な生物の姿を作れたら、きっと迫力満点のはず。
さらに、とくに面白いのが「虫食いの穴が空いている葉っぱ」です。 二つ並んで空いた穴が、まるで人間や動物たちの目、口のように見えてきませんか。これが洋服、これが帽子。穴の空いた葉っぱが顔で、五つに分かれたカエデは両手に……といった感じで、森の妖精が作れるかもしれません。