印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■7月1日(木)から新学期
■通信生の住所シール・項目シールの使い方
■5月の賞状を同封
■賞品の引き換え
■賞品はホームページから
■五感と自己確立
|
|
||
|
言葉の森新聞
2004年7月1週号 通算第845号
文責 中根克明(森川林) |
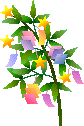
|
|
|
|
||
|
|
||||
| ■7月1日(木)から新学期 |
|
7月1日(木)から新学期が始まります。7月からの教材の説明は、6.4週の山のたよりに同封してあります。 教材は6月28日ごろまでに届いているはずですが、万一まだ届いていないという場合はご連絡ください。 教材の説明は、「学習の手引」にも載っています。 Http://www.mori7.com/mori/gate.html |
|
|
||||
| ■通信生の住所シール・項目シールの使い方 |
|
通信の生徒には、7.1週の山のたよりに住所シール・項目シールが同封されています。 住所シールには、先生の住所が印刷されています。封筒用紙に貼ってお使いください。 項目シールには、週ごとに項目シール又は生徒コードシールが印刷されています。作文・感想文の週は、作文用紙に項目シールをはり、生徒コードは手書きで入れてください。清書の週は、項目シールははらずに、生徒コードシール(バーコードシール)を貼ってください。 |
|
|
||||
| ■5月の賞状を同封 |
|
5月2週の進級試験で、字数が規定以上、構成・題材・表現・主題の4項目のうち3項目が◎で1項目が○以上、の人には認定証を同封しています。字数賞・自習賞・作文賞・皆勤賞は、金賞10クラウン、銀賞5クラウン、銅賞1クラウン、賞外0クラウンです。認定証は今回から10クラウンにしました。(前学期まで1クラウン) 金賞は点数の上位10%、銀賞は10〜20%、銅賞は20〜80%。それ以外は賞外です。 それぞれの賞で点数がなかった人や、5月2週に在籍していなかった人には、賞状は入っていません。 |
|
|
||||
| ■賞品の引き換え |
|
「50クラウン」で、ひとつの賞品と引き換えできます。山のたよりの右上に印刷されている自分のクラウン数を確認して、申し込んでください。クラウン数の足りない人は、次の引き換えのときに、申し込んでください。あまったクラウンは、(または、使わなかったときは)次の賞品引き換えに使えます。 「賞品引換券」に全部記入して、先生宛に作文と一緒に送るか、言葉の森宛に送ってください。賞品の数に限りがありますので、第2希望まで書いてください。第2希望の記入がない場合は、こちらで選ばせていただきます。 ■賞品引き換え券 − − − − − 切 り 取 り 線 − − − − − − 生徒コード____お名前____________学年___年 第1希望(賞品番号と賞品名)_________________ 第2希望(賞品番号と賞品名)_________________ − − − − − 切 り 取 り 線 − − − − − − ※賞品引換券は、同じような形式で封筒用紙に書いていただいても結構です。 ※賞品引換券は、ホームページの「賞状の山」のページから送ることもできます。 賞品のカラー写真はホームページの「賞状の山」に掲載されています。 http://www.mori7.com/yama/syouhinn.php |
|
|
||||
| ■賞品はホームページから |
|
賞品の引き換えは、ホームページから行うと便利です。 「賞状の山」 http://www.mori7.com/yama/syouhinn.php 自分の手持ちのクラウンを確かめて、ホームページから希望の賞品を選択してください。 ホームページから毎月月末までに注文があった賞品は、次の月の第2週の「山のたより」と一緒に送ります。 |
|
|
||||
| ■五感と自己確立 |
 五感とは、目、耳、舌、鼻、皮膚を通して生じる五つの感覚のことです。つまり、視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚の五つの感覚です。これらの感覚は、いつも外界と自分とをつなぐ役割をしています。私たちは、五感によって、外の世界を内へと取り入れ、自分なりに消化しているのです。五感こそが自分というものを認識し、確立する基盤になっていると言っても過言ではないかもしれません。というのは、私たちの心は、何かを感じ取ることによって反応するからです。もし、五つの感覚が何の役割も果たさなくなったら、私は私でなくなってしまいます。つまり、五感がなかったら、自分は無になってしまうということです。逆に考えると、自分の五感をより強く意識することによって、より確かな自分を築き上げることができるということになります。 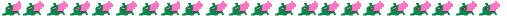 今、目に映っているものは何か、どんな音が聞こえてくるか、そんなことを一つ一つ意識し、五感を研ぎ澄ませることによって、自分の内側の世界も変わってくるはずです。それは、ありのままの現実を素直に取り入れる作業でもあります。一つ一つの感覚をフル活用してみると、私たちがいかに先入観にとらわれたものの見方をしていたかに気づくかもしれません。また、いかにおおざっぱなものの見方をしていたかに驚くかもしれません。そして、普段、五感をほとんど活用していなかったということを認めざるを得なくなるのではないでしょうか。今、あなたの目、耳、舌、鼻、皮膚が何を感じているか少しだけ意識してみてください。道端に咲く可憐な花の色、夕方の町の喧騒、ツツジの花の蜜の味、雨上がりの公園に漂う木の葉の香り、吹き抜けていった風の冷たさ、そんな感覚を一度じっくりと味わってみてください。 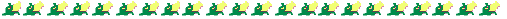 自分で感じたことを自分の言葉で表現する、それが作文を書くということで、自分で感じていないことを言葉にしても読む人の心に響くような作文にはなりません。自分の五感で得たことを精一杯表現しようとした作文からは、その生きた感覚が伝わってきて、読む人は心を動かされます。もちろん、年齢によって表現力や語彙力には差がありますが、幼い言葉で書かれていても、それが書き手の実感なのだということがありありとわかる文章に人は心を打たれるものです。感想文に体験実例(似た話)を入れるのも、長文の内容をいったん自分の問題として自分の内に取り込み、自分自身の生の体験を書くことで、自分の感じ方を直接表現したインパクトのある作品に仕上げることができるからです。 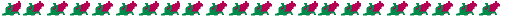 そして、五感を大切にしながら作文を繰り返し書くことは、自己を確立していくことでもあります。先にも書いたように、人は何も感じなければその存在すら意味のないものになってしまいます。外とのつながりによって初めて自分の存在を確認していくものなのです。外の世界を知り、それを受け入れ、自分の内で考えることにより、人は、自分というものを少しずつ確立していくのです。感じ取ることが多ければ多いほど、私たちは心豊かに自己を充実させていくことができます。確かに、いつも何かを感じ取ろうとぴりぴりしていてはとても疲れてしまいます。でも、そんなときは、五感の喜ぶ環境に身を置くこともできるわけです。好きな絵を見たり、好きな音楽を聴いたり、おいしいお料理を味わったり……。そんなふうに五感をうまく活用しながら、自己を確立していくことができたら幸せではないかと思いますし、それこそが生きている意味なのではないかと思います。自己とは、内側に自然に備わっているものではなく、外側の世界との接触によって生まれてくるものなのです。だから、外側の世界にもっと敏感に、積極的に関わっていくことが大切なのではないでしょうか。もっと五感を活用して外側の世界とのつながりを強めればきっと自分の内の何かが変わってくると思います。  山田純子(メグ) 山田純子(メグ) |
|
|
|
|
||||


















































