印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■10月1日(金)から新学期
■通信生の住所シール・項目シールの使い方
■賞状は10.2週に送ります
■作文検定スタート
■記憶よりキロク(あかね/つね先生)
■純粋に楽しむ(はちみつ/おと先生)
■皆さんは、今どんな本を読んでいますか。(クマのプーさん/さと先生)
■ボランティア(こう/ふつ先生)
■アテネオリンピック(まあこ/ゆた先生)
|
|
||
|
言葉の森新聞
2004年10月1週号 通算第857号
文責 中根克明(森川林) |

|
|
|
|
||
|
|
||||
| ■10月1日(金)から新学期 |
|
10月1日(金)から新学期が始まります。10月からの教材の説明は、教材に同封してあります。 教材は9月30日ごろまでに届いているはずですが、万一まだ届いていないという場合はご連絡ください。 教材の説明は、「学習の手引」にも載っています。 Http://www.mori7.com/mori/gate.html |
|
|
||||
| ■通信生の住所シール・項目シールの使い方 |
|
通信の生徒には、10.1週の山のたよりに住所シール・項目シールが同封されています。 住所シールには、先生の住所が印刷されています。封筒用紙に貼ってお使いください。 項目シールには、週ごとに項目シール又はバーコードシールが印刷されています。作文・感想文の週は、作文用紙に項目シールを貼り、生徒コードは手書きで入れてください。清書の週は、項目シールは貼らずに、生徒コードの欄にバーコードシールを貼ってください。 |
|
|
||||
| ■賞状は10.2週に送ります |
| 9.1週の作文進級試験の賞状は、10.2週にお送りします。 |
|
|
||||
| ■作文検定スタート |
|
作文検定を行うための会社を9月3日に作りました。名称は、株式会社日本語作文小論文検定協会です。 10月24日(日)に全国で作文検定試験を行うので、そのためのパンフレット作りが最初の仕事でした。 ホームページは、一応できていましたが、印刷会社に出すためには、これをイラストレーターというソフトで開けるファイルに直さなければなりません。そこで、急いで近くのヨドバシカメラに行ってソフトを買い、近くのブックスキタミという書店でイラストレーターの本を7冊買い、一挙に読んで(一部だけ)やっと印刷できる状態に仕上げました。 この秋、みなさんの通っている学校や塾でも、作文検定を始めるかもしれません。 |
|
|
||||
| ■記憶よりキロク(あかね/つね先生) |
|
かれこれ十数年前、先生がまだ仕事をはじめたばかりのころ、「記憶(きおく)よりキロク」と会社のせんぱいから教わったことがあります。そのころはピンときませんでしたが、最近そのとおりだと気づきました。 むかしのことを振り返ると、部分的に思い浮かぶ一瞬一瞬(いっしゅんいっしゅん)はあるけれど、正確に言葉にはできません。もしその場にいた相手がその事を忘れていたら、本当にそんなことがあったのかどうかもあやしいなぁ、などと考えて見ます。ちょっとむなしくなります。(^^; 最近、先生も、インターネット上で「ブログ」という日記をつけはじめました。なかなか楽しいです。俳優(はいゆう)さんでもない限り、フィルムに一瞬一瞬(いっしゅんいっしゅん)の自分の姿を残したりすることはできません。だからこそ、自分の生きたキロクを残そうと、今、日記(ブログ)をつけることが、流行なのだと思います。みなさんが書いている作文も、あとからふりかえると、きっと、大切な宝物になることでしょう! |
|
|
|
|
||||
| ■純粋に楽しむ(はちみつ/おと先生) |
|
もう新学期が始まってだいぶたちましたね。すっかり学校のペースに戻ったころでしょう。あんなに暑かった夏も終わり、やっと涼しくなってきましたね。みなさんは、そろそろ運動会の練習や文化祭の準備などで、毎日が楽しく、充実していることでしょう。気分も新たに勉強やスポーツにはげんでいるのではないでしょうか。 運動会や文化祭、音楽祭などいろいろな行事ごとは、周囲の人達と共同で作り上げていくものですよね。1つのパーツに過ぎない自分は全体が見えず、ときにつまらないこともあります。長時間にわたる練習や準備の中でもめたり、疲れたり、投げ出したくなることもあるでしょう。練習そのものはおもしろいものでも、愉快でもないでしょう。成果を披露したとき、見てもらい認められたとき、自分の活躍を作品を演奏を楽しみ、喜んでくれる人の存在に気づきます。それが励みになり、意欲へとつながっていくのでしょう。 みなさんもなかなか作文を書いたり、仕上げたり、提出することが難しかったりすることがあるようですね。しかし、読んでくれる人がいる、自分の作品を心から楽しんでくれる人がいる、ということはとても大きなことです。 私はいつもみなさんの作文を楽しみに待っています。電話で話したときにもっと話が弾むからです。みなさんから教えられることもたくさんあります。ヒントを言うときに全然思いつかなかった実例やダジャレやたとえで、みなさんの鋭い観察力や新しい視点に驚かされます。 そして、私の子供もずっと言葉の森を続けてきているのですが、みなさんの作文の内容のおもしろさや感じ方、意見に感心しています。全てに目を通すわけではないのですが、純粋に楽しんでいます。この「純粋に楽しむ」ということが大事なのでしょう。このことを伝えて、どんどん作文を送ってくれるようになった人がいます。そしてまた、送られてくる作文を喜ぶ。こういう交流をこれからもっと作っていけたらいいなぁ、と思っています。 |
|
|
||||
| ■皆さんは、今どんな本を読んでいますか。(クマのプーさん/さと先生) |
 私は指輪物語を読んでいます。映画は「ロード・オブ・ザ・リング」三篇ともみたのですが、最近原作を読み始めて、また違った面白さ、奥深さがあってかなりはまっているところです。世間とはだいぶずれています。本編も先は長いけれど、関連本で面白そうなものもたくさんあるので、まだまだこれから楽しみが続きそうです。  小学生の頃は、読書が大好きな家族・友人に囲まれていたものの、私自身は長編を読むのは苦手な方でした。だから、以前作文用紙に「今読んでいる本」という欄がありましたが、生徒さんの書いている題名をみて、感心したり頼もしく思ったりしたものです。  9.1週のある課題で高齢化・少子化というテーマがありました。M君は「住みやすい町に」という題名で意見と具体的な解決策を展開していました。うちの近くの小学校の校庭にコミュニティハウスがあり、いろいろな人が持ち寄った本を読むことができます。図書館をたくさん建てるのは大変でしょうが、一生読書を楽しむために、こういうコーナーをもっと増やすことは簡単です。いろいろな本にふれられるし、家に眠っている本も活性化できるし、一石二鳥かと思います。  読書の必要性や本を読む意義についていろいろな論を見聞きしますが、私は以前テレビで釘付けになったことがあります。それは、皇后陛下が国際児童図書評議会(IBBY)の大会でなさった基調講演の中の『ある時には私に根っこを与え、ある時には翼をくれました。この根っこと翼は、私が外に、内に、橋をかけ、自分の世界を少しずつ広げて育っていくときに、大きな助けとなってくれました。』というお言葉です。  読書の秋。皆さんはどんな本に出会うのでしょうか。電話の時に、読んで感動した本や面白かった本の話もどんどん聞かせて下さいね。 |
|
|
|
|
||||
| ■ボランティア(こう/ふつ先生) |
 新学期が始まりました。1ヶ月以上続いた夏休みの生活リズムから抜け出すのに苦労していませんか? だるくてやる気が出ないという声が聞こえてきそうです。大丈夫かな? 新学期が始まりました。1ヶ月以上続いた夏休みの生活リズムから抜け出すのに苦労していませんか? だるくてやる気が出ないという声が聞こえてきそうです。大丈夫かな?今年は台風の当たり年のようです。豪雨(ごうう)で大きな被害(ひがい)が出ています。 先生のすむ愛媛県新居浜市でも8/18に集中豪雨がありました。今まで経験したことのない雨の量でした。さいわい先生の家では目立った被害もなく無事に過ごすことができましたが、同じ市内では胸まで水に浸かって(つかって)しまった地域がありました。土砂崩れのせいで水だけでなく泥に埋もれた家もあります。 夏になると、24時間テレビで「愛は地球を救う」と募金活動を始めます。そのテレビのCMが増えてきた頃、先生は新聞で興味深い投稿を見つけました。投稿者は中学生。「愛が大切なのは自分もそう思う。ボランティアだって大切だ。でもお金は?愛をお金で募集するの?募金することがボランティアなの?」という趣旨の投稿でした。みなさんはそのことについてどう思いますか? 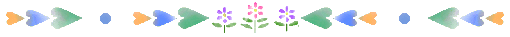 ボランティアに継続して取り組んでいる人にしかられそうですが、以前先生はボランティアをしている人を敬遠していました。 骨折をして2ヶ月歩けず、その後も6ヶ月近くリハビリをしてようやく通院せずに毎日の生活を過ごすことができるようになった経験があります。もちろんその間も会社に行っていましたし、外出も普通にしていました。 その頃、ボランティア熱心な会社の人にかけられたのが、「かわいそうに。なんでも手伝えることがあったら言ってね。」という言葉でした。 「歩く」という動作で精一杯の毎日。確かに手助けしてもらえるととてもうれしかったけれど、「私ってかわいそうなの?」と思いました。正直に言うと、少しショックでした。「大変だけど、かわいそうじゃない!」ってね。 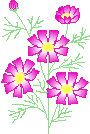 でも、今回の水害を目の当たりにしてボランティアに対する認識が改まりました。 家の中に泥が押し寄せ、何も持たずに逃げ出して、次の日から復旧作業が始まります。まずは手でちょっとずつ泥を外にかきだします。水の底にある重くてベトベトした粘土のような細かい泥です。それが昨日まで生活していた部屋の中にたくさんあります。 想像してみてください。みんなの家の台所、食卓、つくえの引き出し、みんな泥まみれ。まわりを見回して、さぁかたづけようと思ってもすぐに力が沸いて出るかな? やらなきゃいけないと思っても、力の出ない光景だと思います。 先生は、その様子をニュースで見て、そして自分の家のいつもと変わらないようすを見て、何かしなきゃ! と思いました。ボランティアってこういう気持ちから始まるのだと思います。 でも現実には1歳10ヶ月の小さな子がいて、お腹にも赤ちゃんがいます。とても泥をかたづける手伝いができる状態ではありません。気持ちはあるけど状況が行動に移すのを許さないこともあるのです。 そこでちょっとですが募金をしました。義援金(ぎえんきん)ですね。「お金で解決」ではなく、何もできないからせめてお金だけでもという気持ちです。 ボランティアは大切。募金をしようというお話ではありません。何かが起こったときあなたはどう考え、どう動くでしょうか。洪水や地震といった災害でなくてもいいのです。自分自身や周囲の人につらいことがあったとき。幸運にも近くで目にする機会がなければ想像してみましょう。もし自分がそうなったらどうだろう?と。 それが毎日の生活に影響を与えることはないかもしれません。実際にそんなことばかり考えていられる人などいないですね。でも、想像することは無駄ではありません。心の動きに敏感(びんかん)になることは、鈍感よりも価値があります。 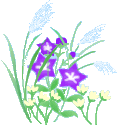
|
|
|
|
|
||||
| ■アテネオリンピック(まあこ/ゆた先生) |
|
アテネオリンピック! 最高でした。日本選手の活躍をみなさんもテレビで応援しましたか? 前回の学級新聞でオリンピックに向ける期待を書きつらねさせてもらいましたが、私自身、こんなにすごい大会になるとは思ってもいませんでした。 ニッポン強し!! うれしい寝不足の日々でした。選手のみなさんありがとう! とくに感動したのは、女子マラソンです。野口みずき選手がみごと金メダルを獲得しました。 前号で紹介したように、その道を走ったギリシャの戦士は命を落としたという過酷(かこく)なコースです。数多くの脱落者が出ました。実際にレースを見に行った人の話によると、その日は体をわしづかみされるような暑さだったそうです。野口選手もゴールしたときには熱中症にかかっていたと聞きました。一歩間違えば本当に死んでしまうかもしれないような命がけのレースだったのです。 しかし、彼女は勝ちました。強い、強い、強い! そこには、きたえられた体だけではない、強い精神力がみなぎっていました。神々しいパナシナイコスタジアムに野口選手の栄光が輝きました。\(*T▽T*)/感動 今回のオリンピックで、次から次へと金メダルを取っていく日本人選手を見ていくうちに、「日本人は変わった」という思いがわきおこってきました。 昔の日本人選手は、期待されていても力を出し切れず、結果を残せないことが多くありました。「日本人は体も小さいし、勝てるような気がしないなぁ。……あぁ、やっぱり負けちゃった」ということがよくあったのです。選手自身も、「国民の皆さんに申し訳ない」とばかりにかくれるようにして落ち込んでいました。 しかし、今回は、期待以上の成果を上げた選手が数多くいました。日本の代表として世界の大舞台に立つ姿には、プレッシャーに押しつぶされないどころか、プラスにしてしまうくらいの精神力を感じました。見ていても「負ける気がしない」と何度思ったことでしょう。また、思ったような成績を残せなくても、「精一杯がんばれました。ありがとうございました」とすがすがしい笑顔で乗りこえていける強さもありました。 そういう姿を見ているうちに、「日本人は変わったのだ」と感じたのです。その違いはなにか。ふと、そこには戦争に負けた記憶のボーダーラインがあるのではないかと気がつきました。私の親世代ぐらいまでは敗戦を体験しています。その親に育てられた子の世代までは、心のどこかに世界にはかなわないという感覚があるのです。しかし、今の若者は違います。世界に対する精神的な負の要因がない。だから強い。そんな気がするのです。 もちろん、二度と戦争を起こしてはいけないという教訓をしっかりと受けつぐために、私たち日本人は、悲惨な過去の現実を決して忘れてはいけません。しかし、吹っ切らなくてはいけない呪縛(じゅばく)もあるのですよね。 日本人選手のさわやかな笑顔が印象的でした。強くて若い日本人の新しい時代を感じたオリンピックでした。 世界から戦争がなくなったら、世界中の選手が自分の力を出し切れるようになるでしょう。そうしたら、オリンピックはますますおもしろくなりますね。オリンピックが本当の平和の祭典になりますように。 さて、未来を担(にな)うみなさんは、オリンピックからどんなことを感じましたか? さまざまな分野でみなさんも輝けるはずです。胸を張って進みましょう。 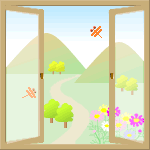
|
|
|
||||