印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■7月〜9月の賞状を同封
■皆勤賞の期間は5ヶ月間
■日本語作文小論文検定(作検)、スタート
■賞品の引き換え
■『博士の愛した数式』(ふじのみや/ふじ先生)
|
|
||
|
言葉の森新聞
2004年10月2週号 通算第858号
文責 中根克明(森川林) |

|
|
|
|
||
|
|
||||
| ■7月〜9月の賞状を同封 |
|
9月1週の進級試験で、字数が規定以上、構成・題材・表現・主題の4項目のうち3項目が◎で1項目が○以上の人には認定証を同封しています。字数賞・自習賞・作文賞・皆勤賞は、金賞10クラウン、銀賞5クラウン、銅賞1クラウン、賞外0クラウンです。認定証は10クラウンです。 金賞は点数の上位10%、銀賞は10〜20%、銅賞は20〜80%。それ以外は賞外です。 それぞれの賞で点数がなかった人や、9月1週に在籍していなかった人には、賞状は入っていません。 |
|
|
||||
| ■皆勤賞の期間は5ヶ月間 |
|
今年の4月1週から8月4週までの5ヶ月間で出席の多かった人に皆勤賞を出しました。 現在の時点の皆勤賞は、ホームページの「賞状の山」で見ることができます。 |
|
|
||||
| ■日本語作文小論文検定(作検)、スタート |
|
9月3日に、株式会社日本語作文小論文検定協会(日作)が発足しました。これは、日本語作文小論文検定(作検)を普及させていく組織で、言葉の森とは独立した形で運営していきます。 第1回の作検は、10月末に実施します(東京と神奈川の一部)。まだ公開会場が充分に手配できないので、全国での個人受検が可能になるのは先になります。当面は、学校や塾などの団体受験の中で受験していただくことになります。 英検や漢検と比べると、まだ知名度は全然ありませんが、これから日本の作文文化を創造するという展望を持って全国に広げていきたいと思っています。 作検の普及は、ブランドの構築にかかっています。インターネットの時代におけるブランドは、広告費ではなくクチコミに支えられています。ぜひ多くのみなさんが、「作検」や「作文検定」や「日本語作文小論文検定」という言葉をいろいろなところで話題にしてくださるようお願いします。その場合、できればいい話題でお願いします。(^^ゞ 日作のホームページは、こちらです。表紙の絵は、あお先生にかいてもらいました。 http://www.mori7.info/ |
|
|
||||
| ■賞品の引き換え |
|
賞品の引き換えは、ホームページの「賞状の山」のページから送ることができます。毎月月末までに送信されたものが翌月2週に賞品として送られます。 ホームページから送信ができない場合は、必要事項を「賞品引換券」に記入して、先生宛に作文と一緒にお送りください。この場合は、賞品の到着が翌々月の2週になります。 山のたよりの右上に印刷されている自分のクラウン数と賞品のクラウン数を確認の上お送りください。クラウン数の足りない人は、次の引き換えのときに、申し込んでください。あまったクラウンは(または、使わなかったときは)、次の賞品引き換えに使えます。 賞品のカラー写真はホームページの「賞状の山」に掲載されています。 http://www.mori7.com/yama/syouhinn.php ◆賞品引き換え券 (似たような形式で封筒用紙に書いていただいても結構です) − − − − − 切 り 取 り 線 − − − − − − 生徒コード______お名前______________学年____年 希望賞品番号と賞品名_______________ _______________ _______________ _______________ |
|
|
|
|
|
|
||||
| ■『博士の愛した数式』(ふじのみや/ふじ先生) |
|
読書の秋といわれますが、本を心のおやつにしている私は、一年中おいしい実(=本)をさがして読むのを楽しみにしています。 今月は、夏休みに私が読んだ本の中から、一冊を挙げてみましょう。 もう読んだ人もいるでしょうか。 『博士の愛した数式』(小川洋子) ベストセラーとしてさかんに宣伝されている本でしたので、みんな大好きな刺激のあるおもしろさなのかと敬遠していたのですが、たまたま図書館にあるのを手に取り、読んでみると……これが、よかった。 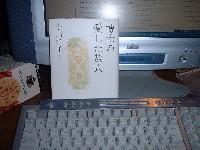 これから読む人がいるかもしれないので、筋書きは内緒にしておきますが、私が魅力を感じたのは、登場人物である「博士」が友人である11歳になる男の子をほめる場面です。 博士の記憶は病気のため、80分しかもちません。80分以上前のできごとはすべて忘れてしまうのです。ですから、一日に何度も「初めて出会うこと」があるのです。男の子が「前にもやったこと」「だれでもできそうな簡単なこと」をしても、「前」や「だれでも」は、博士の記憶には残っていません。 その結果、博士は男の子のすることに、いつも新鮮な感動を覚えるのです。たとえ間違いをおかしても、「ほらほら。また同じ間違いをする!」とか「前にも言ったでしょう」などという言葉は出てきません。そのかわり、「いいところに目をつけた」と、間違いが新しい発見であるかのように喜び、解決法を教えます。いつでも、何度でも(記憶がもたないから前の間違いは忘れてしまえるのですね)。 そのような中で、男の子はこの風変わりな博士のことを信頼し、大切な友人として思うようになります。博士が病気を辛く感じないように、さまざまな心配りをし、同時に博士の数学の世界に興味を持って取り組むようになるのです。それでめでたし、めでたし……だったらいいのですが。そのあとは想像してみてください。 記憶。私たちは毎日、多くのことを忘れないように覚えておこうとします。記憶によって迷わずに行動でき、よりよい結果をすばやく導くことができるのです。日々の音読や、作文の練習もそうですね。 でも、新鮮な驚きや、あやまちをゆるす気持ち、我慢強さなどは、記憶があることで働きが鈍りがちです。これらの人間同士を結びつけるのに必要な感情は、「前も」という記憶があるおかげで、広がりにくくなってしまうのではないでしょうか。もちろん、いやでも覚えてしまうのが人間ですので、目の前で起こったできごとをすぐに忘れてしまうことはできません。「忘れた」と解き放つことならできるかもしれませんが、これには心がけが必要ですね。そう考えると、記憶とは面倒なものだなあ。 日々、家庭で親として子どもと接していて、記憶しすぎているゆえに、「また?」などとつい口走ってしまう私の頭の一部にも、博士と同じ80分の記憶用ビデオテープがあれば……そのように感じながら読みました。 さて、こういう切り口で感想を述べると、大人向けのストーリーのように感じるかもしれませんが、そうではありません。算数に興味のある人、野球が好きな人、よい友達を作りたい人なら、楽しんで読めるエピソードがたくさんあります。比喩(たとえ)表現もすばらしい。小学校高学年ぐらいの人なら、じゅうぶん読めるおすすめの一冊でした。機会があったら手に取ってみてください。 ちなみに私は、図書館に返却してからその足で書店に行き、買いなおしました。 
|
|
|
||||







































































