印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■森リンの点数の生かし方
■「やさしい心」を耕す(ぺんぎん/いのろ先生)
■『火花―北条民雄の生涯』(くりくり/くり先生)
■想像力をやしなうこと、視野を広げること(ひまわり/すぎ先生)
■森リン得点アップ作戦 PART 2
|
|
||
|
言葉の森新聞
2004年10月3週号 通算第859号
文責 中根克明(森川林) |

|
|
|
|
||
|
|
||||
| ■森リンの点数の生かし方 |
|
森リンの点数は、素材語彙×(強力語彙+重量語彙)で計算されています。 このうち、強力語彙と重量語彙の点数は、年齢に比例して書く内容が高度になると自然に高くなってくる点数です。ですから、この強力語彙と重量語彙の点数を上げることは、当面あまり考えなくてもよいと思います。 重要なのは素材語彙です。この素材語彙は、話題が広くなるほど、そして文章の密度が濃くなるほど高くなります。 まず、話題を広げる方法です。 小学校高学年以上の生徒で、説明文や意見文を書いている人は、作文の中に入れる実例の幅を広げることが重要になってきます。例えば、実例を二つ書く場合、一つは自分の体験を書き、もう一つは家族に聞いた話や本で調べた話などを書くということです。似た実例ではなく、できるだけ分野の違う実例を探して書いていくことが大切です。中学生以上の人は、社会実例を入れるときに、昔話や伝記などから幅広く実例を探していきましょう。 次は、密度を濃くする方法です。 密度を濃くするためには、同じ言葉や言い回しをできるだけ使わないことです。森リンの評価を送信した直後に、森リンのグラフの「素材語彙○点○種」と書いてあるところをクリックすると、その作文でどういう言葉が素材語彙として使われたかが表になって表示されます。また、森リンのグラフの下の方には、素材語彙が赤い色で区別された文章が載っています。この素材語彙の種類を多くしていくと森リンの点数が高くなります。 素材語彙の種類を多くする方法は簡単です。自分の書いた元の文章を保存しておき、その中で言い回しを部分的に変えて、森リンのページで送信してみます。言い回しを変えただけで点数が高くなることもありますが、易しい言い回しに変えてしまうとかえって点数が低くなることもあります。これを何回も繰り返すと次第に密度の濃い文章になってきます。 しかし、言い回しを変えることによる点数アップは途中までは簡単ですが、ある段階から急に難しくなります。これは、言い回しを変えるだけでは限界があるということを示しています。それ以上点数を上げるためには、話題そのものを変えなければなりません。 森リンの点数を上げるためには、このように自分の書いた文章を何度も推敲して密度の濃いものにしていくことも大事ですが、より本質的には読書によって幅広い話題と豊富な語彙を身につけていくことが必要になります。森リンの点数と読書量の間には、かなり高い相関があります。 |
|
|
||||
| ■「やさしい心」を耕す(ぺんぎん/いのろ先生) |
 先生は大学1年の夏休みに、北海道を旅しました。寝袋(ねぶくろ)やテントを持ち、駅や山に寝泊りしながら、北の大地を一周したのです。小樽(おたる)の赤岩(あかいわ)というところには、絶壁(ぜっぺき)がありました。私は、そこで茶色にさびたハシゴを使い、断崖(だんがい:がけのこと)をソロリソロリと降りていたのですが、「ふわり」と、体が風に揺(ゆ)さぶられ、一瞬(いっしゅん)、命を落としそうになったのです。生まれて初めて「あ、今、命があぶない!」ということを肌で感じました。その時から、「今、命が“ある”ことは、不思議だな。」と思うようになったのです。 先生は大学1年の夏休みに、北海道を旅しました。寝袋(ねぶくろ)やテントを持ち、駅や山に寝泊りしながら、北の大地を一周したのです。小樽(おたる)の赤岩(あかいわ)というところには、絶壁(ぜっぺき)がありました。私は、そこで茶色にさびたハシゴを使い、断崖(だんがい:がけのこと)をソロリソロリと降りていたのですが、「ふわり」と、体が風に揺(ゆ)さぶられ、一瞬(いっしゅん)、命を落としそうになったのです。生まれて初めて「あ、今、命があぶない!」ということを肌で感じました。その時から、「今、命が“ある”ことは、不思議だな。」と思うようになったのです。 でも、私達の生活は、毎日「危険」を感じるわけではないですね。それは同時(どうじ)に、「安全」であることへの感謝(かんしゃ)もわすれてしまうということでもあります。 でも、私達の生活は、毎日「危険」を感じるわけではないですね。それは同時(どうじ)に、「安全」であることへの感謝(かんしゃ)もわすれてしまうということでもあります。高校一年の春、地学(ちがく)の先生に「みんなぁ。家から学校まで、土を踏(ふ)んで来た者はいるかー?」と、質問されました。その時、私は「あれ? 土を一回も踏まずに学校に来ちゃったな。」と気付かされました。手を上げた人がまばらで驚(おどろ)いたのを覚(おぼ)えています。 みなさんはいかがですか? あ、ぼくも(私も)と、思った人もいるのではないかな? 土や、でこぼこ道を踏むことなく、アスファルトの上だけを歩いて、どこまでも行けてしまうのが、「今の日本」ではないでしょうか。  しかし今、世界ではいたましい事件が数多くおこっています。テレビでは悲しいニュースが毎日のように報(ほう)じられています。家族の人も「なぜこんなことが?」、「ひどいなぁ、かわいそうに・・・・・・・」と、テレビを見ながら口々に言っておられることでしょう。 しかし今、世界ではいたましい事件が数多くおこっています。テレビでは悲しいニュースが毎日のように報(ほう)じられています。家族の人も「なぜこんなことが?」、「ひどいなぁ、かわいそうに・・・・・・・」と、テレビを見ながら口々に言っておられることでしょう。日本での生活はとても安全で、本当に感謝なことです。でも、「私達の幸福が、ほかの人々の不幸に支えられているのであってはならない」という名言があるように、みなさんもぜひ、世界の出来事(できごと)を「自分のことのように思いやる心」を見つけていってほしいなと思います。(先生もまだまだです。)  作文を書くことがなぜいいのか。それは、そういう「やさしい心」を耕(たがや)し、色々なことを考えるきっかけをみなさんにプレゼントしてくれるからです。感じたこと、思ったことを書いてみることで、どんどん心は豊かにされていくのです。みなさんの毎日が一日、一日と足されることをときには深く感謝して、これからも、一つ一つの作品を書いていきましょう。きっと毎日が感動(かんどう)の連続になることでしょうから・・・・・・!(^v^) 作文を書くことがなぜいいのか。それは、そういう「やさしい心」を耕(たがや)し、色々なことを考えるきっかけをみなさんにプレゼントしてくれるからです。感じたこと、思ったことを書いてみることで、どんどん心は豊かにされていくのです。みなさんの毎日が一日、一日と足されることをときには深く感謝して、これからも、一つ一つの作品を書いていきましょう。きっと毎日が感動(かんどう)の連続になることでしょうから・・・・・・!(^v^)
|
|
|
||||
| ■『火花―北条民雄の生涯』(くりくり/くり先生) |
 読書にはもってこいの季節になりましたね。 皆さんは今、どんな本を読んでいますか。 先生は、高山文彦の、『火花―北条民雄の生涯』という本を読みました。 北条民雄は、『いのちの初夜』という本を書いた作家で、ハンセン病にかかっていました。 皆さんはハンセン病って知っていますか?今でこそ感染力の弱く、完治する病気だと知られていますが、北条民雄が生きた大正から昭和初期の日本では、「癩病」と呼ばれ、不治の病だとされていました。皮膚が爛れ,人の形がだんだんと崩れていくという,非常に残酷な病気だったのに加え,つい最近まで,癩予防法により,この病気にかかると隔離され,人としての生活を奪われていました。 ハンセン病患者はハンセン病にかかることにより、肉体的にだけでなく、社会的にも死んでしまうのです。 北条民雄という名前も本名ではありません。ハンセン病患者が身内にいると、親類縁者さえ、差別されてしまうため、彼は自分の名前も、経歴も彼の過去全てを捨てざるを得なかったのです。 「人間ではありませんよ。生命です。生命そのもの、いのちそのものなんです。僕の言ふこと、解つてくれますか、尾田さん。あの人達の『人間』はもう死んで亡ぴてしまつたんです。ただ、生命だけが、びくびくと生きてゐるのです。なんといふ根強さでせう。誰でも癩になつた刹那に、その人の人間は亡ぴるのです。死ぬのです。社会的人間として亡びるだけではありません。そんな浅はかな亡び方では決してないのです。廃兵ではなく、廃人なんです。けれど、尾田さん、僕等は不死鳥です。新しい思想、新しい眼を持つ時、全然癩者の生活を獲得する時、再び人間として生き復るのです。復活、さう復活です。ぴくぴくと生きてゐる生命が肉体を獲得するのです。新しい人間生括はそれから始まるのです。尾田さん、あなたは今死んでゐるのです。死んでゐますとも、あなたは人間ぢやあないんです。あなたの苦悩や絶望、それが何処から来るか、考へて見て下さい。一たぴ死んだ過去の人間を捜し求めてゐるからではないでせうか。」 (いのちの初夜) 皮肉なことに彼はハンセン病にかかることにより、文学的才能を開花させていきます。書くこと以外何も残されていなかったから。彼の存在意義を示すものは書くこと以外になかったのです。 『いのちの初夜』は、彼の魂の叫びです。一度読んで見てください。 
|
|
|
||||
| ■想像力をやしなうこと、視野を広げること(ひまわり/すぎ先生) |
先日ロシアで起きたとても悲しいできごと(学校占拠事件:がっこうせんきょじけん)について、みなさんは知っているでしょう。犠牲(ぎせい)になった人の中には、みなさんと同じくらいの年齢の子どもがたくさんいました。 みなさんに考えてもらいたいことがあります。 みなさんに考えてもらいたいことがあります。一つは、遠い国で起きたできごとで、自分とは関係ないと思わず、想像力(そうぞうりょく)をよく働かせてほしいということです。ロシアでは九月から新しい学年が始まります。新入生はもちろん、学年が一つずつ上がって、みんな新しい気持ちで学校に登校しました。その日に、かれらは恐怖(きょうふ)のどん底につき落とされました。もし、自分の学校でそんなことが起こったら……。想像してみてください。 三年生の項目の中に「もし〜だったら」というのがありますね。これは、頭の中で想像したことを書いてみるという勉強です。想像力というのは、作文を書くことにかぎらず、人間として生きる上でとても大切だと思います。想像力のない人は、他人の痛み(心の痛みも)を感じ取って他人を思いやることがむずかしいのです。 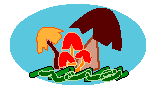 もう一つは、日本にすんでいる自分たちが当たり前だと思っていることが、そうではない場合があるということ。自分にとっての常識(じょうしき)というのは、せまい世界の中の常識だと気づいてもらいたいということです。 もう一つは、日本にすんでいる自分たちが当たり前だと思っていることが、そうではない場合があるということ。自分にとっての常識(じょうしき)というのは、せまい世界の中の常識だと気づいてもらいたいということです。どうしてたくさんの子どもたちが命をうばわれなければならなかったのか。そこには、民族の歴史、宗教、資源(しげん)の問題など、たくさんのむずかしい問題が背景(はいけい)にあります。民族や宗教などの問題には、日本人はとても鈍感(どんかん)です。むずかしくてすぐには理解できなくても、世界にはそういう大きな問題があるということを知ってください。 高学年では、「分かったこと」や「人間にとって○○とは……(一般化)」という作文のまとめかたを勉強します。広い世界を知っていれば、それだけ次元の高い意見を書くことができるでしょう。 作文の勉強では、毎週作文用紙に向かってマスをうめるだけでなく、自分の視野を広げたり、想像力をやしなうことも大切です。先日の事件を例にあげましたが、身のまわりで起きているできごとについて、深く考える人になってくださいね。 |
|
|
||||
| ■森リン得点アップ作戦 PART 2 |
 先月(8月)の学級新聞『逆境克服法』は、小学生のみなさんにはかなりむずかしい内容になってしまいました。ごめんなさい。でも、それにはわけがあったのです。森リンの高得点を狙ったため、むずかしい表現が多くなったのです。(笑) 結果は102点でした。なかなかの高得点でしょう? 作文検定試験を受けていたら、1級です。というのはうそで、時間オーバー。しかも、与えられた課題で書いているわけではないので失格です。75分間という限られた時間で、事前には知らされていない特定の課題で1級に合格するのは至難の業だと思います。 先月(8月)の学級新聞『逆境克服法』は、小学生のみなさんにはかなりむずかしい内容になってしまいました。ごめんなさい。でも、それにはわけがあったのです。森リンの高得点を狙ったため、むずかしい表現が多くなったのです。(笑) 結果は102点でした。なかなかの高得点でしょう? 作文検定試験を受けていたら、1級です。というのはうそで、時間オーバー。しかも、与えられた課題で書いているわけではないので失格です。75分間という限られた時間で、事前には知らされていない特定の課題で1級に合格するのは至難の業だと思います。先生は、森リンで高得点を取るにはどうすればよいかを研究するために、さらなる得点アップに挑戦しました。まず、文末を常体(「〜である。」「〜だった。」という形)に変えることによって、全体を圧縮しました。これだけでも数点得点アップしたのですが、三つの語彙(ごい)の種類、つまり、素材語彙と重量語彙と強力語彙の数を増やすように工夫しました。  素材語彙は、接続詞などあまり特徴のない語彙を除いた語彙です。素材語彙を増やすには、同じ言葉を繰り返さないことが鉄則です。繰り返し使われている言葉があったら、ほかの言葉に言い換えられないかどうか考えてみます。「やって来る」を「訪れる」と言い換えたり、「強固」を「強靭」や「頑強」に置き換えたりといった具合です。 素材語彙は、接続詞などあまり特徴のない語彙を除いた語彙です。素材語彙を増やすには、同じ言葉を繰り返さないことが鉄則です。繰り返し使われている言葉があったら、ほかの言葉に言い換えられないかどうか考えてみます。「やって来る」を「訪れる」と言い換えたり、「強固」を「強靭」や「頑強」に置き換えたりといった具合です。 重量語彙とは、漢字を使った熟語です。たとえば「取る」という言葉を「取得する」に変えると重量語彙になるわけです。重量語彙を増やすことは素材語彙を増やすことにもつながります。重量語彙は、普段の会話では使わない難易度の高い言葉が多いので、読書などによって難しい語彙を身につけておく必要があります。四字熟語などの勉強も役に立ちそうです。ただし、重量語彙を多用しすぎると、文章全体が硬い感じになり、しなやかさがなくなるので、読みやすく、わかりやすい文章を目指すなら使いすぎにも注意する必要があります。 重量語彙とは、漢字を使った熟語です。たとえば「取る」という言葉を「取得する」に変えると重量語彙になるわけです。重量語彙を増やすことは素材語彙を増やすことにもつながります。重量語彙は、普段の会話では使わない難易度の高い言葉が多いので、読書などによって難しい語彙を身につけておく必要があります。四字熟語などの勉強も役に立ちそうです。ただし、重量語彙を多用しすぎると、文章全体が硬い感じになり、しなやかさがなくなるので、読みやすく、わかりやすい文章を目指すなら使いすぎにも注意する必要があります。 強力語彙とは、「しかし」「ゆえに」「〜ならば」「〜はず」「〜だろう。」「〜と思う。」など、意見を組み立てていくときに使う言葉です。強力語彙は、のべ数でカウントされます。つまり、同じ言葉でも、強力語彙と分類されている言葉が現れる度にカウントされるので、極端に言えば、文末に「〜だろう。」や「〜思う。」などをつけていけば数は増えるのですが、実際にそれをすると、とても不自然で幼稚な文章になってしまいます。ですから、文末を工夫するよりも、仮定の表現を入れたり、接続詞を効果的に使う工夫をした方が作品全体の印象がよくなります。 強力語彙とは、「しかし」「ゆえに」「〜ならば」「〜はず」「〜だろう。」「〜と思う。」など、意見を組み立てていくときに使う言葉です。強力語彙は、のべ数でカウントされます。つまり、同じ言葉でも、強力語彙と分類されている言葉が現れる度にカウントされるので、極端に言えば、文末に「〜だろう。」や「〜思う。」などをつけていけば数は増えるのですが、実際にそれをすると、とても不自然で幼稚な文章になってしまいます。ですから、文末を工夫するよりも、仮定の表現を入れたり、接続詞を効果的に使う工夫をした方が作品全体の印象がよくなります。結局、手を加えた『逆境克服法』は、119点という高得点をマークすることができました。でも、得点アップだけを狙ったので、やや読みにくい文章になっています。森リンの得点は、1級レベルの96点以上なら十分で、そこから先は好みの問題になってくるような気がします。実際、自分で書いた、102点のものと119点のものを比べてみると、102点の作品の方が読みやすく、個人的には気に入っています。  今年の10月24日には、第一回作文検定試験が実施されます。作文の力は、一朝一夕に身につくものではありません。日々の音読や読書の積み重ねによって、考える力や語彙力・表現力をつけていかなければなりません。もちろん、実際にさまざまなことを体験していくことも大きな力につながります。長い勉強ですが、その分、本物の力がどんどん身についていくはずです。作文検定の1級を取るのは本当に大変なことです。でも、「いつかは1級!」、そう心に誓い、頂上目指して、一歩一歩進んでいきましょう。 今年の10月24日には、第一回作文検定試験が実施されます。作文の力は、一朝一夕に身につくものではありません。日々の音読や読書の積み重ねによって、考える力や語彙力・表現力をつけていかなければなりません。もちろん、実際にさまざまなことを体験していくことも大きな力につながります。長い勉強ですが、その分、本物の力がどんどん身についていくはずです。作文検定の1級を取るのは本当に大変なことです。でも、「いつかは1級!」、そう心に誓い、頂上目指して、一歩一歩進んでいきましょう。 山田純子(メグ) |
|
|
||||