印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■【重要】1月11日(月)は休み宿題です(再掲)
■言葉の森の夏休みは8/11~8/17に
■初めて暗唱の自習をする子のために、暗唱クラブの構想 2
■算数数学の勉強のコツはまず答えを見ること
■勉強の順番は、1に国語2に国語
■親子の対話の大切さ――「ひきこもりになる子」の記事を読んで
■国語は問題文に線を引いて読む
■暗唱と音読は違う読み方――早口、棒読み、句読点で区切らず、リズミカルに 1
|
|
||
|
言葉の森新聞
2016年1月2週号 通算第1402号
https://www.mori7.com/mori/ |
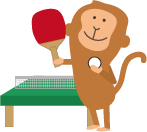
森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
| ■【重要】1月11日(月)は休み宿題です(再掲) |
|
1月11日(月)は休み宿題です。先生からの電話はありませんが、その週の課題を自宅で書いて提出してください。先生からの説明を聞いてから書きたいという場合は、別の日に教室までお電話をして説明をお聞きください。(平日午前9時-午後7時50分。電話0120-22-3987) 電話の説明を聞かずに自分で作文を書く人は、ホームページの「授業の渚」や課題フォルダの「解説集」を参考にしてください。 課題の説明の動画「授業の渚」http://www.mori7.com/nagisa/ オープン教育の掲示板「森の予習室」にも、学年別の予習のヒントが載っています。 |
|
|
||||
| ■言葉の森の夏休みは8/11~8/17に |
|
言葉の森のカレンダーでは、当初、夏休みは8/12~8/18となっておりました。 http://www.mori7.com/cal/ しかし、8/11が山の日で休みになってしまうため、今年から夏休み(休み宿題)は、山の日も含めて8/11~8/17としました。 |
|
|
||||
| ■初めて暗唱の自習をする子のために、暗唱クラブの構想 2 |
|
暗唱は、最初の300字ができるようになれば、あとはやり方がわかるので、ひとりでも続けていけます。 そこで、例えば、午後6時から1番めの100字、6時15分から2番めの100字、6時30分から3番めの100字、6時45分から300字全部などと分けていきます。 すると、自分のやっている部分に合わせてその時間に暗唱クラブに参加すればいいのですから、初めての暗唱でもやりやすくなります。 日本語の暗唱に慣れてきたら、中学生は英語の暗唱もやっていいと思います。これも、コツがわかればひとりでもやれるようになります。 問題は、時差のある海外の生徒ですが、これも、その国で暗唱の自習をする参加者を募れば、そこの時間帯に合わせた暗唱クラブができるようになります。 海外で暮らしていると、子供の日本語教育が不十分になるので、暗唱クラブに参加を希望する人は多いと思います。 暗唱は、やったことがない人は、大変なことのように思うかもしれませんが、実は、やっていると楽しくなるものなのです。 百人一首の百首暗唱を行っていた小学校の校長の杉田久信さんによると、暗唱の勉強が進むにつれて子供たちが明るく元気になっていったそうです。 たぶん、今後行う予定の暗唱クラブも、子供たちの活発な声が響く集まりになると思います。 |
|
|
||||
| ■算数数学の勉強のコツはまず答えを見ること |
|
算数数学の勉強に、時間をかけている人がいますが、答えのある勉強に時間をかけるのは時間の無駄です。 考える時間は、答えのないもののために使うべきであって、その考える力をつけるために、答えのある勉強はすぐに答えを見ることなのです。 |
|
|
|
更に言えば、問題を見て解けそうだとわかる問題は、わざわざ解く必要はありません。解かずに答えを確認するだけで充分なのです。 勉強は、わからないことがわかるようにすることであって、わかることを何度も繰り返したり、わからないことを何時間も考えたりすることではありません。 したがって、算数数学の最もよい教材は、自分にとって適度に難しい問題があり、問題よりも解法のページの方が多いぐらいに充実している教材です。 そして、最もよい勉強法は、その問題集を百パーセント、解けない問題が1問もなくなるまでく繰り返すことなのです。 そのためには、問題の答え合わせは、本人が自分でやることです。 問題の答え合わせを、お母さんがやるようにしていると、答えが合っていることがよい勉強のように思ってしまいます。 答えが合っているということは、その勉強はもともとやる必要がなかった勉強で、ただわかっていることを確かめるために時間をかけただけになるからです。 また、答えが間違っていた場合、一度や二度の説明でその問題が次からできるようになるという保証はありません。 間違いというものは、本人のものの考え方に根ざしていることが多いので、何度も繰り返さないと身につかないことが多いからです。 今の子供たちの多くは、勉強というものを問題を解くもののように考えています。 解くまでが自分の仕事で、○×をつけるのは他人の仕事、教えてくれるのも他人の仕事と考えているのです。 本当の勉強は、自分で答え合わせをすることです。自分で答え合わせをして正しい答えを理解することが勉強です。 こういう勉強をするためには、お母さんは、子供の算数数学の勉強が終わったときに、その中のひとつの問題について子供に解説してもらうといいのです。 「難しかった問題はどれ」と聞いて、「その答えはどうやって出すの」と聞いてみるのです。 その説明がわかりにくくてもかまいません。子供が一生懸命に説明してくれるなら、それはよく理解できるようになった問題です。 そして、子供がうまく説明できなかったときだけ、その問題を一緒に考えて教えてあげるのです。 こういう子供中心の勉強の仕方をすることによって、子供は勉強というものが他人のためにするのでなく自分のためにしているのだということを理解していくのです。 |
|
|
||||
| ■勉強の順番は、1に国語2に国語 |
|
勉強の順番から言うと、国語が一番です。 しかし、この国語は漢字の書き取りや、国語のドリルのような勉強ではありません。まず本を読むこと、そして親子で対話をすること、更にできれば文章を書くこと、つまり文化としての国語なのです。 この国語力さえしっかりしていれば、それ以外の勉強はあとからいくらでも間に合います。 例えば、想像をたくましくして考えてみるとわかりますが、歴史上の有名な人物が、今の社会に突然登場したら、その成績はどんなだったでしょう。 聖徳太子が、突然、現代の中学生になって勉強したとすれば、国語は言葉の使い方にギャップがあるとしてもそれでも高得点でしょう。 しかし、数学は、たぶん0点でしょう。英語も、まず0点でしょう。 しかし、聖徳太子が一念発起して、数学と英語に取り組めば、数年もせずに高得点になるはずです。 例は聖徳太子でなく、西郷隆盛でも、勝海舟でも誰でもかまいません。 つまり、知識的な勉強は、時間はかかるとしてもあとからでも間に合います。しかし、思考的な勉強は、考える力の土台ですから、あとからでは間に合わないのです。 確かに、数学的なものの考え方は大事です。 物事を生まれつき理詰めに考える人もいますが、数学の勉強によって理詰めに考える力が育ちます。 また、これからの社会で仕事をするためには、数学的な素養がさまざまなところで必要になってきます。 外国語は、自分の文化を相対化して考えるために役に立ちます。 また、今はコミュニケーションの道具としても、英語は役に立ちます。 しかし、今の数学と英語の勉強が、学校でなぜ重要になっているかというと、受験で差がつきやすい教科だからという理由の方が大きいのです。 その証拠に、社会に出たら、特に数学や英語を使わなくても日常生活を支障なく送れるという人の方が圧倒的に多いのです。 さて、勉強で大事なのは国語力だとしても、人間は勉強の力だけで生きているわけではありません。 昔から言われているように、知育、徳育、体育のバランスが、人間の生活を作り上げています。 徳育の基本は、正直に生きることと、思いやりを持つこと、勇気ある行動をとれることです。 体育の基本は、健康な生活をすることです。 これらは、いずれも家庭が中心になって行うことです。 だから、国語力を中心とした知育も含めて、子供の教育のほとんどは家庭で作られ、その表面の仕上げのようなところだけが学校や塾で行われているのです。 このように考えると、子育て全体については、1に躾、2に健康、3に読書と対話、あとは自由に、ということになるかもしれません。 |
|
|
||||
| ■親子の対話の大切さ――「ひきこもりになる子」の記事を読んで |
|
日経DUALの記事に、「『ひきこもり』になる子どもの親には共通点がある」というタイトルの記事が載っていました。 ====引用ここから 【ケース1】 子どもの回答を待たずに、先に返事をしてしまう 子どもが「何年生?」と聞かれているのに、親が「2年生です」などと答えてしまう 【ケース2】 家庭での雑談が少ない 「早く勉強しなさい」などと一方的に言ってしまう 【ケース3】 子どもの話を聞き流す、最後まで聞かない 「今忙しいから、ちょっと待って」と、家事の手を休めない 【ケース4】 条件的ほめ&承認をしている 「○○ちゃんが、××してくれたら、お母さんはうれしい」などと言う 【ケース5】 「知力」だけを育てようとして、「感情」に目を向けない 「算数が難しい」と言うのを聞いて、「落ちこぼれちゃうよ。塾行かなくちゃね」と答える 【ケース6】 子どもを自分の思い通りに育てようとしている 「お母さんはこの学校がいいと思う」などと、自分の意見を押し付ける 【ケース7】 子どもの挑戦を回避させようとしている 子どもから「○○をやってみたい」と言われると、「それは危ないからダメ」などと言う 【ケース8】 “さらに上”を要求する 97点だったテスト答案を見せられて、「あと3点で満点だったのにね」と言う ====引用ここまで 親であれば、誰でも多かれ少なかれ似たようなことをしていると思います。 だから、大事なことは、そういうことをしないようにと考えるのではなく、それと正反対のことを積極的にしていけばいいのです。 それが、親子の対話です。 対話と言っても、子供から何かを引き出そうとしたり、親が何かを伝えようとしたりはしなくていいのです。 そういう意味のある対話をしようとすると、子供の話し下手を注意したり、親の一方的な考えを押し付けたりすることになります。 そうではなく、対話を楽しむという話し方をするのです。だから、もちろん話の途中で脱線していくようなことでもいいのです。 対話を楽しむむために必要なものが、ひとつは対話の話題です。もうひとつが親の正直な体験談です。そして、もうひとつはやはり慣れです。 対話の話題は、普通の家庭では、ニュースの話になったり近所の話や学校の話や成績の話になったりしがちですが、そういう話題では話はあまり弾みません。 いちばんいいのは、言葉の森で言えば、毎日の自習の音読長文です。自習の音読をやっていない場合は、国語の問題集に出てくるような説明文や、毎日小学生新聞などの説明的な記事です。 こういう少し知的な話題があると、親子の話も弾み、子供も対話の中で考える力がついてきます。 話をするときに大事なことは、親が知識や意見だけを言わないことです。知識や意見のレベルでは、親の方が子供よりも圧倒的に上なので、一方的に教え込むような話し方になってしまいます。 知識や意見ではなく、親の子供のころの体験などに結びつけながら、子供と同じレベルで話をするのです。 また、知識や意見を言うときでも、「でも」とか「しかし」とかいう反対の言葉はなるべく言わずに、「なるほど」とか「そうだね」という賛同の言葉で、似た話を発展させていくようにするといいのです。対話は、欧米のディベートとは違うのです。 こういう対話が無理なくできるのは、子供がまだ低学年のうちです。低学年のころなら、「さあ、テレビを消して、みんなで話をしよう」と言えば話が始まります。学年が上がってからは、そういうことはなかなかできません。低学年のうちから、家族で話をし、子供の言うことに関心を持って聞くようにしていると、学年が上がっても無理なく対話が続けられるのです。 ところで、ひきこもりや不登校のようなことは、心理的なことでそれぞれの個性によるものですから、機械的にどうすればどうなるということは言えません。 しかし、そういう場合でも、救いになることのひとつがペットを飼っていることだと思います。特に、犬や猫やウサギや鳥のような対話のできるペットは、子供にとって最後のよりどころになることが多いと思います。 |
|
|
||||
| ■国語は問題文に線を引いて読む |
|
国語の問題を解くときには、問題文に線を引いて読むことが大事です。 なぜかというと、問題を見て、その確認にためにもう一度問題文を読み返すときに、線が引いてあると、その傍線の部分がきっかけになって問題文の全体像がすぐわかるからです。 線を引く箇所は、大事なところというのではありません。大事なところというのは、一度全部を読んでみないとわからないからです。 そうではなく、自分が直観的に面白いと思ったところ、内容がよく理解できたところです。 つまり、主観的に線を引いておけばいいのです。 主観的に線を引いた箇所であれば、あとで読み返すときも、その内容がすぐにわかります。 だから、その線を引いた箇所が目印になって、文章の全体像をすぐに思い出せるのです。 ところが、線を引くよりももっと念入りに接続詞を囲んで読むようなことまでする人がいます。 これは、やりすぎです。 試験というものは、ゆっくりやれればあまり差が出ないので、長い文章を短い時間で読んで答えさせる形になっています。 線を引く場合も、この短いじ時間に合わせてすばやく引いていく必要があります。 線を引くというのは、問題文だけでなく、選択問題の選択肢を選ぶときも同様です。 生徒に、国語のテストを見せてもらうと、問題文も選択肢もきれいなままの人がかなりいます。 これでは、そのテストが返されたときに、自分がどういう基準でその選択肢を選んだのか忘れてしまうので、見直しの勉強ができません。 国語の問題は、問題文も選択肢も、線を引いて読むということを習慣にしていきましょう。 |
|
|
||||
| ■暗唱と音読は違う読み方――早口、棒読み、句読点で区切らず、リズミカルに 1 |
|
音読というのは、文章のリズムに沿って読むことですから、句読点で区切って普通に読む読み方でかまいません。 しかし、暗唱の文章も同じように読むと、何度繰り返してもなかなか暗唱できません。 暗唱の読み方は、できるだけ早口で、棒読みで、句読点でもほとんど区切らず、しかしリズミカルに読んでいくのがいいのです。 棒読みでリズミカルにというのがわかりにくいと思いますが、お経のような読み方に似ていると思うといいでしょう。 もちろん、これは最初の暗唱が定着するまでの間で、暗唱がすっかりできるようになったら、句読点で区切る普通の読み方でいいのです。(つづく) |
|
|
||||