印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■春の遠足、スマホアプリ、オンエア特別講座
■中学生の作文が高校生以降の小論文の基本――そのために読む力をつける(つづき)
■田舎に行ったら言葉遊び――暗唱長文集も遊びの感覚で
■中学生の勉強も基本は音読暗唱で
■外国人が日本語を勉強する方法としての読書、音読、暗唱
■作文指導も今後はネットの中で――森林プロジェクトの未来
|
|
||
|
言葉の森新聞
2016年2月3週号 通算第1407号
https://www.mori7.com/mori/ |
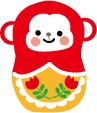
森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
| ■春の遠足、スマホアプリ、オンエア特別講座 |
|
既に言葉の森新聞でお知らせしていますが、続報は随時ホームページに掲載します。既報は言葉の森新聞をごらんください。 http://www.mori7.com/ ●春の遠足 http://www.mori7.com/mori/mori.php?ki=20160201#23719 ●スマホアプリ http://www.mori7.com/mori/mori.php?ki=20160201#23720 ●オンエア特別講座 http://www.mori7.com/mori/mori.php?ki=20160202#23764 |
|
|
||||
| ■中学生の作文が高校生以降の小論文の基本――そのために読む力をつける(つづき) |
|
(2.2週の記事の続きです。) 抽象的に考える初歩の練習は、理由を考えることです。 例えば、意見文で、「○○はよいか悪いか」という題名で書く場合、よいか悪いかの意見は誰でもそれなりに書けます。 その意見の裏付けとなる実例も、多くの人が書けます。 しかし、その実例をより一般化した理由として書くということがなかなかできない人がいるのです。 こういう例もある、ああいう例もある。では、それらの例をまとめてひとことで言うとどうなるかということが出てこないのです。 出てこないものは仕方がありません。そういうときは、いくら考えても出てこないものなのです。 しかし、それは能力がないからではありません。 人間には、もともと抽象的に考える力が備わっています。しかし、それが日常生活の中で必要とされない環境にいるので、磨かれていないだけです。 では、どうしたら、日常生活の中で、抽象的に考えることが必要になる場面が出てくるのでしょうか。 それは、ひとつは親子の会話によって、もうひとつは読書によってです。 つまり、読む力、聞く力が、作文力のもとになっているのです。 作文の欠点を注意しても上手になるわけではないのは、この理由からです。 作文力をつけるのは、作文を直すのではなく、作文を書く土台となる読む力をつけることによってなのです。 |
|
|
||||
| ■田舎に行ったら言葉遊び――暗唱長文集も遊びの感覚で |
|
今の子供は、意外と「いろは」や「子丑寅」を知りません。 ところが、子供は、そういう呪文のような言葉を覚えるのが好きなのです。 そこで、田舎に行ったときなど、おじいちゃんやおばあちゃんに、覚えていることをいろいろ聞いてみます。 |
|
|
|
中には、百人一首や昔の歌謡曲や、更には般若心経などを教えてくれる人もいるかもしれません。 特に、お母さんやお父さんができないことを子供ができるとなると、子供は喜んでそのことに熟達しようとします。 そういうちょっと知的な言葉遊びを楽しんでみるといいと思います。 話は変わりますが、今、言葉の森では新しい暗唱長文集を作成しています。 これまでの暗唱長文集は、子供たちが作文を書くときの参考にできるように、主にその学年の課題の表現項目を入れた文章でした。 しかし、せっかく子供たちが1000字近い文章を暗唱するのですから、その暗唱がずっと記憶に残り、大人になってもときどき思い出せるようなものにしたいと思いました。 そうすればと、やがて覚えた文章を自分の子供にも教えていけるようになり、言葉を通して文化的な伝統も伝えていけるようになると思います。 暗唱の方法というのは、実は簡単です。記憶力や年齢は、全く問題ではありません。正しい方法でやれば、誰でも確実にできるようになります。 だから、暗唱という勉強法は、落ちこぼれというものがありません。また、先に進みたい人はいくらでも先に進めます。 その方法はひとことで言えば、回数がわかる目印になるものを用意し(私がおすすめするのは紙を折る方法ですが)、できるだけ早口で100字ぐらいの文章を30回繰り返すことです。時間は10分程度で、これを毎日続けるのです。 ただ繰り返すだけですから、シャワーを浴びながらでも、道を歩きながらでもできます。こういう方法で、誰でも簡単に暗唱ができるようになるのです。 おじいちゃんやおばあちゃんに教えてもらった文章があったら、この方法で覚えておき、あとで聞かせてあげるといいと思います。 |
|
|
||||
| ■中学生の勉強も基本は音読暗唱で |
|
経済学者の野口悠紀雄さんの中学高校時代の英語の勉強法は、教科書をただ音読することだったそうです。野口さんは、こういう簡単で効率のよい勉強法をなぜ多くの人がやらないのか不思議に思っていたようです。 「『超』英語法」 http://www.amazon.co.jp/dp/4062122669 国語の勉強も同じです。国語の問題集に出てくる文章は比較的難しい文章が多いので、これを繰り返し音読するのです。 なぜ音読がよいかというと、黙読では飽きてそのうちにやらなくなってしまうからです。また、音読したものは自分の耳からも入ってくるので、勉強の密度が2倍になるからです。 音読暗唱という勉強法は、今少しずつ見直されています。 「奇跡の百人一首」(杉田久信著)という本には、小学校で百人一首の暗唱に取り組んだ記録が載っています。 「奇跡の百人一首 音読・暗唱で脳力がグングン伸びる」 http://www.amazon.co.jp/dp/4396315287 著者の杉田さんは、小学校の校長先生をしていました。富山市の五福小学校で初めて全校の百人一首の暗唱に取り組んだとき、ある一つのクラスは、全員が百首を暗唱できるようになったそうです。 すると、次年度の学力テストで、そのクラスだけ国語の平均点が10点近く高くなりました。 百人一首の暗唱をするようになってから、子供たちは普段の生活も明るく元気になり、卒業生は中学・高校でもよい成績を収めるようになりました。 音読暗唱というと、多くの人は、ていねいにゆっくり読むものと思いがちですが、そうではありません。できるだけ早く読んだ方が定着しやすいのです。 杉田さんのやっていた百人一首の暗唱も、5分ぐらいで全部読めることを目標にしていたようです。 英語の教科書の音読も、国語の問題集の音読も、できるだけ早口で読み終えた方がいいのです。 なぜ早く読むことが大事かというと、ゆっくりした読み方では内容を理屈で理解しながら読むことになるからです。そういう理解しながら読む読み方は、普段の生活でも充分にやっています。 理解しただけのものは、まだ自分のものではありません。だから、必要に応じて思い出さなければなりませんし、思い出せないときは忘れたことになります。 しかし、暗唱がある程度まで進むと、内容の理解を考えずに言葉が口から自然に出てくるようになります。このときに、その文章が自分のものとして身についたことになるのです。 音読暗唱の勉強の利点は、落ちこぼれというものがないことです。また、先に進みたい人は独学でいくらでも先に進めることです。 通常の勉強では、先生の説明を聞いて、早く理解できる生徒と、なかなか理解できない生徒が出てきます。その理解を一律にするためにテストをするという勉強の仕方になっています。これは、実は、先生にとっても生徒にとっても無駄の多い勉強の仕方です。 音読暗唱の勉強に慣れてくると、その勉強法をいろいろなところで応用できるようになります。 言葉の森では、1月から新しい暗唱長文集を作って勉強する予定です。 今度の暗唱長文は、百人一首も含め、親子三代で楽しめるような文化的なものを取り入れていきたいと思っています。 |
|
|
||||
| ■外国人が日本語を勉強する方法としての読書、音読、暗唱 |
|
シュリーマンが、さまざまな外国語を独学で習得した方法は、その言語の音読と暗唱でした。 この方法が、外国人が日本語を学ぶ方法として生かせると思います。 言語というものは、おおまかなところでは単語がわかれば内容を理解することができます。 翻訳ソフトのレベルは、既に概要を理解するには充分な域に達しています しかし、細かい微妙なニュアンスの違いなどは、翻訳ソフトではまだ力不足です。 それを文法的に理解する方法もありますが、いちばんよいのは、やはりその言語に慣れることによって身につける方法です。 例えば、日本の中学生の英語のテストでは、語順を入れ替えた文章を正しい語順に直すという問題がよく出ます。これを文法的に理解するのは大変です。しかし、音読で慣れていれば、自然に正しい語順がわかります。 外国人の日本語学習にも、同じことがあてはまります。 文法や単語の学習のほかに、日本語の文章に慣れることによって、微妙なニュアンスも理解するということが勉強の中心になると思います。 幸い、日本は、諸外国の本の多くが日本語に翻訳されています。 これらの本の中で、自分の気にいったものを読み、その中のいい文章を音読し暗唱するのです。 ふりがながないと漢字が読めないという場合は、ルビふりのサイトがあります。 音声がないと読み方がわからないという場合は、音読のサイトがあります。 そのほか、個々の単語の意味はウェブ翻訳で充分にできます。 インターネットの時代には、シュリーマンの学習した方法が、誰でも自宅で簡単にできるようになっているのです。 問題はただひとつ、まだその音読暗唱という方法が、まだ洗練された学習方法として確立されていないことです。 言葉の森では、今後この日本語の音読暗唱という勉強方法を作っていきたいと思っています。 参考までに、「シュリーマンの古代への情熱―シュリーマン自伝 (新潮文庫)」 http://www.amazon.co.jp/dp/4102079017 ドイツ語の原本は、キンドルで無料で読みます。 「Selbstbiographie (German Edition) Heinrich Schliemann」 http://www.amazon.co.jp/dp/B004ZG12DO ちなみに、シュリーマンは、日本にも来ていたそうです。 「シュリーマン旅行記 清国・日本 (講談社学術文庫 (1325)) 」 http://www.amazon.co.jp/dp/4061593250 |
|
|
||||
| ■作文指導も今後はネットの中で――森林プロジェクトの未来 |
|
言葉の森が作文教室を始めたころ、作文教室というような教室はどこにもありませんでした。そういうニーズ自体がなかったのです。 私(森川林)は、普通の勉強なら独学でできるものだと思っていました。だから、普通の勉強は、国語でも算数数学でも教えるつもりはありませんでした。 これに対して、作文の場合は、他人の目でないと自分の作文を評価することができません。だから、作文だけは教室があるべきだと思ったのです。 最初のうちは、作文を勉強したいという子がいないので、ほとんど人が集まりませんでした。しかし、ちょうど2000年のころ、インターネットが広がりだすと、インターネットの通信で参加する人が増え出したのです。 ロングテールという言葉があります。リアルな店舗だと、年に1回か2回しか買われないようなものは、置いておくスペースがもったいないので店には並べられません。よく売れるものだけが、狭い店舗に並びます。 しかし、人間のニーズには、誰でも同じようによく買うものと、買う人がきわめて少ない個性的なものとがあります。 その個性の狭い先端が、長いしっぽのように伸びている状態がロングテールで、インターネットによって、その先端のニーズにまで情報が届くようになったのです。 作文の勉強は、地域で通えるぐらいの距離のところにいる人ではマーケットが小さすぎるので教室としては成り立ちません。(今は、成り立っていますが) しかし、インターネットを経由すれば、世界のすみずみの小さいニーズにも直接情報が届くので、こういうロングテールの教室も成り立つようになったのです。 しかし、ここまでは、どこでもよくある話です。 ネット技術の発達によって、1人の先生が、世界中にいる子供たちを教えるということができるというのは、今のMOOCなどでも既に行われていることです。 今起きている新しい変化は、先生が生徒に教えるという形ではなく、子供たちが相互に交流できる場が生まれ、その交流を生かす勉強ができるようになっているということです。 先生の役割は、教えるというよりも、それらの交流を建設的なものに組み立てる仕組みづくりになります。 もっと大きな目で見ると、これまでのような生産者が消費者に対して物を売るという形ではなく、消費者自身が生産者に働きかけ生産に関与するという流れが生まれているのです。 しかし、この動きを生かす方法は、まだ充分に開発されているとは言えません。 言葉の森では、今後、このネットを使って生徒が参加できる形の勉強を進めていきたいと思っています。 そのひとつが、プレゼン作文発表会です。 また、この生徒が主体的に参加する仕組みを、作文以外の教科の勉強に広げたものが寺子屋オンエアです。 更に、この仕組みを勉強以外のさまざまな活動に広げるものが、これから企画するオンエア特別講座です。 これらの新しい教育を、地域で作文指導を進めている森林プロジェクトの人たちと協力して作っていきたいと思っています。 |
|
|
||||