印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■熊本県地方の地震について――明るい気持ちと行動で逆転を
■【重要】暗唱の自習について――暗唱検定用の長文もチェック可(ただし上限900字まで)
■4月29日(金)・30日(土)は休み
■連休中の予定
■中身があって低コストの「オンエア講座」
■第4週は清書。幼稚園生は作文
●清書の意義と方法
●清書の投稿
●朝日小学生新聞の投稿先
●手書き清書の送り方
●【重要】低学年の実行課題自由課題作文ウェブ発表会
■4週目の読解問題(小1以上)
■糸川英夫を育てた家庭
|
|
||
|
言葉の森新聞
2016年4月4週号 通算第1416号
https://www.mori7.com/mori/ |
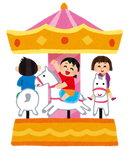
森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
| ■熊本県地方の地震について――明るい気持ちと行動で逆転を |
|
熊本県を中心とした地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 熊本県の地震は、その後、阿蘇地方や大分県にも広がりを見せています。 また、ここ数日の間に、環太平洋を中心にした世界の各地で大規模な地震が発生しています。 しかし、ここで大事なことは、私たちが悪化する未来の一つの兆候としてこの事態を見るのではなく、これから来る新しいよりよい社会の手前にあるいくつかの逆転現象としてこの事態を見ることです。 日本は、今登り口の見えない暗い下り坂に向かっているような印象を多くの人が持っています。NHKで放送されている「老人漂流社会」は、その一つの典型的な未来像です。 しかし、これを不安と嘆息の中で眺めるのではなく、どうしたら明るい未来を切り開けるのかという行動の可能性として見ることが本来の人間のとるべき態度です。 家は壊れたら、また建て直せばいいのです。老人が働けないなら、働ける人がそれ以上に働けばいいのです。仕事がないから、新しい仕事を作ればいいのです。 勇気と知恵さえあれば、どんなことでもよりよい方向に持っていけます。人類の長い歴史は、そういう人間の勇気と知恵と行動の証明です。 今はまだ続く余震の中で、不安と不便の中で暮らしている人も、ぜひ今の事態の先にある明るい未来を見て過ごしていっていただきたいと思います。 そして、それ以上に、私たちがよりよい社会を作る一つのきっかけとして、今の状態を見ていくことです。それは、単なる心の姿勢ではなく、今日から行っていく日々の行動の中に表していくものです。 暗く見えそうな現状を、明るい気持ちと行動でよりよい未来に転換していくことが、今の私たちに求められている役割なのです。 |
|
|
||||
| ■【重要】暗唱の自習について――暗唱検定用の長文もチェック可(ただし上限900字まで) |
|
現在、課題フォルダの1週目にある「課題の長文+その級の作文の見本の長文+暗唱長文」という組み合わせは、今後、暗唱という役割の方だけ廃止する予定です(7月の新学期から)。したがって、課題フォルダにある長文は、毎日の音読に使うことが中心になります。 暗唱長文は、暗唱検定用にウェブに表示されているものに統一します。これは課題フォルダには組み込みません。 http://www.mori7.com/mine/as2.php 暗唱長文は、ウェブからご自分で印刷していただくか、教室に暗唱長文集の郵送をご依頼ください。(郵送は国内のみ。1部12ページ108円) 印刷や有料という形で敷居がやや高くなりますが、無料で全員に送る形にすると、簡単に子供に暗唱の自習をさせようとして無理をしてしまう場合が多いからです。 |
|
|
|
これまでの暗唱チェックは、暗唱という自習の度合いを評価する意味があったので点数をつけていましたが、今後、暗唱の評価は暗唱検定で行うようにします。ですから、今後、普段の授業の前に暗唱を聞く場合の先生の評価も、点数ではなく言葉による励ましやアドバイスが中心になります。 暗唱検定のひとつの級は約3000字を6分以内で読むことになっていますが、通常の作文指導の中では900字を2分以内で聞くのが限界ですので、900字を超える暗唱の練習はそれぞれのご家庭で行ってください。 暗唱検定は、4月4週に行いましたが、今後はもっと柔軟に随時行っていく予定です。なお、暗唱検定には、skypeによる接続が必要ですので、skype接続のテストを希望される方は事務局までご連絡ください。 |
|
|
||||
| ■4月29日(金)・30日(土)は休み |
| 4月29日(金)・30日(土)は、第5週でお休みです。振替授業もお休みです。 |
|
|
||||
| ■連休中の予定 |
|
教室の休みは、課題フォルダに書いてあるとおりです。 5月2日(月)・6日(金)・7日(土)は授業があります。 5月3日(火)・4日(水)・5日(木)は休み宿題です。先生からの電話はありませんが、その週の課題を自宅で書いて提出してください。先生からの説明を聞いてから書きたいという場合は、別の日に教室まで電話をして説明をお聞きください。(平日9時~19時50分) 電話の説明を聞かずに自分で作文を書く人は、ホームページの「授業の渚」か課題フォルダの「解説集」を参考にしてください。 課題の説明の動画「授業の渚」 http://www.mori7.com/nagisa/ オープン教育の掲示板「森の予習室」にも、学年別の予習のヒントが載っています。 5月1週の言葉の森新聞と山のたよりは、早めに発送いたします。 |
|
|
||||
| ■中身があって低コストの「オンエア講座」 |
|
今度、オンエア講座の無料体験学習を行います。 5月から開講するオンエア講座の特徴は、中身があってコストが低いということです。 まず、どうして中身があるのかというと、先生1人に生徒6~7人という少人数のゼミ形式の勉強だからです。 時間は45分で、先生の一方的な講義だけではなく、生徒が参加する形の授業です。機械が教えるのではなく、人間が教えるので、こういう対応ができるのです。 次に、どのように低コストなのかというと、1ヶ月で4回受講して、受講料が月額わずか1,728円(消費税含む)です。 先生が個別に対応できる少人数の授業で、こういう料金設定のところはまずないと思います。 なぜ、このような高品質低コストの勉強を提供できるのかというと、このオンエア講座で利益を上げることを考えていないからです。 このオンエア講座の目的は、インターネットの技術を利用した実力のつくあたりまえの勉強をできるだけ広く普及させることです。 将来、利益を上げるとすれば、オンエア講座の受講者が増えたときに、暗唱検定や自習検定を提供することによってです。 しかし、これはだいぶ先の話になると思います。 オンエア講座を普及させるためのいちばんのネックは、インターネットの利用に際して、ウェブカメラをセットしたり、skypeをインストールしたりすることにまだ慣れていない人が多いということです。 しかし、これは本気になれば誰でもできることなので、いずれこのような障壁はなくなっていくと思います。 今回のオンエア講座は、言葉の森の生徒以外でも受講できます。 詳しくは、言葉の森事務局までお尋ねください。 |
|
|
||||
| ■第4週は清書。幼稚園生は作文 |
|
幼稚園年中と年長の生徒は、第4週も普通の作文を書く練習です。自由な題名で作文を書いてください。 小学1年生以上の生徒は、清書を行います。 清書をしたあと、時間に余裕のある場合は読解問題をしてください。 |
| ●清書の意義と方法 |
|
清書とは、これまでに書いた作文の中で内容がよかったものを書き直すことです。内容がよいとは、個性、感動、共感などがあるということです。 書き直すときは、次の点に留意してください。 (1)漢字で書けるところは漢字で書く。 (2)たとえや自作名言を工夫できるところがあれば工夫する。 (3)似た話や続きの話を書くことによって字数を増やす。 (4)作文用紙の空いているところに絵などをかいてもよい。 |
| ●清書の投稿 |
|
清書した作文は、小学生新聞や一般紙などに投稿してみましょう。 手書きの清書の原本を、新聞社に投稿したり、コンクールに応募したりする場合は、清書のコピーの方を先生に送ってください。 新聞社に投稿する際は、作文用紙の欄外又は別紙に次の事項を記載してください。 (1)本名とふりがな(2)学年(3)自宅の住所(4)自宅の電話番号(5)学校名とふりがな(6)学校所在地(町村名までで可)など。 投稿する際は、ペンネームを本名に訂正しておいてください。作文の中に友達の名前が固有名詞で入っている場合は、イニシアルなどに直しておいてください。投稿する作文の内容は、保護者がチェックしてあげてください。 同じものを複数の新聞社やコンクールに送らないようにしてください。これは二重投稿といって、もし両方に掲載されてしまった場合、掲載先に迷惑をかけることになります。 |
| ●朝日小学生新聞の投稿先 |
|
104-8433東京都中央区築地3-5-4朝日小学生新聞「ぼくとわたしの作品」係 (毎日小学生新聞は、作文よりも俳句を中心に掲載しているようです。) ※清書した作文を投稿しない場合でも、額などに入れて家の中に飾っておきましょう。 |
| ●手書き清書の送り方 |
|
手書きの清書も作文と同じように先生に送ってください、翌月の1週の作文と一緒に返却します。 パソコンで清書を入力した場合、手書きの清書は必ずしも先生に郵送などで送る必要はありません。 手書きの清書のスキャン画像を作文の丘からアップロードした場合も、先生に郵送などで送る必要はありません。 |
| ●【重要】低学年の実行課題自由課題作文ウェブ発表会 |
|
幼長、小1、小2の課題を勉強している人は、実行課題集などを参考に自由な題名の作文を書いています。その小2までの課題の生徒の作文を毎月ウェブで発表します。発表を希望される方は、次のようにしてください。 1、その月に書いた作文の中でよく書けたと思うものに、絵や写真をつけて発表用の作文としてください。(書き直す必要はありません。) 2、名前や固有名詞などが表示されないように、付箋やシールなどで隠しておいてください。 3、その発表作文の写真を撮り(デジカメ、スマホ、スキャナなど)、画像の泉から送ってください。 http://www.mori7.com/izumi/ 4、画像の泉のひとこと欄に、「実行課題作文発表会用」「発表会用」「発表用」など、「発表」という文字がどこかに入るようにしてください。 5、締め切りは、翌月の15日までとします。(例えば、1月の作文の場合は、2月15日までに画像の泉送ってください。それを2月4週に発表します。) http://www.mori7.com/hpk/jkhpk.php |
|
|
||||
| ■4週目の読解問題(小1以上) |
|
小1以上の生徒には、課題フォルダに、4週目の長文をもとにした読解問題を2問載せています。時間のある人は取り組んでください。 問題数を少なくして、問7と問8の2問だけにしたのは、じっくり解いて満点にすることが目標だからです。 問1~6も含めた全問を解きたい方は、「問題のページ」で長文と問題をごらんください。ただし、その場合も、必ず全問正解になることを目標に解いてください。 http://www.mori7.com/marason/ki.php |
|
|
||||
| ■糸川英夫を育てた家庭 |
|
先日、ふとしたきっかけで、糸川英夫さんの「21世紀への遺言」を読みました。その内容にあまりに感動したので(ということがよくありますが)、アマゾンにある糸川さんの本を中古を中心にほとんど買って、今積んであるところです。 これらの本を読むと、糸川さんは本当に創造力のある人だったのだとわかります。その創造力の源泉は、ものごとの本質を抽象的な言葉でとらえる力と、その抽象的な本質を理詰めで展開していく論理力です。これは、理系の創造力なのだと思いました。 理系の人と文系の人の発想の違いは、理詰めで論理を展開していくことに信頼感を持っているかどうかだと思います。 何かの問題があったときに、「ここがこうだから、次はこうなるはずだ」と論理で展開していって、その論理的な結末がいかに常識から離れていても、論理的な結論だから正しいと思えるのが理系的な人です。 それに対して、文系的な人は、論理よりも自分の感覚の方に信頼を置いているところがあります。 しかし、糸川さんは、理系的な論理展開の力があるととともに、音楽や芸術にも深い関心を持っていました。 自伝を見ると、昔の中学5年生で志望校を選ぶ際に、上野の音楽学校(今の芸大)の作曲科にするか、東京高校(今の東大)の理科にするか、入学願書を出すまぎわまで決心がつかずに悩み、母親に相談したそうです。 すると、母親は一瞬顔色をかえたものの、即座に次のように返答しました。 「自分のやりたいものを選べ。ただし入試の難易によって決めるな」 そして、結局紙一重の差で東京高校の理科に決めたということでした。 私はこれを見て、糸川さんの独創性の背景には、こういう生き方の本質を大事にする家庭の存在があったのだと思ったのです。 http://www.amazon.co.jp/dp/4198604452 (現在、中古の本が高くなっていますので、購入は少しお待ちいただくといいと思います。) |
|
|
||||