印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■5月30日(月)・31日(火)は休み
■【重要】6月1週は次学期の進度の参考にする試験
■幅広い読書力と、個性的な経験力をつける、「小1からの読書感想クラブ」
■受験勉強の王道=過去問対策を家庭学習でカバーする、「小4からの公立中高一貫校受験対策」
■自分で計画を立てて勉強する力をつける、「中1からの中学生定期テスト対策と入試国語」
■夏の自然寺子屋合宿の詳細決まる(7/22~7/23)
■なぜ自学自習か――人間は個性的に間違え個性的に理解する(3)(つづき)
■第4週は清書。幼稚園生は作文
●清書の意義と方法
●清書の投稿
●朝日小学生新聞の投稿先
●手書き清書の送り方
●【重要】低学年の実行課題自由課題作文ウェブ発表会
■4週目の読解問題(小1以上)
|
|
||
|
言葉の森新聞
2016年5月4週号 通算第1420号
https://www.mori7.com/mori/ |
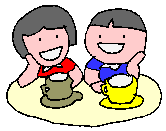
森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
|
■5月30日(月)・31日(火)は休み |
| 5月30日(月)・31日(火)は、第5週でお休みです。振替授業もお休みです。 |
|
|
||||
| ■【重要】6月1週は次学期の進度の参考にする試験 |
|
6.1週は、これまでの2ヶ月間の勉強の実力を見て、次の学期からの進度の参考にする実力試験として行います。 ただし、今学期から受講を開始された方は、実力試験の結果にかかわらず原則として自動進級します。 【課題】 課題はその週の作文又は感想文の課題です。 【評価】 課題フォルダの構成・題材・表現・主題の★印と字数が全部できていることが評価の基準になります。(表現の項目などで二つ以上の項目が指定されている場合はどちらかができていればその項目は◎です)。キーワードと字数が採点の基準ですので、指定された字数以上で必要な項目が全部入る作文を書いてください。項目を入れたところには、項目マークを必ず書いておいてください。 【時間】 時間制限はありませんが、参考のためにかかった時間を作文用紙に記録しておいてください。時間は、課題を見てから書き終えるまでの時間です。作文検定試験では、時間制限も条件になります。 【締切】 作文実力試験の提出締切は、8日ポスト投函までです。 |
|
|
||||
| ■幅広い読書力と、個性的な経験力をつける、「小1からの読書感想クラブ」 |
|
小学校低中学年のころの生活で最も大事なものは、読書力と経験力をつけておくことです。それによって頭の中身をよくしておくのです。 低中学年のころは、勉強的なことはやればすぐに成績が上がります。しかし、この時期の成績は、あとにつながりません。 高学年になって生きてくるのは、低中学年のころの勉強ではなく、読書や経験によって育てた考える力なのです。 読書感想クラブは、googleハングアウトを利用し、6~7名の少人数で、本の読み聞かせと実行課題の紹介を行っています。 また、子供たちが主体的に参加できるように、「今読んでいる本の紹介」や「似た例の発表」なども随時行います。 ○毎週火曜日18:00~18:45 ○受講料月額1,728円 ○無料体験受講が2回できます。 ○言葉の森の生徒以外の方も参加できます。 |
|
|
|
|
||||
|
■受験勉強の王道=過去問対策を家庭学習でカバーする、「小4からの公立中高一貫校受験対策」 |
|
受験勉強は、一般的な学力をつけるための勉強ではなく、生徒がその学校に合格するための勉強です。ですから、実際の過去問にあたることで、問題の傾向を知り、自分の苦手を知ることが大切です。 また、公立中高一貫校の場合は、必要な学力はすべて教科書レベルですが、そこに考える要素が大きく入ってきます。すると、勉強の方法も、ただ解説を読んで理解するだけでなく、その過程で親子の対話などによって考える力をつけることが重要になってきます。 このようにしてつけた学力は、公立中高一貫校の受験だけでなく、その後の高校入試にも大学入試にも生きてきます。というのも、これからの高校入試と大学入試は、公立中高一貫校と同じような問題になってくるからです。既に高校入試の試験問題はそういう傾向になっています。 言葉の森では、作文試験については、普段の勉強と受験直前の受験作文コースでカバーしているので、この受験対策講座では、作文以外の適性検査について実際の過去問をもとに演習と解説を行っていきます。 また、ただ問題を解くだけでなく、できるだけ生徒自身が似た問題を作るようにし、主体的な学習の機会を作っていきます。 |
|
○毎週水曜日19:00~19:45 ○受講料月額1,728円 ○無料体験受講が2回できます。 ○言葉の森の生徒、及び言葉の森の生徒が紹介する生徒以外の人も参加できます。 |
|
|
||||
|
■自分で計画を立てて勉強する力をつける、「中1からの中学生定期テスト対策と入試国語」 |
|
中学生の勉強は、特に難しいものはありません。しかし、それでも点数の差がつくのは、正しい勉強の仕方で勉強をしていない人が多いからです。 特に、中間・期末などの定期テストは、テスト用の計画を立てテスト用の勉強をする必要があります。 テスト用の勉強とは、その教科の出題傾向を考え、出題範囲に絞って、集中して短期間の反復定着学習をすることです。 ところが、多くの生徒は学習塾などでもらってきた大量のプリントを、易しい問題も難しい問題も密度薄く幅広く解くような焦点の絞られていない勉強をしています。 中学生の定期テスト対策講座では、定期テスト前に、前回の傾向を分析し、今回の計画を立て、自分の勉強を自分で評価する機会を作ります。 また、定期テスト期間以外の期間は、普段の勉強で後回しになりがちな国語の学習を、実際の入試問題を中心に解く練習をしていきます。 ○毎週木曜日20:00~20:45 ○受講料月額1,728円 ○無料体験受講が2回できます。 ○参加できるのは、言葉の森の生徒だけです。 |
|
|
||||
| ■夏の自然寺子屋合宿の詳細決まる(7/22~7/23) |
|
夏の自然寺子屋合宿の詳細が決まりました。お問い合わせは言葉の森事務局まで。 ■日程 7月22日(金)~23日(土)1泊2日 22日10時 港南台教室に集合(横浜市港南区 JR港南台駅徒歩3分) 〃 午前中 荒崎海岸で磯遊び(遠浅のきれいな岩場です) 〃 午後 野島青少年研修センターで午後の企画(横浜市金沢区) 〃 夕方 勉強・交流・自由な遊び/保護者と講師の交流 23日午前 野島公園でバーベキューなど 〃 15時 港南台教室で解散 ■費用 生徒(単独参加)……………25,920円 生徒(父母付添い)…………18,360円(親子それぞれ) (父母付添いで子2人目以降は21,600円) ■対象 小1~中3の生徒、及び保護者 ■会合 付添いで参加される保護者の方は、ハングアウトによる事前の打ち合わせにできるだけご参加お願いします。必要な機材はお送りします。接続の仕方などは説明します。 |
|
|
||||
|
■なぜ自学自習か――人間は個性的に間違え個性的に理解する(3)(つづき) |
|
なぜそれほどまでにして、親が関わることが大事かというと、小学生だけでなく中学生でも高校生でも驚くほど見当違いの勉強をしていることが多く、その見当違いの種類がそれぞれに個性的なので、毎日勉強を個人的に見るぐらいの家庭教師でなければ、その勉強の弱点に気がつかないからです。 と言っても、親に専門的な目が必要なのではありません。1日わずか10分でも日常的に子供の勉強に接していれば自ずからおかしいところがあるときは気づきます。農業で言う「主人の足跡は田畑の肥料」と同じことが、教育には更に言えるのです。 算数数学の勉強は、まず子供が自分で解法を読んで理解し、次に子供が自分で解法を理解できないところだけを親に聞き、親がその解法を理解できないときに先生に聞く、という流れです。これが、算数数学の最も理想的な勉強法です。 子供が解法を読んで自分で理解できないという問題の割合は、1時間勉強して1つあるかないかです。もし、それ以上頻繁に子供の質問がある場合は、その問題集の解法が不十分であるか、その問題集がその子にとって難しすぎるということです。 学校や塾の宿題や通信教材の中には、子供がその場ですぐに答え合わせのできないものがあります。そういう教材で勉強するのは時間の無駄です。自学自習できる教材を1冊だけ完璧に仕上げるというのが勉強の鉄則なのです。 受験では、算数数学の差がつきやすいので、家庭学習も、小6又は中3の受験に備えて1年先の学年までやっておくのが理想です。しかし、それ以上先取りする必要はなく、生活時間に余裕があるときは、読書や経験の時間にあててその子の個性を伸ばしておくことです。 |
|
|
||||
| ■第4週は清書。幼稚園生は作文 |
|
幼稚園年中と年長の生徒は、第4週も普通の作文を書く練習です。自由な題名で作文を書いてください。 小学1年生以上の生徒は、清書を行います。 清書をしたあと、時間に余裕のある場合は読解問題をしてください。 |
| ●清書の意義と方法 |
|
清書とは、これまでに書いた作文の中で内容がよかったものを書き直すことです。内容がよいとは、個性、感動、共感などがあるということです。 書き直すときは、次の点に留意してください。 (1)漢字で書けるところは漢字で書く。 (2)たとえや自作名言を工夫できるところがあれば工夫する。 (3)似た話や続きの話を書くことによって字数を増やす。 (4)作文用紙の空いているところに絵などをかいてもよい。 |
| ●清書の投稿 |
|
清書した作文は、小学生新聞や一般紙などに投稿してみましょう。 手書きの清書の原本を、新聞社に投稿したり、コンクールに応募したりする場合は、清書のコピーの方を先生に送ってください。 新聞社に投稿する際は、作文用紙の欄外又は別紙に次の事項を記載してください。 (1)本名とふりがな(2)学年(3)自宅の住所(4)自宅の電話番号(5)学校名とふりがな(6)学校所在地(町村名までで可)など。 投稿する際は、ペンネームを本名に訂正しておいてください。作文の中に友達の名前が固有名詞で入っている場合は、イニシアルなどに直しておいてください。投稿する作文の内容は、保護者がチェックしてあげてください。 同じものを複数の新聞社やコンクールに送らないようにしてください。これは二重投稿といって、もし両方に掲載されてしまった場合、掲載先に迷惑をかけることになります。 |
| ●朝日小学生新聞の投稿先 |
|
104-8433東京都中央区築地3-5-4朝日小学生新聞「ぼくとわたしの作品」係 (毎日小学生新聞は、作文よりも俳句を中心に掲載しているようです。) ※清書した作文を投稿しない場合でも、額などに入れて家の中に飾っておきましょう。 |
| ●手書き清書の送り方 |
|
手書きの清書も作文と同じように先生に送ってください、翌月の1週の作文と一緒に返却します。 パソコンで清書を入力した場合、手書きの清書は必ずしも先生に郵送などで送る必要はありません。 手書きの清書のスキャン画像を作文の丘からアップロードした場合も、先生に郵送などで送る必要はありません。 |
| ●【重要】低学年の実行課題自由課題作文ウェブ発表会 |
|
幼長、小1、小2の課題を勉強している人は、実行課題集などを参考に自由な題名の作文を書いています。その小2までの課題の生徒の作文を毎月ウェブで発表します。発表を希望される方は、次のようにしてください。 1、その月に書いた作文の中でよく書けたと思うものに、絵や写真をつけて発表用の作文としてください。(書き直す必要はありません。) 2、名前や固有名詞などが表示されないように、付箋やシールなどで隠しておいてください。 3、その発表作文の写真を撮り(デジカメ、スマホ、スキャナなど)、画像の泉から送ってください。 http://www.mori7.com/izumi/ 4、画像の泉のひとこと欄に、「実行課題作文発表会用」「発表会用」「発表用」など、「発表」という文字がどこかに入るようにしてください。 5、締め切りは、翌月の15日までとします。(例えば、1月の作文の場合は、2月15日までに画像の泉送ってください。それを2月4週に発表します。) http://www.mori7.com/hpk/jkhpk.php |
|
|
||||
| ■4週目の読解問題(小1以上) |
|
小1以上の生徒には、課題フォルダに、4週目の長文をもとにした読解問題を2問載せています。時間のある人は取り組んでください。 問題数を少なくして、問7と問8の2問だけにしたのは、じっくり解いて満点にすることが目標だからです。 問1~6も含めた全問を解きたい方は、「問題のページ」で長文と問題をごらんください。ただし、その場合も、必ず全問正解になることを目標に解いてください。 http://www.mori7.com/marason/ki.php |
|
|
||||