印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■7月18日(月)は休み宿題(再掲)
■【重要】勉強や子育てに関するご質問ご相談受け付け
■微妙になりつつある中学受験という選択肢――むしろ家庭学習で中高一貫校並みの勉強を
■小1から中3までのオンエア講座を今後広げていきます
●小1~小3
●小4~小6
●中1~中3
|
|
||
|
言葉の森新聞
2016年7月3週号 通算第1427号
https://www.mori7.com/mori/ |
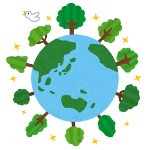
森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
| ■7月18日(月)は休み宿題(再掲) |
|
7月18日(月)は、休み宿題です。先生からの電話はありませんが、その週の課題を自宅で書いて提出してください。先生からの説明を聞いてから書きたいという場合は、別の日に教室までお電話をして説明をお聞きください。(平日9時~19時50分) 電話の説明を聞かずに自分で作文を書く人は、ホームページの「授業の渚」か課題フォルダの「解説集」を参考にしてください。 課題の説明の動画「授業の渚」 http://www.mori7.com/nagisa/ オープン教育の掲示板「森の予習室」にも、学年別の予習のヒントが載っています。 |
|
|
||||
| ■【重要】勉強や子育てに関するご質問ご相談受け付け |
|
ご両親が重要に考えている子育ての問題で、こちらが考えるとすぐに解決のアドバイスをできるようなことがたくさんあります。 これまでによくあった相談の例では、次のようなものがありました。 「国語の模試ですごく悪い成績を取ってきた」 「塾で国語の成績だけが上がらない」 「夏休みの感想文の宿題が書けない」 「学校の評価で、国語特に作文だけが低い成績だった」 「読書をなかなかしない。ちゃんと読んでいるのかどうかわからない」 「勉強に集中しない。だらだらやっている」 「算数の○○の問題が、説明してもどうしても理解できない」 これらのご質問やご相談に、言葉の森代表の中根が具体的にお答えします。 電話でその場で対応する時間が取れないことが多いので、ご質問ご相談は、できるだけ父母掲示板又はファクスでお送りください。いくつかの質問をまとめて、匿名の形でハングアウトの中でお答えします。(そのハングアウトには、保護者の方は必ずしも参加する必要はありません。) ▽父母掲示板 http://www.mori7.com/teraon/hkei.php ▽ファクス 045-832-1466(24時間) |
|
|
||||
| ■微妙になりつつある中学受験という選択肢――むしろ家庭学習で中高一貫校並みの勉強を |
|
子供に中学受験をさせるべきかどうか迷っている家庭は多いと思います。そういう迷いに答える出版物もいくつか出ていますが、あまり多くありません。 中学受験の得失をかなり客観的に取材したものもありますが、その取材時よりも加速度的に現在の状況は変化しているようです。 |
|
|
|
中学受験のプラス面は、大学入試に有利になることです。 今はまだ就職は、大学のブランド名で左右されるところがありますから、名前の通った大学にいることはかなり有利です。もちろん、仕事を始めたら学歴はもう関係ありません。同窓生の人脈ということはあるかもしれませんが、仕事は基本的に実力の世界です。 私立高と公立高を比べると、公立高には勉強面で約1年の遅れがあります。だから、公立高でも1年浪人する覚悟であれば、私立高に行ったことと変わりません。しかし、今の社会では一浪してまで目指す大学に行くという人は少なくなっていると思います。そういう点では、進学実績の高い私立中学に入るのは、大学合格とその後の就職に関しては有利な選択になると思います。 公立校が荒れているから私立を選びたいという人もいると思いますが、学校の荒れは子供の勉強にはあまり関係ありません。というのは、中学高校の勉強では先生に教わって力がつくのではなく、自分でやって力がつくものだからです。私立中でも勉強しなくなる子はたくさんいますし、たとえ荒れた公立中でも勉強する子はちゃんとします。すべて本人次第です。 中学受験のマイナス面は、パズルの解き方を身につけるような条件反射的な学力の詰め込みをしてしまうことです。その結果、考える力が低下し、勉強に対する喜びがなくなり、勉強以外の読書や経験の厚みが不足するという問題が出てきます。今の受験は、そういう詰め込みに耐える子の方が合格するようになっているのです。その結果、一流と言われる大学に入っていながら、本当の学力という点ではかなり怪しい人も最近は増えているようです。 これは、公立中高一貫校の入試でも、残念ながら次第にそういう傾向になりつつあるようです。また、塾に通って公立中高一貫校の受験を目指すと、その公立中高一貫校の受験にとどまらず自然に私立中も併願するようになります。すると、やはり同じように考えない勉強の詰め込みになります。 そして、この傾向は、最近更に加速しているようなのです。 そこで、私が今考えているのは、中学の受験はしないが、家庭で中高一貫校と同じような勉強、特に数学の先取りをしてしまうことです。 今の小学校高学年の勉強にしても、中学生の勉強にしても、勉強内容が易しすぎるので、普通に学力のある子にはかなり物足りない授業になっています。しかし、そこで受験を目指すのではなく、家庭で国語も数学も英語も学校よりも先のレベルの問題もやってしまうようにするのです。国語については、学年を超えた難度の高い文章を読む力をつけていきたいと思っています。 |
|
|
||||
| ■小1から中3までのオンエア講座を今後広げていきます |
|
言葉の森では、今後、作文指導に加えて、オンエア講座を広げていく予定です。 その理由は、子供たちの真の成長を考えると、作文の勉強のもとになる全教科のバランスのよい学力を高めていく必要があると思ったからです。 しかし、それは言葉の森が、単に学習塾や予備校の二番煎じをやることではありません。 今の教育界を見ると、根本的な問題があり、その問題を解決する方向は見つかっていないように思えます。 それは、一つには、早期化、長期化、高額化する教育にもかかわらず、学力が十分に身についていない子供が増えていることです。もう一つには、成績がよいと言われる子に、本来あるべき創造性、思考力、文化性が伴っていないように見えることです。これは、普通に成績がよい子よりも、特に成績がよい子の方に問題があります。つまり、勉強のし過ぎで成績だけがよくなっている子が増えているのです。 この問題の所在を考えると、これからの教育に次の4つの視点が必要になってくると考えられます。 第一は、受験の教育から、実力の教育へです。 第二は、学校・塾の教育から、家庭・地域の教育へです。 第三は、点数の教育から、(点数の見えない)文化の教育へです。例えば、思いやりとか勇気とかいうものが点数として見えないものです。 第四は、競争の教育から、創造の教育へです。これは、将来の仕事にもあてはまります。人よりよいところに就職しようという考えから、今後は新しい仕事を自分で作ろうという方向が徐々に増えてくると思います。 こういう教育を行う際に、今大きな制約になっているものが従来の教育観です。 従来の教育観とは、教室があり、教材があり、先生がいるという教育観でした。 よい教育を受けようとすれば、よい教室、よい教材、よい先生が必要になり、そのよい教育を受けるためには、高い競争率と高い月謝が必要だと考えられていたのです。 しかし、どの塾や学校を見てもわかるように、それらの条件は決して決定的なものではないのです。三拍子そろった「よい教育」を受けても落ちこぼれていく子はいます。また三拍子がそろっていない「悪い教育」を受けても立派に成長する子もいます。むしろ、そういう子の方がずっと多いのです。 では、その違いはどこから来ているかと言えば、家庭の文化と両親の姿勢と本人の意識から来ているのです。 大昔は、教室に行って勉強を教えてもらうのでなければ、場所も、教材も、先生も手に入りませんでした。今でも、途上国の教育は、こういう学校・教材・先生を必要とする教育です。 しかし、現代の日本では、家庭で、自由な教材を使って、親子で又は独学で、十分に優れた教育を受けることができます。そして、同じ学校や塾に通っているのに差が出るというのは、この家庭での生活のスタイルが違うからなのです。 そこで、言葉の森では、オンエア講座として、教室も、教材も、先生ももっと後景に退き、家庭と両親と本人が前面に出るような教育をしようと考えたのです。 これを、無料のクラウドサービスであるgoogleハングアウトを使って行います。今のパソコンの多くはカメラ内蔵なので、ハードの準備は必要ありません。また、パソコンでなくスマホやタブレットで参加することもできます。 しかも、ネットを使った教育ですから、どんな遠方からでも参加できます。 |
| ●小1~小3 |
|
まず、小1~小3は、読書実験クラブという名称で、次のようなことを行います。 (1)読んでいる本の紹介 (2)説明文の本や文章の読み聞かせ (3)その読み聞かせをもとに構想図(構成図)を書く (4)その構想図をもとに子供が後日両親に読み聞かせの内容を説明 (5)両親が似た話を話す形で子供と対話 (6)その構想図をアップロード (7)説明文の内容をもとに実験や観察を行った家庭があればそれを記録したアップロード (8)次の週は、読んでいる本の紹介以外に、それぞれの構想図や実験観察の記録を紹介 これを7、8人の少人数で、保護者も参加できる形で行います。また、参加できない日があった場合も、あとで動画の記録が見られるようにしています。 そして、週1回の参加だけでなく、週の途中に、自由に読書チェックなどの希望日を入れることができるようにします。 小学校1~3年生は、勉強は学校だけで十分です。学校だけでは練習が不足する場合でも、家庭学習で勉強する教材を決めておけばそれで十分に対応できます。この時期に、更に勉強の成績を上げるような試みは、かえって子供の学力も創造力も低下させます。 この時期の真の学力の伸長は、読書と経験と対話によって決まってくるのです。 小1から小3の時期に、このような家庭学習のスタイルが作れれば、その後の家庭学習は更にスムーズに進んでいきます。 ▼読書実験クラブのオンエア講座案内 http://www.mori7.com/oak/oakabc.php |
| ●小4~小6 |
|
次に、小4~小6です。この学年は、思考国算講座という名称で、公立中高一貫校受験に対応できる、考える力をつける国語と算数の勉強をしていきます。 (1)読んでいる本の紹介 (2)公立中高一貫校入試の作文試験の問題文を読み構想図(構成図)を書く (3)その構想図をもとに子供が後日両親に問題文の内容を説明 (4)両親が似た体験談を話す形で子供と対話(公立中高一貫校入試の作文は体験をもとにという条件が多いので、両親の体験をもとに自分の体験を広げる) (5)その構想図をアップロード (6)公立中高一貫校入試の算数の問題を解き、答え合わせをし、解法を読み理解する (7)小4~小5でまだ習っていない単元になる場合は、入試問題は解かずに、算数の学習の学年先取りを行う (8)算数の問題をもとに、自分で似た問題を作った場合はその問題・解答・解法をアップロード (9)次の週は、読んでいる本の紹介以外に、それぞれの構想図や似た問題の記録を紹介 今の公立中高一貫校入試は、初期のころと比べると、考える問題が出尽くしてきた面があり、考える問題から次第に解法を身につける知識の問題になりつつあります。したがって、成績を上げるためには知識の詰め込みを行わなければなりませんが、詰め込み勉強では、かえって本当の学力は低下します。 受験に勝つコツはまた別に説明しますが、ここでは受験を超えて真の学力をつける学習を目的としていきたいと思います。 小4~小6は、親子の共同学習がうまく行かなくなり始める時期です。しかし、この時期に、勉強と対話の面で親子の協力ができれば、それはその後の中学生以降の家庭学習にも生かしていくことができます。 この思考国算講座も、週1回の参加だけでなく、週の途中に、自由に勉強チェックなどの希望日を入れることができるようにします。 |
| ●中1~中3 |
|
中1~中3は、計画先行学習講座という名称で、中学生の定期テスト対策をするとともに、学校の成績を超えたより高度な国語、数学、英語の学習の先取りをしていきます。 (1)読んでいる本の紹介(中学生の時期こそ読書に力を入れる時期だからです) (2)定期テストの勉強計画、テストの結果、今後の方針などを入力する (3)それぞれの勉強計画についてのアドバイス (4)難度の高い国語問題の演習で、国語問題の解き方のコツを学ぶ (5)自主学習として、国語の問題集読書、数学の先取り学習、英語の先取り学習を行う (6)先取り学習の状態のチェック 中学生のテストの成績を上げるコツは簡単です。要するに計画を立てて勉強をすればいいだけです。しかし、現在は多くの中学生が、塾に言われたままの勉強をしたり、無計画にその場の思いつきで勉強したりしています。その勉強計画を自覚的に立てれば成績はすぐに向上します。 しかし同時に、学校の定期テストを勉強の目標にしてしまうと、学習内容はかなり薄まります。高校に進んだときにも役立つような考える学習と、1学年分の先取り学習を独自に進めていく必要があります。 私立中高一貫校が大学入試で高い実績を上げているのは、公立高校に比べて数学で約1年から2年の先取りを行っているからです。数学は、かけた時間によって差がつく教科なので、1年間早く受験数学の勉強をできるかできないかは、入試に大きな影響を与えます。だから、この数学を、公立高校であっても独学形式で先取りしておけばいいのです。わからないときの質問コーナーさえあれば、高校生はどの教科も独学でやっていくことができます。 この計画先行学習講座も、週1回の参加だけでなく、週の途中に、勉強チェックなどの希望日を入れることができるようにします。 |
|
|
||||