印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■謹賀新年――平成29年
■1月9日(月)は休み宿題
■教育の自由化とオンライン教育
●コメント欄より
■創造性と勉強
■学力は平均で、個性は一点集中で――これからの子育てで大事なこと
●コメント欄より
|
|
||
|
言葉の森新聞
2017年1月2週号 通算第1450号
https://www.mori7.com/mori/ |
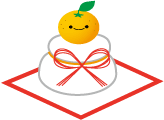
森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
| ■謹賀新年――平成29年 |
|
新年、明けましておめでとうございます。 言葉の森の今年のテーマは三つです。 1.作文一番。 2.メディア&ソーシャル。 3.森の学校kオンエア。 作文教育の分野で、名実ともにナンバーワンの地位を確立します。 メディアの活用と、ソーシャルの交流を結びつけます。そこに、リアルの企画も付加し、顔の見える人間的なつながりを強化します。 森の学校を作り、オンエア教育を普及させます。自然の中での友達との遊びと、自学自習の勉強を両立させる文化を作ります。 時代は大きく変化していますが、その時代の一歩先を行く教室作りを目指していきます。 |
|
|
||||
| ■1月9日(月)は休み宿題 |
|
1月9日(月)は、休み宿題です。 先生からの電話はありませんが、その週の課題を自宅で書いて提出してください。先生からの説明を聞いてから書きたいという場合は、別の日に教室までお電話をして説明をお聞きください。(平日午前9時-午後7時50分。電話0120-22-3987) 電話の説明を聞かずに自分で作文を書く人は、ホームページの「授業の渚」か課題フォルダの「解説集」を参考にしてください。 課題の説明の動画「授業の渚」 http://www.mori7.com/nagisa/ オープン教育の掲示板「森の予習室」に学年別の予習のヒントが載っています。 |
|
|
||||
| ■教育の自由化とオンライン教育 |
|
教育の役割は、基礎学力をつけることと、集団活動の中で子供たちの意欲を伸ばすことの大きく二つに分けられます。 基礎学力は、学校の授業で行われるとともに、定着力を高めるための家庭での宿題として行われてきました。 しかし、今、学力の低下が問題となっているのは、家庭で行われる自学自習形式の学習に十分に対応できない家庭があったからです。そこで、今考えられているのは、家庭での自学自習を支援するためのネットワークの利用です。 教育にネットワークが利用できるような技術革新が、ここ数年の間に急速に発達してきました。これが、これからの教育が大きく変わる第一の条件です。 教育の変化の第二の条件は、副業が原則容認となる社会になりつつあることです。 これまでのインフレの時代には、需要が供給を上回っていたので、どこでも長時間の労働が必要でした。 しかし、これからの時代には、供給力が常に需要を上回る傾向にあるので、ワークシェアリング、派遣労働の普及と同じように、副業が原則として容認される社会になります。 |
|
|
|
すると、会社員でも土日や早朝に子供たちの教育に関与することができるようになります。早朝の教育は特に、時差のある海外で暮らす日本の子供たちの教育に活用できます。 また、平日でも、定年後の高齢者や、子育て中の主婦は、家庭にいながらにしてできる教育の仕事というものが可能になります。 一斉授業の場合の先生の役割には、エンターテイナーの要素が必要でした。 しかし、家庭学習の場合の先生の役割は、ティーチングの力よりもコーチングの力、つまり、子供たちの自学自習をうまく軌道に載せる力が必要になります。 だから、子育ての終わった人で、あまり苦労せずに子育てを行い、子供たちがいずれもいい子に育ったというような家庭の主婦が、教える先生役としては、もっとも適役なのです。 教育の変化の第三の条件は、これから教育の自由化が進むということです。 これまで、国や自治体の教育予算は、学校におろされてきました。それを学校におろすのではなく、保護者におろすバウチャー制度という仕組みがこれから検討されるようになります。そして、保護者が自由に学校や先生を選べるようになるのです。 教育の自由化には、ある程度の基準が必要ですが、その基準をもとにした学力試験や資格試験があれば基礎学力の担保は十分に可能です。 以上の三つの条件のもとで進む教育の大きな変化に対応できるオンライン教育がこれから求められてきます。 そのオンライン教育は、これまで行われてきたMOOCのようなビデオ授業型のオンライン教育でも、マンツーマンの個別指導型のオンライン教育でもなく、少人数のグループ学習を行えるようなオンライン教育です。 そういうオンライン教育を広げるものは、コミュニティです。 インフレ時代には、何かを社会に広げるためには、メディアの力や宣伝の力が必要でした。それは言い換えれば資金力が必要だったということです。 しかし、デフレ時代には、コミュニティの力が社会に広がる原動力になります。コミュニティの中で、よりよいものを提供し、相手の助けになることをするというコミュニティ貢献力がこれからの重要になってくるのです。 そして、このオンライン教育の普及のあとには、リアルな体験型の教育の場もまた必要になってきます。 言葉の森が今考えているのは、自然寺子屋合宿教室をオンライン教育と組み合わせて行っていくことです。これから、そのための講師募集と講師のコミュニティ作りを進めていきたいと思っています。 |
| ●コメント欄より |
|
・これまでの一斉授業型の教育では、教える先生にエンターテイナーとしての力や、子供たちの集団をコントロールする力が必要でした。 しかし、家庭学習をカバーするような基礎学力の教育には、子供たちの自学自習をうまく軌道に載せる力が必要になります。 そういう先生の適役は、自分が子育てを済ませ、子供たちの教育にあまり苦労をせず、子供たちがいずれもいい子に育ったというような経験を持つお父さん、お母さんです。 これから、そのように誰もが子供の教育に関われるという社会がやってくると思います。 |
|
|
||||
| ■創造性と勉強 |
|
創造的な仕事をしている人に、意外と勉強が苦手だった人が多いのです。 最近読んだ本で言うと、賀来(かく)龍三郎さん、土井利忠(天外伺朗)さん、それからさかなクンです。 それはなぜかというと、答えのある解き方の決まっている勉強をすることに興味がわかなかったからではないかと思います。 だから、逆に、答えのある勉強の解法を身につける勉強を長期間やっていると、成績が上がるのに反比例して創造性や思考力が失われていくのです。 では、どうしたらいいかというと、受験勉強は受験の一時期に集中して取り組むことで、それまでは自分の好きなことにたっぷり時間を費やすことです。 創造性と勉強の関係をよく表している賀来龍三郎さんの話です。 「私は父の仕事の関係で、中学校は戦前の中国の青島(チンタオ)中学に学んだ。数学と物理を教わったのが秋山先生という高等師範学校出身の教育熱心な先生だった。秋山先生いわく、『公式など覚えなくていい。それより十分理解することが大事で、理解していればいつでも自分で導きだせる。難しい公式を覚えて応用問題を解こうなどということは考えるな。ただし、中等教育ではレンズの焦点を測る公式と電圧の公式(電流と電圧と抵抗の関係式)だけは覚えておきなさい。それだけはいくら導きだそうと思ってもできないから』。私はクソ真面目な生徒であったので、その教えを忠実に守った。 その後、旧制五高の理科に進学したが、そのときまではその教えでよかった。しかし終戦後、大学に進学するために、いざ受験する段になって公式を覚えないという勉強方法がいかに不利かということを思い知らされた。東大の工学部を受験したのだが、公式を作りながら解いているうちに一問目で二時間のほとんどがすぎてしまい、受験に失敗したのである。 このため私は当時、「秋山先生はけしからん、あんなこと教えるからいけないんだ」と非常に恨んだ。やはり受験には暗記した公式を基にさっさと解いていく受験テクニックが必要なのだと思った。 ところが、実社会に出てみて、私は再び秋山先生の教えが正しかったことを身をもって感じるようになったのである。東大受験に失敗した後、戦後の混乱が続く中、小学校の代用教員や病気になったりしての回り道を経て、九州大学の経済を卒業して、一九五四(昭和二九)年キャノンに入社した。 キャノンに入社して、仕事の中で様々な問題にぶつかる。しかし、どれもこれも前もって決まった答えなどない。ただ時間は十分ある。テーマによっては一カ月でも半年でも一年でもじっくり考えることができる。そうすると、どんな難問でも解決できる。 多くの人は考えることが面倒くさくなり、『会社生活なんて面白くない』ということになるのだが、私は逆に入社早々から仕事が楽しくて仕方なくなってしまった。十分な時間の中で考えることで、答えは必ず見つけられる。これこそ創造的教育のおかげではないかと、秋山先生の教育方針を再評価したのである。」 ただし、「自分の好きなことにたっぷり」というだけでは、リスクが大きいと考える人もいると思います。 そのときに参考になるのが、江戸時代の寺子屋教育です。 自主的に取り組める勉強で基本をしっかり身につけさせ、子供たちがのびのびと遊ぶ時間もたっぷり確保していました。 これが、小中学校時代の勉強の理想だと思います。 |
|
|
||||
| ■学力は平均で、個性は一点集中で――これからの子育てで大事なこと |
|
子供たちを見ていると、勉強のよくできる子もいれば、普通の子も、苦手な子もいます。 しかし、みんなそれぞれの個性を持って生きています。 成績だけを考えればそこで優劣があるように見えますが、人生の成功ということから考えると、スタートラインは全く同じです。 成功とは、自分の個性的な知識の土台の上に創造性を発揮して、世の中で自分にしかできないことをやっていくことです。 そのためには、成績は普通にできていれば十分で、その上に、一点集中した個性を伸ばしていくことが大事なのです。 これからの世の中は、物が拡大していく時代ではありません。 拡大はいったん終了し、更には縮小して、その中で人間の行動が高度化していく時代です。 物が拡大していく時代は、答えのある時代でした。 先に進んでいる人や国が答えで、その答えに追いつくことが成功することでした。 だから、教育も、答えのある勉強でできるだけよい成績を取ることが重視されてきたのです。 よい成績は、よい学校への進学につながり、よい学校の卒業はよい仕事への就職につながりました。 答えのある世界でよい成績を取ることが、成功する人生につながっていたのです。 しかし、これからの世の中では、物はこれ以上拡大しなくなります。 あるいは、また、画期的な産業上の技術革命が起こり、新しい物が爆発的に拡大する時代は将来あるかもしれません。しかし、とりあえずはそういう兆候はまだありません。 これからは、既にある産業の上で、需要は停滞し更には縮小していくのです。 物が縮小していく時代は、逆に、事が高度化していく時代です。 広く浅く何でもできるという分野は、ますます競争が激しくなっていきます。用意されているパイが次第に縮小していくにもかかわらず、多くの人がまだそこに参加しようとしているからです。 これからの時代の成功は、縮小していく答えのある世界で上位を占めることではありません。答えのない世界を自分で作り出し、その世界を個性的に高めていくことが成功の条件になります。 子供の教育に関して言うと、これまでの理想は、国数英理社の全教科でオール5を取るような方向でした。 しかし、現代の早期からの受験勉強が示しているように、長時間の勉強で成績を上位にする方向は、大人数で狭いパイを奪い合う方向なのです。 これからの世の中で必要になる能力は創造力です。 創造力とは、底辺が知識で、高さが創造性となっている三角形の面積です。 底辺がみんなと同じような国数英理社の全教科の知識であれば、その分野で創造力を発揮するのはかなり困難です。誰もが同じような勉強をしているからです。 底辺の全教科の知識は、知識の基本ですから、身につけておく必要はあります。 しかし、その身につけ方は、国数英理社全教科オール3ぐらいでいいのです。 国語も数学も英語も理科も社会も、一応一通りのことはわかっているというのがオール3の水準です。 その全教科オール3の土台の上に、自分の関心のある分野に狭く絞った知識を、他の人が追随できないぐらいに高度化していくのです。 三角形のの底辺となる知識が他の人と異なるところで広がっていれば、それだけで創造力は高まります。 更に、三角形の高さと創造性を高めておけば、その分野で第一人者になることができます。 創造性を高める方法は、知識を詰め込むような勉強に力を入れることではありません。知識は創造力の土台であって、創造性の高さでないからです。 創造性は、自然との触れ合い、人間との関わり、道具の駆使、読書の広がり、暗唱の習得など、多様な身体的経験を通して育ちます。 これからの子育てで大事なことは、勉強の世界で上位に入れてもらうことではなく、人生というより大きな世界で成功することです。 そして、成功とは、創造力を発揮して何らかの分野で第一人者になることであり、そのためには自分の得意な特定の分野で高度な知識を持ち、その知識の土台の上に創造性を発揮することです。 学力は平均でも十分で、その分、一点集中できる分野を見つけ、そこで自分の創造性を発揮していくことが、これからの子育てで重要になってくるのです。 |
| ●コメント欄より |
|
・多くの人は、成績がよければ安心、成績が悪ければ心配、と思っていると思います。 しかし、これからの世の中は、成績のよさだけで渡っていくことはできません。 ゴールドラッシュで成功したのは、ゴールドを探し求めた人ではなく、その人たちにジーンズを売った人でした。 答えのある世界にみんなが殺到しているときに、自分なりに問題を発見した人が成功した人だったのです。 |
|
|
||||