印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■夏休み中の電話を帰省先や旅行先に変更することができます
■これからの子育ては限られた受験教育ではなくトータルな学力教育
●コメントより
■作文はよく書けるが、国語の成績が今ひとつという生徒からの相談
●コメントより
■読むことが苦にならない、覚えることが苦にならない、書くことが苦にならない、というのが本当の学力
●コメントより
■昔テレビで一億総○○化、今はyoutubeで
●コメントより
■読書と勉強を両立させる方法
|
|
||
|
言葉の森新聞
2017年7月1週号 通算第1473号
https://www.mori7.com/mori/ |
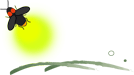
森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
| ■夏休み中の電話を帰省先や旅行先に変更することができます |
|
夏休み中、帰省されたり旅行をされたりする場合、電話先を変更することができます。 変更の連絡は、授業の直前でも可能です。ご遠慮なくご連絡ください。 |
|
|
||||
| ■これからの子育ては限られた受験教育ではなくトータルな学力教育 |
|
これまでは社会全体が上げ潮の時代でした。 それは、高度経済成長時代に見られるように必需品の生産が不足していた時代だったからです。 しかし現在、必需品は、先進国ではほぼ満たされるようになっています。 すると、これからの消費は、より文化的な消費になると考えられます。 文化的な消費とは、自分らしく生きたいという気持ちから生まれる消費です。 すると、今後大事になるのは、上げ潮の時代の価値観ではなく引き潮の時代の価値観に対応することです。 上げ潮の時代は、シェアを拡大できる大きな組織に入ることが人生設計の重要な目標になっていました。 「入ること」、つまり入試が、人生の大きな目的になっていたのです。 そのため、入試の限定された能力評価に特化した教育が行われてきました。 これが受験教育です。 例えば、個性的に考える力よりも、マニュアルを覚えて使う力が重視されました。 この記憶力中心の教育が、現在末期状態に陥っていると考えられます。 さて、引き潮の時代は、自分らしい個性を活かして、自分で仕事をすることが中心になる時代です。 引き潮の時代の社会における消費者は、必ずしも一般大衆ではありません。 だから、マーケットの規模は、次第に問題ではなくなってきます。 引き潮の文化の時代の消費者は、不特定多数の人間ではなく、同じような志向を持つ生産者でありかつ消費者であるような人間です。 そこでは、生産と消費のコミュニティが生まれる中で、経済が回って行くと考えられます。 教え合い学び合う関係の中で、生産と消費が循環していくのです。 このような、多くの人が自立する仕事に従事する時代に対応する教育はどういうものでしょうか。 これが、これから必要とされる全面的な教育です。 受験的な知識の勉強は、もちろんある程度は残ります。 しかし、それとともに個性、情熱、勇気、思いやりなどを目標とした教育が行われるようになるのです。 この教育の一つの基本的な形態が読書です。 そして、人間どうしの対話です。 さらに、自分の考えや感情を表現する力です。 |
|
|
|
このようなトータルな学力を育てていくことが、これからの子育ての目標になっていくのです。 |
| ●コメントより |
|
|
||||
| ■作文はよく書けるが、国語の成績が今ひとつという生徒からの相談 |
|
小学校4年生から始めて現在中学3年生になっている生徒のお母さんから相談がありました。 「作文力がついたし、考える力もついている。とてもよく頑張っていると思うし、言葉の森の先生にもいつも褒められる。しかし、その割に国語の成績がいまひとつのように思う。」 ということでした。 こういう相談は、実はよくあります。そして、それは全然心配ないのです。 あるやり方を説明すれば、文字どおりあっという間に国語の成績は上がるからです。 では、なぜそういう勉強を普段からしないかというと、国語の成績を上げるような勉強は、すぐにできるし、勉強自体がつまらないものだからです。 だから、入試を目前にして、真剣に国語の成績を上げたいと本人が思ったときに、そのやり方を教えるようにしているのです。 そうでないと、ただ説明を聞くだけで、なるほどと納得したような気がして、結局何もしない子がほとんどだからです。 大事なのは国語の実力で行って、成績はその最後の仕上げにすぎません。 では、国語の実力があるはずだと思われるのになぜ国語の成績がそれほど良くないのかと言うと、その原因は国語の問題を理詰めで解くのではなく感覚で解いているからです。 理詰めの解き方を身につける方法は、国語のテストで100点を取ることを目指すことです。 ほとんどの生徒は、国語のテストが返却されたときに、「80点だったからまあいいや」などという考え方をします。 そうではなく、必ず100点満点を取るという気持ちで、間違えた問題を徹底して見直すようにすれば、そこから国語の成績は上昇していくのです。 国語のテストというのは、単なる国語の問題ではありません。 つまり、ちゃんと読めているかどうか確かめる問題なのではなく、普通に読めている子をいかに間違わせて差をつけるかという目的の問題なのです(笑)。 そのために、読みにくい文章を読ませ、素直な読み手の裏をかくような問題を作るのです。 だから、国語の成績を上げるためには、裏をかかれないようにすればいいだけです。 ところが、こういう勉強は面白くも何ともありません。 だから、普段の勉強はもっと面白い勉強、つまり、本を読んで、よく考えて、自分なりに書くという中身のある勉強をしていくのがいいのです。 ▽参考記事 「理詰めで解く国語――センター試験を例にして」 https://www.mori7.com/as/2334.html |
| ●コメントより |
|
|
||||
|
■読むことが苦にならない、覚えることが苦にならない、書くことが苦にならない、というのが本当の学力 |
|
成績は目に見えるものなので、ついそこに関心が向きがちです。 成績の根底にある学力は、目に見えないので後回しにされがちです。 しかし、成績はその気になって取り組めばすぐに上がります。 私の実感では、高校入試で3か月、大学入試でも6ヶ月あれば見違えるほど成績は上がるのです。 では、その学力のもとになるものは何かと言うと、第一は理解力です。第二は、その理解を定着させる記憶力です。 理解力は、難しい文章を読んだり聞いたりすることによって育ちます。 記憶力は、長い文章を音読や暗唱で覚えることによって育ちます。 だから、読書と対話と音読と暗唱と、それらを統合する勉強としての作文が学力を育てる基本なのです。 理解力と記憶力は、成績には直接表れませんが、身近に接していると自ずからわかります。 もし子供が、読むことも、覚えることも、書くこともさして苦にならないというのであれば、その子の学力は十分に育っています。 そして、これらの勉強のほとんどは、家庭での自学自習でカバーできるのです。 ▽参考記事 「家庭での自習のコツ」 https://www.mori7.com/index.php?e=2104 |
| ●コメントより |
|
|
||||
| ■昔テレビで一億総○○化、今はyoutubeで |
|
昨日の小6の思考発表クラブで、子供がyoutubeなどインターネットを長く見るようになって、その分読書量が減っている気がする、という相談がありました。 昔、テレビが普及し始めたころ、評論家の大宅壮一氏は、一億総白痴化という言葉で、テレビが人間の思考力や想像力を低下させていると警鐘を鳴らしました。 このテレビよりも誘惑度の高いのが、インターネットの世界です。 テレビや漫画は、つい惰性で見るので無駄な時間を過ごしがちです。 インターネットは、それ以上に惰性で見てしまうことが多いのです。 数年前、イギリスの中学生がSNSに時間を取られ、読書をしなくなったという記事が載っていました。 これは、日本でも同じ事情になりつつあると思います。 では、どうしたらいいかというと、これはやはり自己コントロールによる、生活とインターネットの共存しかないのです。 禁止というのは、小学校低学年のころはあり得ますが、高学年や中学生の子に禁止というのは、問題を先送りするだけになります。 誘惑に負けるというのは、子供だけの問題ではなく、大人も含めた人間の本質的な問題です。 それを克服するのが、広義の教育です。 私の考えの基本は、「よく遊び、よく学べ」です。 youtubeも楽しむ、SNSも楽しむ、そして読書も、勉強もたくましくやり遂げる、しかし、そういうことができない人とも仲よく接する、という人間像の目標を立てて、そこに近づくように親子で努力していくということな のです。 ▽参考記事 「国語の成績は、氷山の水より上の部分。下の部分は、親の価値観と生活習慣」 https://www.mori7.com/index.php?e=2184 |
| ●コメントより |
|
|
||||
|
■読書と勉強を両立させる方法 |
|
勉強の時間と読書の時間の両立に苦労している方は、意外と多いようです。 基本的な考えは、「勉強が学校でするもの、読書は家庭でするもの」です。 しかし、学校の勉強だけでは、わからないところが出てきたり、習熟のための時間が不足したりすることがあります。 そこで、家庭学習のような形で勉強をする必要が出てきます。 このときに家庭での勉強と読書の両立を工夫する必要があるのです。 一般に、勉強は面白くないもので、読書は面白いものです。 だから、この二つをうまく組み合わせることが両立させるコツになります。 まず最初に机に向かうきっかけとして、読書を始めます。 しかし、この読書はタイマーなどで時間を短く区切っておく必要があります。 区切る時間は、5分や10分です。 読書でウォーミングアップができたら、その勢いで勉強に取りかかります。 そして、勉強が一段落したら、あとの自由時間にたっぷり読書の続きをするのです。 このやり方とは逆に、最初に読書をしてしまうと、そのまま勉強する時間がなくなってしまいます。 読書-勉強-読書というサイクルでやっていくのが、読書と勉強を両立させる方法です。 ▽参考記事 「勉強の始めに5分間読書、勉強の終わりにたっぷり読書」 https://www.mori7.com/index.php?e=2606 |
|
|
||||