印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■【重要・再掲】8月11日(金)、および8月12日(土)-18日(金)は休み宿題
■振替授業について
■休み中は返却講評が遅れることがあります
■「読書ゼロ冊」の予備軍にならないために
■自学自習でやっていると、学年が上がるほど勉強の能率が上がる
■子供に作文を教えるために、自分が作文を習う方法もある
■受験作文コースについて
|
|
||
|
言葉の森新聞
2017年8月1週号 通算第1476号
https://www.mori7.com/mori/ |
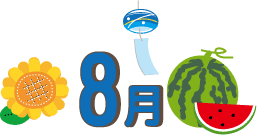
森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
| ■【重要・再掲】8月11日(金)、および8月12日(土)-18日(金)は休み宿題 |
|
8月11日(金)は、祝日のため休み宿題となります。 また、カレンダーに記載してあるとおり、8月12日(土)-18日(金)は言葉の森の夏休みとなり、同じく休み宿題です。 先生からの電話はありませんが、自宅でその週の課題を書いて作文を提出してください。他の日に教室に来るか教室に電話をして、その週の説明を聞いてから書くこともできます。 休み宿題のときに、電話の説明を聞かずに自分で作文を書く人は、ホームページの「授業の渚」か課題フォルダの「解説集」を参考にしてください。 「授業の渚」 http://www.mori7.com/nagisa/index.php 「ヒントの池」 http://www.mori7.com/mine/ike.php |
|
|
||||
| ■振替授業について |
|
電話による振替授業の受付時間は、下記の通りです。 (月~金)9時-19時50分 (土)9時-11時50分 振替授業は予約制ではありません。(受講時間や、先生の指定は原則としてできません) 生徒さんが在宅で、作文を書けるときに直接教室にお電話ください。 なお、夏休み中は、混み合うことがあるため、20分くらいお待ちいただく場合があります。 8月12日(土)-18日(金)は、上記の通り教室が夏休みのため、振替授業もありません。第5週目もお休みとなります。 |
|
|
||||
| ■休み中は返却講評が遅れることがあります |
|
夏休み中は、教室が休みになる週と担当の先生が休みをとる週があるため、作文の返却や講評が一時的に遅れる場合があります。ご了承ください。 |
|
|
||||
| ■「読書ゼロ冊」の予備軍にならないために |
|
小学生の子は、誰でも普通に本を読みます。 それは小学生の間は、学校が読書に力を入れているからです。 しかし中には、「読書は学校でやっているから家では読まなくてもいい」と言う子がいるのです。 こういう子は、中学・高校生での読書ゼロ冊の予備軍になります。 読書は人に言われて一応読むというのでは不十分です。 読書が大好きで、本がなければ夜も日も明けないぐらいになっておく必要があるのです。 |
|
|
|
そういう読書大好きの子を育てる最初の一歩が、毎日10ページの読書です。 読書が苦手な子は、最初はぎりぎり10ページ読み終えて、「ああ、やれやれ」という読み方でもいいのです。 本には、読み手を引き付ける力があります。 いつかおもしろい本に巡り会い、1日で思わず1冊読み終えてしまったという日が来るのです。 大事なことは、子供に対する「読書10ページ」の目標を、親の目標にしないことです。 親の目標は、読書大好きの子供を育てることです。 小学校時代の学力とは、算数の計算力でも国語の漢字力でももちろん英語力でもなく、読書力に尽きるからです。 子供の今の成績を見てわかるのは、勉強しているかどうかだけです。 その子がどう伸びるかは、今の成績ではわかりません。 子供の将来の伸びがわかるのは、どういう読書をしているかによってです。 しかし、この読書の差は、目につく機会はほとんどありません。 だから、子育ての基本は、気長に読書好きの子を育てることに尽きると言ってもいいのです。 昔の子供は、よく本屋さんで立ち読みをしました。 それで、はたきで追い払われたり(笑)。 しかし、今はそういう身近な本屋さんがあまりありません。 だから、アマゾンなどで試し読みできるようにしておくといいのです。 1ヶ月いくらまでは本を買ってよいというようにしておけば、子供はだんだん本を選ぶことが上手になります。 しかも、kindleは6台の端末で共有できるので、同じ本を、兄弟も、両親も、田舎の祖父母も読むことができます。 読書を中心とした生活は、やり方によっては、昔よりもずっと容易になっているのです。 |
|
|
||||
| ■自学自習でやっていると、学年が上がるほど勉強の能率が上がる |
|
勉強でも、勉強以外の習い事でも、初心者のうちは人から教えてもらうことが必要で、教えてもらう方が上達は早いものです。 しかし、ある程度レベルが上がってくると、それぞれの個性に応じてよくできるところと、あまりできないところが出てきます。 すると、人に教えてもらう場合でも個別の指導が必要になります。 学校で言うと、小学校低学年のころは一斉指導でわかりやすく教えてもらう方が能率よく勉強できます。 しかし、高学年になってくると、だんだん個別指導が必要になってくるのです。 それは、学年が上がってくると、得意なところと苦手なところが人によって分かれてくるからです。 そして、更に学年が上がり、中学生、高校生になると、この個別指導の必要性はますます高まってきます。 そして、究極の個別指導は独学なのです。 高校生になって独学中心に勉強していくためには、小学生のころから独学的なやり方で勉強をしておく必要があります。 その独学的な勉強の仕方が、家庭学習です。 |
|
|
|
その家庭学習も、親が教材の内容を把握していることが必要です。 そして、子供の出来具合に応じて、教材の選択を変えられるようにしておくことが大事です。 しかし、それは親がつきっきりで子供の勉強を見ているということではありません。 子供が自主的に勉強できるような方法を親が作っていくということなのです。 この自学自習を勉強の基本にしていると、学年が上がるほど勉強の能率が上がってくるのです。 勉強の基本は家庭学習です。 今は、インターネットの普及で、教材も勉強の仕方も容易に手に入るようになりました。 そして今では、一緒に勉強する友達も、家庭学習の中で探せるようになっているのです。 学校にいる間は、まだ人に教わるかたちの勉強でもいいのですが、社会に出たら教わるだけでは限界があります。 自分で工夫して学ぶことは、仕事が高度になればなるほど必要になってきます。 だから、学校にいる間から、そういう自主的に学ぶ姿勢を作っておくことが大事なのです。 |
|
|
||||
| ■子供に作文を教えるために、自分が作文を習う方法もある |
|
子供に家庭で作文を教えるのは、かなり難しいものです。 それは、教える当のお母さんやお父さんが、子供のころに作文の書き方を習ったことがないからです。 だから、作文を書くときの子供の気持ちがよくわかりません。 昔、こんなことがありました。 「楽しかったこと」という題名の作文がなかなか書けないので、お母さんがしまいに怒り出して、子供が泣きながら「楽しかった」という作文を書いた、という笑い話のようなかわいそうな話です。 教える人が作文を書くときの苦労がわかっていれば、子供にも書きやすくアドバイスすることができます。 その方法の一つが、大人が子供と同じ作文を書く練習をすることです。 例えば小学2年生の子供の作文を教えてあげたければ、大人が小2の作文の課題から練習をするのです。 そして、自分が教わった方法で子供に書き方を教えてあげます。 言葉の森では、このように、社会人が小学生の作文を書く練習をすることもできます。 もう一つは、もっと本格的に森林プロジェクトの作文講師資格講座を受講することです。 これは、小1から高3までの作文指導を本格的に学べます。 これから、記述力や作文力は入試でも大事になってきますから、自分の勉強も兼ねて作文の教え方を学ぶのは役に立つと思います。 作文は、勉強の中で最も教えにくいものでないかと思います。 その理由は、答えがないということと、そのときの精神的なものに左右されたり、題材のよさという偶然に左右されたりすることがあるからです。 また、作文の勉強は、話し声のあるところでは書きにくいという特徴があります。 そして、いちばん大きな原因は、上にも書いた通り、作文を教える人が作文の書き方を習ったことがないことです。 低学年の子の作文指導をするとき、先生が子供が書くよりももっといい表現を教えて書かせてしまうことがあります。 |
|
それは、一見指導のように見えますが、作文の結果がよくなるだけで、子供の実力がついたわけではありません。 ということは、少し考えればわかることですが、今でもこういう教え方をしているところが多いのです。 大事なのは上手な作文を書かせることではなく、そういう作文が書ける実力をつけてあげることです。 |
|
|
||||
| ■受験作文コースについて |
|
来年の春、中学、高校、大学を受験する人向けの「受験作文コース」を受け付けています。 受験作文コースの期間は、中学受験は「受験前の4か月間」、高校受験は同じく「3か月間」、大学受験は同じく「2か月間」です。 受験作文コースは、作文の試験がある学校が対象です。その学校の過去問の傾向に合った問題で作文を書く練習をしていきます。 作文試験と銘打ってはいても、100字や200字の長さでは作文ではなく、記述問題の長いものという扱いになります。 記述問題への対応は受験作文コースでは行いません。それは、わざわざ特別のコースで練習をしなくても家庭で十分に対応できるからです。そのかわり、個々に記述問題練習の仕方を説明することができますので、まずはご相談ください。 受験作文コースの取り組みで大事なことは三つあります。 第一は、自分らしい個性や感動のある実例を見つけていくことです。 受験コースのそのときどきの課題で、いい実例を見つけていると、それが試験の本番でも応用できるようになります。 実例は、子供が自分で考えるだけでなく、親が似た例を話してあげることも大事です。親の似た例にヒントを得て、子供が更によい例を考えつくということも多いからです。 第二は、深い感想や意見を書く練習をすることです。 作文の課題が、例えば「これまでの学校生活の思い出」のような身近なものであったとしても、身近な話をそのまま書いたのでは、受験用の作文とはなりません。 自分の書いた文章の中に、必ず大きい視点、深い見方、個人の実例を超えたより一般的な考え方というものが必要になってきます。 これは、小学6年生の課題で「一般化の主題」として勉強してきたものです。 第三は、切れ味のよい表現を作っていくことです。 受験の作文を採点するのは人間ですから、単に正しいことを書いてあるだけでなく、読む人の心にひびくような表現が使われていることが大事です。この切れ味のよい表現が、作文の結びの5行以内に入っていると、読んだあとの印象がかなり上がります。 同じレベルの作文であれば、結びの5行に切れ味のよい表現があるかどうかで、合否もほぼ決定するのではないかと思います。 ところが、この切れ味のよい表現は、作文をいくつも書く中で、偶然に出てくる面があります。 だから、毎回表現の切れ味を意識して書き、そこに両親も参加してアドバイスするという形をとっていくといいのです。 |
|
|
||||