印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■作文好きな子集まれ。ハイパー作文クラス、体験生徒募集中
■寺オン作文クラスの土曜9:00~9:45がスタート
■特色入試型の子供たち
■子供が学校に行きたくないと言い出したら
|
|
||
|
言葉の森新聞
2018年3月3週号 通算第1507号 https://www.mori7.com/mori |
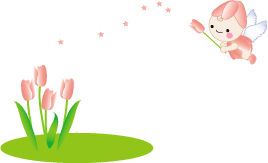
森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
| ■作文好きな子集まれ。ハイパー作文クラス、体験生徒募集中 |
|
この春から、作文のオンライン少人数クラスを始めました。それが、寺子屋オンライン作文クラスです。 このオンラインと、少人数という組み合わせが、実はかなり難しいのです。 オンラインのビデオ授業や、オンラインのマンツーマン指導はどこでもやっていますが、オンラインの少人数というのは、多くの場合ごく狭い範囲でしかできません。組織的にオンライン少人数指導を行うとなると、運営上のハードルが格段に高くなるからです。 さて、このオンライン少人数クラスは、グループディスカッションができるクラスですから、特色のある教え方をしたいと思っています。 その一つが、作文の好きな子が集まり切磋琢磨をしながら、よりレベルの高い作文を書くという前向きな勉強をしていくことです。 それで、この少人数作文クラスの愛称を、ハイパー作文クラスとしました。何しろ前向きに、高度なことをしていくのです。 この場合、作文が好きであるということが唯一の条件で、上手だとか下手だとかいうことは問いません。 作文が苦手な子であっても、書くことが好きであればいいのです。または、面白そうだからやってみたいという子であればいいのです。子供の意向が第一です。 ただし、作文を毎回アップロードするのに、保護者の協力が必要です。といっても、もちろん難しい操作ではありません。慣れれば子供でもできる手順です。 また、お母さん又はお父さんが、最低限月に1回は必ず懇談会に参加できるということも条件にします。ただし、懇談会と言っても、授業のあとのミニ懇談会を予定しているので、15分程度のものです。 こういう親子の協力があれば、子供の作文は更に充実したものになるからです。 ハイパー作文クラスは、次のようなわかりやすい目標を決めて勉強していきます。 まず第一に、小学校低学年・中学年であれば、各種コンクールに入選することを目標にします。 しかし、大事なことは実力で入選することですから、先生が作文に手を加えたり、上手になる表現を教えたりというようなテクニック的な指導はしません。本人の実力を伸ばして入選することが目標です。 第二に、小学校高学年の場合は、公立中高一貫校の作文試験に合格できるだけの作文力をつけることを目標にします。 かなり難度の高い指導項目も出てきますが、小学校高学年の生徒はそういう難しいチャレンジを喜ぶようなところがあるので、かえって面白い勉強になると思います。 第三に、小学校高学年、及び中学生で、パソコン入力ができる生徒は、森リン大賞の毎月入賞を目標にして書いていきます。 森リン点を上げるにはいろいろな条件が必要になりますが、その条件を工夫していくことが表現力と語彙力を伸ばすことにつながるからです。 |
|
|
|
中学生の場合は、高校入試に作文があれば、これがそのまま入試作文の対策になります。 高校生の小論文入試対応講座や、センター試験国語満点講座したいのですが、今は時間的に難しいのでそれはまたいつか単発講座としてやっていきたいと思います。 ハイパー作文クラスは、当面は限られた曜日・時間でしかできませんが、運営が軌道に乗ったら、また別の特色を持った作文クラスを運営していきたいと思っています。 例えば、kindle出版を目指すクラスとか、祖父母の自分史を取材して書くクラスとか、四コマ漫画とセットにした作文クラスとか、英語翻訳作文クラスとか、いろいろ考えられます。 教える先生の個性を生かした特色あるクラスが、いくつもできると思います。 講師は、中根と、森林プロジェクトで作文講師資格講座に合格した先生です。 オンライン少人数クラスは、リアルな教室と違ってオープンな研修環境があります。 リアルな教室は、学級王国と言われることがあるように、どうしても閉鎖的になりがちです。たまに、授業参観や研修があっても、そのときだけ外向けの特別な授業になりがちです。 その点、オンライン少人数クラスは、日常的な指導の中でも常時研修が可能なので、生徒ばかりでなく講師も成長する条件が整っています。 このオンライン少人数クラス(正式名称は、寺子屋オンライン作文クラス)を、これからの作文小論文指導のスタンダードにしていきたいと思っています。 ▽現在開設している寺子屋オンライン作文クラス ・月19:00~19:45 ・水17:00~17:45 ・木17:00~17:45 ・木19:00~19:45 ・土 9:00~ 9:45 言葉の森に作文を習いに来る生徒には、作文が好きで得意だからという子もかなりいます。 もちろん、苦手で困っているからという子もいますが。 得意な子と苦手な子がいた場合、教える先生は人情としてどうしても苦手な子に力を入れがちです。 得意な子は、教えればどんどん上手に書けるので、それ以上のことは特に必要ないと思ってしまうのです。 そこで、今度のオンライン少人数クラスは、むしろ得意な子、好きな子の力を伸ばすという方向で進めることにしました。 と言っても、何もスパルタ式でやるのではありません(笑)。 子供たちどうしのディスカッションを生かし、自然に前向きになる勉強をしていくのです。 |
|
|
||||
| ■寺オン作文クラスの土曜9:00~9:45がスタート |
|
これまで、電話通信コースの土曜クラスは満員だったため、体験学習の受け付けができませんでしたが、3月から新たに寺オン作文クラスの土曜クラスを開設することにしました。 https://www.mori7.com/teraon/shlist.php 土曜の作文受講を希望される方は、寺オン作文クラスにご参加ください。 なお、寺オン作文クラスは、毎週生徒どうしの発表と交流を行いますので、どちらかと言えば作文の好きな子に向いています。 特に、小学校高学年の生徒の作文指導については、受験作文にも対応した比較的高度な学習にしていく予定です。 電話通信コースの方は個別指導ですので、作文の好きな子にも、苦手な子にもどちらにも対応できます。 |
|
|
| どちらのクラスがよいか判断しかねる場合は、言葉の森までご相談ください。 |
|
|
||||
| ■特色入試型の子供たち |
|
これまでの受験は、覚えた知識をいかに正確に再現できるかという能力の評価が中心になっていました。 それは、考える勉強と思われている入試の算数数学の世界でも同じです。 算数数学も、入試問題のレベルで言えば解法の記憶と組み合わせと再現にすぎません。 もちろん、その習得には時間がかかりますし、物事を数学的に処理する土台として重要ではあるのですが、基本は記憶と再現なのです。 さて、今後の入試は、人工知能に代替される記憶の再現を中心にしたものではなく、人工知能に代替されない人間の能力を見るものが中心になってきます。 世界の大学の入試の主流は、ペーパーテストから人物評価のようなものに移りつつあります。 東大・京大が、推薦入試・特色入試の枠を作ったのは、日本だけが記憶力中心の入試を行っていたのでは、世界の水準から立ち遅れることが分かったためです。 では、人工知能に代替されない人間の能力とは何でしょうか。 それは、学力の面に関しては創造性です。 その創造性の根底にあるものは、自分の好きなことを追求したいという意欲です。 好きなことがあり、その好きなことに費やした時間のあることが、その人物の個性とほぼ同じものだと言えるのです。 個性が、社会に役立つ創造性となるための前提として必要な学力は、センター試験の8割が取れていれば十分で、あとは必要に応じていくらでも身につけていけるという考えが、これからの入試の基本的な考えになっていきます。 ところで、人物評価をどのようにするかと言うと、それはその人物の未来の夢や理想ではなく過去の実績です。 受験作文コースの生徒の志望理由書を見ていると、その志望理由書の内容だけで合格間違いなしと思われるような子もいます。 それは、過去の実績がしっかり書かれているということです。 その反対に、志望の理由として自分の憧れや希望や理想を書いただけのものは、結局誰も同じような内容になってしまいます。 つまり、その人が未来に何をしたいかではなく、過去にどのようなことをしてきたかという蓄積が、その人物そのものと見なされるのです。 今、思考発表クラスに参加している生徒の中に、毎回、個性的な作文構造図や独自の理科実験をアップロードしてくる子供たちがいます。 こういう、今の世間の概念では勉強と言えないような勉強を毎週している子は、逆に将来は、その蓄積を見せるだけで特色入試は合格圏内に入るようになるのではないかと思います。 これからの世の中は大きく変わります。 廃(すた)れつつある過去の社会を基準にして子育てを考えるのではなく、来たるべき未来の社会を基準にして子育てを考えていくことです。 その子育てにおける勉強の仕方の基本は、これまでのような苦しいことに耐えて無理に頑張らせる勉強ではなく、つまり人工知能と競い合うような勉強ではなく、本人の個性を生かした伸び伸びとした楽しい勉強になるはずなのです。 |
|
|
||||
| ■子供が学校に行きたくないと言い出したら |
|
実は、私のうちの子も小学校4年生のころに不登校になりました。 理由は、学校で友達が授業中に先生からいじめられているのを見るのが苦しいからということでした。先生からというところが何か変ですが(笑)。 |
|
|
|
私は、自分自身が学校に行くのがあまり好きではなかったので、その話を聞いたときにはすぐに賛成しました。 私が、学校時代にいちばん嫌だったのが、硬い椅子に座って先生の話をただ聞いているだけの退屈な時間を我慢することでした。 だから、学校に行かずに家でのんびり楽しいことをしていた方が、ずっと人間らしい生活が送れるという感覚が自分の中にあったのです。 子供の不登校ということについては、全く何も心配していませんでした。 子供と話をしていて、まともに対話ができるのであれば、学校に行くとか行かないとかいうことはどうでもいいことだと思っていたからです。 社会が決めた路線から子供を見るのではなく、親が自分の目で見てちゃんと育っていると思う子であれば、学校に行こうが行くまいが、成績がよかろうが悪かろうが、そういうことはあとからどうにでもなるのです。 特に、今は学校に行かなくても、主要教科の参考書を一冊ずつ用意して家庭で勉強すれば、学校に行くよりもずっと短時間で多くのことを学べます。 授業的なことをしたいのであれば、スタディサプリなどで勉強をしていくこともできます。 学校の利点は、友達や先生との集団生活が行えるということですが、それは放課後の地域のサークルのようなところに参加してもいいですし、又は、インターネットでいろいろな集まりに参加してもいいと思います。 今の社会では、勉強する手段はいくらでもあるし、友達と交流する手段もいくらでもあるので、学校に行くということを義務と感じる必要は全くないのです。 そして、いちばん大事な考え方は、人生の目的は仕事をすることであって学校に行くことではないということです。 昔は、学校に行くことが仕事の最初のステップであるかのように考えられていましたが、今はそういうことはありません。 学歴で採用を決めるような企業はもちろんありますが、世の中にはどこの学校を出ていようが関係がないという仕事の方がずっと多いのです。 今仕事をしている大人の人は、同じ仕事をしている仲間がどこの学校を出たかということとその人の実力はほとんど関係がないことを知っているはずです。 関係があるとすれば、それは偏差値の高い学校を出た人は誤字が少ないとか、長い文章を読むのが苦にならないという程度のことです。 その程度の長所は、その他の様々な長所でいくらでも逆転するごく一部の長所にすぎません。 ですから、今子供が不登校になると心配している人については、むしろ不登校を活かして自分らしい個性的な生き方をしていくチャンスだと考えていくことです。 今の世の中の大人の多くは、まともな路線を歩んできている人が多いので、人と違うことをやることに不安や恐怖を覚えるようです。 しかし、大きく考えれば人生は誰にとってもチャレンジの連続で安心できるような道などはどこにもありません。 それならば、むしろ人と違う道を歩むということをいい機会だと考えていくといいのだと思います。 ところで、最初に書いたうちの子は、今は普通の社会人で子供もいて普通に仕事をしています。 不登校の時期に、北海道の山村留学に行きしばらく暮らしていましたが、近くの海でウニを取って浜辺で焼いてみんなで食べたのがすごくいい思い出になっているようでした。 どんなことも過ぎてしまえば、みんな楽しい思い出になるのです。 だから、今起きていることは、どれも必然で必要なことで、それがあとで必ずいい結果になると考えていくといいのです。 |
|
|