印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■【重要】新学期の教材を発送します
■第4週は清書。幼稚園生は作文
●清書の意義と方法
●清書の投稿
●小学生新聞の投稿先
■4週目の読解問題(小1以上)
■3月29日(木)、30日(金)、31日(土)は休み
■子供の勉強は、やらせることよりも、やらせないことを先に考える
■低学年の作文、高学年の作文は頭の使い方が180度違う
■すぐに書き出せる作文――そして密度濃く、楽しい授業
■もっと字を丁寧に書かなきゃ、と言うよりも
■新しいコンセプトの勉強
|
|
||
|
言葉の森新聞
2018年3月4週号 通算第1508号 https://www.mori7.com/mori |
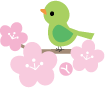
森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
| ■【重要】新学期の教材を発送します |
|
4月~6月分、新学期の教材を、3月16日(金)~19日(月)の期間に発送する予定です。 国内の生徒で、26日以降になっても届かない場合はご連絡ください。 |
|
|
||||
| ■第4週は清書。幼稚園生は作文 |
|
幼稚園年中と年長の生徒は、第4週も普通の作文を書く練習です。自由な題名で作文を書いてください。 小学1年生以上の生徒は、清書を行います。 清書をしたあと、時間に余裕のある場合は読解問題をしてください。 |
| ●清書の意義と方法 |
|
清書とは、これまでに書いた作文の中で内容がよかったものを書き直すことです。 内容がよいとは、個性、感動、共感などがあるということです。 書き直すときは、次の点に留意してください。 (1)漢字で書けるところは漢字で書く。 (2)たとえや自作名言を工夫できるところがあれば工夫する。 (3)似た話や続きの話を書くことによって字数を増やす。 (4)作文用紙の空いているところに絵などをかいてもよい。 |
| ●清書の投稿 |
|
清書した作文は、小学生新聞や一般紙などに投稿してみましょう。 手書きの清書の原本を、新聞社に投稿したり、コンクールに応募したりする場合は、清書のコピーの方を先生に送ってください。 新聞社に投稿する際は、作文用紙の欄外又は別紙に次の事項を記載してください。 (1)本名とふりがな(2)学年(3)自宅の住所(4)自宅の電話番号(5)学校名とふりがな(6)学校所在地(町村名までで可)など。 投稿する際は、ペンネームを本名に訂正しておいてください。作文の中に友達の名前が固有名詞で入っている場合は、イニシアルなどに直しておいてください。投稿する作文の内容は、保護者がチェックしてあげてください。 同じものを複数の新聞社やコンクールに送らないようにしてください。これは二重投稿といって、もし両方に掲載されてしまった場合、掲載先に迷惑をかけることになります。 |
| ●小学生新聞の投稿先 |
|
■104-8433東京都中央区築地3-5-4 朝日小学生新聞「ぼくとわたしの作品」係 ■100-8051(住所はいりません 毎日小学生新聞「さくひん」係(600字以内) ※清書した作文を投稿しない場合でも、額などに入れて家の中に飾っておきましょう。 |
|
|
||||
| ■4週目の読解問題(小1以上) |
|
|
|
小1以上の生徒には、課題フォルダに、4週目の長文をもとにした読解問題を2問載せています。時間のある人は取り組んでください。 言葉の森ホームページの「読解マラソン」のページには、全8問の問題とそれに対応した長文がありますが、課題フォルダには問題数をしぼり、問7と問8の2問だけ掲載しています。 これは、この2問をじっくり解いて満点にすることが目標だからです。 問1~6も含めた全問を解きたい方は、読解マラソンの「問題のページ」で他の長文と問題をごらんください。 ただし、その場合も、当てずっぽうで全部解くのではなく、必ず全問正解になることを目標に解くようにしてください。 http://www.mori7.com/marason/ki.php |
|
|
||||
| ■3月29日(木)、30日(金)、31日(土)は休み |
|
今月末の3月29日(木)、30日(金)、31日(土)は、第5週のためお休みです。 先生からの電話はありません。振替授業もお休みです。 |
|
|
||||
| ■子供の勉強は、やらせることよりも、やらせないことを先に考える |
|
幼児のころから、勉強も、スポーツも、音楽もといろいろなことをやって、どれも優秀な成績を収めている子がいました。 しかし、その子が、高学年になったころ、どれもほどほどにやるようになっていたのです。 どれも、一応合格点ぎりぎりのところまでやるが、決してそれ以上はやろうとしない、つまり熱中するような取り組みなどはなく、言われたことを言われた範囲できちんとこなすというやり方になっていたのです。 こういう子と反対の子もいました。 大人が見て、いかにも無駄で無意味だと思われるようなことに熱中する子です。 しかし、その子が学年が上がり、入試に取り組むようになると、その集中力であっという間に実力をつけていきました。 小学校時代の子供の生活で大事なことは、今の成績を上げることではありません。 能率は悪くてもいいから、自分の意志でやることと、何かに熱中できる生活をすることです。 親は、子供の生活をコントロールする前に、まず自分が子供のころ、どういうことがうれしかったかを考えてみることです。 そして、自分にないものを子供に求めるのではなく、自分の今につながっていることと同じことを子供にも認めてあげることです。 今の自分を形成しているものの中には、当時は無駄だと思われていたようなこともたくさんあったはずです。 そうすれば、さまざまな勉強や習い事で子供の時間を埋めるのではなく、もっと役に立たないように見える時間を大切にすることができるのではないかと思います。 ▽昔の関連記事 「勉強をコントールする力をつける――そのための親の勉強観」 https://www.mori7.com/as/2921.html |
|
|
||||
| ■低学年の作文、高学年の作文は頭の使い方が180度違う |
| 低学年の作文と高学年の作文の最も大きな違いは、低学年の作文が題材中心であるのに対して、高学年の作文は主題中心であることです。 |
|
|
|
だから、よく出す例ですが、「私の友達」という題名で作文を書く場合、低学年のうちは友達とのさまざまな交流の出来事を書いていけばいいのですが、高学年になったら、「友情とは何か」ということを考えながら書いていくようになるのです。 そして、更に言えば、その主題に合わせて実例を選び直すという書き方をします。 同じ題名で書いていても、低学年と高学年では、頭の使い方が180度違うことが要求されるのです。 しかし、厳密にそういう評価をしたら、小学6年生の子でその要求に沿って書ける子はほとんどいなくなります。 だから、構成の形だけ指示して、その構成に合わせる勉強をする中で、学年が上がるにつれて次第に主題中心に書く書き方ができるようにしていくのです。 ▽関連記事 「高学年になって作文が得意になるには、低学年のときからの作文指導が大事」 https://www.mori7.com/as/2890.html |
|
|
||||
| ■すぐに書き出せる作文――そして密度濃く、楽しい授業 |
|
オンラインの作文の少人数クラスでは、開始の合図とともに、みんなが一斉に作文を書き出します。 通信指導や家庭学習で作文を書く場合、書き出す前にはエネルギーがかなり必要ですが、オンラインを少人数クラスではみんなが書き出すので自然にすぐに書き始める雰囲気ができあがります。 オンラインの少人数クラスのいいところは、このように他の人と一緒に交流することが勉強の励みになることです。 また、個別に説明が必要な場合は、ブレイクアウトセッションという分科会の会場に移動してもらい、その生徒だけに詳しく説明することができます。 これは、リアルな教室よりも優れている点です。 リアルな教室では、みんなが静かに書いている中で一人ひとりに個別の話をすると、中にはその声が気になって集中しにくいという子も出てきます。 作文の勉強は、他の勉強と違って人の声が聞こえるところではかなり書きにくくなるからです。 オンライン少人数クラスの場合は、静かな部屋は静かなままで書き続けることができます。 このオンラインの教室のもう一ついいところは、授業の様子をあとでお父さんやお母さんが見ることができるという点です。 先生がどんなことを説明して、子供がどんな風に勉強したかということが分かるのです。 また、授業のあとの保護者懇談なども、すぐに行うことができます。 オンラインの作文の少人数クラスは、先生にとっても利点があります。 それは赤ペン添削のような時間のかかることを大幅に省略して、口頭での説明を中心にできるからです。 口頭説明とは、作文の該当する箇所に番号をつけて、その番号のところを詳しく説明するのです。 ですから、同じ時間内に伝えられる内容はかなり多くなります。 オンライン少人数クラスの作文指導というのは、全く新しい授業形態なのでまだどこでも行われていないと思います。 しかし、これから作文指導の理想的な形として広がっていくと思います。 ところで、今、電話通信で作文の授業を受けている生徒は、今の先生のまま授業を続けたいと思っている人も多いと思います。 その場合は、今の電話通信の先生が、オンラインの作文の少人数クラスを担当するまで待っていただくといいと思います。 電話通信から、オンライン少人数クラスへの移行は、意外に早く進むのではないかと思っています。 |
|
|
|
|
||||
| ■もっと字を丁寧に書かなきゃ、と言うよりも |
|
子供の作文を見て、よく「もっと字をていねいに書かなきゃ」と言うお母さんがいます。 そう言いたい気持ちはわかりますが、問題は子供の字にあるのではなく、つい先に欠点を見て指摘しまうお母さんの方にあるのです。 そう考えれば、世の中は簡単です。 悪いことがあるのではなく、もちろんあることにはあるのですが、その悪い方を先に見てしまう心の姿勢の方にあるのです。 このことで思い出すのは、中村天風の話です。 あるとき、師のカリアッパ氏が天風に質問をしました。 後ろから虎が追いかけてくる。やっと木に登ったら、その木の上から大蛇が近づいてくる。急いで枝から出ている蔦(つた)につかまったら、その蔦の根元をリスがかじっている。下は千尋(せんじん)の谷だ。どうする。 天風は、すかさず答えました。なあに、落ちてから考えりゃいい。 困ったことは、それが起きてから考えればいいという姿勢でいれば、どんなときでもたくましく生きていけます。 困ったことを先回りして考えれば考えるほど、人間は小さくなっていくのです。 真面目な人ほど、「○○しなかったら、○○しなくなるよ」というような言い方をします。 強調するために、二重に否定語を使ってしまうのです。 同じことを、「○○したら、○○するよ」と言うだけで、子供の受け取る感じは全く違ってきます。 聞いていて明るくなるのです。 あれも直して、これも直してと、直すだけで一生終わってしまうような生き方をするのではなく、まず最初に今あるいいところを生かしてそれを伸ばす工夫をすることです。 よいところを伸ばしているうちに、直すつもりだったところは単なる小さなエピソードになってしまうことがほとんどなのです。 |
|
|
||||
| ■新しいコンセプトの勉強 |
|
今、新しいコンセプトの勉強を考えています。 第一は、先生の授業を聞くことよりも、生徒が自分で考えて発表することを大事にする勉強です。 第二は、みんなと同じ正しい答えを出すことよりも、自分らしい問題を作ることを大事にする勉強です。 第三は、子供だけにさせる勉強ではなく、お父さんお母さんと協力して行う過程を大事にする勉強です。 第四は、すぐ役に立つことばかりでなく、今は役に立つかどうかわからないようなことでも本人の好きなものをやることを大事にする勉強です。 これからの世の中は、ますます創造性が必要とされるようになります。 正しいことをきちんとこなす仕事は、人工知能が代替していきます。 答えのある勉強は学力の基礎ですが、その基礎は勉強の目的ではなく創造性を発揮するという勉強の手段です。 だから、学校で教わる勉強以上のことをするのが、寺子屋オンラインの勉強です。 今度、寺子屋オンラインでは、理科、社会の勉強も取り入れる予定です。 テスト勉強という目から離れると、理科も社会も面白い創造的な勉強になるのです。 |
|
|