印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■提出率百パーセントの通信作文とは
■今、寺子屋オンラインシステムで考えていること(3)――森林プロジェクトの講師
■google+終了につき、寺子屋オンラインの作品アップの移行先にWorkplaceを検討中
■「良い子」とは少し外れたところにいるのが本当の良い子
|
|
||
|
言葉の森新聞
2018年10月3週号 通算第1535号 https://www.mori7.com/mori |
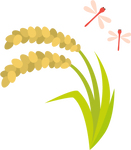
森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
| ■提出率百パーセントの通信作文とは |
|
作文の勉強は、通信教育で行われていることが多いと思います。 通学形式の作文教室ももちろんありますが、これは運営が少し難しいところがあります。 それは、進度の異なる複数の生徒を同時に教えるカリキュラムのないところが多いからです。 言葉の森の場合は、もちろんその進度別のカリキュラムがあります。 言い換えれば、言葉の森が日本で初めて小1から高3までの進度別の作文指導のカリキュラムを作ったということです。 しかし、そういう指導の流れがはっきりしている教室の場合でも、通学教室では、ひとりでもおしゃべりな子がいたり、質問ばかりする子がいたりすると、教室全体の運営が難しくなります。 作文の勉強というのは、言葉を使った考える勉強なので、ほかの教科の英語、数学などの勉強に比べると、言葉の雑音にきわめて弱いところがあるのです。 ですから、家庭で作文を書く場合でも、テレビの音声が背後で流れていたり、他の家族の話し声がしたりする環境では、高学年の作文はまず書けません。 そういう静かな環境を作るという点で、通学教室は運営が難しくなるところがあるのです。 通信教育は、家庭で個別に行う学習ですから、家庭内で雑音がない状態を作れば、通学教室のような問題はありません。 しかし、その分、通信教育は強制力がないので、続けにくいという問題も出てきます。 子供が小学4年生のころまでであれば、作文の課題もそれほど難しくありませんし、何よりも親の言うことをまだよく聞く年齢ですから、提出が滞るということはあまりありません。 しかし、小学校高学年になり、中学生や高校生になり、生徒本人の自主性に任せて勉強するような年齢になると、通信教育の強制力のなさが次第に表面化するようになってくるのです。 これまでの通信教育は、たとえ言葉の森の電話通信指導であっても、先生からの電話の説明のあと、作文を書き出し、書き上げるのは本人の自主性に任されていました。 そのため、電話の説明をよく聞いていても、実際の作文は書き出せず、翌日以降に持ち越してしまうという生徒がよくいました。 ところが、今回、言葉の森が始めた寺子屋オンラインという少人数の通信指導では、この問題が根本的に解決する道筋が見えてきました。 寺子屋オンラインは、当初、子供たちの作文を発表し合うという形で進めていました。 正確には、作文を発表し合うというよりも、作文の準備を発表し合うということで、予習シートや構想図の発表、そして読書紹介などを中心とした運営をしていました。 しかし、発表だけで1時間近く取って授業が終わってしまうと、そのあとの作文は、本人が別の時間に独自に取り組まなければなりません。 これは、高学年の難しい作文を書く生徒にとっては、やや負担の大きいことになります。 そこで、今度、寺子屋オンラインの少人数クラスでは、学年別の個別指導と、それに並行する形での作文実習を中心に行う形にしました。 |
|
|
|
発表の方は逆に短時間にし、読書紹介などを中心とするものにとどめ、作文の発表と交流は月に1回の発表交流会で行うことにしました。 この形であれば、学年別の個別指導は、電話通信の個別指導と同じで、しかも同じ学年の他の生徒の準備 も聞けるので、より充実した内容になります。 そして、その個別指導が終わったあとは、その場で会場を移動して作文実習を始めることができます。 1時間の授業の終わりには、全員が再び集まり、どこまで作文を書いたかということがチェックできます。 そのあとその作文を書き終えるまで、その会場にいるというようにすれば、作文を書き出す率は百パーセントで、最後まで書き上げる率も百パーセントに近いものになります。 通学教室の利点は、提出率百パーセントということです。 そのかわり、通学教室では、集中して作文を書けない状況がたまに生まれることがあります。 集中して学習できるというのは、通信教育の利点です。 そのかわり、強制力がないので提出率が低下するというのが通信教育の弱点でした。 寺子屋オンライン方式の少人数クラスは、この通信教育と通学教育の両方の利点を生かし、両方の弱点を解消できるものになります。 また、寺子屋オンラインクラスの更に優れたところは、全国の生徒が対象ですから、生徒数が多くなればなるほど、学年別・進度別の指導がしやすくなることです。 そのかわり、少人数指導の運営をするための独自のノウハウが必要になりますが、これはシステムをプログラミングすれば何とかなります。 現在、作文指導とは別に行っている発表学習コースでは、読書好きで独創的な生徒が集まり、毎回充実したコミュニケーションを交わしているクラスがいくつもあります。 これから、寺子屋オンラインの少人数作文クラスが多くなれば、そういう燃える作文クラスというものも多数生まれてくると思います。 このために、現在、寺子屋オンラインクラスの作文を指導できる、言葉の森の講師資格を持つ先生をウェブで募集しているのです。 |
|
|
||||
| ■今、寺子屋オンラインシステムで考えていること(3)――森林プロジェクトの講師 |
|
寺子屋オンラインの授業は、今後、実習時間の確保、学年分け、定期テストなどの改良とともに、クラス数も増やして、誰でも利用しやすいようにしていく予定です。 ということを、前回の新聞にも載せました。 ところで、寺子屋オンラインシステムの拡充のためには、現在の言葉の森の講師の人数では間に合いません。 現在の講師はそれぞれ担当時間が埋まっているため、新しく時間を割くことが難しいからです。 そこで、更に多くの講師を、森林プロジェクトの寺子屋オンライン作文講師育成講座で募集することにしました。 その募集の前提として、言葉の森では、講師の役割を次のように考えています。 まず、勉強の重要な要素は、教室、教材、教師などだと考えられています。 しかし、私はいちばん大事なものは、一緒に学ぶ友達と、教育の目的だと思います。 今の学校や塾で行われている勉強の多くは、答えがある問題のその正しい答えを早く見つける勉強です。 そのため、答えを見つける勉強の発展した形は、難しい問題を解く勉強という方向に進みます。 それは結局、難しい問題を出すことによって子供たちに差をつけて評価することを目的としているからです。 しかし、勉強の本来の目的はそうではなく、すべての子供が必要な学力をつけることと、そしてその基本となる学力を生かして、創造的な学力を育てることです。 |
|
|
|
例えば、算数の問題でも、難問を解く力よりも、自分で新しい問題を作る力の方が重要になってくるのです。 創造力を育てるという勉強の目的にとって重要なのは一緒に学ぶ友達です。 子供たちは、勉強にしても、遊びにしても、他の人との関わりがあることによって意欲的に取り組めるからです。 こういう教育の目的を考えると、先生の役割というものはこれまでとは大きく違ったものになってきます。 これまでの先生は、教えることを中心とした仕事をしていました。 そのため、現在も学校の教科書は、教えることを前提にして作られています。決して、独学で学べるようには作られていないのです。 しかし、教科書以外の市販の問題集や参考書の中には、子供が保護者と協力して独学で学べるような仕組みのものも数多く作られています。 また、ネットを使ったビデオ授業のように、子供がその授業を視聴するだけで、新しい勉強の中身を習得できるようなものも増えています。 すると、先生の役割は、ますます勉強を教えるということからは遠ざかります。 そしてそのかわり、参加する子供たちの集団を活性化し、仲間はずれを作らず、みんなが協力し励まし合いながら勉強進めていくような、動的なクラスを作ることが重要な仕事になってくるのです。 もちろん、先生には、教える教科の知識があるに越したことはありません。 しかし、小中学校の義務教育の範囲の勉強は、大人であれば既に一度は学び終わった内容ですから、少し時間をかければ誰でもできるようになるのです。 寺子屋オンラインは、単に勉強を教える教育ではなく、従来の学力とともに新しい思考力・創造力・共感力・発表力を伸ばす教育として広げていく予定です。 その寺子屋オンラインの少人数クラスをカバーする先生は、「教える」先生というよりも、「子供たちの集団を活性化させる」先生です。 そういう先生を、今後、森林プロジェクトの寺オン作文講師育成講座で募集していきたいと思っています。 今の教育は、次第に「ティーチング」から「コーチング」の方向に向かっています。 先生が知っている知識を、その知識をまだ知らない生徒に教えるというのは、インターネットなどがなかった時代の古い教育です。 これからは、知識はそれぞれの生徒が自主的に習得し、その成果を互いに発表し合い、友達との交流の中で創造的に発展させるという学び方になってきます。 そういう時代の先生の役割は、これまでとは大きく変わったものになってくるのです。 そうした新時代の教育方法や講師の活動にご興味のある方は、ぜひ下記ページの内容をご覧ください。 「作文講師資格講座」、また「寺オン講師育成講座」の受講者も、随時受け付けています。 ●森林プロジェクト/作文講師資格講座の案内 https://www.mori7.com/sikaku/ ●寺子屋オンライン(寺オン)講師募集/講師育成講座の詳細 https://www.mori7.com/sikaku/index.php#terakou |
|
|
||||
| ■google+終了につき、寺子屋オンラインの作品アップの移行先にWorkplaceを検討中 |
|
google+が2019年8月に終了するとのニュースがありました。 言葉の森の寺子屋オンラインでは、google+は、facebookと違い個人情報がゆるやかなので、作品のアップロードや交流などに利用していました。 |
|
|
|
しかし、アップロードしたものがすぐに反映されないとか、制限ページに承認した人が入れないとか、小さなバグがあり、googleに問い合わせをしていたのですが、いつも返事がありませんでした。 そこで、今後の寺子屋オンラインの交流の場をどうするか、今検討しているところですが、最も可能性が高いのは、Workplace by facebookに移行することです。参加は無料です。 Workplaceは、画面や操作がfacebookとほとんど同じなので、facebookを利用したことのある人は使いやすいと思います。 ただし、facebookのような個人情報を入れる必要はないようです。 また、facebookのアカウントとは別のアカウントとなるので、facebookとの関連付けもないようです。 google+の終了に伴い、これまでアップロードしていた画像や動画で残しておきたいとものは、各自が保存し直しておくといいと思います。それぞれの参加コミュニティで、自分の名前を検索すると、これまでにアップロードしたものが表示されます。 また、今回の移行に伴い、今後、画像のアップロードについては、自分のgoogleフォトなどにアップロードし、そのリンクをコミュニティや「作文の丘」に貼り付けることを検討しています。 言葉の森も、以前は自前で掲示板やさまざまな動的ページを作っていましたが、インターネット技術の変化が速いので、今はできるだけクラウドサービスに移行する方向を考えています。 これからの時代は、インフラの先進性ではなく、コンテンツの個性が重要になってきます。 個人の作り出す個性的な創造は、高い利益率を維持できます。これから来るのは、個人の作り出す多様な世界になってくるのです。 |
|
|
||||
| ■「良い子」とは少し外れたところにいるのが本当の良い子 |
|
良いことをした結果としてご褒美をあげるというのは、悪いことではありません。 しかし、褒美をあげることを手段として良いことをさせるというのは、あまり良いことでありません。 結果としての褒美はいいのですが、手段としての褒美は良くないのです。 それは、なぜかと言うと、褒美という報酬によって子供をコントロールするようになるからです。 人間の本質は、自主性です。 本来自主的な人間が、他人からのコントロールを受け入れることによって、自我が縮小し、自分に対する価値観、自分自身に対する尊厳のようなものが低下していくのです。 自分に対する価値観が低下すると、それにしたがって意欲も低下していきます。 すると、次に同じような行動をさせるためには、さらに大きな報酬が必要になってきます。 逆にもし報酬なしで、しかも困難なことを成し遂げたとすると、その子は自分の自我を拡大させます。 すると、さらに難しいことにも挑戦したいという意欲を持つようになるのです。 子育てのコツは、結果を褒めることは良いが、褒めることを手段にし子供をコントロールしようとしないということです。 そして、褒めることについても、いちばん良いのは心からの感謝や賞賛であって、できるだけ物化しないものの方が良いのです。 犬や猫などの動物は、人間の与える手段によって行動をコントロールすることができます。 犬や猫にとっては、それが嬉しいことでもあるので何も問題はありません。 しかし、人間は、本質的に自分で自分をコントロールするという自主的な生き物です。 大人が考える「良い子」というのは、コントロールしやすい子という面があります。 本当は、そういう「良い子」とは少し外れたところにいるのが、本当の良い子なのです。 子供を素直な良い子に育てるのは基本ですが、素直すぎる良い子の場合は、できるだけ子供の自主性に任せるようにすることです。その自主的な選択が子供なりに合理的なものであれば、親の希望に沿わないときでもそれを認めてあげることです。 近回りで良いことをさせるよりも、遠回りで行った方が、長い目で見れば人間を成長させることも多いのです。 |
|
|