印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■第4週は清書。幼稚園生は作文
●清書の意義と方法
●清書の投稿
●小学生新聞の投稿先
■4週目の読解問題(小1以上)
■1月29日(水)・30日(木)、31日(金)は休み
■これからの勉強はどういうものになるか――教育改革のもっと先の話
■勉強の面白さを知る実験と観察
■国語ドリルでは国語力はつかない
|
|
||
|
言葉の森新聞
2020年1月4週号 通算第1596号 https://www.mori7.com/mori |

森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
| ■第4週は清書。幼稚園生は作文 |
|
幼稚園年中と年長の生徒は、第4週も普通の作文を書く練習です。自由な題名で作文を書いてください。 小学1年生以上の生徒は、清書を行います。 清書をしたあと、時間に余裕のある場合は読解問題をしてください。 |
| ●清書の意義と方法 |
|
清書とは、これまでに書いた作文の中で内容がよかったものを書き直すことです。 内容がよいとは、個性、感動、共感などがあるということです。 書き直すときは、次の点に留意してください。 (1)漢字で書けるところは漢字で書く。 (2)たとえや自作名言を工夫できるところがあれば工夫する。 (3)似た話や続きの話を書くことによって字数を増やす。 (4)作文用紙の空いているところに絵などをかいてもよい。 |
| ●清書の投稿 |
|
清書した作文は、小学生新聞や一般紙などに投稿してみましょう。 手書きの清書の原本を、新聞社に投稿したり、コンクールに応募したりする場合は、清書のコピーの方を先生に送ってください。 新聞社に投稿する際は、作文用紙の欄外又は別紙に次の事項を記載してください。 (1)本名とふりがな(2)学年(3)自宅の住所(4)自宅の電話番号(5)学校名とふりがな(6)学校所在地(町村名までで可)など。 投稿する際は、ペンネームを本名に訂正しておいてください。作文の中に友達の名前が固有名詞で入っている場合は、イニシアルなどに直しておいてください。投稿する作文の内容は、保護者がチェックしてあげてください。 同じものを複数の新聞社やコンクールに送らないようにしてください。これは二重投稿といって、もし両方に掲載されてしまった場合、掲載先に迷惑をかけることになります。 |
| ●小学生新聞の投稿先 |
|
■104-8433東京都中央区築地3-5-4 朝日小学生新聞「ぼくとわたしの作品」係 ■100-8051(住所はいりません毎日小学生新聞「さくひん」係(600字以内) ※清書した作文を投稿しない場合でも、額などに入れて家の中に飾っておきましょう。 |
|
|
||||
| ■4週目の読解問題(小1以上) |
|
小1以上の生徒には、課題フォルダに、4週目の長文をもとにした読解問題を2問載せています。 時間のある人は取り組んでください。 言葉の森ホームページの「読解マラソン」のページには、全8問の問題とそれに対応した長文がありますが、課題フォルダには問題数をしぼり、問7と問8の2問だけ掲載しています。 これは、この2問をじっくり解いて満点にすることが目標だからです。 問1~6も含めた全問を解きたい方は、読解マラソンの「問題のページ」で他の長文と問題をごらんください。 ただしその場合も、当てずっぽうで解くのではなく、必ず全問正解になることを目標に解くようにしてください。 http://www.mori7.com/marason/ki.php |
|
|
||||
| ■1月29日(水)・30日(木)、31日(金)は休み |
| 1月29日(水)・30日(木)、31日(金)は、第5週でお休みです。先生からの電話はありません。振替授業もお休みです。 |
|
|
||||
| ■これからの勉強はどういうものになるか――教育改革のもっと先の話 |
|
これからの勉強は、自分の好きなことを好きなだけ学ぶ勉強になります。 そして、その勉強の延長が自分の仕事につながり、将来、自分の好きな仕事を好きなだけするような生活をするのが理想です。 そのためには、今の学校で必要とされる勉強は、能率よく学んでおく必要があります。 試験のための枝葉の勉強を早期からやるのではなく、本質的な学習をしておく必要があります。 本質的な学習さえしていれば、試験勉強は短期間で済むからです。 これが、自主学習クラスの目指す学習です。 そして、本質的な学習によって余裕のできた時間は、ひとつは考えを深める学習に、もうひとつは自分の個性を生かした学習に向けるのです。 考えを深める学習の基本は、読書と作文と対話です。 これが、作文読解クラスの学習です。 個性を生かした学力を伸ばす動機は、友達との交流の中で生まれます。 これが、創造発表クラスの学習です。 やがて、その創造を形にするための実験室や工作室も必要になるでしょう。 そして、これらの基礎学力、思考力、創造力の土台の上に、将来の実際の仕事に必要なコミュニケーション力と人間関係力を育てていくのです。 もちろん、このような勉強は、個人の力だけではなかなかできません。 社会の仕組みも、それに合わせて変えていく必要があるからです。 しかし、その仕組みのビジョンは、すでにできています。 これから短期間のうちに、教育も社会も大きく変わっていくと思います。 |
|
|
||||
| ■勉強の面白さを知る実験と観察 |
|
答えのある勉強は、答えが合っていれば○になり褒められるだけです。 答えのない実験や観察や工作の勉強は、○や×のつかない勉強で、子供の個性の数だけ答えがある勉強です。 この自由で創造的な勉強の中で、子供の知的好奇心が育ち、勉強の面白さを知るようになります。 これからの社会で必要になるのは、この勉強に楽しく取り組める姿勢なのです。 言葉の森のオンラインの創造発表クラスは、全員が発表し、全員が質問や感想を述べ合うクラスです。 人前で自分の考えを発表し、相手の話を聞き、互いに質問や感想を言い合う授業は、10人以上のクラスではまずできません。 創造発表クラスは、5、6人の少人数に限定した授業なので、全員に話をする機会があります。 毎回みんなの前で話す経験の中で、これから社会で必要になる発表力とコミュニケーション力が育っていきます。 創造発表クラスの授業は、先生が中心になって教える授業ではなく、生徒それぞれが実験や工作や研究を自由に発表する授業です。 自分が発表することも勉強なら、人の発表を聞くことも勉強で、互いに質問や感想を言い合うことも勉強です。 この勉強がオンラインのウェブ会議で、互いに相手の表情や動作を見ながら行われるので、自然に勉強友達が生まれます。 読書紹介の時間に友達の紹介した本は、自分も読んでみたくなります。 知的な友達関係が自然にできるのが、オンラインクラスの特徴です。 これからの教育に求められるものは、子供たちの個性を伸ばし、創造力と思考力を育てる教育です。 それは、従来の問題を解いて○×をつけるような教育ではなく、子供たちがそれぞれに自分の興味あるテーマを自由に研究し発表する教育です。 答えも試験も点数もない教育を支えるものは、子供たちが本来持つ知的好奇心です。 自然科学の世界と手作りの経験が、子供たちの個性的な学力を育てていくのです。 東大の推薦入試、京大の特色入試は、学生の個性と思考力と探究心を評価することを主眼とした入試です。 これまでの記憶力中心の試験では、本当に優れた学生が採用できないことがわかってきたからです。 高校までの学習は、全教科バランスよく8割できていればよく、それよりも勉強に対する自分らしい好奇心があることが最も重要です。 創造発表クラスの学習が目指すものと同じ学力が、これから求められているのです。 これまでの勉強は、答えのある勉強でした。 だから、詰め込みの勉強が効果を発揮していたのです。 しかし、みんなが同じ知識を覚えてそれを再現するだけの学力は過去のものになりつつあります。 これからの学力は、その子の個性を生かした学力になります。 それが、言葉の森の創造発表クラスが目指す真の学力です。 理科実験や工作は、参考になるテキストはありますが、実際にやってみなければ結果が出ない勉強です。 自分の手で実験をしたり工作をしたりして、その結果から原因や理由を考えるようになります。 答えのない勉強だからこそ、子供の思考力と創造力が育つのです。 実験や工作は、材料をそろえ手順を整えるために、お父さんやお母さんの協力が必要になることがあります。 この協力の中で、親子の対話が生まれ、知的な家庭文化が生まれます。 子供の考える力は、教科書や問題集の中からではなく、実際の経験と親子の対話の中から育っていくのです。 理科実験や工作の教材の中には、誰でもすぐにできる簡単なものから、ある程度の準備を必要とするものまでいろいろなレベルのものがあります。 その中から、低学年でできるものを探していくと、小1から理科実験や工作の勉強を楽しむことができます。 実験の器具も、家庭の日常生活で使うものが多いので、材料や道具を工夫することができます。 小学生に最も大切な勉強は、この自分で工夫し創造する勉強なのです。 ▼学生の「工作」の本をSTEM教育のうちのエンジニアリングの基礎として https://www.mori7.com/as/3926.html ▼白い理科実験とアクティブラーニング https://www.mori7.com/as/3920.html 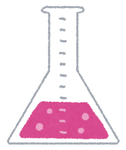
|
|
|
|
|
||||
| ■国語ドリルでは国語力はつかない |
|
国語力をつける方法は、国語のドリルを解くことではありません。 国語のよくできる生徒は、問題集を解くような勉強はしていません。 しかし、国語力は生まれつきの力ではありません。 難しい文章を読み、書き、考えることによって国語力がついてきます。 読む力、書く力、考える力を育てるのが、言葉の森の勉強です。 読書の基本は、自分の好きな本をたくさん読むことです。 そして、たくさん読むことに加えて、難しい文章も読むようにすることです。 難しい文章として手に入れやすいのは、国語の読解問題集です。 国語力のある生徒は、問題集の問題文も読書と同じように楽しく読むことができます。 問題集を読むことによって、語彙力や記述力もついてくるのです。 問題集読書は、言葉の森の自主学習クラスで行っています。 友達との読書紹介で、読書の習慣がつくのです。 国語の読解問題は、感覚や勘で解くのではなく理詰めに考えて解くものです。 言葉の森の読解検定を受けると、読解問題を理詰めに解く方法が身につきます。 読解検定は、小1から高3まで毎月受験できるので、学年に応じた読解力がつくとともに、自分の読解力の進歩のあとが分かります。 読解検定は、言葉の森のホームページから申し込めます。 「小学生のための読解・作文力がしっかり身につく本」(中根克明著 かんき出版)」は、読解力、記述力、作文力をつける方法を総合的に説明した問題集型の参考書です。 この本は、小学生ばかりでなく、中学生にも高校生にも大学入試直前の受験生にも役立ちます。 小学生の場合は、子供に読ませるより前に、お父さんお母さんが読んで子供に教えるようにしてあげてください。 読解、記述、作文のそれぞれの成績を上げる方法がわかります。 言葉の森の暗唱検定は、百人一首、枕草子、平家物語など、日本の古典を中心にした暗唱力の検定試験です。 暗唱の仕方の説明に沿って練習すると、誰でも短期間で暗唱ができるようになります。 暗唱力がつくと、記憶力、語彙力、表現力が身につき、国語の力だけでなく教科全体の学力が向上します。 言葉の森の感想文の勉強をすると、文章を読み取る力と、その文章に合わせて自分の考えを書く力が育ちます。 読解と作文の両方の勉強が、同時にできるのが感想文の勉強です。 言葉の森の感想文指導は、小3から始まり、小5からは本格的な入試問題レベルの感想文の学習になります。 国語力を早めにつけておくと、国語の実力は高いところで安定します。 すると、受験勉強の際にも、国語の勉強はせずに英語、数学など他の教科の学習に集中できます。 また、国語力は、大学入学後にも役立つ学力です。それは勉強の仕方のほとんどが、日本語を使う力によっているからです。 英語ができると言っても、英語の難しい文章を読み取る力は国語力です。 計算が早くできると言っても、算数の文章題を読み取る力は国語力です。。 国語力はあらゆる勉強の基礎で、国語力がつくことによって、他の教科の学力もさらに向上します。 その国語力を総合的につけるのが、言葉の森の作文・感想文指導です。 |
|
|