印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■言葉の森のオンラインスクールが目指すもの
■1日3時間の勉強で990円。オンラインスクールの昼食の時間は参加無料
■「小学校最後の3年間で本当に教えたいこと、させておきたいこと」3月6日発売!
|
|
||
|
言葉の森新聞
2020年3月3週号 通算第1603号 https://www.mori7.com/mori |
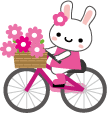
森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
|
■言葉の森のオンラインスクールが目指すもの |
|
言葉の森は、この3月3日からオンラインスクールを始めました。 これは、以前から計画していたことですが、ちょうどその時期に、コロナウイルスによる学校の休校があったためスタートを早め、午前中から全学年の国語、算数数学、英語、読書、図工のクラスを作ることにしました。 (本当や理科や社会もあったのですが、教科が多すぎると参加する人が混乱するので、今回は主要教科だけに絞りました。) これは、コロナウイルスに合わせた便乗商法ではありませんが、学校が休校になり困っている人もいることを考えて、料金は格安に設定し、担当する講師もほとんどボランティアという形でお願いしました。 なぜ料金を取るかというと、もし無料でこういう企画を行うとすると、参加者が多すぎてパンクしてしまうので本当に必要とする人に届かないからです。 しかし、高額の料金であれば、そもそも参加することができない人も出てきます。 そこで、継続的に参加できる最低の料金を設定しました。 これは、担当する先生が協力してくれることによって可能になった料金設定です。 今回のオンラインスクールは、たまたま学校の休校対策に合わせる形でスタートしましたが、今後の運営は次のように考えています。 第一は、コロナウイルスやそれに続く第二第三の感染症が発生した場合でも、すぐに対応できる体制を整えるということです。 これは、現在の段階で、すでにできています。 第二は、コロナウイルスが今後収束したとしても、経済の落ち込みはこれから続くので、子供の教育を担う新しい少人数の低料金の創造性と自主性を生かした教室を展開していくことです。 料金は、4500円から5000円で、少人数の個別指導ができるのですから、他の通学式の教室よりもずっと利用しやすいものになると思います。 これも、現在の段階で、ほとんどできています。 第三に、現在不登校の増加に見られるように、行き詰まりつつある現在の学校教育の受け皿に代わるものをオンライン教育として提供していくことです。 言葉の森の考える、この新しいオンライン教育は、四つの方針を持っています。 第一は、受験から実力へという方向です。 現在の教育の問題点のひとつば、子供たちの勉強が、人生や生活に必要な実力をつけるための勉強ではなく、短期的な受験のための勉強になっていることです。 そのために、本当に必要なことよりも、受験で点数の差がつきやすいところをできるようにするための勉強が中心になっているという現状があります。 言葉の森では、自主学習という方法によって、子供が自分にとって本当に必要な実力を付け、また読書と作文によって学力の基本を育てる教育を中心に行なっていこうと思っています。 第二は、学校や塾から家庭へという方向です。 家庭の教育が必要なのは、親子の対話によって勉強以外の生き方やものの見方が学べるからです。 また、家庭で行う教育によって、親が子供に勉強や勉強以外のことを教える教育力が育ちます。 教育を専門の先生に任せるのは、高校や大学などの専門化した教科に関して言えることであって、小中学校の義務教育の段階では、親が子供に勉強の内容を教えることは、現在の豊富な教材の環境を考えると難しいことではありません。 それを自主学習を中心とした家庭教育で行っていけば、親の時間的負担も少なく、子供との対話を楽しむような教育が可能になります。 言葉の森は、このような家庭を重視した教育を考えています。 第三は、点数から文化へという方向です。 学校教育においては、点数化されないものは教育のシステムに乗りにくいものになっています。 例えば、子供の道徳教育などは、点数で評価されるものではありません。 それは、もともと学校や塾の教育には向かないものです。 家庭において、お父さんやお母さんが自分の信念や価値観に基づいて子供を育てることが文化の教育で、この教育においてはそれがどのように学校の成績に結びつくかということは考える必要はありません。 例えば、現在、言葉の森で行っている創造発表学習は、大きな目で見れば子供たちの創造力や発表力や自然科学を中心とした学問の世界に対する関心などを育てていますが、それが具体的にどの教科の成績を上げるかということは言えません。 しかし、このような学校の成績のどこに反映するかわからないような教育こそが、子供たちの文化力や人間力を育てていくのです。 第四は、競争から創造へという方向です。 現在の勉強は、受験勉強に見られるように、他人との競争に勝つことを目的としたものになっています。 確かに、人生には、他人と競争して勝つことが必要になる場面もあります。 しかし、競争に勝つための勉強は、勝つためのテクニックに力点を置いた勉強になりやすい面があるのです。 それは、例えば、難しい問題は飛ばして、確実に解ける問題を先に解くというようなテクニックです。 勉強の真の目的は、自分が向上し、新しいものを創造し、社会に貢献し、幸福に生きることです。 これらの目的の中心となるものは、創造であって競争ではありません。 その創造する力を育てるための教育を、作文教育と創造発表教育で進めていきたいと思っています。 言葉の森のオンラインスクールは、以上のような目標を持ってスタートしました。 このオンラインスクールを成功させる鍵は、5、6人の少人数のクラスで、子供たちと先生とのコミュニケーションがあるクラスを作ることです。 このような少人数の対話型の教室作りを行うことは、大企業ではできません。 それは、担当する先生の急な休講や振替授業などに対応するには、運営が複雑になりすぎるからです。 しかし、個人企業では、たまたま集まった少人数の生徒を一緒に教えることはできますが、組織的に少人数のクラスを維持し運営することはできません。 言葉の森は、このような微妙な位置にある新しいオンライン教育を進めていこうと考えています。 |
|
|
||||
| ■1日3時間の勉強で990円。オンラインスクールの昼食の時間は参加無料 |
|
コロナウイルスによる休校対策として始めた日中のオンラインスクールは、体験学習がしやすいように1時間550円としましたが、長時間継続したいという方もいるので、3時間990円のコースも設けました。 1日の勉強時間は、朝9時から午後4時までの6時間です。 この時間帯の中で3時間以上受講する方は、1時間330円で計算していきます。 また、昼食をひとりで食べるという子供さんもいると思うので、昼食の時間は誰でも参加できる形にし、それはもちろん無料で、友達と一緒に昼ご飯を食べるということができるようにしました。 昼食には、職場から、お父さんやお母さんもオンラインで参加し、子供と一緒に食事をとることができます。 昼食会場は、100人まで入れます。 昼食は、どの学年の会場に参加してもよく、途中参加、途中退出も自由です。 昼食会場では、カメラはオンにし、マイクは話をするときだけオンにしてください。 参加申し込みは、担当の先生の配置が必要なので、前日の午後7時までにお願いします。 土曜、日曜は休みなので、月曜日の参加申し込みは、日曜日の午後7時までにお願いします。 オンラインスクールの参加者の声を一部紹介します。 ●休みで子供が家で退屈しているので、こういう企画があって本当によかったです。 ●工作の時間で紹介いただいたブーメランを作り工夫して飽きもせずい遊んでいます。 ●授業を受けてみて、本人は、「楽しかったよ。またやるよ」「お友達がまた増えた気がするお。おしゃべりできたのがよかった」と言っていました。 ●学校が休みで時間がたっぷりあるので、自主学習クラスの問題集をどんどん進めていきたいと思います。 ●同じ学年の子供たちと自己紹介をしたり、一緒に勉強したりするのが面白かったようです。 ●兄弟の上の兄がやっているのを見て、下の子もやってみたがったので、パソコンとは別にスマホで参加することにしました。 二人が別の会場でそれぞれ楽しくやっています。 ●私(母)が在宅勤務になったので、家にはいるのですが、一緒に勉強を見てやることができないので、こういう企画があって助かりました。 ▼「オンラインスクール朝から」時間割と参加フォーム https://www.mori7.com/asakara/ |
|
|
||||
| ■「小学校最後の3年間で本当に教えたいこと、させておきたいこと」3月6日発売! |
|
小学4・5・6年生の勉強と生活について、言葉の森の約40年間の経験の中から大事だと思ったことを書きました。 小学4・5・6年生の土台は、小学1・2・3年生で、また、小学4・5・6年生は、次の中学生・高校生の土台になります。 この長い子育ての期間をどう過ごすかということで大事なのは、親の人生観です。 今の目の前にいる子供を見るだけでなく、その子が10年後、20年後に、どういう人生を送るかということを考えて子育てをしていくことが大切です。 そして、今の世の中は、人間が幸福に生きることに対するさまざまな障害や困難があるように見えますが、未来の世の中は、誰もがもっと自由に生きられる社会になっているはずです。 その新しい世の中に生きる上で大事なことは、長所をたっぷり伸ばして生きていくことです。 この基本路線さえ忘れなければ、子育ては苦しい中にも楽しいものになります。 逆に言えば、今の世の中のニーズに合わせるために短所を直すことを中心に子育てをしていくと、それは親にとっても子供にとっても苦しいものになるのです。 ぜひ、この本を参考に、楽しい子育てを目指していってください。 目次を紹介します。 「小学校最後の3年間で本当に教えたいこと、させておきたいこと」【目次】 ■小4・小5・小6の過ごし方が未来を決める 「小学校最後の3年間」は人生でにとても重要なとき 「10歳からは親の言うことを聞かなくなる」は本当? 4年生は小学校生活の大きな転換期 5、6年生は精神的に一気に大人に近づく時期 一方的な「ダメ」「こうしなさい」は効かない。接し方を変える 勉強はほどほどがいい 「本さえ読んでいれば大丈夫」という思いがある 親の人生観を伝えていく絶好の時期 ■高学年も家庭学習で学力を伸ばす 勉強が難しくなる高学年も家庭学習で十分間に合う 国語の勉強法 【オススメ本】「物語」の本→小学4・5・6年生の読書に参考になる本を載せています。 【オススメ本】「説明文」の本→同じく。 算数の勉強法 理科・社会の勉強法 中学受験するなら「ダメ元で公立中高一貫校」 塾に行かずに公立中高一貫校を目指す場合の勉強法 「考える力」を育てるには読書と作文 ■10歳からさせたいこと、教えたいこと 親のいない放課後の時間、どう過ごさせる? ゲームは禁止しなくていい お小遣いで「お金の使い方」を覚えさせる 家族の中での「自分の仕事」を与える キャンプや合宿で「他の子との共同生活」の経験を いよいよ「自然あそび」を豊かに楽しめる年齢 ペットの存在が心のよりどころに 家庭内で守るルールを決めたら、あとは自由にさせる 「いざとなればガツンと叱る」のが父親の役割 子供の心配事は「時がきたら解決する」ことばかり ■友達関係と学校のこと 「良い友だちをつくる」ことより大切なこと この時期の男子の友達関係 この時期の女子の友達関係 いじめにあったら「早めの対処」が重要 いじめる側にしないための「あらかじめの教育」 不登校は無理に学校に行かせようとしない ■中学校以降は自立めざして 中学生はどうなる? 反抗期も叱るべきときはきちんと叱る 「個性を生かして仕事をする」大人に育てるのが目標 親が生き生きと働く姿を見せる 子離れしていくための考え方 「将来、親の面倒をみる」自覚が自立をうながす 親離れさせるために、何に気をつければ良い? |
|
|