印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■オンライン教育は少人数クラスと結びついて初めて効果を発揮する
■午前9時からの「森のオンラインスクール」が6月から始まりました
■港南台の通学教室を、全面的に通学オンラインクラスに
■風邪の中をプログラミング
|
|
||
|
言葉の森新聞
2020年6月2週号 通算第1614号 https://www.mori7.com/mori |
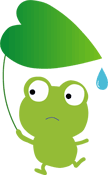
森新聞 |
|
|
|
||
|
|
||||
|
■オンライン教育は少人数クラスと結びついて初めて効果を発揮する |
|
新型コロナウイルスによる学校の休校に対応するために、急速にオンラインビジネスやオンライン学習のニーズが生まれました。 Teamsの利用者は、2020年3月の1週間で1日当たりのアクティブユーザー数が1200万人増え、合計4400万人になったそうです。 一方、Zoomの利用者も、2019年12月に1000万人だった1日当たりのアクティブユーザー数が2020年3月には2億人に達したそうです(TechTarget) しかし、、現在行われているオンライン学習のほとんどは、単なるビデオ授業であったり、これまでリアルな教育で行っていた授業をそのまま動画として流すものなので、子供たち特に低学年の子供たちの学習意欲を引き出すものになっていません。 言葉の森では、設立当初から作文の電話指導による「オンライン」教育を行ってきましたが、2013年から、試験的に5人程度の少人数のオンラインクラスを作り、子供たちどうしの対話のある触れ合えるオンライン教育を模索してきた。 このオンラインシステムには、最初のころはGoogleハングアウトやスカイプを使っていましたが、2017年からZoomを使う形のオンライン教育に切り替えました。 理由は、性能面でZoomの方が優れていたためです。 しかし、パソコン操作が苦手という保護者が多く、生徒数はずっと150名程度で推移してきました。 ところが、2020年3月から、東京都をはじめとする7都府県の学校休校措置が始まり、この休校に対応するため3月8日から国語、算数数学、英語、読書、図工などのオンラインスクールを開始したところ、新規の参加者が増え連日のべ100名の人が朝のオンラインスクールに参加するようになりました。 オンライン学習は、他の学校や塾でも行われるようになりましたが、言葉の森の場合は5人程度の生徒数を維持し、先生による生徒の個別の指導もあるオンライン学習ですから、1コマ45~60分550円という有料の企画でありながら保護者から参加型の学習によって子供が意欲的に取り組んでいるという高い評価を受けました。 言葉の森のオンライン教育と他のオンライン教育との違いは、言葉の森の場合は、低学年の生徒が喜んで参加していたことです。 オンライン教育の先進国と言われているアメリカでも、実質は授業をただオンラインの動画で流すだけなので、低学年の生徒は授業に集中できないという問題が指摘されていました。 オンライン教育は、リアルの教育ができないからやむを得ずその代替手段として行われるものではなく、リアル教育ではできないオンライン独自の特徴を生かして行われて初めて意味あるものになります。 そのオンライン独自の特徴とは、同質の少人数のグループの対話と交流のある教育が可能になるということです。 つまり、オンライン教育に参加する子供たちが、いつの間にかそこで親しい勉強友達になることを目指したオンライン教育だということです。 そのための参加生徒数の上限は、5名程度です。 これまでの経験で、生徒数が4~6名であれば、全員が発言し密度の濃い授業ができることがわかりました。 これが7名になると、かなり忙しく授業をしなければならなくなります。 しかし、3名以下になると、友達どうしの交流が少ない、やや寂しい授業になります。 また、学年がほぼ同じで、同性の集団であれば話がはずみますが、そうでないと生徒どうしの自然な交流が少なくなります。 さらに、授業の形態も、正しい答えを教えるような詰め込み学習的なものではなく、生徒一人ひとりが参加し発言するような性質のものにする必要があります。 言葉の森の考えるオンライン教育の理想は、小学校低学年のころからオンラインスクールで仲よくなった子供たちが、小学校高学年になっても同じように勉強を続け、中学生になっても、高校生になっても、さらに大学生になっても、社会人になっても同レベルの知的交流を続けていけることです。 もちろん、途中でクラス替えがあったり、新しい教科による新しい出会いがあったりするでしょうが、学習を通じて交流するというつながりは続いていきます。 学習を通しての交流を続けるためには、互いに切磋琢磨し、同じレベルの学習を維持しなければなりません。 その切磋琢磨が今でも既に表れているのが、生徒どうしの読書紹介です。 少人数のクラスで、ある生徒が面白そうな本を紹介すると、ほかの生徒もその本に関心を持つようになります。 また、高学年になるにつれて、一人ひとりができるだけ自分なりにレベルの高い本を紹介するようになります。 毎回、それぞれが自分の読んでいる本を紹介するだけで、読書の質も量も上がっていくのです。 しかし、この読書紹介と、その読書に対するそれぞれの質問と感想の時間を確保するためには、生徒数が5名程度である必要があります。 だから、オンライン教育は、少人数クラスと結びついて初めてその効果を十分に発揮できるようになります。 8人以上の生徒を相手にしたオンライン教育は、よほどうまく運営しない限り、単にリアルな授業をオンラインで流すだけになります。 知識を詰め込む形の学習であれば、人数が多くても進めることができますが、生徒一人ひとりの発言と参加を促す形の授業であれば、5名程度の生徒数というのは重要な条件になります。 そして、これから必要とされる学力は、思考力や創造力や共感力という一人ひとりの発言と参加を必要とする学力なのです。 |
|
|
||||
| ■午前9時からの「森のオンラインスクール」が6月から始まりました |
|
6月から学校が再開になりましたが、まだ午前と午後に分かれた登校や、隔日の登校などとなっている学校が多いようです。 言葉の森の「森のオンラインスクール」は、6月から、これまでの「朝のオンラインスクール」と同じように、午前9時から受講できるようにしました。 受講形態は、固定した受講だけではなく、これまでと同じように毎日そのつど受講を選択することができます。 対象学年は、小1から中1までです。 各クラスの定員は5名です。 固定受講の場合は1ヶ月3,300円、選択受講の場合は1コマ880円です。 時間帯によって科目クラスが決まっていますが、将来は希望に応じて科目数を増やしていきます。 明日6月5日(金)の科目クラスは、 9:00~国語 10:00~算数・数学 11:00~英語/暗唱 13:00~読書 16:00~低国算(小1~2の国語と算数) 18:00~低国算/読解・記述 などです。 これらの科目クラスのほかに、作文読解クラスと創造発表クラスがありますが、作文読解クラスと創造発表クラスは、それぞれ生徒の準備が必要になるので、そのつどの選択受講はなく、固定受講での体験学習になります。 いずれも、1クラスの定員は5名程度ですので、受講を希望される方はお早めにお申し込みくださるといいと思います。 学年別のクラス分けではありませんが、先に参加している生徒の学年を参考に受講クラスを選択してください。 ▼森のオンラインスクール クラス一覧表 https://www.mori7.com/teraon/shlist.php ・受講お申し込みの期限は、前日までです。 前日のお申込みを忘れて、当日のお申し込みを希望される場合は、お電話でお申し込みください。 ただし、クラスが満員になっている場合はお申し込みできません。 |
|
|
||||
| ■港南台の通学教室を、全面的に通学オンラインクラスに |
|
6月から、これまでコロナ対策のため、電話通信に切り替えていた港南台の通学教室を再開しました。 しかし、今後のことを考え、単なる通学ではなく、教室に入ったあとにそれぞれがパソコンの前にすわり、オンラインのクラスにZoomで参加するかたちの通学オンラインクラスです。 以前、アメリカで話題になっているブレンディッド教育というものを紹介しましたが、そういう中途半端なものではありません。 ブレンディッド教育とは、日本流に言えば、学校に通って、一人ひとりがパソコンの前でスタディサプリを使って勉強するというようなイメージです。 一見、両方の長所を兼ね備えた教育方法のように見えますが、万能ナイフと似ていて、どれもそれぞれに使いにくいというのが特徴ですから、長い間にはどちらかに収斂していくのです。 通学オンラインクラス、そういう過渡的なブレンディッド教育のようなものではなく、オンラインクラス自体が独立して成り立つようなオンライン教育です。 では、そこに通学という要素が入るのはなぜかというと、そこに、学習面とは違う教育の要素があるからなのです。(つづく) |
|
|
|
|
||||
| ■風邪の中をプログラミング |
|
コロナウイルスなんて免疫力があれば大丈夫、と思っていましたが、木曜日の夕方から急に風邪を引いたようで(笑)、頭痛と背中の痛みが急に増してきました。 ちょうど教室が休みだったので、6月からのオンラインスクールのプログラムを作りながら、時どき寝ながら、やっと3日目の今日、プログラムを作り終わりました。 「プログラミングなど人に任せればいいのに」と言う人がいるかもしれませんが、それは何を作るかが隅から隅まではっきり決まっているときの話です。 新しいことを始めるときは、自分自身が何を作りたいかかがわかっていないところがあります。 そして、作っている間に、よりよいアイデアを思いつくことがあるのです。 ところが、アイデアを思いつくのは簡単ですが、それをこれまでの古い仕組みに組み込むことが非常に大変なのです 例えて言うと、アイデアは3次元で思いつくのですが、それをプログラミングするときは2次元で作業しなければならないという感じです。 これをもしほかの人にプログラミングを頼むとしたら、その頼まれた人は、あまりの仕様変更の多さに過労死に近いところまで行くと思います。 だからこそ、私は、簡単なプログラミングは、誰でも自分でできるようにしておく必要があると思います。 そして、もうひとつは、今後のプログラミングは、もっと3次元的なものになっていく必要があると思います。 既にそういう動きはあるのかもしれませんが。 
|
|
|