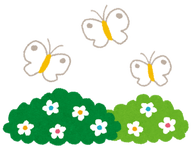あおそふさん、今回の小論文における取り組みを拝見しました。あなたの作文の深い思考と独自の視点が表れており、非常に興味深く読むことができました。
まず、日本の教育システムに対する批判的な視点を持ちつつも、その歴史的背景を理解している点が印象的です。教育がどのように進化してきたのか、その理由を明確に述べることで、読者に対しても教育の
変遷が理解しやすくなっています。また、現代の教育における問題点を
指摘しつつ、それに対する具体的な解決策を提案している点も評価できます。特に、「考える時間を自ら設ける」という方法は、自主的な学びの重要性をうまく表しています。
さらに、ニュートンの例を引用して、実際の歴史的人物がどのようにして学問に対する疑問を深めていったのかを
紹介することで、説得力を持たせています。これは「歴史実例がよく書けています」と言えます。
そして、自作の名言「知識の
詰込みは有限」というフレーズは、あなたの考えを効果的に表現しており、「名言がよく書けています」と評価できます。
このように、あなたの作文は多くの良い点を持っており、特に問題提起とその解決策の提示がうまく行われています。これからも、あなたの
鋭い洞察を活かした作文を期待しています。
###
項目評価
-歴史実例がよく書けています。
-名言がよく書けています。
森リン評価 疑問に思うこと wa 04月1週 あおそふ字数/基準字数:
1622字/600字
思考点:73点
知識点:88点
表現点:90点
経験点:95点
総合点:86点 | ●語彙学年表
| | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | |
|---|
| 思考点 | | | | | | | | | | | | | | | 知識点 | | | | | | | | | | | | | | | 表現点 | | | | | | | | | | | | | | | 経験点 | | | | | | | | | | | | | | | 総合点 | | | | | | | | | | | | | |
|
1200字換算:
思考点:点
知識点:点
表現点:点
経験点:点
総合点:点 | ●換算語彙学年表
| | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | |
|---|
| 思考点 | | | | | | | | | | | | | | | 知識点 | | | | | | | | | | | | | | | 表現点 | | | | | | | | | | | | | | | 経験点 | | | | | | | | | | | | | | | 総合点 | | | | | | | | | | | | | |
|
●語彙の説明| 語彙 | 種類 | 個数 | 種類率 | 点数 | 説明 |
|---|
| 思考語彙 | 27種 | 39個 | 69% | 73点 | 考える言葉です。
理由、方法、原因などの説明の語彙。
多すぎると、説明の多い硬い文章になる可能性があります。
|
| 知識語彙 | 68種 | 114個 | 60% | 88点 | 難しい言葉です。
社会的な例や調べた例の語彙。
多すぎると、難しい言葉の多い重い文章になる可能性があります。
|
| 表現語彙 | 127種 | 209個 | 61% | 90点 | 豊かな言葉です。
話題の幅が広い語彙。
多すぎると、散漫な文章になる可能性があります。
|
| 経験語彙 | 47種 | 76個 | 62% | 95点 | 詳しい言葉です。
身近な例や経験した例の語彙。
多すぎると、身近な話の多い狭い文章になる可能性があります。
|
| 種類率は、60%以上が目標。70%以上の場合は多様な語彙が使われています。 |
1622字
 | | 73点
 | | 88点
 | | 90点
 | | 95点
 |
| 字数 | | 思考語彙 | | 知識語彙 | | 表現語彙 | | 経験語彙 |
■思考語彙 27個
n確か,n第,。しかし,あろう,いるから,からこそ,しよう,せざる,そのため,て考える,とおもい,として考える,と思う,ならば,におもい,に思う,に考える,のかも,のため,はなぜ,みよう,ものに対して,作ろう,努めるべき,置くと,話そう,難しいかも,
■知識語彙 68種
万有引力,不思議,世界,主体,人間,会計,価格,保温,偉業,先述,勉強,勝手,受動態,名言,否定,商品,大事,大切,大手,学年,学校,学者,小学校,小川,工作,工夫,幼少,得意,微積分,必要,情報,憶測,成績,担当,授業,教育,数学,方法,日時計,時間,有名,有限,模型,水筒,水車,沢山,法則,洋服,物理,疑問,発明,知識,社会,端末,簡単,経歴,習得,能動態,自作,自分,表示,購入,過程,重力,関係,限界,風力,風車,
■表現語彙 127種
n確か,いじめ,うえ,こと,ご存知,さまざま,せつ,そう,そのため,その後,ところ,のため,ひと,みたい,めい,もの,クロ,サー,セル,トップ,ニュートン,バーコード,ファースト,フード,メーカ,モス,ユニ,レジ,一つ,万有引力,不思議,世界,主体,二,人,人間,他,会計,価格,保温,偉業,先述,力,勉強,勝手,受動態,台,名言,否定,品,商品,大まか,大事,大切,大手,学び,学年,学校,学者,家,小学校,小川,工作,工夫,幼少,店,彼,待,得意,微積分,必要,情報,憶測,成績,我々,担当,授業,教育,数学,方法,日時計,時間,更,有名,有限,期,様々,模型,気持ち,水,水筒,水車,沢山,法,法則,洋服,物理,疑問,発明,的,知識,社会,私,端末,答え,簡単,経歴,習得,能動態,脳,自ら,自作,自分,表示,詰込み,買い物,購入,通り,過程,違い,重力,関係,限界,頃,頭,風力,風車,
■文化語彙 47種
うまれる,える,かいす,かざす,くれる,さぐる,しまう,しる,しれる,つくる,つくれる,て考える,できる,とおもい,として考える,と思う,におもい,に思う,に考える,やる,れる,わかる,作る,使う,働く,入れる,出す,出来る,努める,受ける,回る,得る,成し遂げる,打ち込む,抑える,持つ,流れる,生み出す,知る,置く,見つける,見出す,解く,設ける,詰め込む,話す,隠す,
疑問に思うこと
高1 あおそふ(aosohu)
2025年4月1日
今日の義務教育は単なる知識の詰込みであると学校生活を通して感じた。日本は明治維新から欧米諸国との大きな知識のギャップを埋めるために知識の吸収に特化した教育を行ってきた。という文章を以前読んで知識の詰込みをする日本の教育方針にたいして一部、理解することができた。理解はできたものの、日本は先進国といわれるようになって他国との知識のギャップはほとんどなくなっただろうに、それでも知識を詰め込む学校教育を続ける意味が私にはみいだせなかった。これからは、先陣をきって今までにないものをつくり、あるいは発見しなければならなくなる。それができるようになるには疑問をもつことの大切さを見直すべきだと思う。
第一の方法は、考える時間を自ら設けることだ。
同じことを何度もいって申し訳ないが今日の学校教育は知識の詰込みに重きを置いている。それを急に、すべての学校で探求型の授業に変えることは難しい。じゃ、どうするか棚からぼたもちが落ちてくることを期待せずに、自分で疑問におもうことを見つけて考えることが大事だと思う。学校の授業だけで疑問を見出すことは難しいかもしれないが、社会のあらゆるところに隠されている様々な工夫から簡単に疑問を見出すことができる。大手洋服メーカのユニクロに買い物に行った人ならわかると思うが、セルレジの会計において、バーコードをかざしていないのに商品をレジの台に置くと勝手に購入品が端末に表示される。どうやって購入品を知ることが出来たのかと不思議だと思わないか。他にもサーモスの水筒はなぜ保温力が高いのか、ファーストフード店はなぜあんなにも価格を抑えることができるのか。うまれた疑問にたいして自分なりに考えて答えを出すことが大切だとおもう。そのためには、主体的な学びとして考える時間を自ら設ける必要がある。
第二の方法は、工作を沢山することだ。
イサク・ニュートンというかの有名な物理学者はご存知であろうと思うが、知らないひとのために大まかに彼の経歴を話そう。彼は、微積分法の発明や万有引力の法則を解いた人だ。万有引力の法則というのは重力を数学的にせつめいしたものである。そんな偉業を成し遂げた、ニュートンの幼少期についてさぐってみようではないか。小学校の頃はどうやら、成績が悪かったそうだが水車模型という小川に流れる水を使って回る小さな水車を作ったり、他にも風力で働く風車、日時計をつくるなど、沢山のものをつくる発明家だったそうだ。その後、学校でのいじめを受け勉強でみかいしてやりたいという気持ちから勉強に打ち込み、学年トップの成績になったそうだ。あくまでも私の憶測だが彼が学年トップの成績になったのには、さまざまなものを工作していたことが関係しているとおもう。工作をしるにあったて、作ろうとしているものに対してある程度の情報がないとつくれない。彼は工作をするうえで沢山の知識を習得できたのであるとおもう。先述で知識の詰込みをする教育を否定していたが、疑問に思ったことから知識を得るのと、学校の授業での知識の詰込みとでは違いがあると思う。工作をする過程でえる知識というのは、受動態ではなく能動態であると思う。受動態の知識は頭に入れることが出来ても能動態の知識みたいに更なる疑問を生み出してくれないとおもう。そのため、工作をして自ら知識の習得に努めるべきだと思う。
確かに、沢山の知識を詰め込んでいるからこそ、新しい発明ができたり、新しいものがつくれたりするのかもしれない。しかし、知識の詰込みは有限という自作の名言の通り、人間の脳に詰め込むことのできる情報には限界がある。また、知識を詰め込むのが人間より得意なAIがこの世界にはできてしまった。知識の詰込みを担当してくれるものがいるならば、我々人間は人間しかできないことをしようではないか。私は、疑問を持つということは人間にしかできないことの一つだと思う。