
■AI時代に、学び方はどう変わるのか
AI時代の教育は、大きく変わろうとしています。
これまでは、先生に教えてもらわなければ新しい内容が分からないため、学校で一斉に授業を受ける形が主流でした。
しかし、この一斉指導の学び方には、いくつかの無駄な部分がありました。
よく理解できている子にとっては、すでに分かっている内容を聞き続けることが退屈になります。
一方で、分からないことがあっても個別に質問できず、理解できないまま授業が進んでしまうこともありました。
■一斉指導を補うための工夫と、その限界
こうした問題を補うために、学校や塾では全員に一律の宿題を出したり、一斉のテストを行ったりしてきました。
しかし、AIが利用できる時代には、必要な学習をAIが個別に支援してくれます。
AIには、分からないことは何度でも質問でき、理解を深めるための問題を作ってもらうこともできます。
これまで家庭で保護者が担ってきた「学校教育の不足を補う役割」は、これからはAIによる家庭学習が中心になっていくのです。
■勉強の本当の目的とは何か
勉強の目的は、良い大学に入ることではなく、良い人生を送ることです。
これまでは、良い大学から良い会社に入り、終身雇用と年功序列のもとで安定した生活を送るというモデルがありました。
しかし現在、その前提は大きく崩れています。
技術の進歩やグローバル化により、仕事の内容そのものが変わり、専門分野を変える必要が生じることもあります。
さらにAIの進展によって、専門知識が必要とされてきたホワイトカラーの仕事も、今後は縮小していくと考えられます。
■これからの教育で大切にしたいこと
このような時代だからこそ、教育の目的は「良い大学」ではなく、「良い人生」に置く必要があります。
人生の形は人それぞれですが、大切なのは、自分の興味関心を持てる分野で社会に貢献することです。
そのために重要なのは、次の三つです。
1. トータルな学力を身につけること
2. 幅広い読書をすること
3. 自分の好きなことに熱中すること
■トータルな学力と幅広い読書
トータルな学力とは、中学・高校時代に国語・数学・英語・理科・社会をバランスよく身につけておくことです。
また、幅広い読書とは、物語文だけでなく、理科や社会、人生に関する説明文や意見文を、教科の勉強と同じくらいの熱意で読むことを指します。
■「好きなことに熱中する」経験の価値
自分の好きなことに熱中する経験は、どの分野であっても大切です。
その興味が一生続くとは限りませんが、熱中して取り組んだ経験そのものが、その後の人生で何かに打ち込む際の土台になります。
■これからの学習の基本は家庭学習
これからの勉強は、学校の授業だけで足りない部分を塾で補うという形ではなく、AIを活用した家庭学習が中心になります。
一斉指導は一見安心感がありますが、実際には無駄な時間も少なくありません。
教えてもらう時間をできるだけ減らし、その分を読書や自分の好きなことに使うことが、これからの学び方として重要になります。
■子どもに必要な「学びを共有する場」
ただし、小中学生のうちは、まだ学習に対する自覚が十分ではありません。
そのため、友達と一緒に学べる環境や、読書紹介や発表会を通して交流する場が必要です。
言葉の森のオンライン少人数クラスは、そうした「学びを共有する場」として位置づけています。
■言葉の森・全科学力クラスの特徴
言葉の森の全科学力クラスでは、小学1年生から中学3年生までを対象に、
国語・数学・英語・プログラミング・創造発表を学びます。
国語読解については、高校生まで対応しています。
担当する先生によって、国語中心、プログラミング中心、全科目対応など、カバーできる範囲は異なります。
■先生の役割は「教える」から「支える」へ
AIを基本とした学習のため、先生の役割は知識を教えることではありません。
授業を活性化し、子ども一人ひとりのトータルな学力や可能性を見ながら、適切なアドバイスを行うことが主な役割になります。
■週1回の授業と毎日の家庭学習
全科学力クラスは、週1回の授業で希望する全教科をカバーします。
その学習を支えるのが、毎日の家庭学習です。
小中学生の中には、家庭学習の習慣がまだ身についていない子もいます。
そのため、24時間利用できるオンライン自習室を活用し、毎日の学習と週1回の授業によるチェックを連動させています。
■体験学習のご案内
現在、全科学力クラスの体験学習を募集しています。
対応科目は、国語・数学・英語・創造発表・プログラミングです。
ただし、当面は担当する先生によってカバーする分野が異なります。
能率のよい学習と幅広い学びを身につけるために、
ぜひ全科学力クラスを積極的にご活用ください。
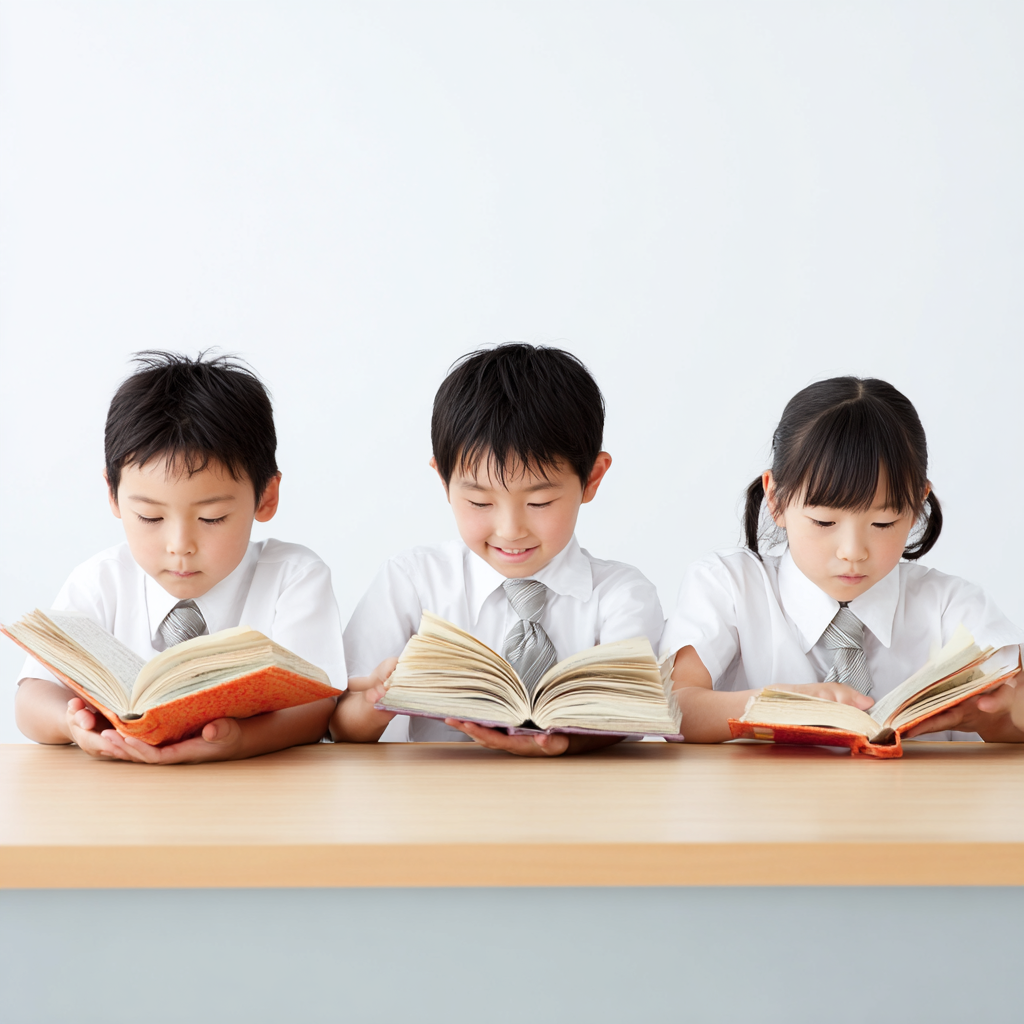 https://youtu.be/PSoVGdi0D1o
https://youtu.be/PSoVGdi0D1o
●作文力の土台としての読書力
作文力の土台となるのは、読書力です。特に小学3、4年生のころに読書の楽しさを覚えると、言葉が実感を伴って心に入るようになります。この時期に物語を多く読む経験は、物語文の読解力だけでなく、説明文や意見文を理解する力の基礎にもなります。
読書は、読む力を育てるだけでなく、考える力そのものを強くします。読書力のある子は、難しい数学の図形問題の解説でも、ただ答えを追うのではなく、考えながら文章を読み、理解しようとします。文章を正確に読み取る力は、すべての教科の土台になっています。
●読書を習慣にするために
言葉の森の少人数クラスでは、毎週の授業の前に、全員が自分の読んでいる本を紹介する「読書紹介」の時間があります。この時間があることで、毎日本を読むことが自然な習慣になり、また、ほかの人が紹介する本に刺激を受けて、読む本の範囲も広がっていきます。
家庭では、まず「10ページでいいから毎日読む」という習慣をつけることが大切です。本は易しいもので構いませんが、漫画や図鑑、雑誌のように絵に頼るものではなく、文章が中心の本を選びます。読書の呼び水として、保護者の方が読み聞かせをしてあげることも効果的です。
●読書と学力の関係
脳科学者・川島隆太さんの調査では、読書習慣の有無が、勉強時間以上に成績と強く相関していることが示されています。睡眠時間よりも読書時間のほうが学力を左右するという指摘もあります。
私自身の長年の実感としても、よく本を読む子は、高校生になってから成績が自然に伸びていきます。勉強は成績を上げるためのものですが、読書は頭そのものを良くする働きを持っています。これは、小中学生の指導を続けてきて強く感じるところです。
また、新井紀子さんの著書『シン読解力』では、読解力の高さと学力の間に強い相関があることが、実データで示されています。短い文章でも、厳密に読む力を測るテストによって、読解力の重要性が明らかになりました。
●読解力を育てる読書とは
読解力を育てる最も効果的な方法の一つは、内容の密度が高く、抽象度のある文章をじっくり読み、自分の考えを書き表すことです。言葉の森の読解検定でも、記憶の仕組みや社会現象など、日常では触れにくいテーマの文章を扱っています。
子供たちが学校や図書館で借りてくる本を見ると、軽い内容のものが多すぎると感じることがあります。本を読んでいるという事実だけで安心せず、その中身を見ることが大切です。読む力のある子は、字の多い本をしっかり読んでいます。小学校高学年からは、物語文だけでなく、説明文や意見文の本を読む力をつけていきましょう。
●読書がつくる長い差
中学生になると、定期テストなどに追われ、読書が後回しになる子が増えます。しかし、小学生時代に読書の面白さに目覚めた子は、テスト期間中でも、息抜きに好きな本を少し読むという生活を続けています。この差は、高校生、大学生、社会人になるほど大きくなっていきます。
目標は、社会人になって仕事に追われるようになっても、毎日50ページ以上本を読むことです。そのためには、子供に言うだけでなく、親自身が日々新しい読書に取り組む姿を見せることが大切です。
●本は子供の一生の財産になる
図書館で借りて読んでみて、よい本だと思ったら、同じ本を購入して手元に置いておくことをおすすめします。そうすれば、時間をおいて繰り返し読むことができます。よい本は、デジタルとは別に、アナログとして家に置いておく価値があります。本は、子供にとって一生の宝物になるものだからです。