作文は、日本語力の集大成です。
話し言葉の日本語は、文法も平易で、音の種類も少ないので、外国人にとっても学びやすい言語だと言われています。
しかし、書き言葉になると、この日本語が急に難しくなります。
だから、大人でも、作文を書くと、誤字や読みにくいところがあちこちにあるのが普通です。
しかし同時に、日本語は一音がひらがなの一文字に対応しているので、小学1年生でも、ひらがなが書ければ、自分の話したいことを作文という形で書くことができます。
日本で、小学1年生から作文の勉強が可能なのは、日本語のこういう特殊性があるからです。
この作文を、小学1、2年生で書く場合の重点は題材です。
ちなみに、小学3、4年生の重点は表現で、小学5、6年生の重点は主題で、中学生以上の重点は構成です。
構成、題材、表現、主題という区分は、言葉の森の独自の考え方で、ほかにこういうことを言っているところはないと思いますが。
さて、なぜ小学1、2年生の重点が題材かというと、この時期は、思ったことがそのまま言葉になって出てくる時期だからです。
この時期の子供たちには、いい題材を選ぼうという意識はありません。
だから、日曜日にどこかに遊びに行ったら、そのことを書くし、特に何もなかったら、今日のことを書きます。
その「今日のこと」も、いつも同じ内容の、サッカーをしたことや、友達と遊んだことでいいのです。
毎回同じことを書いても、苦になりません。
思ったことが、書き言葉になって出てくること自体が面白いというだけなのです。
小学1年生は、まだ指の力がないので、長く書くことはできないのが普通ですが、小学2年生になり、ある程度指の力がついてくると、子供たちは作文を長く書くことに燃えるようになります。
この時期は、長く書くことがうれしい時期なのです。
子供によっては、どこかに出かけたことを書く場合でも、朝起きてから夜寝るまでのことを千字以上書くこともあります。
また、本をよく読んでいる子は、本に書かれているのと同じような空想の話を延々と書くこともあります。
しかし、これは、子供たちの作文の実力ではありません。
頭の中に思い浮かんだことをただ文字にして書いているだけなのです。
この時期に大事なのは、ただあったことを書かせることではありません。
そういう作文であれば、作文は普通に書けるからいいということになってしまいます。
小学1、2年生の時期は、親子で経験を共有し、その経験をもとに対話をし、親の持っている語彙やものの見方や考え方を対話の中で自然に伝え、その対話の手段として親子で表現項目を工夫することなのです。
言葉の森が、小学1、2年生の生徒向けに実行課題集を作っているのは、そういう経験の共有という目標があるからです。
親が子供と一緒に行う経験には、季節の行事や、自然観察や、理科実験や、料理や、工作や、親子で楽しむ遊びなど、さまざまなものがあります。
それらの経験が作文の題材になります。
その経験のためには、わざわざお金をかけてどこかに出かける必要はありません。
日曜日などのちょっとした時間に、「今日は、これをやってみようか」という感じで、親子で気軽に取り組むようなものこそが、子供にとって深い経験になります。
そういう親子で共有できる経験を提供してくれる本が、最近数多くか出ています。
私が、いいと思う本には、次のようなものがあります。
「理科好きな子に育つ ふしぎのお話365」
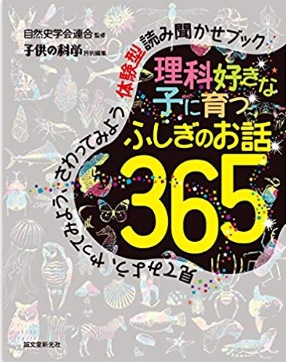
「しぜんとかがくのはっけん! 366」
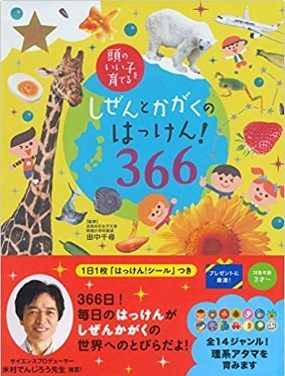
高学年の生徒であれば、理科実験の本がいいでしょう。
しかし、これらの本を勉強的に使うのではありません。
親子で共有する経験の材料として使うのです。
小学1、2年生の作文の勉強は、表現を工夫することが目的ではなく、経験と対話から生まれる、言葉の使い方や、ものの見方や、感じ方や、考え方を自然に育てることに意義があり、それがその後の作文力の土台となっていくのです。