春の読書作文キャンプで、初日の午後に行く場所です。
ザリガニのいるはずのところには、まだ見えませんでしたが、網ですくうとたぶん小さいのが見つかると思います。
行くところは、どこも教室の近くなので、これからの読書作文キャンプは、すぐに企画できそうです。
今度は、読解検定付きの読書作文キャンプにしたいと思っています。
予定としては、4月20日(土)午後2時から21日(日)午後2時で、のちほど参加フォームを作成します。
オンラインで勉強し合っている子供どうしが誘い合って、リアルな場所で再会するといいうのが感動的で面白いと思います。
▽里山の光景です。

▽細い道が15分ほど続きます。

▽道に沿って小さな川が流れています。
昔、犬を連れて遊びに行くと、すぐに道をそれて川の中をジャブジャブと歩き出しました。
ゴールデン・レトリバーなので、水が大好きだったのです。

▽田んぼがあります。

▽カワセミがいました。ほかにも、キジとか、フクロウとか、タヌキとかいるようです。

▽終点の池。カモが泳いでいました。

▽スミレが咲いていました。

▽田んぼの近くの水路に小さなオタマジャクシ。
ザリガニ君たちは、まだ寝ているようでした。

▽水路の近くにセリが生えていました。

この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
通信教育の弱点は、自然や人間とのリアルな交流ができないことです。
だから、那須に合宿所を作りました。
しかし、新幹線で東京から2時間とは行っても、やはり那須は遠いです。
そこで、新しい教室で土日合宿ができるようにしました。
横浜市とは行っても、横浜市の外れに近いのでかなり自然はあります。
ここで、将来、読解マラソンと読解検定合宿をする予定です。
読書作文キャンプは、本当は保護者の懇談会もあるといいと思うので、日中、子供たちは読書作文キャンプ、保護者は鎌倉散策で、夕方にみんなで食事をしながら作文発表会という形もいいかと考えています。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14)
東北大学大学院理学研究科 H.O.さん
(担当講師より)
以前、生徒だったH.o.君が東北大学大学院理学研究科(地球物理学専攻および地球・噴火予知研究観測センター所属)に合格しました。
お母様のお話によると、信州大学では地球学(地質)と少し遠回りしましたが、大学院で念願の地震の研究をしますとのことです。
おめでとうございます!
地震の研究、がんばってください。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)
京都大学文学部 M.O.さん
(担当講師より)
以前、生徒だったM.O.君が京都大学文学部に合格しました。
京都の街で文化遺産に囲まれながら歴史(世界史)を学びたいという念願が叶ったそうです。
おめでとうございます!
自分が本当に好きなことを勉強できるって幸せですね。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)
作文は、日本語力の集大成です。
話し言葉の日本語は、文法も平易で、音の種類も少ないので、外国人にとっても学びやすい言語だと言われています。
しかし、書き言葉になると、この日本語が急に難しくなります。
だから、大人でも、作文を書くと、誤字や読みにくいところがあちこちにあるのが普通です。
しかし同時に、日本語は一音がひらがなの一文字に対応しているので、小学1年生でも、ひらがなが書ければ、自分の話したいことを作文という形で書くことができます。
日本で、小学1年生から作文の勉強が可能なのは、日本語のこういう特殊性があるからです。
この作文を、小学1、2年生で書く場合の重点は題材です。
ちなみに、小学3、4年生の重点は表現で、小学5、6年生の重点は主題で、中学生以上の重点は構成です。
構成、題材、表現、主題という区分は、言葉の森の独自の考え方で、ほかにこういうことを言っているところはないと思いますが。
さて、なぜ小学1、2年生の重点が題材かというと、この時期は、思ったことがそのまま言葉になって出てくる時期だからです。
この時期の子供たちには、いい題材を選ぼうという意識はありません。
だから、日曜日にどこかに遊びに行ったら、そのことを書くし、特に何もなかったら、今日のことを書きます。
その「今日のこと」も、いつも同じ内容の、サッカーをしたことや、友達と遊んだことでいいのです。
毎回同じことを書いても、苦になりません。
思ったことが、書き言葉になって出てくること自体が面白いというだけなのです。
小学1年生は、まだ指の力がないので、長く書くことはできないのが普通ですが、小学2年生になり、ある程度指の力がついてくると、子供たちは作文を長く書くことに燃えるようになります。
この時期は、長く書くことがうれしい時期なのです。
子供によっては、どこかに出かけたことを書く場合でも、朝起きてから夜寝るまでのことを千字以上書くこともあります。
また、本をよく読んでいる子は、本に書かれているのと同じような空想の話を延々と書くこともあります。
しかし、これは、子供たちの作文の実力ではありません。
頭の中に思い浮かんだことをただ文字にして書いているだけなのです。
この時期に大事なのは、ただあったことを書かせることではありません。
そういう作文であれば、作文は普通に書けるからいいということになってしまいます。
小学1、2年生の時期は、親子で経験を共有し、その経験をもとに対話をし、親の持っている語彙やものの見方や考え方を対話の中で自然に伝え、その対話の手段として親子で表現項目を工夫することなのです。
言葉の森が、小学1、2年生の生徒向けに実行課題集を作っているのは、そういう経験の共有という目標があるからです。
親が子供と一緒に行う経験には、季節の行事や、自然観察や、理科実験や、料理や、工作や、親子で楽しむ遊びなど、さまざまなものがあります。
それらの経験が作文の題材になります。
その経験のためには、わざわざお金をかけてどこかに出かける必要はありません。
日曜日などのちょっとした時間に、「今日は、これをやってみようか」という感じで、親子で気軽に取り組むようなものこそが、子供にとって深い経験になります。
そういう親子で共有できる経験を提供してくれる本が、最近数多くか出ています。
私が、いいと思う本には、次のようなものがあります。
「理科好きな子に育つ ふしぎのお話365」
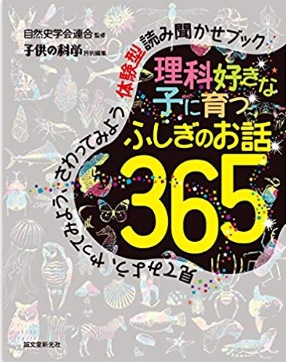
「しぜんとかがくのはっけん! 366」
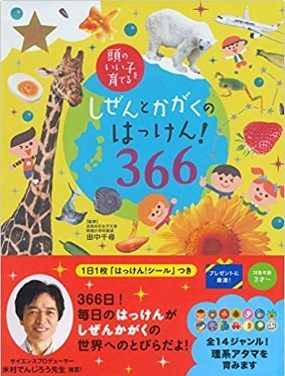
高学年の生徒であれば、理科実験の本がいいでしょう。
しかし、これらの本を勉強的に使うのではありません。
親子で共有する経験の材料として使うのです。
小学1、2年生の作文の勉強は、表現を工夫することが目的ではなく、経験と対話から生まれる、言葉の使い方や、ものの見方や、感じ方や、考え方を自然に育てることに意義があり、それがその後の作文力の土台となっていくのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
小学校低学年の学力で最も大事なものは、日本語力です。
日本語の力は、単に国語という一つの教科の力ではなく、ものごとを考える土台となる力だからです。
しかし、日本語は話し言葉が容易なので、子供が話しているのを聞いているだけでは、日本語力は何も問題ないと思ってしまうのが普通です。
書くときになって初めて、その子の日本語力が出てくるのです。
うちの子は、何の習い事もせず、塾にも予備校にも行かず、やったのは小1からの言葉の森だけ。(あと、1人の子はバスケットボール。)
自分ではななく、ほかの先生に教えてもらいました。
家でやっていた勉強は、音読と読書と対話と算数をほんの少しだけ。
だから、算数は途中まで苦手か普通でしたが、受験勉強を始めるとすぐにできるようになりました。
こういう生活でいちばんよかったと思うのは、小中学校時代はかなり暇だったことです(笑)。
今日の記事ですすめた2冊の本は、読むためだけの読書ではなく、実験したり観察してみたりするための読書です。
子供は、面白そうなことが書いてあると、すぐに自分でもやってみたくなります。
そのための材料を提供してくれる本が、小学校低学年のいい本です。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。小学校低学年(79) 親子作文コース(9)
小学5年生の課題は、急に難しくなります。
それは、受験作文に対応できるモードになるからです。
小4までの作文は、子供が似た話を親に取材したときでも、その場で簡単に答えることができました。
例えば、「がんばったこと」とか、「痛かったこと」とか、「私の大好物」とかいう課題だったからです。
しかし、小5からは、親も準備をしておかないと、とっさには答えられないような話を聞かれるようになります。
例えば、「創造とは」とか、「科学の発達について」とか、「里山の自然」とかいう課題になるからです。
このときに、お母さん(時にはお父さん)が話してくれる似た話は、子供にとって初めて聞くことが多いものです。
それは、家庭の日常会話で、親が突然、「あのね、創造とはね……」というような話をすることはまずないからです。
子供はもちろん、友達どうしでもそういう会話はしません。
読んでいる本も、そういう話題の本であることはまずありません。
ところが、受験の作文課題や、国語の問題では、そういう抽象的な分野が出てきます。
そのときに、問題集だけで勉強してきた子と、親と話してきた子では、問題の消化の仕方がかなり違ってくるのです。
先日の作文発表交流会で、やはり小学校高学年の子が発表した作文の内容は、どれもそういうお母さんに聞いた具体的な話が入っていました。
こういう会話が毎週あるというのは、親にとっては負担があるかもしれませんが、同時に子供と話す楽しい時間でもあると思います。
そして、この親との対話の中で、子供の語彙力や思考力が育っていくのです。
▽先日の作文発表交流会の作文から(面白い作文がたくさんありましたが、その中からひとつだけ)
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
子供たちはみんな、学校で同じような勉強をしています。
子供たちを取り巻く社会の環境も、大体どこも同じです。
生まれつきの差はあるかもしれませんが、それはほんのわずかです。
しかし、小学校低学年のころから既に思考力の差がかなり出てきます。
それは、家庭での日常生活における読書(読み聞かせ)と対話の差なのです。
だから、勉強をさせるために塾に通わせるより、毎日の生活の中で、読書と対話を少し意識的に行うだけで子供は大きく変わります。(ただし、最初のうちはその変化は目立ちませんが。)
子供の学力の差とは、日本語力の差です。
その日本語力は、塾で国語の勉強をすることによってつくのではありません。
もちろん通信教育の国語の問題集でつくのでもありません。
家庭の日常生活の中の読書と対話によってつくのです。
だから、読書と対話のきっかけとなる言葉の森の作文の勉強が大事になるのです。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表交流会(20)
勉強のほとんどは、記憶の勉強です。
漢字の書き取り、計算の問題、図形の問題、英語の問題など、すべて記憶したパターンを思い出してそれを答えにあてはめる勉強です。
しかし、そうでない勉強もあります。
それが創造の勉強です。
そのひとつの典型が作文の勉強です。
記憶を思い出して書くのではなく、その場で自分で先の流れを創造しながら書いていくからです。
その創造に必要なのは、意欲です。
新しい、より価値のある、より個性的なものを生み出したいという意欲が創造の源泉です。
この意欲というものは、数値で評価できません。
ここが、漢字の書き取りや計算の問題が、点数で簡単に表示できるのと根本的に違うところです。
点数の出る勉強は、点数が出たらそれで終わりです。
100点を取ったら、その先に110点や120点はありません。
点数の出ない、意欲に依拠した創造の勉強は、100点を取ったあとに、110点や120点を目指すようなことができます。
それが創造性です。
その創造性は、平面的な数値では評価できませんが、人間にはその創造性を感知する力があります。
だから、上手だがあまり創造的でないものと、下手だがその底に創造性があるものとの違いがわかるのです。
作文の書き手にとって大事なのは、目標の字数まで書けたとか、項目が指示どおりできたとかいうこと以上に、他人が自分の作文をどう読んだかという評価です。
点数の出る勉強であれば、点数が目標になりますが、作文は点数以上に他人の評価が目標になります。
そして、その他人の評価とは、自分の創造性がどう他人に評価されたかということなのです。
記憶の勉強は、答えがあるので、その答えを基準にした独学ができます。
創造の勉強は、答えがないので、創造という目標に近い他人の評価が必要になります。
創造の勉強を進める意欲の源泉は、他人との関わりの中にあるのです。
言葉の森が、寺子屋オンラインという少人数の作文クラスを始めたのは、この他人との関わりの中で、作文がより意欲的に書けるとわかってきたからです。
小学校低学年の子供にとっては、親や先生の評価が作文を書く意欲につながります。
しかし、学年が上がるにつれて、親や先生以上に友達の評価が作文を書く意欲に大きく影響します。
記憶の勉強は、独学でもできるし、その反対に学力別の集団教育でもできます。
創造の勉強は、顔の見える少人数の中でなければできません。
しかも、その少人数は、信頼のできる親しい少人数である必要があります。
だから、寺子屋オンラインのクラスは、小学校低学年のうちから始めて、友達との信頼できる人間関係を作るのが最初の目標です。
小学1、2年生のころの子供は、他人にはあまり関心がありません。
自分と親と先生という狭い範囲が、周囲の世界のほとんどと占めています。
しかし、その時期に他の子供と接する時間を持ち、そこで信頼できる人間関係を築いておくのです。
言葉の森が、寺子屋オンラインの作文の勉強で、小学校低学年のクラスに独自に力を入れているのは、以上のような子供の成長の発達段階の見通しがあるからなのです。
▼参考資料「カテゴリー小学校低学年]
https://www.mori7.com/beb_category.php?id=6
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
これからの社会を考えると、点数で表される学力を必要とする仕事は、次第にAIに取って代わられていきます。
今の子供たちが社会人になるころには、その人でなければできない個性や創造性がより大きく評価されるようになります。
しかし、その個性や創造性を発揮できる分野は、スポーツや芸術や音楽のようなところよりも、科学と技術の世界で大きく広がっています。
スポーツや芸術や音楽は多様なように見えても、例えばオリンピックの種目の数に見られるように数えることができる程度に限られています。
科学と技術の世界で個性や創造性を発揮できる場は無限に広がっています。
だから、子供時代に第一に取り組むべきものは、創造性を育てる勉強なのです。
そして、第二以降は、幸福に生きること、向上心を持つこと、世の中に貢献する意識を持つこと、です。
寺子屋オンラインの子供たちの作文は、ただ通り一遍に書ければいいというのではなく、面白いものを書きたいという意識が表れています。
ただし、それは小学校中学年以上のことで、小学1、2年生のころは、他人がどう受け止めるかということに対する関心はまだありません。
しかし、この他人に対する関心がない時期に接した友達が、信頼できる友達になります。
信頼できる人間関係の中で、創造性を育てる勉強をすることが、寺子屋オンライン教育の目標です。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。小学校低学年(79) 寺子屋オンライン(101)
■合否の基準
検定試験の問題は8問で、全問正解が100点です。
検定試験の合格基準は100点を取ることです。
100点に達しなかった人は不合格となります。
しかし、これは間違えたところを自分で理解することが勉強ですので、
100点を取れなかった場合は、むしろこれから読解力が一歩進むと考えておいてください。
■検定の進度
読解検定は、小学1年生から高校3年生まで毎月受けることができます。
進度は次のようになります。
| 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
| 4月 | 白12級 | ピンク12級 | 黄12級 | 茶12級 | オレンジ12級 | 赤12級 | 緑12級 | 水12級 | 青12級 | 黒12級 | 銀12級 | 金12級 |
| 5月 | 白11級 | ピンク11級 | 黄11級 | 茶11級 | オレンジ11級 | 赤11級 | 緑11級 | 水11級 | 青11級 | 黒11級 | 銀11級 | 金11級 |
| 6月 | 白10級 | ピンク10級 | 黄10級 | 茶10級 | オレンジ10級 | 赤10級 | 緑10級 | 水10級 | 青10級 | 黒10級 | 銀10級 | 金10級 |
| 7月 | 白9級 | ピンク9級 | 黄9級 | 茶9級 | オレンジ9級 | 赤9級 | 緑9級 | 水9級 | 青9級 | 黒9級 | 銀9級 | 金9級 |
| 8月 | 白8級 | ピンク8級 | 黄8級 | 茶8級 | オレンジ8級 | 赤8級 | 緑8級 | 水8級 | 青8級 | 黒8級 | 銀8級 | 金8級 |
| 9月 | 白7級 | ピンク7級 | 黄7級 | 茶7級 | オレンジ7級 | 赤7級 | 緑7級 | 水7級 | 青7級 | 黒7級 | 銀7級 | 金7級 |
| 10月 | 白6級 | ピンク6級 | 黄6級 | 茶6級 | オレンジ6級 | 赤6級 | 緑6級 | 水6級 | 青6級 | 黒6級 | 銀6級 | 金6級 |
| 11月 | 白5級 | ピンク5級 | 黄5級 | 茶5級 | オレンジ5級 | 赤5級 | 緑5級 | 水5級 | 青5級 | 黒5級 | 銀5級 | 金5級 |
| 12月 | 白4級 | ピンク4級 | 黄4級 | 茶4級 | オレンジ4級 | 赤4級 | 緑4級 | 水4級 | 青4級 | 黒4級 | 銀4級 | 金4級 |
| 1月 | 白3級 | ピンク3級 | 黄3級 | 茶3級 | オレンジ3級 | 赤3級 | 緑3級 | 水3級 | 青3級 | 黒3級 | 銀3級 | 金3級 |
| 2月 | 白2級 | ピンク2級 | 黄2級 | 茶2級 | オレンジ2級 | 赤2級 | 緑2級 | 水2級 | 青2級 | 黒2級 | 銀2級 | 金2級 |
| 3月 | 白1級 | ピンク1級 | 黄1級 | 茶1級 | オレンジ1級 | 赤1級 | 緑1級 | 水1級 | 青1級 | 黒1級 | 銀1級 | 金1級 |
今回3月の試験は、自分の学年の1級を受けたことになります。
例えば、小学3年生の生徒だと、黄1級を受けたということです。
この黄1級で100点が取れたら、黄1級は合格です。賞状が送られます。
黄1級が100点ではなかったら、黄1級は合格しなかったということで、賞状は送られません。
いずれの場合も、次の小4の4月の読解検定を受ける場合は、茶12級を受検します。
小4の4月は受検せずに、小4の5月に読解検定を受ける場合は、茶11級を受検します。
このように、毎回該当月の読解検定があり、合格すればその級の合格の賞状が送られ、不合格の場合は賞状は送られません。
■「山のたより」との連動
言葉の森で作文の勉強をしている人は、「山のたより」という作文の評価が毎週ウェブに表示されています。
この検定試験は、もともと毎月第4週に、清書以外に取り組む読解の勉強として始めたものです。
したがって、
検定試験の結果は、「山のたより」にも表示されるので、自分の成績の推移がわかるようになります。
■読解検定の効果
読解問題は、満点を取ることを目標にして解くことによって国語力が向上します。
国語力とは、日本語で物事を理解する力ですから、国語力が向上することで学力全体が向上します。
これまで、この読解問題を毎月満点を目指して取り組んでいた生徒の多くは、難関校に合格しています。
ですから、読解検定位取り組む人は、毎回100点を取ることを目標にしてください。
■検定試験で満点が取れなかった場合
読解力は、読む力と解く力の総合力です。
読解検定に取り組むことによって、解く力はつきますが、読む力がないと解く力だけでは満点は取れなくなります。
読む力をつけるための最もよい方法が、音読と暗唱と読書と問題集読書です。
小学校低中学年の生徒は、主として音読、暗唱、読書に力を入れていってください。
小学校高学年以上の生徒は、主として読書と問題集読書に力を入れていってください。
読む力をつける練習は、毎日行うのが基本です。
毎日欠かさず行って半年ぐらいたつと、読む力が向上していることがわかってきます。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
読解問題は、真剣に解くと読解力がつきます。
真剣に解かないと、読解力はつきません。
だから、読解検定は、百点を取ることが合格の基準です。
答えが合っていたところは、これまでの実力で合っていたところですから、そこは何も問題ではありません。
答えが合っていなかったところは、どうして合っていなかったか考えるところですから、そこが最も重要なところです。
合っていなかったところで、なぜ合っていなかったのかを理解すれば、そこで読解力が一歩向上します。
だから、合っていなかったところが、いちばん価値あるところです。
このようにして、真剣に解こうとすると、読解の問題文も一生懸命読むようになります。
すると、その問題文の内容が頭にしっかりと入ります。
国語の問題は、意外と似たテーマが取り上げられていることが多いので、一度真剣に読んだジャンルの文章は、次には読むのがずっと楽になります。
だから、この読解検定は、読解力を評価するための試験ではなく、読解力をつけるための試験なのです。
昔、読解試験を全員一律にやっていました。
そのころ、「75点だから、よかった」とか、「間違えたのは一問だけだからよかった」などと言っていた子は、実力がつきませんでした。
絶対に100点を取るつもりで取り組んで、1問でも間違えるとくやしがっていた子は確実に実力をつけました。
普通の国語の試験は、先生の主観で左右される場合がありますが、この読解問題は客観的な問題ですから、満点を取ることが目標です。
満点を取ることを目標にしている子は、今回の点数がよくても悪くても、これから国語力をどんどんつけていきます。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)
親は、子供が勉強している姿を見るとうれしいものです。
反対に、子供がゲームに熱中している様子を見ると、何かひとこと言いたくなってきます。
敏感な子供は、そういう親の気持ちを察して、親にとっていい子でいようと思うようになります。
そうして、だらだら長時間勉強する子が生まれるのです。
しかし本来、子供は勉強など好きなわけがありません。
勉強が好きになるのは、もっとずっとあとになって高校生ぐらいになってからです。
小中学校時代の勉強は、面白くも何ともないものです。
だから学校に行って強制的にやらせるのです。
親は、そういう子供の気持ちを察しなくてはなりません。
そして、「勉強はもういいから、もっと好きなことをして遊びなさい」と言ってあげるのです。
そういうふうに育てられた子は、勉強が必要だと感じたときに自分から進んで取り組むようになります。
勉強を全くさせないと言うのではありません。
家庭でルールを決めて、子供が無理なく自分の力でできる範囲のことは毎日やるようにします。
それは、例えば、読書や音読や暗唱や算数の問題集です。
毎日のルーティンワークとして決められた勉強であれば、子供はそれをなるべく早く終わらせて自分の好きなことをしたいと思うようになります。
そして、自然に能率よく片付ける方法を身につけます。
そのときに、お母さんが、「そんなに早く終わるなら、これも……」と勉強の追加をさせてはいけないのです。
勉強の追加をされた子は、能率よくやると自分が損をするということを学びます。
そして、それからは能率悪く長時間かけてだらだらと勉強をするようになるのです。
それがマイナス面として出てくるのは、その子が中学生や高校生になってからです。
小学校時代に身につけた能率悪く勉強する方法が、中学生や高校生になってからも続くのです。
小学校時代はよくできたのに、高校生になってから伸び悩むというのは、そういう子です。
学力の本当の差がつくのは、高校生になってからです。
小学生時代の学力の差は、それがどんなに大きく見えようと、見た目だけのものです。
だから、小学校時代は、勉強面でがんばる必要はないのです。
そのかわり、その子が自分の好きなことをして個性を伸ばしていくことを第一に考える時期なのです。
子供に勉強させすぎるお母さんやお父さんは、自分が子供時代にもっと勉強していれば、もっといい人生になっていたはずだと漠然と思っています。
しかし、そんなことはありません。
子供時代に勉強しようが何をしようが、自分の実力で今の人生があるのです。
だとしたら、自分ができなかったことを子供にさせるのではなく、自分が子供時代にやってよかったと思うことを子供にさせることです。
子供時代にやってよかったと思うことの大部分は、楽しかった遊びです。
だから、子供はたくさん遊ばせてあげるといいのです。
ところで、この記事だけでは、言葉の森の勉強との関連がわからないと思うので追加します。
言葉の森で作文の勉強をして、その作文の勉強を軸に、読書と音読と暗唱を行い、親子で対話をする時間を作ります。
そして、自主学習コースで、毎日の問題集読書と算数問題集の家庭学習の習慣をつけます。
更に、発表学習クラスで、自分の個性的で創造的な学習を発表し、友達と学問的な交流をします。
最後に、夏休みに読書作文キャンプで、オンラインで知り合った友達と自然の中でリアルな交流をするのです。
この記事に関するコメント
コメントフォームへ。
子供は、将来いい学校に入るために生きているのではありません。
今を楽しく過ごすために生きているのです。
その原則をふまえた上で、勉強をしたり躾をしたりしてしていくのです。
小学4、5年生になれば、子供は、親が追加の勉強をさせようとしても、自分が嫌だと思えば嫌だと言います。
しかし、小学1、2年生のころは、親の言うことはほぼ絶対です。
だから、本当は嫌なことでも楽しそうにやります。
だから、その小学1、2年生ころこそ、親は子供の本当の気持ちを察してあげる必要があるのです。
娘(小6)は作文を週に500字書くのも苦痛のようです。
今日は清書を書き上げたあと、「もう作文やめる。次は書かない」と言いました。私も「じゃあ、ゲームも無しな!」とゲームを取り上げるともうそれでいいよという感じでした。
勉強が子供から前向きな姿勢を奪います。家庭や育て方の問題かもしれませんがどうしたら良いのかわかりません。
それは、ひとことで言えば、課題が難しいからです。
課題の学年を下げれば書けるようになりますが、それでは本人がかえってやる気をなくします。
だから、課題の難しさに追いつくように、毎日の音読に力を入れて、長文を理解できるようにしておくことが必要になります。
作文が書けないというのではなく、作文を書く前の読む力がまだ不足しているのです。
しかし、これは今後、中学生になっても高校生になっても必要な学力ですから、まず毎日の音読から気長に続けて、さらに力をつけるとすれば、問題集読書も並行してやっていくといいと思います。
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 勉強の仕方(119)