印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■9月20日(月)・23日(木)は休み宿題
■パソコン書き練習方法(ねこバス/なおこ先生)
■花たちと向き合って(はるな/みき先生)
■太陽光で焼き芋づくりにチャレンジ(ふじのみや/ふじ先生)
■茶道(スフレ/なえ先生)
■新潮文庫の100冊(スピカ/かも先生)
■言葉(はちみつ/おと先生)
|
|
||
|
言葉の森新聞
2004年9月3週号 通算第855号
文責 中根克明(森川林) |

|
|
|
|
||
|
|
||||
| ■9月20日(月)・23日(木)は休み宿題 |
| 9月20日(敬老の日)と23日(秋分の日)は、休み宿題です。先生からの電話はありませんが、その週の課題を自宅で書いて提出してください。先生からの説明を聞いてから書きたいという場合は、別の日に教室までお電話をして説明をお聞きください。(平日午前8時半〜午後8時。電話0120-22-3987) |
|
|
||||
| ■パソコン書き練習方法(ねこバス/なおこ先生) |
|
今、大人の人が会社でみんなに読んでもらう書類を手で書くことはまずありません。みんなパソコンの文書作成ソフトで書くのが常識になっています。そのほうが、きれいに速く書くことができるからです。 欧米では以前から書類でタイプを打つことは普通に行われていましたが、それはアルファベットの字数が26文字と少ないため、簡単な機械ですべての文字をタイプできたからです。(2.6文字/指)それに対して、日本語が普通の人でもタイプできるようになったのは、ここ20年くらいのことです。コンピューターの発達によって、漢字変換が誰にでも簡単にできるようになったからです。 大人の世界では必要があって「パソコン書き」がこれほど普及していますが、学校では未だにみんなが「パソコン書き」を勉強するという環境にはなっていません。それは、字を書くためにタイプをするという文化が、まだ日本では定着していないということも関係しています。 だからといって、子供が日本語をパソコンで書いてはいけないという理由は、ほとんどといっていいほどありません。確かに漢字を覚える必要があまりなくなるので、大人が漢字を忘れて手で書けなくなるという欠点はありますが、それはパソコンで文章を書けなくなるという不便さに比べれば取るに足りないものです。 パソコンで書くためには、タッチタイピングを覚えることがあとあと便利です。画面だけをみて、キーボードを見ないでタイプする方法です。パソコンは画面とキーボードの明るさが違うので、目の疲れを軽くするためにも大切な方法です。一週間くらい毎日練習するとなれてきます。50音でキーの位置を覚えるより、ローマ字変換の方が便利です。 タイピング練習ソフトは、子供向けのキャラクターのものがPCショップやインターネットで3000円くらいで売っています。フリーソフト(無料)は、 http://computers.yahoo.co.jp/download/vector/win/edu/comp/typing/ というサイトで探すことができます。先生は、ここから見つけた「かえるさんたいぴんぐ」というソフトが、ベーシックで可愛いので気に入っています。 Http://www.vector.co.jp/soft/win95/edu/se219833.html?y 「Lhasa」(ラサ)をダウンロードしないと解凍(パソコンで読めるように圧縮ソフトを変換すること)できませんが、ラサは一度セットすると便利なソフトなのでお勧めです。フリーソフトをダウンロードするときに、ラサのダウンロードも一緒にできます。「かえるさんたいぴんぐ」の実行プログラムとデータは、同じフォルダにコピーしてから使ってくださいね。 
|
|
|
||||
| ■花たちと向き合って(はるな/みき先生) |
|
今年は、梅雨が早く明けてしまい、7月に入って、連続で真夏日の日が続いてまったくやりきれませんね。ついこの前、東京は、なんと観測史上最高の39.5度。記録的な猛暑となりました。でも、「あれは、観察箱のなかで調べた温度であって、実際はそんなもんじゃないなあ」と、先生は、心の中でつぶやいていました。 アスファルトによる照り返しと、建物から冷房の熱風が排出されて、相乗効果で、ヒートアイランド現象の最たるものとなり、体感温度ではさらにそれを大きく上回っていたことでしう。 おそらく、大都会の日中は、外の温度は45度くらいになっていたのではないのでしょうか。 ふだんは、元気印の先生も、さすがに、熱波のような都心の蒸し暑さで、無気力になって、とうとう夏風邪をひいてダウンしてしまいました。 みみずく学級新聞も、発刊して、今度9回目となりました。クラスの皆さん。この、猛暑の夏休みを元気に過ごしていますか? 先生は、この夏、花作りに精を出しています。 植木鉢の水遣り(みずやり)も、早朝と、就寝前だけでは追いつかず(鉢が小さすぎるのかな?)、陽射が陰ってくるのと同時にもう一回・・・・・・というふうに、「一本も枯らせたくない」一心で、日に3回の水遣りしています。このペースで、ようやく足りているようで、ハイビスカスやあさがお、バイオレットセージのハーブ類など、夏の花々が、可憐(かれん)に咲いてくれています。(^_-)-☆ 昼間、しおれかけているような草花も、水をあげてしばらくするとピーンと、立ち上がってくるようで、いきいきしとよみがえってきます。それをみると、思わず先生は「ガンバったね!! 」「あっ、元気になってよかったねえ。」と話しかけてしまいます。 こちらが、手間ひまと、愛情をかけて育てた分、見事に大輪の花を美しく咲かせ、周りの人々の期待に、きちんとこたえてくれるようです。 「物言わぬ花たちも、ちゃんと、心を持っているのかもしれない」と、先生はまじめに、そのように、考えたことさえありました。こんなとき、きまって私は、「花の絵を描き始める時」という長文の一節を、思い出してしまうのです。 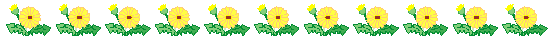 「風で折れてぶらさがっているのもあれば、病気か何かでゆがんで咲いているのもある。日向で勢いよく咲いているのもあるが、根元の方では雨の日に土のはねかえりを受けて、うすぎたなくなったのもある。そういうのを見ていると、人間の社会と同じだなあと思ったりする。頭の良いのもいれば、悪いのもいる。美しい人も、そうでない人も、病気の人も、健康な人も……、いろいろな人がいる。 しかし、私自身、「あいつは、ああいうやつなんだ」とほんのわずかしか知らないうちに決めつけてしまうことが、なんと多いのだろう。花の色が一日にして変化するのだから、まして心を持っている人を見るとき、自分のわずかな秤で決めつけてしまうのなんて全く間違っていると思う。 いま私の前には、みごとな菊の大輪が咲いている。菊は比較的長い期間咲いている花だけれど、それでも人にその花をほめられている時期はほんとうにわずかである。花の下にある葉の一つ一つを、さらにその下にある土の中の根の美しさを、花びらの中に描けるようになりたいと思っている。」 (『風の旅』星野富弘著)より 花々が、個性豊かに美しく咲き誇っている時期は、本当に短くて、その間も、風雨にさらされたり、虫に葉っぱを食べられたりして、いろいろと苦労がたえません。 きれいな花を支えている根や茎、葉、土の養分、水・・・・・・等々。地味だけれども見えないところでふんばっているものたちに、存在感を見出せるような、奥の深い人間になりたいなあ、と、強く感じるのです。 と同時に、先入観で人や、周囲の現象を捉えることのないように、公平で高い視野にたって物事を見極められる人格をみがきましょう、と心に誓うのです。 「明日も、また蒸し暑い一日になるでしょう。」お天気キャスターの声が、テレビから流れてきます。 さあ、水遣り、また、ガンバルゾ(^^)/~~~ 
|
|
|
||||
| ■太陽光で焼き芋づくりにチャレンジ(ふじのみや/ふじ先生) |
 新聞やテレビのニュースに、「暑い」という文字を見ない日はありませんね。今年の夏休み。みなさんはどのように過ごしていますか? 新聞やテレビのニュースに、「暑い」という文字を見ない日はありませんね。今年の夏休み。みなさんはどのように過ごしていますか?夏休みで思い出すのが、学校の自由研究。私は小学生のとき、田んぼの「ウキクサ」を採集してきて増えかたを調べたことがあります。庭やベランダに大きなたらいを置き、ウキクサがどのような条件でもっとも増えるのか調べました。家族にはたいへん迷惑がられ、また、ウキクサは見ていて楽しい植物でもないので、最後のほうは「どうせならもっと派手なホテイアオイにすればよかった」と、後悔したのを覚えています。 自分が親になって、今度は子どもの自由研究のようすを見ることになりました。 子どものころは、「めんどうだな」という気持ちのほうが強かったのですが、大人になって距離をおいた立場で見てみると、これが結構楽しそう。 昨年は、手作り納豆を作りました。蒸した大豆に納豆菌を植え付けて、あたたかい場所に約一日置けばできあがり。市販のものより匂いがやわらかく、まずまずの味わいでした。 今年は太陽光で焼き芋づくりにチャレンジです。これは装置の準備に手間取ったわりに、結果はどうなるかわかりません。  材料集めや研究の組み立て方など、横で見ていると「ああ、もう! それはこうでしょ!」と言いたくなり、実際にちょっと手を出したりするのですが、手を出せば出すほどつまらなそうな顔をするので、助けを求めてきた場合以外は本人に任せておくことに。 助けを求められたときは、ちょっと意地悪をして「○○で調べたらありそうよ」と回りくどいアドバイスをします。すると思っていたより時間がかかって、さすがに子どももうんざりした様子を見せ始めるのですが、それこそ、自由研究の醍醐味。存分に味わっていただきましょう! もちろん、本気で意地悪  をしたいわけではないので、ネットや図書館を使って、おもしろそうな情報は集めておき、アドバイスしたりはします。子どもが興味を持ってくれれば、これは親の醍醐味でしょうか(笑) をしたいわけではないので、ネットや図書館を使って、おもしろそうな情報は集めておき、アドバイスしたりはします。子どもが興味を持ってくれれば、これは親の醍醐味でしょうか(笑)たまたまネットで検索をしていてヒットしたのが、『特許庁電子図書館』のページ。ここでは、権利化された特許や実用新案を簡単に閲覧することが出来ます。難解なものばかりではありません。「こんな思いつきで……」というちょっとしたアイデアが、技術用語を駆使した立派な「特許権」となっているのも数々。子どもが苦しんでいるのを横に、しばし見入ってしまいました。ここはまた、自由研究のネタさがしの宝庫でもあります。 自由研究の題材選びに困ったら、一度のぞいてみてはいかがでしょうか?  ←これが苦心の作!【太陽光調理器】! ←これが苦心の作!【太陽光調理器】!
|
|
|
||||
| ■茶道(スフレ/なえ先生) |
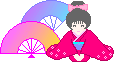 みなさんは、「茶道(さどう)」ということばをきいたことがありますか? 自分で経験したことがある人もいれば、お父さん、お母さんなど、家族の方に経験がある人もいるかもしれませんね。 私は、今までまったく茶道というものに接点がなく、お抹茶を飲んだ経験さえあまりなかったのですが、つい先日、「お茶会」に参加することができたので、そのことについて書こうと思います。 私の娘の通う幼稚園では、年長さんになると、お茶のおけいこがはじまります。私がそのおけいこの手伝いをしている縁で、そのお茶会に娘とともに連れて行っていただけることになったのです。 お茶会は、関西の中学校・高校の茶道部の部員たちと顧問の先生が主催していて、私たちはお茶をおよばれするお客さまとして参加しました。娘はお茶を運ぶ係もやりました。 お茶を飲む方にも運ぶ方にも、いろいろな決まりがあり、お茶会の2週間前にみっちり教えてもらいました。(もちろん、すべてではありませんが) ・ お菓子をもらう前には、となりの人におじぎをしながら一言、 「おさき。」 ・ お茶をいただく前に、お茶碗を2回まわして(これは有名かな)3回くらいで飲む。 返すときは反対に2回まわす。 ・ お茶を運ぶとき、部屋に入るのは右足で、出るのは左足から出る。 などなど、いろいろありました。本番で失敗しないよう、家でも何回も練習でした。 お茶会は、大阪市天王寺区の生國魂(いくたま)神社の中にある、「玉秀庵(ぎょくしゅうあん)」というお茶室で開かれました。 中ではたくさんの高校生・中学生たちがお茶やお菓子を運んでいて、こんなにたくさんの若者が茶道にたずさわっていることが、意外に感じました。 結局、本番では多くのお客さんたちの中で緊張する間もなくお茶をよばれ、娘たち幼稚園の代表4人がお運びをするときも中の様子を見せてもらえず、あっという間にはじめてのお茶会は終ってしまいました。 しかし、娘のおかげでとてもいい経験ができた、と私は大満足でした。 みなさんももし、お茶会に参加できたり、お抹茶をいただけるような機会があったら、ぜひ体験してみてほしいです。お抹茶はちょっと苦いけれど、お茶の前に食べるお菓子がとってもおいしいんです! |
|
|
||||
| ■新潮文庫の100冊(スピカ/かも先生) |
|
小学校高学年以上の人なら、目にしたり耳にしたりしたことはあるでしょう。 夏になると、その年の「100冊」が選ばれ、書店には、平積みに並べられます。「選ばれ」と言っても、そうそう毎年変わるわけではありません。手元に2004年版の冊子がありますが、「名作」というくくりの中にあるものは、半分くらい、最初から変わっていないのでは、と思います。 まだみなさんには早いかなあ、という作品が多いですが、そうでもないものも、けっこうあるようです。 この冊子が、パラパラめくってながめていると、なかなかおもしろかったです。103冊(なぜか3冊オーバー)が、あらすじとともに紹介されていて、すでに読んだ本、まだ読んでいないけれど気になっている本などについて、なつかしく、または興味深く見入ってしまいました。1冊の紹介が200字程度で大したことは書いていないし、もちろん、出版社が出している宣伝文句なわけで、「これはちょっと大げさだなあ」と苦笑してしまうようなものもあるのですが、全体として、「読みたい気分」にさせる魅力があるのです。さすが老舗(しにせ)。かなりうまい200字の「要約」です。(笑) 古今東西の「名作」「現代文学」「エッセイ・ノンフィクション」が網羅(もうら)されていて、バランスもなかなかです。私が、後にも先にも一回だけ、198X年に100冊全てを読んだときは、今よりずっといわゆる「名作」に偏っていました。今は、例えば、江國香織さん、宮部みゆきさんが4冊で、夏目漱石の3冊より多く入っています。中2のSさんが、毎週の作文の読書欄に書いてくれていたので初めて知った梨木香歩さんの作品も2冊。 しかし、やはり、新潮文庫は、名作にとどめを刺す。(笑) 冊子の中に、「ロングセラーのTOP20」というのがありました。さすがに、全て読んだことのある作品でしたが、そのうち15冊が、この新潮文庫で読んだものでした。ちなみに、TOP5は 1 こころ(夏目漱石) 2 人間失格(太宰治) 3 老人と海(ヘミングウェイ) 4 友情(武者小路実篤) 5 異邦人(カミュ) でした。見事に全て新潮文庫で読んだ本です。そういうお父さんやお母さん、多いと思います。 高校生になるころには読める本ばかりです。このあたりは、先生として、安心してお勧めできる本です。(笑) ぜひ一度読んでみてね。  Yonda? Yonda?
|
|
|
||||
| ■言葉(はちみつ/おと先生) |
 夏を楽しんでいますか。海や山に出かけたり、めったに会えないおじいちゃんやおばあちゃんやいとこたちに会えたりと、ふだんはなかなかできないことができます。思い出をたくさん作ったことでしょう。 夏を楽しんでいますか。海や山に出かけたり、めったに会えないおじいちゃんやおばあちゃんやいとこたちに会えたりと、ふだんはなかなかできないことができます。思い出をたくさん作ったことでしょう。 「サウンドオブミュージック」という有名な映画を見たことがありますか。雷雨でねむれないと集まった子ども達にマリアが「好きなものをあげてみよう。」と歌うシーンがあります。「バラの上の露」「子猫のひげ」……。みなさんのお気に入りは何ですか。つらいこと、こわいこと、悲しいことがあったときに元気にしてくれる言葉を思い浮かべてみましょう。夏休みにそのリストが増えたのではないでしょうか。 言葉の力は大きいものです。きれいな言葉、肯定的(こうていてき)な言葉をたくさん覚えて使いましょう。名作と言われる本にはそんな言葉がたくさんつまっています。自然やきれいな音楽や絵に触れて、お気に入りを増やしましょう。大好きな人たちとの会話や思い出も、好きな言葉を増やすきっかけになることでしょう。 古代の人たちは、言葉をとても大切にしていました。言葉にもたましいが宿ると考えていたのです。言葉にすると、きっと夢や願いもかなうと思われていました。いい言葉、すきな言葉を思いついたら、口に出して言ってみましょう。やりたいこと、なりたいものがあったら声に出して言ってみるといいかもしれませんね。 |
|
|
||||