印刷設定:A4縦用紙 :ブラウザの文字のサイズ:最小 ブラウザのページ設定:ヘッダーなし フッターなし 左余白25 右余白8 上下余白8
■父母の広場より
■ネット作文コンクール(熱作)、作品募集中(再掲)
■あおぞら先生の絵葉書
■森リンに三角グラフと折れ線グラフ
■自分の言葉で思いを伝えよう(スズラン/おだ先生)
■究極のダジャレ講座
|
|
||
|
言葉の森新聞
2005年5月2週号 通算第886号
文責 中根克明(森川林) |

|
|
|
|
||
|
|
||||
| ■父母の広場より |
| ◆中学受験との両立(小4父母) |
| 4年1学期になり、進学塾の宿題をこなすのが大変になりました。特に子供は成績が良くないので宿題に時間がかかります。国語の成績(特に読解)が悪いので言葉の森を続けたほうがよいか、時間がないので退会して塾に専念すべきか悩んでいます。「高学年のほうが効果が出る」とHPにもあったので、ここで退会するともったいない気もします。中学受験の方はどう両立されているのでしょうか? ちなみに本人は作文を書くことには前向きな姿勢ですし、毎日長文も読んでいます。 |
| ◆中学受験との両立(教室より) |
|
塾の勉強に専念しても、国語の成績は上がりません。 言葉の森の長文音読と感想文の練習をしつつ、家庭で問題集読書をしていかれるのがいちばんよいと思います。 しかし、時間的な負担が大きいようでしたら、家庭での学習に絞って勉強していかれるとよいと思います。家庭学習のコツは、問題集を繰り返し読むことが中心になります。 言葉の森の勉強は長い展望の勉強ですから、受験と時間的に両立しにくくなったときはいったん退会して、中学生になってからまた再開するということで考えていってください。 |
|
|
||||
| ■ネット作文コンクール(熱作)、作品募集中(再掲) |
|
日本語作文小論文検定協会では、この4月15日〜5月31日、ホームページでネット作文コンクールを開催します。 テーマは、父の日母の日にちなんで、「父」又は「母」、又は自由なテーマとします。 ホームページ上で作文を送信していただき、森リンの点数と学年を勘案して、上位者10名に森リン大賞として図書券5000円をプレゼントします。 1人何編でも応募できます。一度応募したものを再度修正して応募することもできます。 朝小・毎小などの外部に発表したものでなければ、普段の作文を送っても結構です。 言葉の森のみなさんは、ぜひ応募してください。 Http://www.mori7.info/conc/ |
|
|
||||
|
■あおぞら先生の絵葉書 |
|
言葉の森のあおぞら(あお)先生は、ハワイに引っ越ししたため、現在一時お休みをしています。 そのあおぞら先生が絵葉書を作りました。俳句と絵を組み合わせた味わいのある絵葉書です。 大きい画像は、ホームページをごらんください。 http://www.mori7.com/ehon/ehagaki.php |
 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30
|
|
|
||||
|
■森リンに三角グラフと折れ線グラフ |
|
PHPというスクリプト言語からmingというソフトを使ってflashという動画のファイルを生成できることがわかったので、連休中にサーバーに入れました。 flashは日本語に対応していないので、だいぶ苦労しましたが、jamingというソフトで何とか日本語も表示できるようになりました。 折れ線グラフは、それぞれの生徒の過去60週間分の得点の推移が表示されるようになっています。 折れ線グラフの傾向が分かるように近似曲線を入れてみました。エクセルを見てみると、近似曲線には最小二乗法を使っているようです。Y=aX+bという近似曲線(直線も曲線の一つの形態なので曲線と呼びます)と実際の(X座標、Y座標)の差の二乗を合算します。例えば座標(X1,Y1)におけるY座標の差の2乗は(Y1−(aX1+b))2ですから、全部加えると、(Y1−(aX1+b))2+(Y2−(aX2+b))2+……+(Yn−(aXn+b))2となります。これをaについて解くとaの二次関数ができます。 二次関数の最小値は、確か微分すると出るという高校時代の勉強を思い出しました。計算が苦手なので、慎重に計算して、やっと式を出しました。同じことをしている人がいないかとインターネットを探してみると、やはりいました。(笑) http://szksrv.isc.chubu.ac.jp/lms/lms1.html 苦労して計算した式と同じものが出ていました。(T_T)しかも、慎重に計算したはずなのに、私の計算ではプラスとマイナスがひっくりかえっていました。(計算、苦手) 高校時代は、数学の勉強は単なる勉強としてやっていましたが、こうやって実際に仕事に使ってみると、すばらしい学問なのだということが改めてわかりました。 さて、式ができてみると、あとはそこに60週間分の数値を入れて計算するだけです。この計算は、コンピュータがやってくれるので一瞬です。この計算式をPHPのスクリプトに書き込んで、フォームから送信すると、自動的にMySQLというデータベースから60週間分のデータを取り出して計算して結果を出してくれます。 その計算結果を今度は、フラッシュに引き渡します。すると、フラッシュで折れ線グラフと近似曲線がきれいに出ました。バチバチバチ。数学とオープンソースに感謝。PHPもMySQLもmingもapacheもlinuxもすべてオープンソースなので、ここまで全部無料です。(笑) 森リンの得点は、その日の文章や調子によって点数が上がったり下がったりします。そのため、努力の結果が、まだ今ひとつわかりにくいところがありましたが、この60週間分の近似曲線を見ると、進歩のあとがかなりはっきりとわかります。どの生徒も平均して、1年間で5点ぐらい上昇しています。Y=aX+bの意味は、Yが得点、Xが年、bが初期値の得点、aが1年間で上昇した得点です。例えば、Y=5X+70の場合は、最初に70点ぐらいの実力があり、現在1年間に5点ぐらい上昇する割合で進歩しているということになります。得点上昇率の高さと読書や長文との相関関係は、かなり高いはずです。 連休の前半3日間は、このグラフ作成でした。 そのあと、フラッシュをうまく使えば、長文速読のページができると気づきました。そこで、連休の後半3日間は、フラッシュの研究。しかし、ほとんどは、日本語がうまく表示できないとか、音が出ないとかいうトラブルの原因探しでした。オープンソースなので、自分でインターネットのあちこちに探しに行かないとわからないのです。 連休の後半が終わるころ、やっと見通しがつきました。もうしばらくすると、課題の岩で長文速読のページができると思います。 |
|
|
||||
| ■自分の言葉で思いを伝えよう(スズラン/おだ先生) |
|
新学期が始まりました。新しい学年になり、クラスのお友達も新しくなった人もいるかもしれませんね。このスズラン学級も4月から新しいメンバーが加わり、新学期をスタートしました。今学期も元気で楽しくやっていきましょう。 新しい先生やお友達になった新学期は、いろいろ心配をすることや、緊張(きんちょう)することや、楽しいことなどあるかと思いますが、そんなとき、皆さんは自分の気持ちをどんなふうに表していますか。 「決まっているでしょ。言葉で伝えますよ。」と言っている声が聞こえてきそうですが、どんなときでも自分の思っていることをはっきりと伝えることができていますか。 じつは、この「言葉で伝える」ということは、なかなか難しいことのように感じます。でも、言葉で伝えなくては、相手に分かってもらえないですよね。 赤ちゃんは、誰におしえられなくても、お腹がすいたとき、眠いとき、おむつが濡(ぬ)れたとき、痛いとき、どんな場合も泣くということで自分の気持ちを表し、嬉しいときは笑顔で答えてくれますね。お母さんは「この泣き方は……」と気持ちをちゃんと受け止めてくれますし、赤ちゃんとの会話が成り立っています。少し大きくなって、言葉を覚え始めると、周りの人の言葉を聞きながらどんどん言葉を話すようになりますね。あとは知らず知らず言葉が多く蓄積(ちくせき)されていきます。きっと皆さんは沢山の言葉を知っているから不自由しないと思っていることでしょう。私もそう思っているのですが、思っていることを伝えることはやっぱり難しいですね。 そこで、問題になるのが、自分の思いが正確に伝わるように話したり、書いたりしているのかということになりそうです。 近頃、自分の気持ちを伝えられずに力で相手を傷つけてしまったという事件が案外多いように思います。言葉で解決できないときに思わず暴力(ぼうりょく)を使ってしまうことになるのでしょう。言葉で自分の気持ちをはっきりと伝えることができ、相手にも分かってもらえればお互いに理解しあえるわけです。 では、言葉で自分の気持ちを伝えるためにどうすればいいのでしょうか。 それは、ただ言葉を沢山知っているということではなく、ものごとに対して自分がどう思ったのか、これを伝えるためにはどういう言葉を使えばいいのかという練習をしてみるといいと思います。 お母さんとの会話のなかに、たとえば、食事のとき、子どもが「みず」と言っただけで、お母さんはさっとコップの水を差し出す光景が目に浮かびませんか。私は子どもがそう言ったときには「お水がどうしたの?」と尋ねていました。何回かそんなやりとりのうちに「お母さん、お水がほしい。」とつながってきました。ほんの小さな例ですが、小さいときから、何も言わなくても分かってくれるということはないのだということを子どもは学んだと思います。親は子どもがしてほしそうなことはすぐ分かるのですが、そこをぐっとおさえて子どもの言葉を待ちましょう。そして、子どもが要領(ようりょう)よく話せなくても、「ゆっくり聞いてあげる」という姿勢がほしいと思います。 また、会話と同じぐらい大切なのは、本を沢山読む(読んであげる)ことでしょう。本から(主に物語)こんなときにはどんな言葉をつかえばいいのかを多く学ぶでしょう。 私たちは、普段の家の中での会話、本に接する、言葉の森で毎週作文を書くために出来事を思い出す、こういう日常の積み重ねから自分の気持ちを上手に伝えることができるようになり、話す、書くという基本力を高めていけるのではないかと思います。 新学期、新しいお友達や先生へ自分の気持ちを伝えられるように、頭の中で伝えたい文を言葉で組み立ててみましょう。その言葉にはたくさんの気持ちがこもっているはずです。きっと、思いが伝わるでしょう。 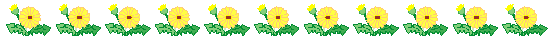
|
|
|
||||
| ■究極のダジャレ講座 |
 あなたにとって、究極の九曲は何ですか? などと言っている場合ではなく、今学期からダジャレ表現に●印のついているあなたのために、ダジャレ講座をお届しましょう。もちろん、ただですよ。銀行口座から講座料を引き落としたりしませんからご安心を。 あなたにとって、究極の九曲は何ですか? などと言っている場合ではなく、今学期からダジャレ表現に●印のついているあなたのために、ダジャレ講座をお届しましょう。もちろん、ただですよ。銀行口座から講座料を引き落としたりしませんからご安心を。 ダジャレを得意にするためには、寝ても覚めてもダジャレを考え続けることです。というのはちょっとオーバーですが、せめて暇なときはおもしろいダジャレを考えてみましょう。私は、電車に乗っているとき、なかなか眠れない夜、何もかもがいやになったとき(笑)などにダジャレを考えます。暇つぶしにもなるし、いやなことも忘れられるからです。一度、考え始めるとつい夢中になり、ダジャレの世界にどっぷりとつかってしまいます。 ダジャレを得意にするためには、寝ても覚めてもダジャレを考え続けることです。というのはちょっとオーバーですが、せめて暇なときはおもしろいダジャレを考えてみましょう。私は、電車に乗っているとき、なかなか眠れない夜、何もかもがいやになったとき(笑)などにダジャレを考えます。暇つぶしにもなるし、いやなことも忘れられるからです。一度、考え始めるとつい夢中になり、ダジャレの世界にどっぷりとつかってしまいます。 目にうつるもの、ふと脳裏に浮かんだ言葉など、何かをもとに、ダジャレができないかどうか考えを巡らせます。慣れてくると、ダジャレになりそうな言葉とそうでない言葉の見分けがつくようになります。(ここまでいけば達人です。) 目にうつるもの、ふと脳裏に浮かんだ言葉など、何かをもとに、ダジャレができないかどうか考えを巡らせます。慣れてくると、ダジャレになりそうな言葉とそうでない言葉の見分けがつくようになります。(ここまでいけば達人です。) まずは、簡単なところで、二文字のダジャレ。駅のホームにハトがいます。さあ、「ハト、ハト、ハト……。」と繰り返してみましょう。ほら、「ハトにはっと驚く」が浮かびましたね。「ハトのハートがはっとする」などというトリプルダジャレが浮かんだ人もいるかもしれません。二文字のダジャレは初心者向きですが、中にはその単純さゆえに輝きを放つダジャレもあります。「たこ買った子」「棚があったな」などは、シンプルで嫌味のないダジャレと言えるでしょう。 まずは、簡単なところで、二文字のダジャレ。駅のホームにハトがいます。さあ、「ハト、ハト、ハト……。」と繰り返してみましょう。ほら、「ハトにはっと驚く」が浮かびましたね。「ハトのハートがはっとする」などというトリプルダジャレが浮かんだ人もいるかもしれません。二文字のダジャレは初心者向きですが、中にはその単純さゆえに輝きを放つダジャレもあります。「たこ買った子」「棚があったな」などは、シンプルで嫌味のないダジャレと言えるでしょう。 では次。三文字のダジャレです。川を見ると魚が泳いでいます。橋の上で、誰かがパン粉をまいています。そこで、あなたはふと思うわけです。「魚のえさかな?」と。ほら、知らないうちにもうダジャレが……。こういうダジャレは、作文の中にも自然に入ります。「私は、魚のえさかなと思いました。」と書けば、誰もダジャレだとは気づきません。(べつにかくす必要はないのですが……。) では次。三文字のダジャレです。川を見ると魚が泳いでいます。橋の上で、誰かがパン粉をまいています。そこで、あなたはふと思うわけです。「魚のえさかな?」と。ほら、知らないうちにもうダジャレが……。こういうダジャレは、作文の中にも自然に入ります。「私は、魚のえさかなと思いました。」と書けば、誰もダジャレだとは気づきません。(べつにかくす必要はないのですが……。) だんだんむずかしくなりますが、今度は四文字のダジャレです。時はクリスマス。街にはクリスマスソングが流れています。♪真っ赤なお鼻のトナカイさんは……。♪ ここで「トナカイ」を見逃してはいけません。さらに、「と」と「なかい」を切り離して考えることができるかどうかがいいダジャレを思いつくかどうかの分かれ目となります。「と」は「AとB」というように何かと何かをつなぐ役割をしますね。トナカイと言えばサンタクロース。サンタクロースは「トナカイと仲いい」となります。 だんだんむずかしくなりますが、今度は四文字のダジャレです。時はクリスマス。街にはクリスマスソングが流れています。♪真っ赤なお鼻のトナカイさんは……。♪ ここで「トナカイ」を見逃してはいけません。さらに、「と」と「なかい」を切り離して考えることができるかどうかがいいダジャレを思いつくかどうかの分かれ目となります。「と」は「AとB」というように何かと何かをつなぐ役割をしますね。トナカイと言えばサンタクロース。サンタクロースは「トナカイと仲いい」となります。最初が「と」で始まる言葉に出合ったら、同じパターンでダジャレができないかどうか考えてみましょう。たとえば「とかげ」を「と」と「かげ」に分けます。「とかげとかげ」。無駄のないダジャレができ上がりました。  では、このへんで、「南国ダジャレ」というものをご紹介しましょう。「南国ダジャレ」というのは、実は「難語句ダジャレ」のことなのです。中学生以上の人には是非覚えて作文に使ってほしい言葉をダジャレで覚えてしまおうというものです。たとえば「観劇で感激中の間隙を突く」では、「間隙を突く」という言い方を覚えましょう。「熱燗で圧巻」では、「圧巻」という言葉の意味を覚えましょう。(「熱燗」の方は覚えなくてもいいです。) では、このへんで、「南国ダジャレ」というものをご紹介しましょう。「南国ダジャレ」というのは、実は「難語句ダジャレ」のことなのです。中学生以上の人には是非覚えて作文に使ってほしい言葉をダジャレで覚えてしまおうというものです。たとえば「観劇で感激中の間隙を突く」では、「間隙を突く」という言い方を覚えましょう。「熱燗で圧巻」では、「圧巻」という言葉の意味を覚えましょう。(「熱燗」の方は覚えなくてもいいです。) ダジャレを考えることは、頭の体操にもなります。おもしろいダジャレのポイントは、語感が自然でありながら意外性があるということです。でも、むずかしく考えず、あなただけのオリジナルダジャレを作ってみてください。他人を笑わせることだけがダジャレの目的ではありません。ダジャレ作りの過程をじっくり楽しむことが大切なのです。 ダジャレを考えることは、頭の体操にもなります。おもしろいダジャレのポイントは、語感が自然でありながら意外性があるということです。でも、むずかしく考えず、あなただけのオリジナルダジャレを作ってみてください。他人を笑わせることだけがダジャレの目的ではありません。ダジャレ作りの過程をじっくり楽しむことが大切なのです。 山田純子(メグ) 山田純子(メグ)
|
|
|
||||