先頭ページ
前ページ
次ページ
最終ページ
| | 日本の宝 |
| | アジサイ | の | 森 | の広場
|
| | れもん | / | ふれ | 小4 |
日本の大地に根をおろしたいねは、たくさんのみのりをあげてくれました。毎年毎年おなじようにつくられるということも、なんとありがたいこ |
| とでしょう。六世紀ごろまでに日本のあちこちに、そんな小王国がいくつもできるようになり、それはやがてひとつに統一されて、「日本」という |
| 国がつくられていくのです。 |
| |
私はこの話を読んで、このころ、いねというものは、まるで今のお金のような「これさえあればなんでもできる。」というものだったのだな、と |
| 思いました。けれど、お金とちがうところがひとつだけあります。それは、お金とはちがって、人口がふえればふえるほど、もっとおおぜいの力を |
| あわせることができ、いままでよりも大きな川から、水を引くことができたということです。そして、もっとたくさん、水田をひらくことができ、 |
| もっとたくさんお米をつくることができるようになったということです。たくさんの人の力をあわせれば、その分だけ、よいものをつくることがで |
| きるということは、お金にはない、人間にとって一番大切なことだと思います。 |
| |
私の身近なところで、昔のいねの役目をしているのが、合唱、劇、合奏などです。私は学芸会で、合唱、劇、合奏は全てやっています。その中で |
| 、一番心に残っているのは、三年生の時に学芸会でやった「どろぼう学校」という劇です。学芸会では、一年生の時も劇をやりましたが、一年生の |
| 時とは、先生の対応がまるで、天国と地国のような差がありました。私はどろぼうの役をやりました。せりふは少ししかありませんでしたが、その |
| 少しのせりふの言い方などで、最初はたくさん注意されました。やっと先生に、せりふの言い方でほめられるようになったら、今度はみんなとあわ |
| せるせりふのないときの場面などで、注意されました。やっとほめられるようになると、今度は場面と場面とのつながりなどなど、ひとつがほめら |
| れるようになってもまたちがうところで注意されるということの繰り返しでした。そして、全部ができるようになったときは、とうとう学芸会本番 |
| の前日となっていました。そして、無事本番は大成功しました。あとから、もしひとりだけだったらこんな大きな劇はできなかっただろうな、と思 |
| |
このように、やはり、いくら自分がすごい才能をもっていても自分一人だけだったら何もできないのだと思います。 |
| |
いねというものは、お金の役割だけではなく、たくさんの人をまとめることもした、日本にとっての宝なのではないのでしょうか。 |
| |
|
| |
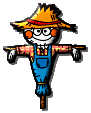 |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
ホームページ